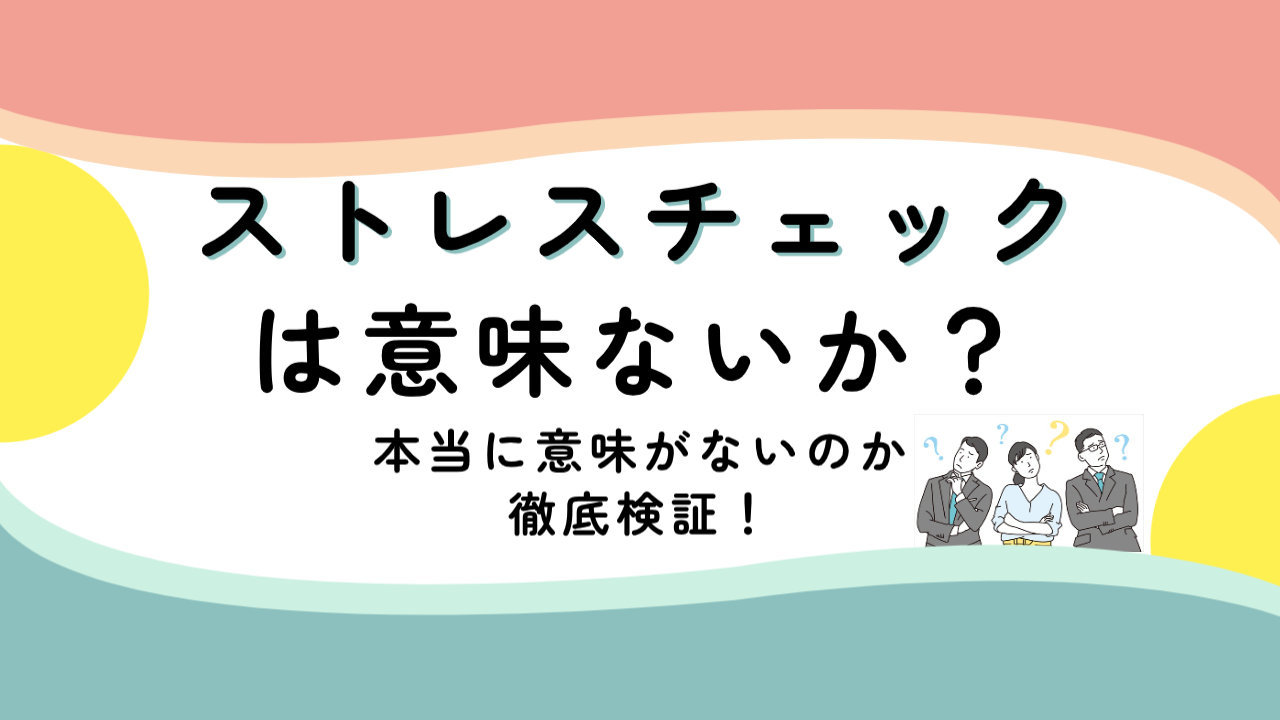
ストレスチェックを受けても、職場のストレスや人間関係の悩みが解消されない――そのような声から「ストレスチェックなんて意味がない」と感じる人も少なくありません。
確かに、チェックを受けるだけでは職場環境が劇的に改善するわけではありませんが、その目的や正しい活用方法を理解すれば、従業員のメンタルケアや組織づくりに大きな効果をもたらすこともあります。
ここでは、なぜ「ストレスチェックは意味がない」と言われるのか、その理由を整理し、本当に意味がないのかどうかを検証していきます。
目次
ストレスチェックは意味ないと言われる理由

従業員50人以上の事業場で働く人であれば、すでに何回かストレスチェックの受検経験はお持ちだと思います。
しかし、「ストレスチェックは意味がない」「ストレスチェックを実施してもストレスが解消したという声は聞かない」「職場全体でメンタルヘルス不調者が減った実感はない」という声も聞かれます。
(1)受検した労働者の割合が低い
「ストレスチェックは意味がない」という声が聞かれるのは、ストレスチェックの目的を理解していないために受検した労働者の割合が8割程度にとどまっていることも原因のひとつと考えられます。
厚生労働省の調査によると、事業規模が大きいほどストレスチェックの受検率が高くなる傾向が見られます。特に1,000人以上の企業ではほぼ全員が受検しているのに対し、50~99人規模の中小企業では74.5%と低めです。大企業では制度や人事体制が整っている一方、中小企業では実施体制や従業員の理解が十分でないことが背景にあると考えられます。
| 事業規模 | 50~99人 | 100~299人 | 300~999人 | 1,000人以上 |
| 受検した労働者の割合 | 74.5% | 91.7% | 98.1% | 99.9% |
厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況」/ストレスチェック制度 の実施状況(令和5年)
一般定期健康診断については、労働者は受診することが義務とされていますが、ストレスチェック制度については労働者に受検は義務づけられていません。すでにうつ病等のメンタルヘルス疾患で治療を受けている人は不要とされますし、労働者に強制して受検させることはできません。しかし、事業者には50人以上の労働者を抱える事業場でストレスチェックを実施する義務がありますし、2028年には全事業場がストレスチェックの対象となります。
そもそも、ストレスチェック制度の目的は、労働者にストレスへの気づきを促し、職場の改善につなげ働きやすい職場づくりを推進し、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することです。
したがってストレスチェックを受検しないことを選択できることは伝えるべきですが、職場の実情を正確に把握するためにも、できるだけ受検をするよう勧めることが大切です。
(2)医師による面接指導を受けた労働者の割合が低い
ストレスチェックの結果、高ストレス者と選定された労働者がいた場合、事業者はその労働者から申し出があった場合に医師による面接指導を実施しなければなりません。そして面接指導実施後には医師から意見聴取を行い、必要に応じて就業上の措置を講じなければなりません。
事業場としては、高ストレス者と選定された労働者が面接指導を受けることの重要性を正しく理解するように説明し、面接指導を受けたことで不利益取り扱いがされないことなどを周知し、面接指導の実施が進むよう措置を講じることが必要です。
つまり事業主は、本人が自主的に面接指導の申し出ができる(=会社を信用している)体制の整備が大切であることを認識することが大切です。
(3)集団分析を職場環境改善に活用できていない
ストレスチェックは実施して終わりではなく、その結果を集団ごとに分析して職場の課題を見つけ、職場環境の改善に活用することが求められます。
厚生労働省の調査によると、ストレスチェック後の「集団分析」の実施率は、事業規模が大きいほど高い傾向があります。特に1,000人以上の企業では8割を超える一方、50~99人規模の中小企業では6割程度にとどまっています。分析には専門的な知識や時間が必要なため、小規模事業所では実施が難しい現状が伺えます。
| 事業規模 | 50~99人 | 100~299人 | 300~999人 | 1,000人以上 |
| 受検した労働者の割合 | 61.0% | 63.8% | 80.1% | 81.4% |
「ストレスチェックや集団分析を実施するだけでは、従業員のストレスの改善や職場の生産性向上は得られない。集団分析結果に基づく職場環境改善が必須である」という研究結果もあります。つまり、ストレスチェックを実施するだけ、集団分析を実施するだけでは、お金の無駄遣いになりかねないということになります。
厚生労働省「ストレスチェック制度の実施状況」/ストレスチェック制度 の実施状況(令和5年)
集団分析結果から課題を見つけ、各事業場や従業員の傾向に合った対策を実施することは、職場環境を改善するだけでなく、会社が本気で「従業員の心の健康を考えている」というメッセージを示すことにもなります。
したがってストレスチェックを意味がないと考える人は、集団分析結果を活用し働きやすい職場環境の構築や従業員のワークエンゲイジメントを向上させる施策の実施こそが、ストレスチェックの集団分析に基づく職場環境活動の最終目標だということを改めて認識することが大切です。
ストレスチェックは本当に意味ないか?
これまでご紹介してきたように、ストレスチェックが「意味がない」と感じる人がいる背景には、労働者の受検率の低さや、集団分析の結果が十分に活用されていないことなどが挙げられます。形だけの実施にとどまり、改善につながらないケースがあるのも事実です。
しかし一方で、ストレスチェックを正しく運用し、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の見直し、ひいては従業員のモチベーション向上や生産性の改善につなげている企業も少なくありません。適切な活用こそが、制度の価値を最大限に引き出す鍵となります。
(1)集団分析を活用してセルフケアの情報を提供
ストレスチェックでは、ストレスによって起こる心身の反応も確認することができます。
不眠や頭痛、腹痛といった身体の不調(身体愁訴)は、メンタルヘルス不調によってもあらわれることがあり、ストレスが原因であることに本人が気づくのが遅れてしまうケースも少なくありません。
したがって、特定の部署で身体愁訴の得点が高い傾向が見られる場合には、長時間労働や過度なプレッシャーの有無を確認し、必要に応じてセルフケアに関する情報提供を行うことが重要です。
セルフケアとは、自分自身の心身の状態を理解し、ストレスへの反応を正しく認識する力を高めることを指します。
自らのストレスに気づき、予防や軽減の方法を意識的に取り入れ、適切に相談につなげることができれば、メンタルヘルス不調の早期発見や未然防止にも大きく寄与します。
(2)ストレスチェックで従業員の意識を改革
ストレスチェックの結果を集団分析し、職場環境の改善を行う際には、管理監督者だけでなく、部下にも積極的に参加を促すことが大切です。
結果が個人に通知されるだけで職場で何の変化もなければ、従業員は「結局、ストレスチェックなんて意味がない」と感じてしまうでしょう。担当者だけでなく、経営層や管理職が職場のストレスの存在を真剣に受け止め、改善に取り組む姿勢を見せることが、社員の安心感や組織への信頼につながります。
具体的には、まず衛生委員会での調査・審議を踏まえて集団分析の結果を検証し、他の職場や他社の成功事例も参考にします。従業員が参加するワークショップを行う場合には、ストレスチェックの意義を十分に理解していない人も多いので、最初のうちは産業衛生スタッフや実施事務従事者がファシリテーターとして参加し、正しい方向へ議論を導くと効果的です。
そのうえで、職場の課題や強みを整理し、改善に向けたアクションプランを策定します。策定した計画は全員に共有し、実施後は成果や課題を検討してPDCAサイクルを回すことで、継続的により良い職場環境づくりを進めていくことができます。
(3)メンタルヘルス対策を経営課題と捉える
職場の生産性は、多くの経営幹部や管理者が抱えている問題です。
ストレスチェックの結果、「生産性低下の原因は職場のストレスによるものである」という仮説が立つのならば、メンタルヘルス対策は経営課題と捉えるべきです。
実際に、職場環境の改善活動は、仕事のストレス要因や健康状態が改善するだけでなく生産性が向上することが多くの研究で報告されています。
従業員の健康増進が生産性の向上に与える影響を理解することは、企業がより積極的に経営資源を投入する大きなきっかけになります。
たとえば、ある企業ではストレスチェックの結果を踏まえて「チャージ休暇」という制度を導入しました。これは、従業員が心身のエネルギーをリセットし、生産性を高めてほしいという目的で設けられたもので、条件によっては交通費の補助も行われ、積極的な休暇取得を促しています。
このように休暇の目的を明確にすることで、企業がメンタルヘルス対策を経営課題として真剣に捉え、組織の成長やミッション実現に向けて本気で取り組んでいる姿勢が従業員にも伝わります。仕事のストレスが個人や職場全体にどれだけ影響を与えるかを理解し、それを解消するための仕組みを整えることは、まさに経営者の重要な使命です。
ただし、経営者によるトップダウンだけでは、従業員が「自分たちは考えなくていい」と受け身になってしまう可能性もあります。そのため、職場改善の取り組みは全従業員にオープンにし、意見を交わしながら一緒に取り組む姿勢をつくることが、より良い職場づくりの第一歩といえるでしょう。
まとめ
効果的なストレス対策を行うためには、労働者個人のストレス対策だけでなく、職場環境の改善などの組織的なストレス対策も組み合わせて行うことが重要です。
ストレスチェックを意味のないもので終わらせないための施策は、どんなに有能な経営者でも管理監督者でも、一足飛びに行えるわけではありません。
大切なのは、はじめの1歩を踏み出し継続することです。適切にストレスチェックを実施し、その結果を集団分析して改善活動を継続すれば、職場環境の改善、生産性の向上を実現することができるはずです。売上や利益に即効性を感じられなくても、人材への投資になることは間違いありません。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、幅広い組織で導入されてきた実績と高い信頼を誇ります。未受検者への自動リマインド機能、リアルタイムの進捗確認、医師面接希望者の自動集計など、実務を支える多彩な管理機能を標準搭載しています。さらに2025年5月からは、無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能に。これにより、欠勤や離職といった深刻な状況に至る前の段階で課題を発見し、早期対応が可能になります。導入から運用まで、専門チームによる丁寧なサポートも受けられるため、初めての企業でも安心して導入できるツールです。ストレスチェックの実施から集団分析、職場環境の改善までサポートを行い、適切な職場運営を後押しさせていただきます。社内の実施事務従事者にストレスチェックのシステムをご利用いただく『無料プラン』もございます。お気軽にお問い合わせください。

