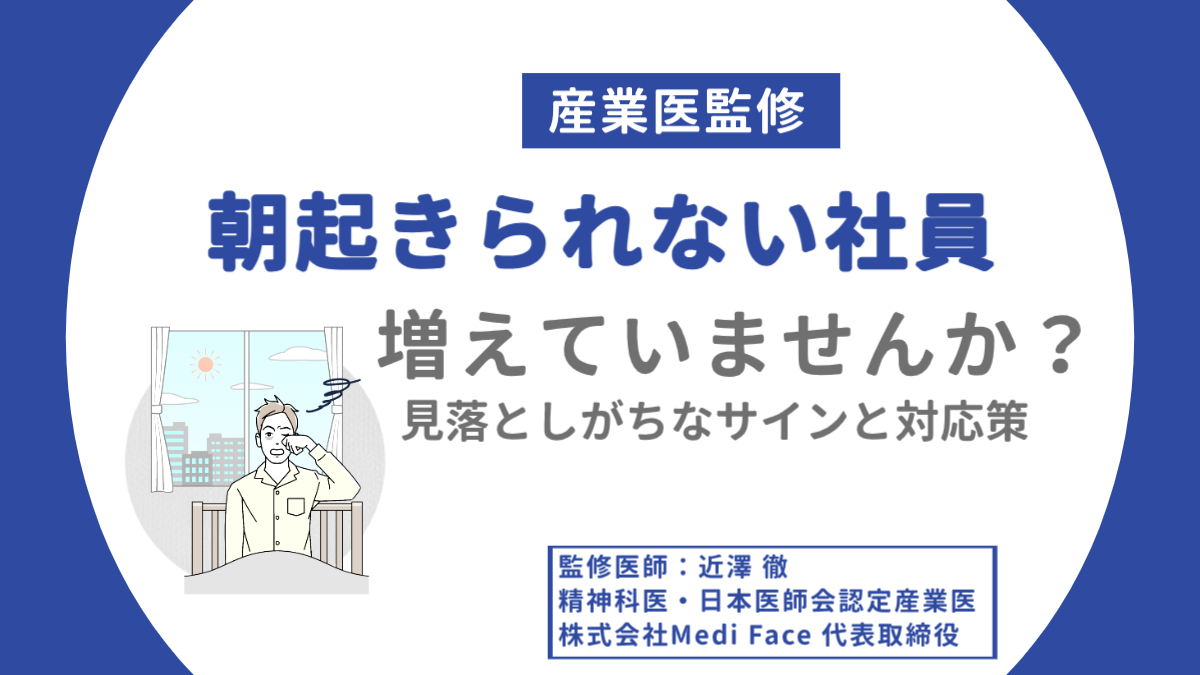
従業員から「朝どうしても起きられない」と相談された場合、単なる生活習慣の乱れだけではなく、ストレスやうつなどの心理的な要因が関係している可能性があります。心が疲れていると、起きようという意欲自体が湧かなくなることもあり、背景には睡眠障害や起立性調節障害といった病気が隠れている場合もあります。
メンタル不調は自覚しづらく、日常的な感情の一部として見過ごされがちです。多くの人は困難を乗り越えることに価値を感じ、無理をしてでも目標達成を目指してしまいます。その姿勢を周囲も応援しがちです。
しかし、このような状態を放置すると、遅刻や欠勤の増加だけでなく、自己肯定感の低下や職場での孤立にもつながりかねません。企業としては、こうしたサインを早期に把握し、適切に対応できる環境づくりが求められます。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
「朝起きられない」とはどういう状態?
「朝起きられない」とは、目覚ましが鳴っても起き上がれない、何度も二度寝を繰り返してしまう、頭がぼんやりして体が動かないといった状態が続くことを指します。単に「眠い」だけでなく、本人の意思ではどうにもならない感覚で、多くは睡眠不足や生活リズムの乱れが背景にありますが、ストレスやうつ状態、ホルモンの働き、自律神経の乱れなどが関係している場合もあります。中には「起立性調節障害」や「睡眠相後退症候群」といった病気が隠れていることもあります。
単なる寝坊との違い
「朝起きられない」という状態は、単なる寝坊とは本質的に異なります。寝坊は一時的な睡眠不足やアラームの聞き逃しなど、偶発的な理由によって起こることが多く、基本的には本人の意思や努力で改善可能です。
一方、「朝起きられない」は、目覚ましを何度も止めても起き上がれなかったり、強い倦怠感や意欲の低下で布団から出られなかったりと、日常的かつ慢性的に起こるのが特徴で、意志の問題だけではありません。背景には、生活リズムの乱れだけでなく、ストレス、抑うつ状態、自律神経の不調、さらには睡眠関連の疾患などが関係していることもあります。
夜型の生活の見直し
夜型の生活が定着している従業員の場合、十分な睡眠時間を確保できず、朝起きることがつらくなっているケースが少なくありません。特に、スマートフォンやパソコンを就寝直前まで使っていると、ブルーライトの影響で体内時計が乱れやすくなり、入眠が遅れる要因にもなります。このような生活習慣の乱れは、単なる眠気や疲れだけでなく、仕事への集中力や意欲の低下にもつながります。さらに、慢性的な睡眠不足が続けば、ストレスやメンタルヘルスの不調を引き起こすリスクも高まります。
ストレス過多や精神的疲労
朝起きられない背景には、ストレス過多や精神的な疲労が影響していることもあります。仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなどで日中に強いストレスを感じていると、夜になっても緊張状態が続き、脳や神経がうまく休まらなくなります。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりして、十分な休息がとれないまま朝を迎えることになり、起床がますますつらくなってしまいます。このような状態が続くと、日常業務への集中力や意欲の低下を招くだけでなく、メンタルヘルス不調へのリスクが高まります。
食事や運動のリズムが不規則
朝食を抜く、夜遅くにドカ食いをする、日中の活動量が少ないといった生活は、睡眠と覚醒の切り替えに必要な体内リズムを乱す原因になります。人間の体内時計は、光・食事・運動といった外的な刺激によって調整されていますが、それらが不規則になると、朝に目覚めるタイミングがずれてしまい、起きてもぼんやりした状態が続いたり、二度寝が習慣化したりします。特に朝食を抜くことは、内臓や脳に「活動のスイッチが入らない」状態をつくり、1日中だるさや集中力の低下を招く要因になります。また、夜に重い食事をとると、胃腸が活発に働いたまま睡眠に入ることになり、深い眠りが妨げられて、結果として朝の目覚めが悪くなることもあります。
働き方や人間関係
朝起きられない背景には、社会的な要因も大きく関係しています。特に現代の働き方は、長時間労働やシフト勤務、リモートワークによる昼夜逆転など、生活リズムを崩しやすい状況が多く、朝の決まった時間に起きることが難しくなっている人も少なくありません。
また、職場の人間関係にストレスを感じている場合、「行きたくない」「顔を合わせたくない」といった心理的な負荷が無意識のうちに朝の目覚めを妨げることもあります。
起立性調節障害や睡眠相後退症候群
朝起きられない状態が長期間続いている場合、病気が隠れている可能性もあります。たとえば「起立性調節障害(OD)」は、自律神経の働きが乱れ、朝に血圧が上がらず、めまいや倦怠感、動悸などが起きやすくなる症状です。思春期の子どもや若い人に多く見られる症状で、ストレスや生活習慣の乱れが引き金になることがあります。
また、「睡眠相後退症候群」は、体内時計が大きくずれてしまい、夜中にならないと眠れず、朝に強い眠気が残る病気です。意識して早寝をしようとしても眠れないという特徴があり、本人の努力では改善が難しいため、専門医に相談することが重要です。
「朝起きられない」を放置によるリスク
従業員が「朝起きられない」と訴える状態をそのままにしておくと、生活リズムがさらに乱れ、昼夜逆転や職場・社会とのつながりの希薄化を招くことがあります。その結果、自己肯定感の低下や無気力感が進行し、やがてうつ病や不眠症といったメンタル不調へとつながるリスクも高まります。こうした問題は、本人の意思や努力だけでは乗り越えがたい場合も少なくなく、職場としての早期対応や周囲の理解が欠かせません。
日常生活への支障|遅刻・欠勤・自己肯定感の低下
時間どおりに起きられないことが習慣化すると、学校や仕事への遅刻・欠勤が増え、自分自身への焦りや罪悪感が蓄積し、「自分はダメな人間だ」といった自己否定感を抱きやすくなります。
また、起きられなかったことを周囲に説明できず、人との関係に壁を感じるようになることもあります。
悪化のスパイラル|昼夜逆転・孤立
「朝起きられない」状態を放置すると、生活全体が徐々に崩れ、悪化のスパイラルに陥る可能性があります。寝時間が遅くなり、さらに朝がつらくなるという「昼夜逆転」の生活が定着しやすくなれば、仕事の時間に合わせた行動ができなくなり、外出する機会も減少していきます。すると、人と会う機会が少なくなり、連絡も取りづらくなり、孤立してしまうという状態を招いてしまうこともあります。
うつや不眠症など精神疾患との関連性
「朝起きられない」状態が、うつ病や不眠症などの精神疾患と深く関係してくることがあります。うつ病の初期には、朝に強い倦怠感や無気力を感じ、布団から出ることが極端に困難になるケースが多く見られます。
不眠症の場合は、入眠が難しかったり、夜中に何度も目が覚めたりすることで、睡眠の質が低下し、朝の目覚めが悪くなる傾向があります。これが続くと「眠れない」「起きられない」という悪循環に陥り、日中の集中力や判断力にも悪影響が及びます。さらに、「朝起きられない自分」を責め続けることで、自己否定感が強まり、精神的な負荷が蓄積されていきます。こうした状態を放置してしまうと、心のバランスを崩し、回復までに長い時間がかかる場合もあります。
企業がすべき「朝起きられない」対策
従業員が「朝起きられない」と訴える場合、まずは生活リズムの見直しを促すことが大切です。企業としては、夜はスマートフォンやパソコンの使用を控えるよう指導し、就寝・起床時間を一定に保つ生活習慣の大切さを伝えることが求められます。朝は自然光を浴びる、朝食をとる、軽く体を動かすといった行動が体内時計のリセットに効果的であることも、従業員への指導ポイントになります。
また、生活習慣の乱れは、ストレスやメンタル不調のサインである場合もあるため、ストレスチェック制度を通じて早期に気づき、適切な支援へとつなげられる体制を整えることが重要です。
まずは生活習慣の見直しから
睡眠リズムの乱れが朝の不調につながっている例は多く見られます。就寝・起床時間が毎日バラバラな場合には、まず「一定のリズムを保つこと」を意識させることが重要です。夜に眠れなくても、朝は同じ時間に起きて朝日を浴びることで、体内時計の調整が期待できます。また、就寝1時間前からスマートフォンやパソコンの使用を控えるよう促すことで、睡眠の質も改善されやすくなります。こうした生活改善の指導は、本人の体調管理だけでなく、仕事への集中力や意欲の回復にもつながります。
光・音・香りの活用法
社内報のコラムなどで、光・音・香りの活用法を周知するのも、おすすめです。
たとえば、光には体内時計を整える働きがあるため、冬場や曇りの日には光目覚まし時計や高照度の照明を取り入れたりすることができます。
また、アラームはけたたましい音ではなく、小鳥のさえずりや自然音など、心地よく目覚められるものを選ぶよう促すと、起床時のストレス軽減につながります。
香りについても、柑橘系やペパーミントなどは交感神経を刺激し、気分をスッキリさせる効果が期待できます。朝にアロマを活用したり、香り付きのハンドクリームで軽くマッサージしたりする方法なども、気軽に取り入れられる内容として発信できます。こうした情報を社内で広く伝えることで、従業員の生活改善と生産性の向上につなげることができます。
相談窓口の整備
「朝起きられない」という悩みは、生活習慣の乱れだけでなく、うつ病や不安障害、自律神経の不調といった心身の不調が背景にあることも少なくありません。ただ、従業員本人は「怠けていると思われたくない」「言い訳に聞こえそう」と感じ、周囲に伝えることをためらいがちです。こうした状況に対し、職場としては「話しやすい雰囲気づくり」や「小さな不調の共有を肯定する姿勢」が重要です。たとえば「最近朝がつらくて…」という一言をきっかけに、本人が少しずつ自分の状態を言葉にできるようサポートしていくことが求められます。上司への相談を通じて、業務量の調整や出勤時間の配慮、在宅勤務の活用など、柔軟な対応を検討できることもあります。
改善しないときは専門医へ相談
「朝起きられない」状態が2週間以上続き、仕事や日常生活に支障をきたしていると判断した場合は、専門医への相談を検討するタイミングです。
職場としても受診を促すような声かけや情報提供が重要になります。治療には、薬を使うだけでなく、生活リズムの調整や認知行動療法といった非薬物的なアプローチもあります。精神科の受診に不安を抱える人も多いですが、早期の受診が回復を早めることを、周知しておきましょう。
ストレスチェックの活用
休職や環境調整も選択肢に「朝起きられない」状態が長期に続き、業務に深刻な支障が出ている場合は、従業員本人の努力に頼るだけでなく、休職や勤務環境の調整を前向きに検討することが大切です。無理に通常通り働き続けようとすると、かえって心身の状態を悪化させる恐れがあります。在宅勤務の活用や出勤時間のスライド、静かな作業環境の整備など、働き方を柔軟に見直すことで、症状が軽減するケースもあります。「しっかり休む」「無理のない環境に切り替える」といった対応は、決して甘えではなく、心の健康を回復させるための積極的な選択肢です。ストレスチェック制度を導入し、従業員の不調のサインを早期に把握できれば、こうした判断や支援にもつなげやすくなります。職場全体で適切な対応をとることで、生産性の維持・向上にもつながるはずです。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
「ストレスチェックは実施しているけれど、実際には従業員の小さなストレスのサインを十分に活かせていない」と感じているご担当者の方は、見えづらいリスクに早めに気づける仕組みとして、ストレスチェックサービスの活用を検討してみませんか?
2025年5月1日からは、無料プランおよびWEB代行プランにて「プレゼンティーイズム(体調や心理的な負担でパフォーマンスが下がっている状態)」の測定が可能になります。本人が自覚していない疲れや意欲の低下を数値で把握できるようになり、深刻化する前に対応を考えるきっかけになります。
さらに、どの部署に負荷が集中しているのか、どんな傾向の不調が起きやすいのかといった職場全体の状態も見えてきます。まずは一度、お気軽にご相談ください。
:参照記事
>一次予防とは?二次予防・三次予防との違いは?

