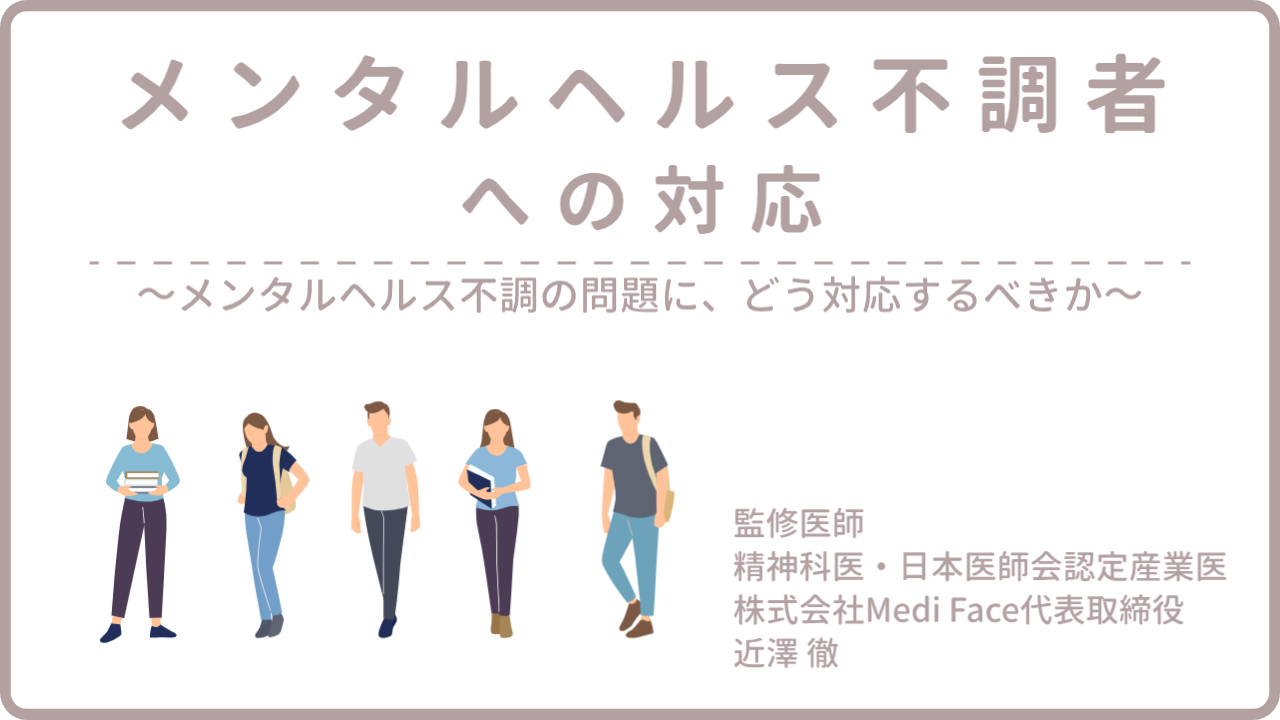
メンタルヘルス不調への対応においては、なかなか専門医に結びつかないという課題があります。
厚生労働省が行った調査でも、うつ病の患者のうち、調査を受けるまでに精神科医を受診したり相談したりした割合は、わずか3割程度しかなく、うつ病を含めた何らかの精神障がいがある人で調査を受けるまでに受診したり相談したりした割合は、非常に低いことが明らかになっています。
しかしメンタルヘルス不調に限らず、どのような病気でも早めに医療機関を受診して治療を受けることが大切です。
職場のメンタルヘルス対策でも、早期発見の重要性が再認識されています。厚生労働省では、職場のメンタルヘルス対策のガイドラインである「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、早期発見と適切な対応が重要である旨を強調しています。
参考:厚生労働省/職場における心の健康づくり
そこで、この記事では管理職はメンタルヘルス不調の問題に、どのように対応するべきかについてご紹介します。
目次
メンタルヘルス不調者とは
メンタルヘルス不調とは、仕事や日常生活におけるストレスが原因で心の健康が損なわれ、精神的・身体的に支障をきたす状態を指します。主な症状としては、不安や抑うつ、意欲の低下、睡眠障害、食欲不振、集中力の低下などが挙げられます。職場においては、業務のパフォーマンスが落ちたり、対人関係が悪化したりすることが多く、重症化すると長期の休職や退職につながるケースもあります。
メンタルヘルス不調の要因は、職場の過度なストレス、人間関係のトラブル、過労、プレッシャー、プライベートの問題などさまざまです。特に現代社会では、テレワークの普及や労働環境の変化によって新たなストレス要因が増え、より一層のケアが求められています。
企業にとって、メンタルヘルス不調者の増加は業務効率の低下や職場環境の悪化を招くため、組織全体での対応が必要不可欠です。
(1)メンタルヘルス不調は早めの治療が大切
メンタルヘルス不調は、早期発見と適切な対応が非常に重要です。初期段階で適切なサポートを行うことで、症状の悪化を防ぎ、スムーズな回復が可能になります。
軽度のストレスや疲労感がある段階で専門家のカウンセリングを受けたり、ストレス対策のセミナーを受講したりするだけでも、回復を早めることができます。しかし不調を放置すると、抑うつ状態が深刻化し休職や退職につながるリスクが高まります。
企業側としては、従業員が気軽に相談できる窓口を設けたり、産業医やメンタルヘルスの専門家と連携したりしながら、早期に対応できる体制を整えることが求められます。また、上司や同僚が部下の様子に気を配り、小さな変化に気づくことも早期発見につながります。
以下のようなサインが見られる場合、早めに声をかけたり、相談窓口を案内したりすることが重要です。
仕事に関する変化
パフォーマンスの低下
これまで問題なくこなしていた業務にミスが増えたり、作業スピードが落ちたりする。
集中力や判断力の低下
資料作成や会議での発言が少なくなり、単純なミスが増える。
遅刻・欠勤・早退の増加
遅刻や欠勤が増えたり、頻繁に早退したりするようになる。
業務への興味・意欲の喪失
以前は積極的に仕事に取り組んでいたのに、指示待ちが増える
行動や態度の変化
数が減る・会話が少なくなる
以前はよく話していたのに、急に無口になり、コミュニケーションが減る。
イライラしやすくなる
些細なことで怒ったり、不機嫌な態度をとったりする。
笑顔が減る・表情が暗い
以前は明るく笑っていたのに、無表情になったり、ため息が増えたりする。
身だしなみの変化
清潔感があったのに、服装が乱れていたり、髪型に気を使わなくなったりする。
健康状態の変化
疲れた様子が続く
いつも眠そうにしていたり、体調不良を頻繁に訴えたりするようになる。
食欲の変化
昼食を取らなくなったり、逆に暴飲暴食が増えたりする。
体重の急激な増減
明らかに痩せたり、急に太ったりする。
対人関係の変化
職場の人との関わりを避ける。
昼休みに一人で過ごすことが増えた、飲み会などの社交的な場を避けるようになる。
報連相(報告・連絡・相談)が減る。
業務の進捗を報告しなくなった、指示を受けても曖昧な返事をすることが増える。
過剰に謝る・自己否定が強くなる
ちょっとしたことで「すみません」と頻繁に謝るようになった
こうした変化が見られた場合は、すぐに「大丈夫?」と声をかけるだけでも安心感につながります。ただし、無理に踏み込まず、本人が話しやすい雰囲気を作ることが大切です。また、必要に応じて産業医やカウンセリング窓口の活用を促すのも有効です。
(2)リスク管理とコンプライアンス
メンタルヘルス不調は、従業員本人の問題にとどまらず、企業全体のリスク管理やコンプライアンスの観点からも重要な課題です。
職場のストレスが原因でうつ病を発症し、適切な対応をしなかった場合、企業は安全配慮義務違反として訴訟リスクを抱える可能性があります。
また、メンタルヘルスの問題が適切に管理されていないと、職場全体の士気が低下し、離職率の増加や生産性の低下につながります。従業員が安心して働ける環境を整えることは、企業にとっての義務であり、持続的な成長を支える要素でもあります。
厚生労働省は、不調者への対応について「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」の中で、不調者対応の考え方や標準的な対応方法について説明しており産業医や主治医と連携しながら、復職の可否判断を行うべきなどが5つのステップに分けて明示されています。
これをある種のコンプライアンスと意識しつつ、労務管理の一環として対応しなければならないことと理解しておくことが大切です。
(3)産業医・人事との連携
メンタルヘルス不調者の対応において、産業医や人事部門との連携は欠かせません。産業医は、従業員の健康状態を専門的に診断し、職場復帰の判断や勤務形態の調整を行う役割を担います。また、人事部門は、休職・復職の手続きや職場環境の整備を担当するため、両者のスムーズな連携が求められます。
また、不調者本人の家族とも情報交換を行うこともおすすめします。
療養する場合でも受診する場合でも、不調者に必要なのは身近な支援者だからです。
メンタルヘルス不調を未然に回避するための方法
メンタルヘルス不調を未然に防ぐためには、職場環境の改善が重要です。
ストレスチェックを定期的に実施し、従業員の負担を把握し、早期対応できる体制を整えます。また、メンタルヘルス研修やセミナーを開催し、上司や同僚が適切なサポートを行えるよう研修やセミナーを実施することも有効です。さらに、働き方の見直しとして、業務量の調整や適切な休暇取得を促すことが必要です。定期的な面談や相談窓口の設置も、早期発見・予防につながります。
(1)ストレスチェック
ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための重要な手段のひとつです。企業は年に1回、全従業員を対象にストレスチェックを実施し、その結果をもとに職場環境の改善や個別のフォローアップにつなげていくことが求められます。特に、ストレスの程度が高いと判断された従業員に対しては、医師との面談を促し、状況に応じて柔軟かつ適切なサポート体制を整えることが大切です。こうした取り組みを通じて、社員が安心して働ける環境づくりを進めていくことが、組織全体の健康と活力にもつながっていきます。
(2)セミナー等の実施
ストレス管理やメンタルヘルスに関するセミナーを定期的に開催することは、従業員の意識を高め、職場全体の健康意識を向上させるうえで非常に効果的です。ストレスのセルフチェックや、手軽にできるストレス解消法、呼吸法やマインドフルネスなどのリラックス法、さらに職場内でのハラスメント防止やコミュニケーションの取り方など、多岐にわたるテーマでセミナーを開催するのがおすすめです。
こうしたセミナーを通じて、従業員一人ひとりが自分の心の状態に目を向けるきっかけとなり、早めの対処や周囲への配慮にもつながります。組織としてメンタルヘルスの重要性を共有し、風通しのよい職場環境をつくっていくためにも、継続的な取り組みが求められます。
(3)職場環境の改善
職場の環境を改善することも、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ重要な要素です。ストレスチェックの集団分析は、職場環境の改善に役立つ重要なツールです。個人のストレス状態を把握するだけでなく、部署ごとのストレス要因を可視化し、業務負担の偏りや職場の人間関係の課題を明確にできます。ストレスの高い職場を特定できれば、早めに環境改善を進めることで、メンタルヘルス不調の予防につながります。
たとえば、労働時間の見直し、業務分担の最適化、コミュニケーションの活性化など具体的な対策を講じることが可能になります。その他、適切な業務量の調整、上司と部下の円滑なコミュニケーションの促進、働きやすい職場づくり、休憩スペースの充実やフレックスタイム制の導入、リモートワークの推奨なども、ストレスの軽減に寄与します。
まとめ
メンタルヘルス不調は、個人の働く意欲や生活の質を損なうだけでなく、生産性の低下や離職の増加といった形で企業全体にも大きな影響を及ぼす深刻な課題です。こうした問題を未然に防ぐためには、早期発見と早期対応が非常に重要であり、そのための手段としてストレスチェックの活用や職場環境の継続的な見直しが欠かせません。また、産業医や人事担当者との連携を強化し、必要に応じてカウンセリングの機会を設けるなど、従業員一人ひとりの状況に応じた柔軟な対応が求められます。復職支援にも力を入れることで、メンタルヘルスに不安を抱える従業員が無理なく職場復帰できる体制を整えることができ、結果として組織全体の安定と活力にもつながります。企業としては、メンタルヘルス対策を一過性の取り組みではなく、持続的かつ戦略的に位置づけ、長期的な視点でしっかりと取り組んでいく姿勢が問われています。
:参照記事
>一次予防とは?二次予防・三次予防との違いは?
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹
| 【監修医師】 精神科医・日本医師会認定産業医 株式会社Medi Face代表取締役 近澤 徹  オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。 |

