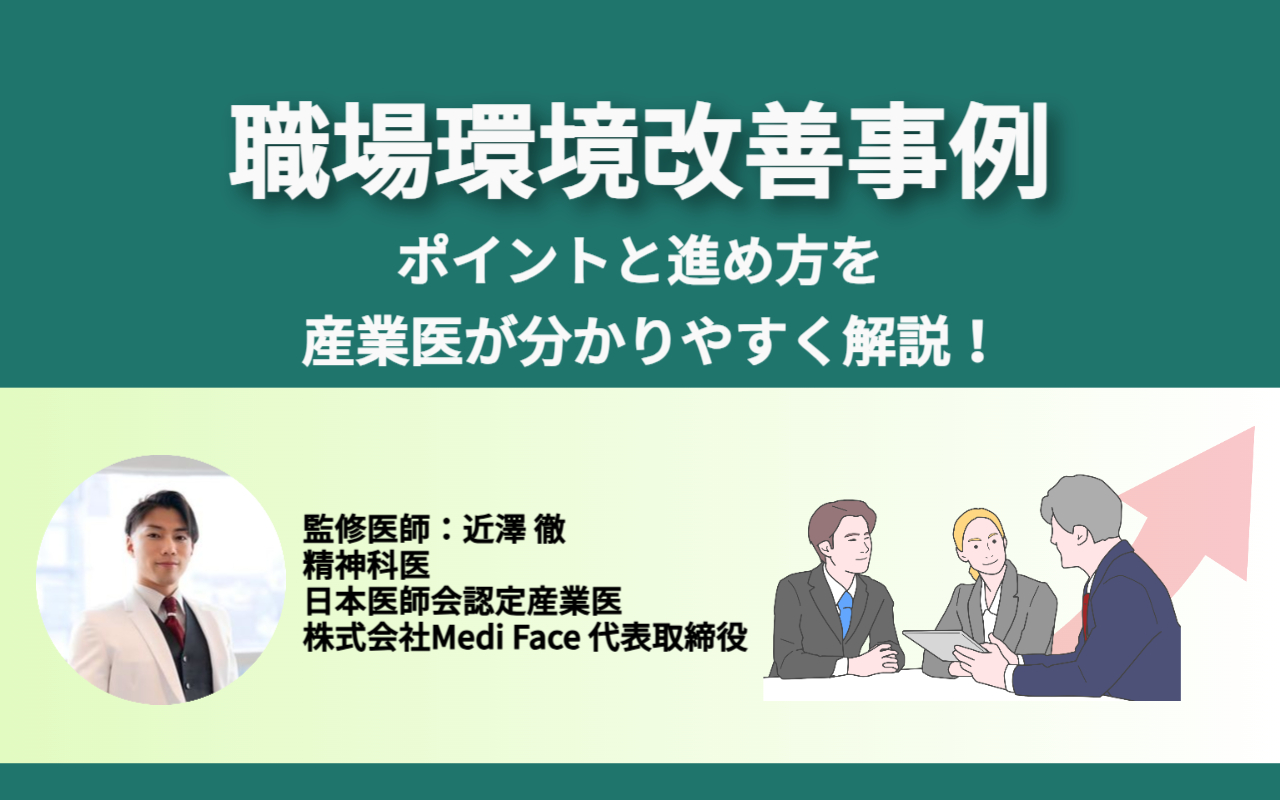
職場環境の改善は、従業員の健康維持や生産性向上に不可欠です。快適な労働環境はストレスを軽減し、モチベーションやチームワークを高めます。働きやすい環境を整えることで、離職率の低下や企業の成長にもつながります。
職場環境の改善とストレスチェックは、働く人の健康を守るために密接に関わっています。ストレスチェックは、労働者の心理的負担を測定し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐ制度で、職場の問題点が可視化され、業務の負担や人間関係など、ストレスの要因を特定できます。
目次
職場環境改善の取り組み事例
ストレスチェックを実施し、集団分析を行い、職場の活力を向上するためのプロジェクトを行っている企業が増えています。ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスを把握してストレス要因を分析し、職場環境の改善や生産性向上につなげることができます。
(1)東海旅客鉄道株式会社
東海旅客鉄道株式会社では、2009年から全従業員を対象にストレスチェックを実施しています。
そしてストレスチェックの結果をセルフケアに活用してもらうよう、安全衛生委員会や社内報などを通じて周知しています。
面談が必要と医師が認めた場合や従業員が希望した場合には、産業医による面談を実施する体制を構築し、さらに高ストレス者に対する医師による面談指導を実施する体制も整えています。
また、ストレスチェック集団分析の結果をもとに、職場管理者と産業保健スタッフが意見交換を行い、各事業所の職場環境改善の取り組みを支援しています。
参考:厚生労働省 / 実践報告③東海旅客鉄道株式会社(平成30年度職場のメンタルヘルスシンポジウム)
(2)三井化学株式会社
三井化学株式会社では、ストレスチェックの集団分析結果を正しく対象者に理解してもらうことを重視しています。
集団分析結果を全体で見ると、仕事の負担感が高い職場、上司や同僚の支援の低い職場、総合健康リスクなどのリスクが高い職場が目につくものです。
しかし、こればかりに目を奪われていると、結果の良くない職場のみがターゲットになってしまい、ストレスチェックの本来の趣旨である一次予防につながらないリスクがあります。
そこで逆に、集団分析結果で職場の支援感が非常に良い職場などをピックアップして、メンタルヘルス管理者研修や安全衛生委員会などにフィードバックして、水平展開を行っています。
参考:産業医学ジャーナル/ストレスチェックの現在地点と今後の課題 ―施行から10年目を迎えて
(3)大阪市
大阪市では、ストレスチェックの集団分析の結果について意見交換等を行っています。
安全衛生委員などを対象とした講習会で情報交換した課題別事例や総合健康リスクが大幅に改善した事例を作成し、職場環境改善の参考ツールとして各職場に配布して、活用を促進しています。
また、健康情報紙などを通じて、セルフケアや職場環境改善などのメンタルヘルス対策に関する情報などの提供を行っています。
2011年の開始当初から見ると、集団分析結果における総合健康リスク値は改善していますが、一方でメンタルヘルス不調による休職者率は増減を繰り返しているという事情もあります。
そこで、さらに取り組み内容を経年的に見直し、PDCAサイクルに基づく具体的な手法や実践につながる研修の充実に努めています。
参考:一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会/大阪市の取組 健康で笑顔あふれるいきいき職場をめざして
職場環境改善のための5つのステップ
これまでご紹介してきたように、多くの事業場でストレスチェックの結果を職場環境改善への取り組みにつなげています。
ストレスチェックの結果をもとに、勤務時間の見直しや業務の適正化、ハラスメント対策などの環境改善が進めば、従業員の満足度や生産性の向上につながります。ストレスチェックは単なる診断ではなく、職場環境をより良くするための第一歩として活用することが重要です。
ここでは、職場環境改善のための5つのステップをご紹介します。
(1)事業場の方針の表明
まず、企業のトップや管理職が職場環境の改善を重要視し、その方針を明確に示すことが大切です。例えば、「従業員の健康を第一に考え、働きやすい環境を整える」などの方針を策定し、社内外に周知します。管理職や労働組合が協力し、従業員が安心して意見を言える環境をつくることも重要です。改善の方針が明確になることで、従業員の理解と協力を得やすくなります。
なお、実施するうえでは実施の担当者を明確にすることも大切です。
計画から実行にあたっては、関係部署との調整や外部委託先を活用するための手続きなどもあるので、予算も扱える人が望ましいでしょう。
(2)ストレスチェックの集団分析
ストレスチェックを実施し、その結果をもとに職場のストレス要因を分析します。ストレスチェックの集団分析結果の「仕事のストレス判定図」では、事業場全体、部、課などの集団を対象として職場のストレス要因の一部を評価し、それが従業員のストレスや結果リスクにどの程度の影響を与えているかを判定しています。
例えば、「業務量が偏っている」「コミュニケーションが不足している」「評価制度に不満がある」など、具体的な課題を浮き彫りにすることができます。従業員の声を収集し、職場のストレスレベルを数値化することで、改善すべきポイントが明確になります。
(3)目標の設定と計画の立案
ストレスチェックの結果をもとに、職場環境を改善するための具体的な目標を設定し、実行計画を立案します。例えば、「定期的な1on1ミーティングを導入して上司と部下の対話を増やす」「チーム内の業務負担を見直し、適正な分担を行う」「残業時間を削減するために業務効率化ツールを導入する」など、具体的な施策を検討します。
(4)進捗の確認とツール導入の検討
計画を実施し、その進捗状況を定期的に確認します。施策がうまく機能しているかを定期的に見直し、必要に応じて改善策を追加します。
業務効率化のためのツールを導入する、メンタルヘルスケアの相談窓口を設置する、ハラスメント対策を強化するなど、状況に応じた施策を検討します。また、従業員の声を定期的にヒアリングし、実際の職場環境の変化を把握することも大切です。
職場環境改善実施のための有用なツールとしては、「職場環境改善のためのヒント集(メンタルヘルスアクションチェックリスト)」や「メンタルヘルス改善意識調査票」などがあります。
参考:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」(厚生労働省サイト)/職場環境改善ツール
(5)効果の評価と計画の見直し
一定期間後に取り組みの効果を評価し、改善すべき点を洗い出します。
対策の評価としては、目的とする結果の指標が改善したかどうかを評価する「アウトカム評価」と、実施事項が計画通り行われたのかを評価する「パフォーマンス評価」の2つの側面から行います。
|
アウトカム評価:ストレス関連疾患による休業日数が減ったか、ストレスの訴えが改善したかなど パフォーマンス評価:立てた計画が予定通りに実施されたかどうかなど |
「ストレスチェックの結果が改善されたか」「離職率が低下したか」「従業員満足度が向上したか」など、数値データをもとに評価を行います。効果が見られた施策は継続し、成果が不十分な施策については、新たな改善策を検討します。職場環境の改善は一度の取り組みで終わるものではなく、継続的な見直しが必要です。定期的にストレスチェックを実施し、効果を測定しながら改善を続けることで、働きやすい職場環境を維持できます。
対策の評価としては、目的とする結果の指標が改善したかどうかを評価する「アウトカム評価」と、実施事項が計画通り行われたのかを評価する「パフォーマンス評価」の2つの側面から行います。
アウトカム評価:ストレス関連疾患による休業日数が減ったか、ストレスの訴えが改善したかなど
パフォーマンス評価:立てた計画が予定通りに実施されたかどうかなど
まとめ
以上、職場環境改善の事例と実施方法についてご紹介しました。
適切にストレスチェックを行い、その結果をもとに職場環境改善を実施することで、従業員のストレスを軽減し、モチベーションを向上させることが期待できます。また、職場環境が改善されることで、企業の生産性向上や離職率の低下にもつながります。従業員が安心して働ける環境をつくるために、組織全体で継続的な取り組みを進めていくことが重要です。
ストレスチェックは、従業員が自身の健康状態を把握するだけでなく、職場全体の課題を明確にし、改善へとつなげる重要な手段です。
:参照記事
>ストレスチェックの高ストレス者が中間管理職に多い職場とは
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹
| 【監修医師】 精神科医・日本医師会認定産業医 株式会社Medi Face代表取締役 近澤 徹  オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。 |

