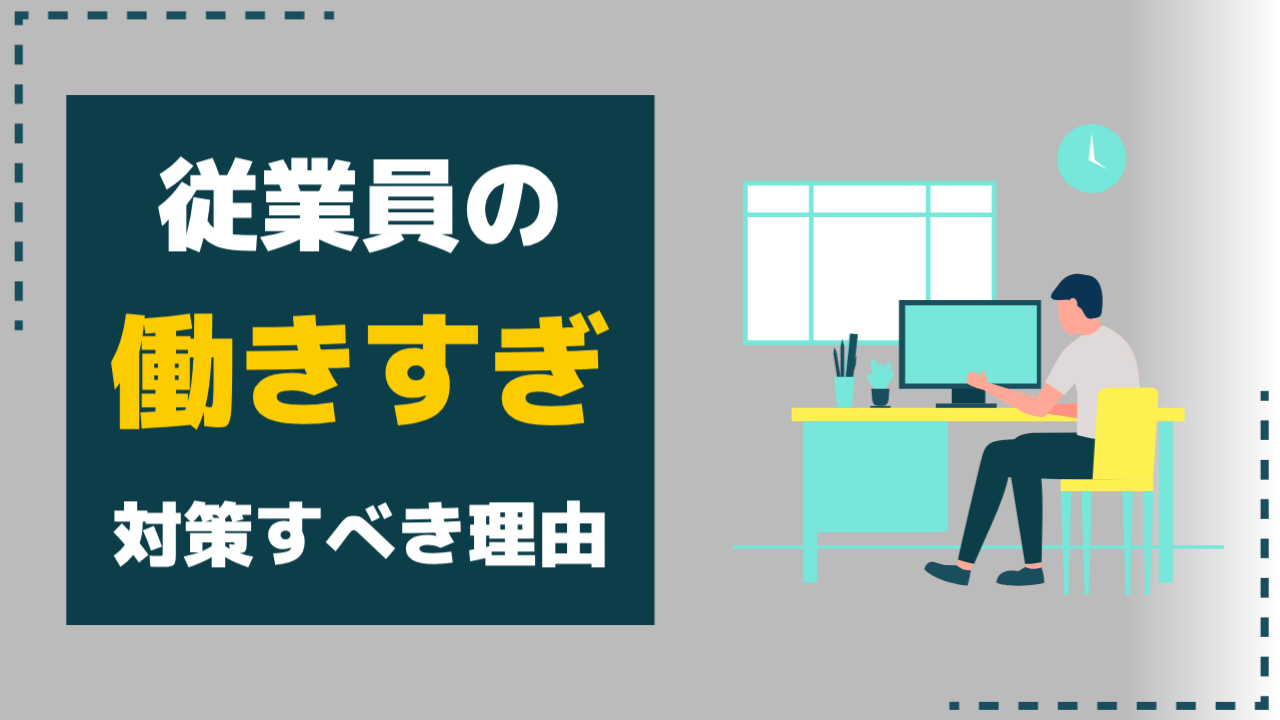
最近、「休んだのに疲れが取れない」「仕事のしすぎでつらい」といった声を職場で耳にすることはありませんか?日本の職場では「このくらいは普通」と無理を受け入れる空気が根強く、メンタル不調のサインが見過ごされがちです。多くの人は困難を乗り越えることを良しとする価値観を持ち、「あと少し」と無理をしてしまうケースが少なくありません。また、それを周囲も応援してしまうため、結果として本人の負荷が増していきます。
そもそもメンタル不調は自覚しづらく、漠然とした不安や疲れを「ただの気分の波」として処理してしまうケースも多いものです。しかし、そうしたサインを放置すれば、本人だけでなく職場全体にとってもリスクになります。企業には、些細な変化に早期に気づき、声をかけ、適切にサポートする体制が求められています。
この記事では、「働きすぎ」がどういう状態を指すのか、職場での早期発見につなげるための視点、そして企業としてできる対策についてまとめています。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
「働きすぎ」とはどういうこと?
「働きすぎ」と聞くと、単純に「長時間働いている状態」を思い浮かべるかもしれません。厚生労働省では、月の残業が80時間を超えると、過労死のリスクが高まるとされています。
たしかに、長時間労働は働きすぎの一つの目安です。
しかし実際には、単に時間だけではなく、仕事のストレス、精神的なプレッシャー、人間関係、仕事の責任の重さなど、さまざまな要素がからみあって「働きすぎの状態」は起きます。
たとえば、業務量は多くないのに、常に緊張感があって気が休まらない環境だったり、ミスが許されないプレッシャーにさらされ続けていたりすれば、「働きすぎの状態」になってしまうことがあります。
働きすぎの代表的なサインとは?
働きすぎの怖さは、「本人が気づかないうちに進行していること」にあります。
下記のような兆候があれば、従業員の状態を見直すタイミングかもしれません。本人は「まだ平気」と思っていても、実際には心身のバランスが崩れ始めている可能性があります。
|
こうした状態が続いているとき、本人では「まだ大丈夫」と思っていても、すでに心と体が限界に近づいていることがあります。
日本の働き方の変化と見えないプレッシャー
日本ではかつて「長時間働くこと」が美徳とされてきましたが、近年は働き方改革の推進により、その考え方も少しずつ変わってきています。実際に、企業によっては残業を抑える取り組みや、有給休暇の取得促進、リモートワークの導入などが進み、以前よりも「時間に縛られる働き方」は減少傾向にあります。
とはいえ、「定時で帰るのは気まずい」「仕事を早く終えると暇だと思われる」といった空気感は、まだ一部の職場に根強く残っているのも現実です。
つまり、“見えないプレッシャー”によって働きすぎが起きているケースも少なくありません。
一方で、欧米諸国では「成果重視・オンとオフの切り替え」が徹底されています。ドイツや北欧では定時退社が当たり前で、長時間労働は非効率と見なされることも。フランスでは長期休暇の取得も一般的で、仕事以外の時間を充実させることが社会的に認められています。
日本でも制度面は整ってきていますが、働く人一人ひとりの意識や職場文化を含めた「働き方の中身」を見直すことが、今後の課題といえるでしょう。
働きすぎがもたらすリスクとその実態
働きすぎが続くと、本人の心身に影響が出るだけでなく、業務全体やチームにも悪影響を及ぼします。
集中力や判断力の低下によるミスの増加、モチベーションの低下、職場の雰囲気悪化、離職リスクの上昇など、組織の生産性にとって大きな損失となります。
心のリスク|うつや不安症状などメンタル不調
うつ病、不安障害、パニック症状など、働きすぎが引き金となって心の病を発症するケースは少なくありません。これらの症状は、最初は「なんとなく気分が沈む」「不安を感じやすくなった」といった軽い兆候から始まり、徐々に悪化していきます。感情のコントロールがきかなくなり、突然涙が出たり、怒りっぽくなったりすることもあり、本人にも理由がわからず戸惑う場面が増えます。その結果、家族や友人、同僚との人間関係にひびが入り、孤立感が強まることもあります。
また、朝起きるのがつらい、通勤中に動悸や吐き気が出る、会社の名前を聞いただけで緊張するといった「仕事への極度の恐怖感」にまで発展する場合もあります。この段階に至ると、通常の生活すら困難になり、就業上大きな支障が出てしまうため、早めの対応が欠かせません。
体のリスク|不眠・自律神経の乱れなど
睡眠障害(不眠・中途覚醒など)は、働きすぎの初期に現れる身体のサインのひとつです。「疲れているのに眠れない」「夜中に何度も目が覚める」「朝早く目が覚めてしまう」などの状態が続くと、回復力が落ち、日中の集中力や判断力にも大きな影響が出ます。
さらに、慢性的なストレスにより交感神経が過剰に働くことで、高血圧や胃腸の不調、頭痛といった症状が現れることもあります。
こうした不調が積み重なると、自律神経が乱れてしまい、気温の変化や気圧の変動に体がついていかない「自律神経失調症」になることもあります。さらに深刻なのは、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気のリスクが高まるので、40代以降の従業員が多い職場では特に要注意です。
働きすぎを防ぐために企業としてすべきこと
働きすぎを防ぐために、企業はまず業務の効率化と適正な負担分担を徹底すべきです。業務フローの見直しやツールの導入、業務の優先順位付けを行い、無駄な時間を削減します。また、有給休暇の取得を促進し、休暇制度やフレックスタイム制度、リモートワークの導入など柔軟な働き方を支援します。
さらに、職場文化として無理をしない働き方を奨励し、上司やリーダー層には健康的な働き方の重要性を周知することが大切です。ストレスチェックやメンタルヘルス研修を実施し、従業員の健康を守るためのサポートを強化することも必要です。
働きかけと文化の改革
業務量やプロセスが過剰になっている可能性があるため、業務の効率化や優先順位付けを見直し、適切な負担分担ができるよう改善策を講じることが重要です。具体的には、業務フローの見直しやツールの導入、業務のアウトソーシングを検討し、従業員が効率的に働ける環境を整備します。
また、働きすぎを美徳とする職場文化が根付いている場合には、その文化を変えていくための教育を行います。上司やリーダー層に対しても、健康的な働き方を促進するための意識改革を図り、無理をしない働き方が評価される環境を作ります。従業員が柔軟に働けるように、フレックスタイム制度やリモートワークの導入を進め、仕事とプライベートのバランスを保つ支援を強化します。
時間の使い方を見直すセルフチェック
ざっくりで構いませんので、起床から就寝までの時間帯ごとに、自分が何をしているかを記録することで、無駄に費やしている時間や、必要以上に仕事に取り組んでいる部分が見えてきます。
「仕事の準備に毎日1時間以上かかっているが、それは本当に必要なのか」「退勤後にメールチェックがダラダラと続いている」「本来30分で済むはずの資料作りに2時間もかかっている」といった見直しポイントが発見できるかもしれません。こうした気づきは、従業員の時間の使い方を効率化する手助けになります。
無意識に費やしていた時間を意識的にコントロールできるようになると、働きすぎの予防にも効果的です。この方法は、従業員がストレスの原因を認識し、より健全な働き方をするための第一歩となります。
業務の優先順位と断る勇気の大切さ
従業員には、「すべてを自分で引き受ける必要はない」ということを認識してもらいましょう。責任感が強い人ほど、「自分がやった方が早い」「誰かに頼むのは申し訳ない」と思いがちですが、この考えが積み重なることで、逆に自分の負担が増えてしまうことがあります。
仕事はチームで行うものであり、「分担する」「頼る」ことは、決して怠けや甘えではありません。それどころか、自分の時間とエネルギーを守り、より重要な業務に集中するための重要な方法です。また、「手放す勇気」を持つことは、長期的に働き続けるための知恵であるということを、日々のコミュニケーションで周知しましょう。
職場の相談先や専門機関の活用
職場の上司や同僚、産業医、カウンセラーなどに相談できる重要性を周知しておきましょう。
自分の中だけで悩みを抱え込むと、問題が次第に大きく感じられます。しかし、誰かに話すことで気持ちが整理され、心の負担が軽くなることがあります。たとえ相手が解決策を提供できなくても、「自分の話を聞いてくれた」「共感してもらえた」という経験が、大きな支えになることがあります。
特に産業医は、働く人々の悩みを聞き、サポートする専門家です。また、会社の相談窓口や外部の相談機関も積極的に活用することができます。これらのサポートを通じて、従業員が抱えるストレスや悩みを軽減し、職場環境の改善につなげることができます。
有給・休職制度は「自己管理」
「休むことの重要性」について、伝えることも大切です。
休むことは決してサボりや甘えではなく、自己管理の一環です。自分のコンディションを冷静に見極め、適切に休む判断ができる人こそ、長期的に安定して働き続けることができるのです。
周囲の目が気になり、「自分だけ休むのは申し訳ない」と感じる従業員がいるかもしれませんが、無理をして限界を超えた結果、体調を崩し長期的に休まなければならなくなった場合、本人だけでなく、職場全体にとって大きなダメージになります。
また、もし体調が優れない日が続いている場合は、産業医や医師に相談し、必要であれば休職制度の利用を勧めることも一つの選択肢です。
ストレスチェック制度を活用しよう
働きすぎは、心と体にじわじわと負担をかけ続け、気づかないうちにメンタルや健康をむしばみます。こうした状態を早めに把握し、予防や対処につなげるために活用できるのが「ストレスチェック制度」です。労働安全衛生法に基づき、従業員50人以上の事業場では年1回の実施が義務づけられている制度(今後は、全事業所が対象)で、自分のストレスの度合いや職場環境の問題点を可視化することができます。
チェックは質問形式で行われ、結果は本人にフィードバックされるので、「働きすぎかも?」と感じている人が自分の状態を冷静に振り返るきっかけになります。「高ストレス」と判定された場合には、産業医との面談を受けることができ、職場改善や業務調整などにつなげることも可能です。
セルフケアを習慣化しよう
「セルフケア」は、働き方を見直す上で欠かせない視点です。Googleのマインドフルネスの例では、1日の中で「1分間の深呼吸」を取り入れ、リラックスする時間を作ることが推奨されています。その他にも、十分な睡眠を取ることや、食事を抜かないこと、1日10分でもリラックスする時間を確保することなど、セルフケアの重要性を従業員に周知しましょう。
無理に頑張りすぎず、「今日は休もう」と思える柔軟さを持つ職場は、健康的に働き続けるために必要です。適切な休養を取ることで心身のリフレッシュが図れ、結果として仕事の効率が向上します。働きすぎを防ぐことで、従業員のパフォーマンスが持続的に高まり、長期的な生産性向上につながります。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
「ストレスチェックは実施しているけれど、実際には“働きすぎのサイン”をうまく活かせていない」と感じている担当者様は、ストレスチェックサービスを活用し、従業員の“見えないリスク”に早期に気づく仕組みを取り入れませんか?
2025年5月1日から、無料プランおよびWEB代行プランにて「プレゼンティーイズム(体調や心理的負担で生産性が低下する状態)」の測定が可能になります。本人が気づいていない疲れややる気の低下を数値で把握し、問題が深刻化する前に対応できるきっかけとなります。
また、どの部署にストレスが集中しているのか、どのようなタイプの不調が起きやすいのか、職場全体の傾向も把握できます。まずはお気軽にご相談ください。
:参照記事
>一次予防とは?二次予防・三次予防との違いは?

