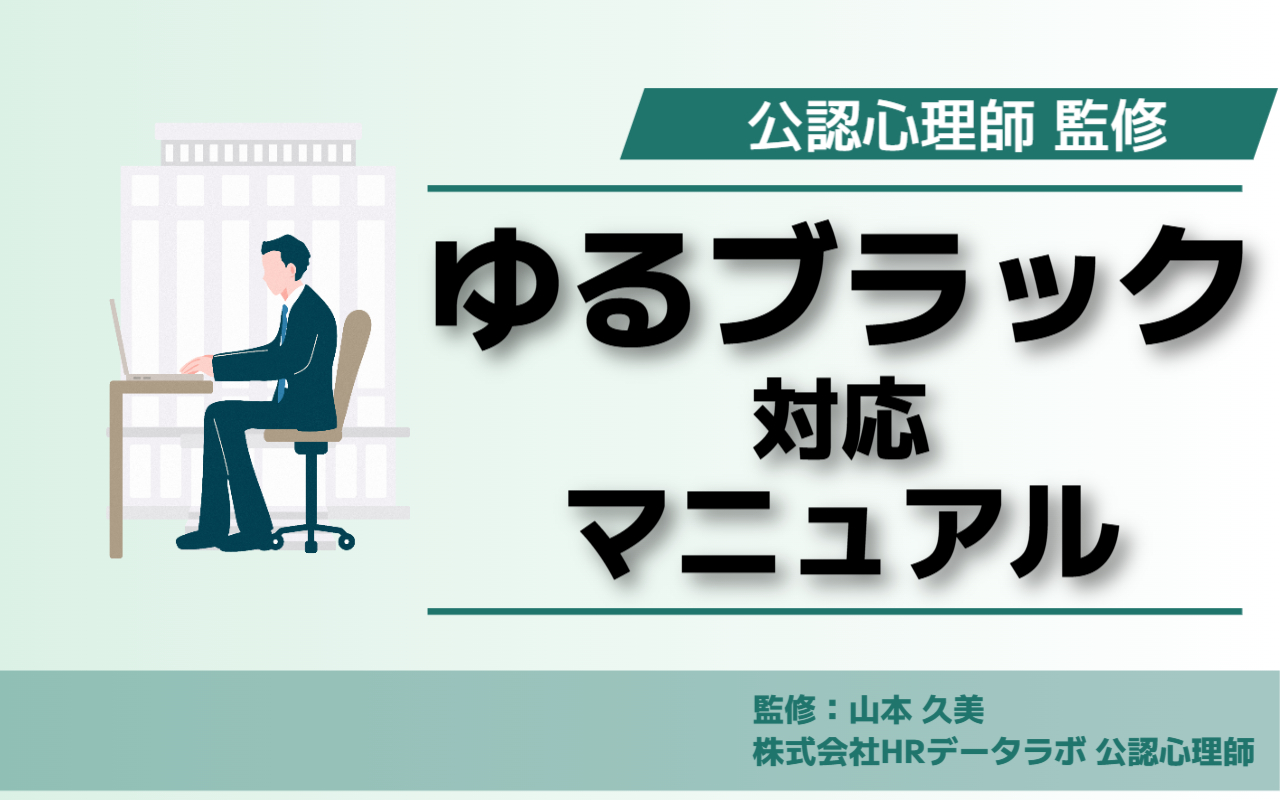
近年、「ゆるブラック」と呼ばれる職場が、じわじわと組織の活力を奪うとして注目されています。
残業はほとんどなく、有給もしっかり取れて、ハラスメントの気配もない——ぱっと見はホワイトそのものなのに、若手従業員が長く続かない、不満の声はあまり聞こえないのに、どこか職場に元気がない——そんな状態に心当たりがあるなら、それは「ゆるブラック」のサインかもしれません。
この「ゆるブラック」がやっかいなのは、その兆候が数字に表れにくく、人事側も気づきにくいという点にあります。
本記事では、「ゆるブラック」の背景や見えにくいリスクの正体を整理したうえで、人事担当者としてどのようにストレスチェックを活かすべきか、また、具体的にどんな対策を講じればよいのかを解説します。
監修:山本 久美
(株式会社HRデータラボ 公認心理師)
目次
ゆるブラックとは
「ゆるブラック」とは、外から見るとホワイト企業のように見えるものの、実際には従業員がやりがいや成長を感じにくく、モチベーションの低下や静かな離職につながっていくような職場環境を指します。
残業は少なく、定時で帰宅できるためワークライフバランスは比較的良好で、パワハラやセクハラといったハラスメント行為もなく、一見ホワイトな職場に見えるものの、業務はルーチンワーク中心で、自己成長やスキル向上の機会が限られています。また、昇給や昇進の機会も少ないため、長期的にモチベーションを維持するのは難しいといった傾向があります。
最近では、20代後半〜30代前半の若手従業員や第二新卒層を中心に、「ブラックではないけれど、なぜか満たされない」「何となく息苦しい」といった違和感を抱き、SNSや転職活動のなかで「ゆるブラック」という言葉を使ってその実態を共有するケースが増えています。
人事が気づきにくい静かな職場リスク
ゆるブラックな職場環境は、従業員が不満や違和感を表に出しにくく、データ上にも現れにくいため、人事担当者にとって見逃されやすい傾向があります。不満の声が上がらず、無関心やあきらめの空気が静かに広がっていくため、表面的なヒアリングや数値では見えにくいのです。さらに、人事として働きやすさの制度を整えたという達成感があると、現場の違和感を見落としやすくなるといった面もあります。結果的に、問題が顕在化したときにはすでに離職が続いていたり、職場に活気がなくなっていたりするケースも少なくありません。
ホワイト企業との微妙な違い
ゆるブラックとホワイト企業は、どちらも残業が少なく、有給が取りやすく、ハラスメントも表面化していないなど、働きやすい環境が整っているように見えます。
しかし、両者の大きな違いは「従業員の内面」にあります。
ホワイト企業では、働きやすさに加えて、やりがいや成長実感、適切な評価制度が備わっており、従業員が前向きに働ける土壌があります。
一方、ゆるブラックでは成長機会が乏しく、評価も曖昧で、働いていても達成感や手応えが感じられません。表面的には問題がなくても、実はモチベーションを失い、静かに職場を離れていく――この“見えないリスク”こそが、ゆるブラックとホワイト企業との決定的な違いです。
高ストレス者がいない=安心ではない
ストレスチェックで高ストレス者が出ていないからといって、安心とは限りません。むしろ、表立った不満やトラブルが見えにくいからこそ、職場に潜むリスクが見逃されがちです。
なぜなら、従業員がやりがいや成長を感じられず、心身に不調をきたすほどではないが、無気力や無関心の状態に陥っているケースでは、高ストレスとは判定されないからです。また、既に意欲を失った従業員は声を上げず、静かに辞めていくため、人事が異変に気づきにくいといった面もあります。
つまり、ストレスチェックの高ストレス者がいないことはあくまで一つの指標であり、「問題がない証拠」ではないのです。
数値に安心するのではなく、職場の空気感や変化の兆しを見極める視点が欠かせないと言えるでしょう。
なぜゆるブラック環境が生まれるのか?
ゆるブラックな職場環境は、企業側が意図せずに作り出していることも少なくありません。
たとえば、年功序列や指示待ち文化が根強く残っている職場では、挑戦や成長の機会が限られます。また、若手や中堅従業員の意見が上層部に届きにくい組織構造では、現場の課題が放置されがちです。
さらに、評価制度が形だけになっていると、努力や成果が正当に報われず、従業員の意欲が失われていきます。
年功序列・指示待ち文化の温存
ゆるブラックな職場環境が生まれる背景には、年功序列や指示待ち文化の温存が大きく関わっています。
年功序列が根強い職場では、年齢や勤続年数が重視され、若手や成果を上げた従業員の努力が正当に評価されにくくなります。また、指示を待つことが当たり前の文化があると、従業員が自ら考えて動く機会が減り、やりがいや成長実感が得られにくくなります。
さらに、上層部の顔色をうかがうような空気が強まると、職場には「とりあえず何も言わずに従う」ことが正解とされる風潮が広がり、挑戦や改善の意欲も失われがちです。
そして、こうした状態が続くと、表面上は問題が見えにくくても、内側では活力が失われていき、結果として、静かに離職や無気力が広がる、ゆるブラック環境が形成されてしまうのです。
若手や中堅層の意見が埋もれる構造
若手や中堅従業員の意見が埋もれてしまう組織構造も、ゆるブラックな環境が生まれる要因のひとつです。
上層部の意見が強く、現場の声が届きにくい職場では、実際の課題や改善のヒントが無視されやすく、従業員は「どうせ言っても変わらない」と感じるようになります。その結果、自発的な発言や提案は減り、職場全体に無関心やあきらめの空気が広がっていきます。
また、意思決定が一部の限られた層に集中していると、多様な視点が失われ、変化や成長のきっかけも生まれにくくなります。若手や中堅が安心して声を上げられない職場では、表面的には落ち着いて見えても、内側では活力が失われていき、結果としてゆるブラックな状態が定着してしまいます。
評価制度が形骸化している
従業員の成果や努力が正当に評価されない職場では、「頑張っても報われない」という意識が広がり、次第にやる気や向上心が失われていきます。特に、評価基準が曖昧だったり、年功や在籍年数が重視されていたりすると、若手や成果を出している従業員ほど不満を抱きやすくなります。
また、フィードバックが形式的で形だけの面談に終始していると、従業員は自分の成長や課題を実感できず、仕事に対する目的意識を持てなくなります。
こうした環境では、不満の声が上がることも少なく、外からは問題が見えづらいため、人事や管理職が変化に気づきにくいのも特徴です。
人事がやりがちなNG対応
ゆるブラックな環境が続く背景には、人事担当者の対応が原因となっていることもあります。
特に多いのが、「数字に問題がないから大丈夫」と判断してしまうことです。残業時間やストレスチェックの結果に異常がなければ安心してしまい、職場に漂う無気力感や閉塞感に目を向けなくなります。また、形だけの1on1やヒアリングでは従業員の本音を聞き出せるものではないですし、「働きやすさ=満足度」と捉えて制度面だけを整えて終わりにしてしまうのもNGです。従業員の成長実感ややりがい、組織の活力といった“見えにくい部分”にこそ丁寧なアプローチが必要です。
また、人事が「問題が起きてから動く」スタンスでいると、静かに進行するゆるブラックの兆候を見逃してしまい、離職やパフォーマンス低下につながるリスクがあります。
ゆるブラックを防ぐ!人事ができる5つのこと
ゆるブラックな職場を未然に防ぐためには、人事の積極的な介入と継続的な改善が欠かせません。
まず有効なのが、ストレスチェックの集団分析を活用することです。集団分析を行なえば、数値に表れにくい職場の空気や課題を客観的に把握できます。
そして、その結果をもとに「仮説→実行→検証」のサイクルで改善施策を回し、継続的に検証します。定量的なデータに加えて、1on1や現場ヒアリングなど定性的な情報も組み合わせるのも、職場のリアルな空気感をつかむためには重要です。また、管理職へのマネジメント研修を通じて心理的安全性を高めることも、ゆるブラック防止に効果的です。
ストレスチェックの集団分析を活かす
ゆるブラックを防ぐために、人事がまず取り組むべきなのが、ストレスチェックの集団分析を活用することです。
ストレスチェックを、年1回、形式的に実施して終わらせるのではなく、結果をていねいに読み解くことで、職場ごとの傾向や見えにくいリスクを把握できます。
表面上は高ストレス者がいなくても、「活気がない」「職務満足度が低い」といった兆候が集団分析で見えてくることがあります。部署間で結果を比較することで、どこに課題があるのかが浮かび上がり、ピンポイントで対策を立てやすくなります。
また、数値の背後にある背景を探ることで、漠然とした不安や不満がどこから来ているのかを探るきっかけにもなります。集団分析は、数値で“空気”を可視化する有効な手段です。
集団分析結果をもとに、施策を「仮説→実行→検証」で回す
ストレスチェックで集団分析を行なったら、施策を立てて実行・検証まで行うサイクルを回すことが大切です。
「職場の活気が低い」という結果が出た場合であれば、その原因を仮説として立て、1on1の頻度を増やす、チームミーティングの形式を変えるなど具体的な施策を試してみます。そして、その後の変化を再度集団分析で確認することで、施策の効果や次の課題が見えてきます。
この「仮説→実行→検証」の繰り返しが、職場の空気の改善に直結し、ゆるブラック化を防ぐ大きな手がかりになります。
ストレスチェックの結果を「職場をより良くするヒントの宝庫」と捉え、継続的な改善に活かすことが人事の重要な役割です。
定量+定性で“今の空気感”を掴む
ゆるブラックを防ぐには、職場の“今の空気感”を正しくつかむことが重要です。
そのためには、ストレスチェックや離職率といった定量データだけでなく、現場の声や日常の雰囲気といった定性的な情報もあわせて見ることが欠かせません。
数値に表れない違和感や不満、無気力といった兆候は、1on1やアンケート、ちょっとした雑談などから見えてくることもあります。
ストレスチェックで問題がないように見えても、面談では「やりがいがない」「先が見えない」といった声が上がることがあります。こうした“ズレ”に気づけるかどうかも、人事としての大切な視点です。
管理職へのマネジメント研修/心理的安全性の構築
現場の管理職のマネジメント力を高めることも重要です。
たとえば、心理的安全性の高い職場づくりを支えるマネジメント研修の導入です。
心理的安全性とは、従業員が「失敗しても叱責されない」「意見を出しても否定されない」と感じられる状態のことです。この心理的安全性が担保されていないと、従業員は本音を言いづらくなり、課題や不満が表面化せず、やがて静かな離職や無気力につながっていきます。
管理職が日常のコミュニケーションの中で信頼関係を築けるように、傾聴力やフィードバックのスキルを学ぶ場を提供し、現場リーダーの意識改革と実践力を向上させることは、ゆるブラックの予防に直結します。
「評価・育成・キャリア支援」の制度をセットで見直す
評価・育成・キャリア支援といった人事制度を「個別ではなく、連動した仕組み」として見直すことも重要です。
成果に対する評価制度が不明瞭なままでは、育成やキャリア支援の意義も伝わりにくく、社員の成長意欲は鈍ってしまいます。逆に、評価・育成・キャリア支援が連動していれば、社員は「自分の努力がどう評価され、どのようなキャリアに結びつくのか」を明確にイメージできるようになります。
また、キャリアの方向性やスキルアップの機会が可視化されることで、やりがいや定着率の向上にもつながります。
制度として形だけ整っていても、現場で実感できなければ意味がありませんから、制度のつながりと実効性を再確認しながら、社員の期待に応えられる環境づくりが求められます。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。
まとめ
ゆるブラックという状態に早期に気づくには、ストレスチェック後のていねいな分析と対応が鍵になります。
ストレスチェッカーは、日本最大級のストレスチェックツールです。
部署ごとのストレス傾向や、不調が出やすい要因の把握も可能です。「上司との関係性」「業務負荷の偏り」「職場の一体感の欠如」など、定性的に把握しづらい要素も浮き彫りになり、職場改善に向けた具体的なヒントが得られます。
2025年5月からは、無料プランおよびWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調や心理的負荷による生産性の低下)」の測定が可能になり、本人がまだ自覚していない疲労感やモチベーションの低下といった変化も数値として可視化でき、問題が深刻化する前に対策を講じるきっかけが得られます。
ぜひ、ストレスチェックを“実施して終わり”にせず、実際に“活かす”体制をつくる第一歩するためにも、ストレスチェッカーにぜひ一度ご相談ください。
:参照記事
>上司ガチャとは?ストレスにどう気づく?

