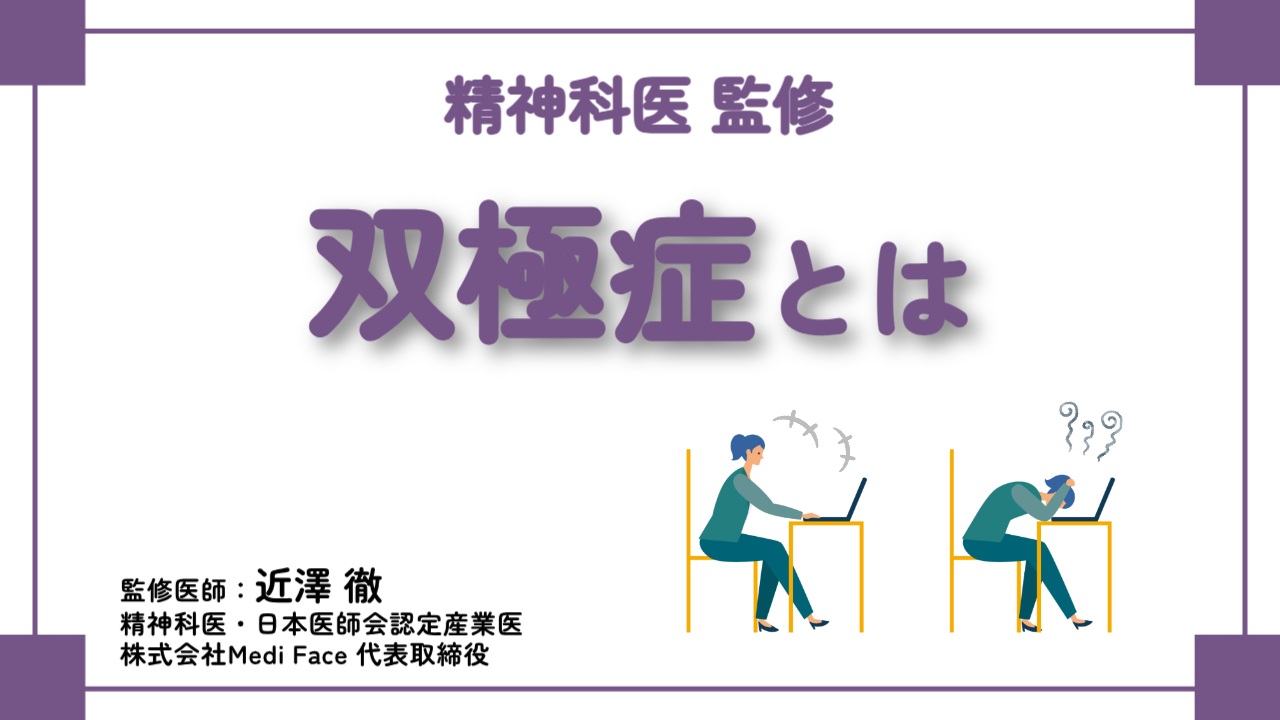
双極症(双極性障害)は、もともと「躁うつ病」と呼ばれていて、昔は統合失調症とともに精神科の二大疾患といわれており、精神疾患の中では代表的な病気のひとつです。
双極症のある方がいる職場では、症状の波を理解し、無理なプレッシャーをかけないことが大切です。体調の変化に応じた柔軟な勤務調整や、本人が安心して相談できる環境づくりが求められます。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
双極症(双極性障害)とは
双極症(双極性障害)は、躁状態とうつ状態という両極の気分状態を繰り返す精神疾患です。
躁とうつが混ざった「混合状態」が起こったり、うつ状態から躁状態へ、躁状態からうつ状態へ急激に移り変わる「躁転・うつ転」が起こったり、カタトニアなどが現れることもあります。
双極症にはⅠ型とⅡ型の2つのタイプがあり、どちらも共通してうつ状態が現れますが、躁の程度に違いがあります。入院が必要なほどの強い躁状態を伴うのがⅠ型、そこまで強くない軽躁状態が続くのがⅡ型です。軽躁は、本人も周囲も単なる「元気な状態」と誤解しやすく、発見が遅れたり再発につながってしまったりすることもあります。
なお、「双極性障害」と「双極症」は基本的に同じ病気を指しますが、「障害」という言葉がハンディキャップという意味を持つことから、「双極症」と呼ばれることになりました。
これは、WHO(世界保健機関)の国際疾病分類の改訂版「ICD-11」の変更に伴うものです。
躁状態の時の特徴
双極症の「躁状態」になると、気分が異常に高ぶり、「自分は何でもできる」といった万能感に包まれます。エネルギーに満ちあふれ、休むことなく動き続け、睡眠さえも必要としないかのように行動が加速します。このような状態では判断力が鈍ることも多く、過剰な買い物や借金、思いがけない暴言や衝動的な行動に至ることも少なくありません。また、躁状態が激しくなるほど、反動としてのうつ状態も深刻になりやすく、その落差が心身に大きな負担をもたらします。うつ状態の時期には、躁状態での自身の言動を思い出して深く後悔したり、自責の念に苦しめられたりすることもあります。双極症は気分の波が激しく、本人も周囲も戸惑うことが多いため、早期の治療と理解あるサポートが重要です。
うつ状態の時の特徴
双極症の「うつ状態」のときは、心も体もすっかりエネルギーを失ったような感覚になります。これまで楽しめていたことに対してもまったく関心が持てなくなり、何をしても気分が晴れません。良いことがあってもポジティブに受け取ることができず、日常の小さな出来事すら重く感じられます。自分を過剰に責める思考にとらわれ、眠れなくなったり、逆に長時間眠り続けたりといった睡眠の乱れも現れます。中には体が鉛のように重く感じられて、布団から起き上がることができないという人もいます。また、双極症のうつ状態では、一般的なうつ病よりも動きが極端に遅くなる傾向があるとも言われています。思考力や判断力も低下し、日常生活に支障をきたすことが多く、妄想や幻聴といった精神症状が加わる場合もあります。これらの症状は本人の努力ではどうにもならないものであり、周囲の理解と早めの治療が重要です。
双極症のうつ状態は、一般的に言われる「うつ病」と比べると、動作がゆっくりになることも多いと言われます。
躁とうつが入り混じる「混合状態」
混合状態とは、通常の躁状態とうつ状態とは異なり、躁状態にうつ状態が混ざっていたり、うつ状態に躁状態が混ざっていたりする状態です。
躁状態で活動的になっているけれど気分的にはうつであったり、うつ状態で気分が落ち込んでいるのに、動き回ってしまったりします。
この混合状態が一番つらいという患者さんも多く、自殺のリスクが高まるとも言われているので、特に注意が必要です。
妄想が現れることも
双極症は、妄想や幻聴を伴うことがあります。
事実とは異なることを事実と思い込み「自分は神の生まれ変わりだ」「重要人物だから、暗殺者に狙われている」などと思い込んでしまいます。
妄想や幻聴によって現実との境界があいまいになり、日常生活に支障が出ることも少なくありません。家族や周囲の人が異変に気づき、早めに医療機関へ相談することが大切です。
一時的な興奮・昏迷(カタトニア)
双極症の症状が重くなると、一時的に興奮や昏迷を生じる「カタトニア」と呼ばれる症状がみられることがあります。
昏迷では、意識は保たれているものの外部からの刺激に反応せず、自らの意思を示しません。
また、自らの医師が極端に低下してしまい同じ姿勢を取り続ける「カタレプシー」という症状が現れることもあります。
話しかけても言葉を発しなかったり、態度や行動で拒絶を示したりすることもあります。
さらに、「反響動作」や「反響言語」といった症状が現れる場合もあります。これは、相手が手を上げると同じように手を上げ、「どうしたの?」と声をかけると「どうしたの?」とそのまま返すように、相手の行動や言葉をそのまま真似てしまう状態です。これらの症状は、周囲の人が見ると驚くような反応かもしれませんが、カタトニアには薬による治療法が確立されており、比較的回復もしやすいため、早めの受診が重要です。
病相の間隔が短くなることも
病相の間隔がどんどん短くなってしまうことを「急速交代型(ラピットサイクラー)」といいます。
「双極症を発症したときから急速交代型であるタイプ」と、「途中から急速交代型になるタイプ」がありますが、8割以上が「途中から急速交代型になるタイプ」です。
急速交代型になると、ストレスとは関係なく再発するようになってしまいます。めまぐるしく気分が変わり、本人はもちろん、周囲の人や家族にとっても大きな負担となってしまいます。
双極症と区別しにくい「うつ病」
双極症と見分けがつきにくいうつ病も存在します。うつ病にはさまざまなタイプがあり、双極症と似たような症状を示すものも少なくありません。
・メランコリー型うつ病
もっとも一般的なタイプとされる「メランコリー型うつ病」は、几帳面で責任感の強い性格の方が、真面目に仕事や役割をこなそうとするあまり、心身のバランスを崩してしまうケースが多くみられます。日々の義務感に押しつぶされてしまうような形で発症する傾向があります。
・否定型うつ病
「否定型うつ病」は、メランコリー型とは異なり、楽しいことがあると一時的に気分が持ち直すという特徴があります。過眠や過食になりやすく、周囲の人の言動に対して強く反応してしまうこともあります。このタイプは、幼い頃の愛着の問題やトラウマ体験が関係しているのではないかと指摘されています。
・双極スペクトラムうつ病
現在はうつ病と診断されているものの、今後、軽い躁状態や躁状態があらわれ、将来的に双極症と診断が変わる可能性のあるケースです。診断基準であるDSM-5には正式には含まれていませんが、家族に双極症の方がいる場合や、抗うつ薬が効きにくい場合などには、双極症になるリスクが高まると考えられています。
・季節性うつ病
「季節性うつ病」は、特に秋から冬にかけて気分が落ち込み、意欲が低下するなどの症状が強くあらわれるタイプで、季節の変化に合わせて毎年繰り返す傾向があります。
双極症(双極性障害)の治療法
双極症の治療の中心となるのは薬物療法で、主に気分安定薬や抗精神病薬が使われます。これらの薬は躁状態やうつ状態の再発を予防し、症状の安定を図るために継続的に使用されます。
場合によっては、うつ状態が強い時に抗うつ薬が用いられることもありますが、躁転(躁状態への切り替わり)のリスクがあるため、慎重に使用されます。
認知行動療法(CBT)は、再発予防や日常生活の安定をサポートする心理的アプローチとして有効です。
「認知」とは、物事の受け取り方や考え方のことで、偏った思考パターンを自覚して、客観的で合理的な考え方に修正していく方法です。
患者が自分の気分の変化に気づきやすくなり、過度なストレスや不安、行動パターンに対応できるようになります。また、生活リズムの安定や人間関係の改善にもつながります。薬物療法と併用することで、より安定した日常生活の維持が期待できます。
双極症(双極性障害)とストレスチェック
双極症(双極性障害)は、ストレスチェックで診断することはできません。しかし、自分がどのような状況でストレスを感じやすいか、気分の変化に気づくきっかけとしては有効です。ストレスチェックの結果をきっかけに、早めに専門機関へ相談することが大切です。
本質的な判断には使えない
ストレスチェックは、職場などで心の状態を把握するためのツールとして活用されますが、双極症(双極性障害)のような気分障害を正確に判断するためのツールではありません。質問項目はうつ状態に関する内容が中心であり、双極症に特徴的な躁状態を見落とす可能性があります。そのため、ストレスチェックの結果だけで双極症の有無を判断するのは不十分であり、あくまで自分のストレスの傾向に気づくきっかけとして利用するものと捉えるべきです。
専門医の診断が重要
双極症は、うつ状態と躁状態が周期的に現れる疾患であり、診断には経過やエピソードの把握が欠かせません。うつ病と誤診されやすく、適切な治療につながらないケースも少なくありません。そのため、ストレスチェックや自己判断に頼るのではなく、精神科や心療内科などの専門医による診察を受けることが重要です。
専門医は問診や生活状況のヒアリングを通して、正確な診断と治療方針を立て、必要に応じて薬物療法や心理的支援を行います。早期の受診が回復への第一歩となります。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
双極性障害(双極症)は、躁状態とうつ状態を繰り返す精神疾患です。躁状態では気分が高ぶり活動的になりますが、うつ状態では気分が沈み込み、無気力な状態が続くことがあります。この疾患は、かつては「躁うつ病」と呼ばれていましたが、現在では「双極性障害」あるいは「双極症」という呼び方が一般的になっています。
ストレスチェック制度は、本人では気づきにくい疲労感や不安のサインを見つけるための手がかりとなるツールです。定期的にストレスチェックを行い、その結果をもとに面談やサポートの機会を設けることで、職場での精神的な負担にいち早く気づき、適切な支援につなげやすくなります。ただし、ストレスチェックの結果だけで双極症の有無を判断することはできません。あくまでも、自分のストレスの傾向に気づくための参考として活用することが大切です。
「ストレスチェッカー」は、官公庁や上場企業、大学、大規模病院など、さまざまな組織で導入されている国内最大級のストレスチェックツールです。受検画面やメール文面のカスタマイズ、未受検者への自動リマインド、リアルタイムでの進捗管理、医師面接希望の収集など、実際の運用に応じた柔軟な対応が可能です。2025年5月からは、無料プランおよびWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調や心理的な負担によってパフォーマンスが低下している状態)」の測定に対応しました。これにより、自覚のない疲れや気力の低下も数値として可視化できます。導入をご検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>燃え尽き症候群とは?精神科医が解説

