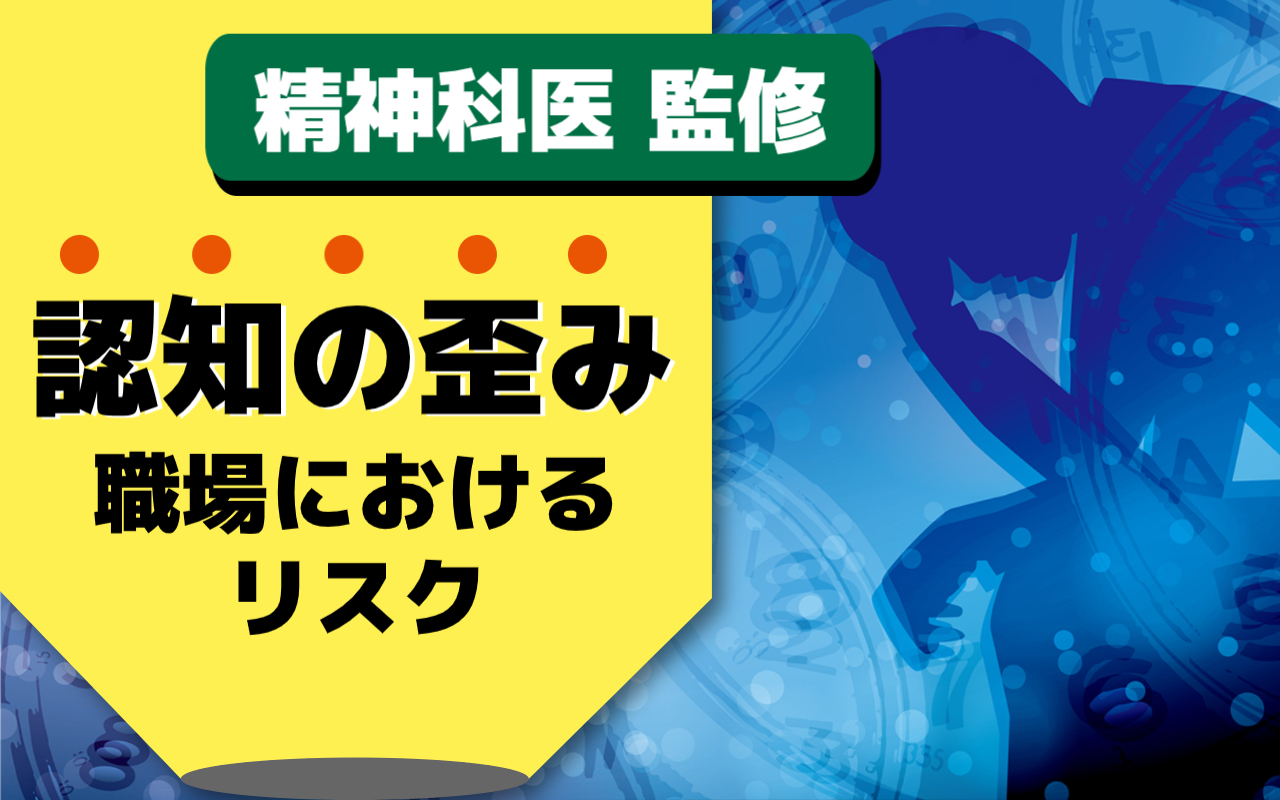
「認知の歪み」とは、物事の受け取り方や考え方が偏ってしまい、現実を正確に捉えられなくなる心理的傾向を指します。
たとえば、上司の指摘を「自分は全てダメだ」と極端に受け止めてしまったり、周囲の反応を過剰に気にして不安を抱いてしまったりといったケースなどです。
本記事では、認知の歪みの具体例とそのメカニズム、さらに職場でのリスクや対応のポイントについて、専門的な視点から分かりやすく解説します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
認知の歪みとは
「認知の歪み」とは、物事の捉え方や判断の仕方が偏り、現実を正確に見ることが難しくなる心理的な傾向のことを指します。誰にでも起こりうる自然な思考のクセですし一時的であれば問題ありませんが、慢性的になるとストレスや不安、職場での人間関係トラブル、モチベーション低下などを引き起こすことがあります。認知の歪みを理解し、自身や組織内で意識的に修正していくことは、メンタルヘルスの維持と健全な職場づくりの第一歩といえます。
認知の歪みの原因
認知の歪みは、過去の経験や思考習慣、信念、ストレスなど、さまざまな要因によって形成されます。幼少期に否定的な言葉を受けたり、認められない経験をしたりしたことが、ネガティブな思考の基盤となることがあります。
また、物事を自動的に否定的に捉える「思考の癖」や、「完璧でなければ価値がない」といった極端な信念(スキーマ)も、歪んだ認知を固定化させます。
さらに、強いストレス下では物事を悲観的に解釈しやすくなり、体調不良や知識不足、先入観なども判断を歪める要因となります。場合によっては、人格特性や精神的疾患が背景にあるケースもあります。
認知の歪み一覧
認知の歪みの代表的なパターンとしては、たとえば「全か無か思考(物事を白黒でしか判断できない)」「過度の一般化(1度の失敗をすべてに当てはめてしまう)」などが挙げられます。
これらは、無意識のうちに現実の見え方をゆがめ、ストレスや人間関係のトラブルを引き起こす原因になります。認知の歪みは誰にでも起こる自然な心理現象ですが、放置すると職場でのモチベーション低下や誤解の連鎖を招くこともあるため、まずは自分や他者の思考の傾向を客観的に理解することが大切です。
白黒思考
「白黒思考」とは、物事を極端に「良い・悪い」「成功・失敗」といった二択で捉えてしまうケースです。中間的な状況や多様な視点を受け入れられず、「少しでも間違えたら全てダメ」と考えてしまう傾向があります。
完璧主義や自己否定につながりやすく、職場では小さなミスを過度に恐れたり、他者に対しても厳しい評価を下してしまったりする原因になります。
過度の一般化
「過度の一般化」とは、ひとつの出来事や限られた経験を、すべての状況に当てはめて考えてしまう認知の歪みの一つです。たとえば、一度の失敗を「自分は何をやってもダメだ」と決めつけたり、特定の従業員とのトラブルを「職場の人間関係はすべて悪い」と感じてしまったりするような思考です。
このような思い込みは、自己評価の低下や他者への不信感を招きやすく、職場では挑戦意欲の減退やコミュニケーションの停滞につながる可能性があります。
心のフィルター
「心のフィルター」とは、物事を偏った視点で見てしまう認知の歪みの一つです。ポジティブな評価や成果があっても、それを無視して些細なミスや否定的な出来事ばかりに注目しがちです。その結果、全体像を正しく把握できず、自己評価が不当に下がったり、職場の人間関係を悪く捉えてしまったりします。
たとえば、上司から「全体的によくできていたが、ここだけ直そう」と言われた際に「注意された=評価されていない」と感じてしまったり、会議で一度意見が採用されなかっただけで「自分の意見は無価値だ」と思い込んでしまったりします。
否定的な予測
「否定的な予測」とは、明確な根拠がないにもかかわらず、将来の出来事を悲観的に決めつけてしまう認知の歪みの一つです。
たとえば、「次のプレゼンはきっと失敗する」「新しい業務でもミスをするだろう」「相手から連絡がないのは嫌われたに違いない」といった思考が典型例です。
このような傾向のある人は、「いつも」「絶対」「必ず」といった極端な表現を使いやすく、感情をそのまま事実とみなしがちです。結果として、挑戦意欲の低下や不安の増大を招き、職場では本来のパフォーマンスを発揮しにくくなります。
感情的決めつけ
「感情的決めつけ」とは、自分の感情を事実と混同してしまい、自分が感じたことを根拠がないのに「感じたこと=現実」として判断してしまう認知の歪みの一つです。
たとえば、「気分が悪いから、今日は何もできない」「あの人のことが好きになれないから、きっと悪い人に違いない」「自己嫌悪を感じるから、自分なんていない方がいい」といった思考です。
このような思い込みは、感情に行動を支配されやすくし、客観的な判断を妨げます。職場では、人間関係の誤解や自己評価の低下、パフォーマンスの不安定化を招く要因にもなります。
レッテル貼り
「レッテル貼り」とは、自分や他者を一つの出来事や特徴だけで否定的に決めつけてしまう認知の歪みの一つです。
たとえば、一度の失敗で「自分は無能だ」と思い込んだり、相手の小さなミスを見て「あの人は信用できない」と判断してしまったりするケースです。
この思考パターンは、限られた情報で全体を判断し、他のポジティブな側面を見落とす傾向があります。職場では、自己評価の低下や人間関係の悪化、チーム内の不信感を生みやすく、協働や成長の妨げになることがあります。
べき思考
「べき思考」とは、「~すべき」「~してはいけない」といった強い義務感にとらわれる認知の歪みです。「べき思考」は、自分や他者に対して過度に厳しい基準を設け、柔軟な対応を難しくします。
たとえば、「上司は常に完璧であるべき」「部下は自分の意図を理解すべき」といった考えが強いと、理想と現実のギャップに苦しみ、苛立ちや失望を感じやすくなります。
拡大解釈と過小評価
「拡大解釈と過小評価」とは、失敗や短所を実際以上に大きく捉え、成功や長所を過小に評価してしまう認知の歪みの一つです。
拡大解釈では失敗を誇張し、自信を失いやすく、過小評価では努力や結果を認めずに自己価値を低く見積もる傾向があります。
たとえば、ちょっとしたミスを「致命的な失敗だ」と感じたり、大きな成果を「たまたま上手くいっただけ」と軽視したりするような思考がこれにあたります。
多くの場合、両者はセットで現れ、自己肯定感の低下を招きます。特に、真面目で責任感の強い人ほどこの傾向が強く、慢性的なストレスや燃え尽きにつながることもあります。
パーソナライゼーション
「パーソナライゼーション」とは、自分に直接関係のない出来事を、あたかも自分のせいや自分に向けられたもののように受け取ってしまう認知の歪みの一つです。他人の感情や行動を過剰に自分と結びつけるため、不必要な罪悪感や不安を抱えやすくなります。
たとえば、同僚が不機嫌な様子を見て「自分が何か悪いことをしたのかもしれない」と感じたり、他人が笑っているのを見て「自分のことを笑っているのでは」と思い込んでしまったりするケースが典型です。
職場では、誤解や対人ストレスを生み、人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。状況を客観的に捉え、「他の可能性もある」と視点を広げることが、パーソナライゼーションを緩和する鍵となります。
職場における認知の歪みのリスク
職場における認知の歪みは、コミュニケーションの誤解やチームワークの低下、ストレス増大など、組織全体に悪影響を及ぼすリスクがあります。
たとえば、上司の指摘を「自分は無能だ」と極端に受け止めたり、同僚の反応を過度に気にして不安を抱いたりしてしまえば、生産性や集中力が低下します。
また、他者へのレッテル貼りや「~すべき」という思考が強いと、相互理解が損なわれ、対人関係の摩擦を生みやすくなります。さらに、こうした歪んだ思考が蓄積すると、離職やメンタル不調といった深刻な問題につながることもあります。
対人関係の悪化
職場における認知の歪みは、特に人間関係の悪化を招きやすいリスクを含んでいます。
たとえば、ある従業員は上司から「ここをもう少し工夫すると良くなるね」と言われただけで、「自分は全く評価されていない」と極端に受け止めてしまいました。実際には改善を促す前向きなフィードバックだったにもかかわらず、「指摘=否定」と捉え、以降は上司との会話を避けるようになってしまったのです。
また、別の事例では、同僚が忙しそうにしているのを見て「自分が仕事を増やしてしまったのでは」と思い込み、声をかけづらくなった従業員がいました。実際には同僚が別の案件に集中していただけなのに、誤った思い込みが関係をぎくしゃくさせたケースです。
さらに、「部下は指示通り動くべき」と考える上司の場合、部下の自主的な意見を受け入れられず、衝突や不満を生むこともあります。
このように、認知の歪みは小さな誤解から信頼を損ね、チーム全体の協力関係や職場の雰囲気を悪化させる要因になります。
うつなどのメンタル不調
職場における認知の歪みは、うつ病などのメンタル不調を引き起こす大きな要因となることがあります。
たとえばある従業員は、上司から軽い注意を受けただけで「自分はもう信頼されていない」「この職場に自分の居場所はない」と感じてしまい、メンタルヘルス不調から休職につながってしまったケースがありました。
また、「完璧に仕事をこなすべき」「ミスしてはならない」といった「べき思考」を強く持つ人ほど、自分を追い込みやすく、達成感を感じにくい傾向があります。
結果として慢性的な疲労感や無力感が積み重なり、うつ症状へ発展するリスクが高まります。認知の歪みは本人に自覚がないまま進行することも多いため、周囲が変化に気づき、早めに声をかけることが重要です。
行動上の混乱
職場における認知の歪みは、思考だけでなく行動にも影響を及ぼし、混乱や非効率を生む原因となります。
たとえば、ある従業員が会議で意見を否定された際に「自分の発言はいつも間違っている」と過度に一般化し、その後は発言を控えるようになってしまうケースがありました。このような思考の偏りは、チームの意見交換を阻害し、職場全体の生産性低下につながります。
また、「上司に認められなければ意味がない」「失敗してはいけない」といった「べき思考」が強い人は、慎重になりすぎて行動が遅れる傾向があります。逆に、感情的決めつけによって「どうせ努力しても無駄だ」と投げやりな態度をとることもあり、いずれも本来の判断力や行動力を失わせる結果となります。
さらに、パーソナライゼーションの影響で、他人の言動を過剰に気にし、確認や謝罪を繰り返すことで業務が停滞することもあります。
ストレスチェックの活用
職場における認知の歪みは、ストレスの蓄積や人間関係の悪化、業務パフォーマンスの低下につながる要因の一つです。こうした思考の偏りを早期に把握するためには、従業員の心理的状態を定期的に可視化できる仕組みが有効です。
ストレスチェックは、その一助として従業員のストレス度や職場環境の問題点を客観的に把握する手段となります。結果を分析し、特定部署や個人の傾向を把握することで、認知の歪みが生じやすい状況を予防・改善できます。組織として心理的安全性を高めることが、健全な職場運営につながります。
認知の歪みへの気づき
ストレスチェックは、従業員が自身のストレス状態を客観的に把握するだけでなく、認知の歪みに気づくきっかけとしても有効です。
多くの場合、認知の歪みは本人が自覚しにくく、無意識のうちに思考の偏りが定着しています。ストレスチェックの結果を通して、特定の状況で強いストレスを感じやすい傾向や、特定の人間関係で過剰に反応している傾向が明らかになると、自身の思考パターンを見直す手がかりになります。
たとえば、ネガティブな評価を過大に受け止めていないか、他者の言動を自分に結びつけすぎていないかを振り返ることができます。こうした“気づき”は、メンタル不調の早期予防や、より柔軟な思考を身につける第一歩となります。
適切な治療へつながる
ストレスチェックの結果から高ストレス者が抽出された場合、産業医などの専門職が面談を行うことで、適切な治療や支援につなげることができます。面談では、単にストレスの有無を確認するだけでなく、本人の認知の歪みや思考の偏りが、どのようにストレス反応や行動に影響しているかをていねいに把握します。
たとえば、「自分は役に立たない」「失敗してはいけない」といった極端な思考を抱えている場合、産業医が早期に気づき、必要に応じて精神科や心療内科などの医療機関への受診を勧めることが可能です。
また、職場環境の改善が必要な場合には、管理職等に対して具体的な助言を行い、再発防止策を講じることができます。
認知の歪みの治療法
認知の歪みの治療法として広く用いられているのが、「認知行動療法(CBT)」です。これは、自動的に浮かぶ否定的な考え方や思い込みを客観的に見直し、現実的で柔軟な思考に修正していく心理療法です。
たとえば、「自分は失敗ばかりしている」と感じた場合、実際の事実を整理し、「うまくいった事例もある」と捉え直す練習を行います。このプロセスを繰り返すことで、思考の偏りが緩和され、ストレス反応が軽減されます。
また、産業医や臨床心理士による面談を通じて、個々の認知の歪みの傾向を把握し、必要に応じて専門的な医療機関への紹介やカウンセリングを行うこともあります。
ストレスチェックで高ストレスが判明した場合、早期に面談や治療につなげることで、うつ病や不安障害といった深刻な状態に進行するのを防ぐことができます。認知の歪みの修正は、個人のメンタルケアだけでなく、職場全体の健全性向上にも寄与します。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
職場における認知の歪みは、ストレスや人間関係の悪化、業務パフォーマンスの低下などにつながる要因の一つです。ストレスチェックを活用することで、従業員の心理的負担や思考の偏りに早期に気づき、適切なサポートにつなげることが可能になります。結果をもとに産業医面談を実施すれば、必要に応じて専門的な治療や環境改善へとつなげることもできます。定期的なストレスチェックは、従業員一人ひとりの気づきを促すとともに、企業全体のメンタルヘルス対策を体系的に進めるための有効な手段といえるでしょう。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、幅広い現場で活用されてきた信頼と実績を持つツールです。未受検者への自動リマインドやリアルタイムでの進捗確認、医師面接希望者の収集など、実務に直結する機能を標準搭載。2025年5月からは、無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能になります。
欠勤や離職といった深刻な事態に至る前に、ストレスや認知の歪みの兆候を早期に把握し、適切な支援や治療につなげることができます。ぜひお気軽にご相談ください。
:参照記事
>ストレスチェックサービスおすすめ22選

