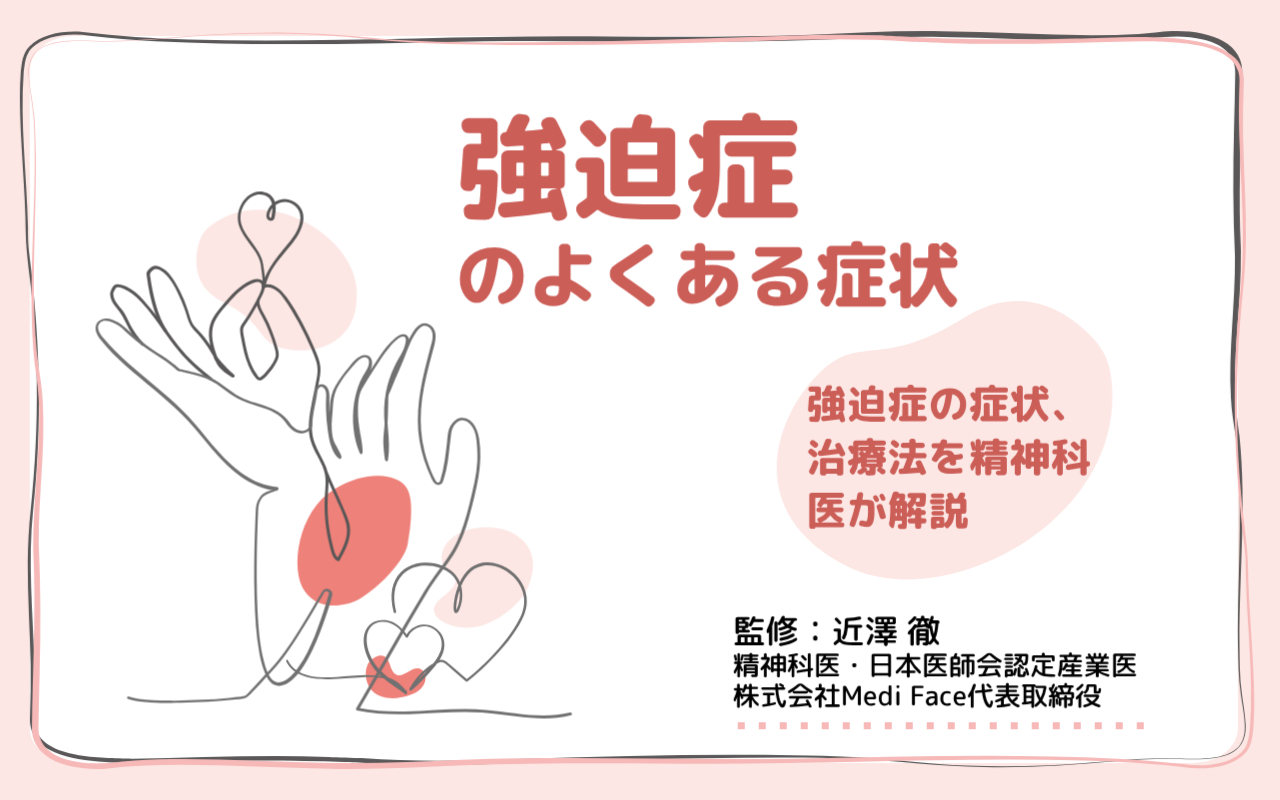
強迫症(OCD:強迫性障害)とは、「手が汚れている気がする」「鍵をかけ忘れたかもしれない」といった嫌な考えやイメージが浮かんでしまい、「何度も手を洗う」「戸締まりを何回も確認する」といった行動を抑えられなくなる病気です。本人もその行為の過剰さを自覚していることが多いですが、不安を抑えるためにやめられず、日常生活に支障をきたすケースも多々あります。
強迫症のある人には、確認作業が多い業務では不安が強まりやすいため、作業工程を明確にし、チェックリストを用意するなどの工夫が有効です。また、突発的な指示や急な変更が負担となることがあるため、業務の見通しを持てるよう配慮し、安心して相談できる雰囲気づくりも重要です。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
強迫症とは
強迫症とは、「強迫観念」と「強迫行為」を繰り返す精神疾患です。
強迫観念とは、頭から離れない不安な考えやイメージのことで、「手が汚れている気がする」「鍵をかけ忘れたかもしれない」といった思いが代表的です。一方、強迫行為はその不安を打ち消すための行動で、何度も手を洗う、戸締まりを何回も確認するといった行動が見られます。
多くの場合「強迫行為をやめたいけれど、強迫観念によって生じた苦痛を和らげるためには強迫行為をするしかない」と感じています。
原因は脳内の神経伝達物質の不均衡やストレスなどが関係しているとされ、遺伝的な要因も一部考えられています。治療には、認知行動療法(とくに暴露反応妨害法)や薬物療法(SSRIなど)が効果的とされています。
洗浄強迫
洗浄強迫とは、手洗いや入浴、物の消毒などの「洗浄行為」がやめられなくなる強迫症のタイプです。ばい菌や外の汚れ、感染症、洗剤そのものに強い不安や嫌悪感を抱き、1回の手洗いに30分以上かけるケースもあります。
また、外出先でトイレを使用することに強い抵抗を感じるため、トイレに行かずに済む範囲でしか行動できなくなるなど、日常生活に大きな支障をきたします。
単なる衛生観念の問題ではなく、心理的な嫌悪感や不安によって「汚れている」という感覚が強まることがあり、道徳的に否定的な感情を持つ相手に対して「汚れている」と感じたり、自分が他人を汚染させてしまうという強い思い込みを持ったりする場合もあります。
確認強迫
確認強迫とは、何かを「確認する」ことを繰り返してしまうタイプの強迫症です。「鍵をちゃんと閉めたか」「ガスの元栓を切ったか」といった不安から、何度もチェックを繰り返してしまうこともあります。
本人にとって確認行為は安心を得るための手段でありながら、実際には不安を強めてしまうという悪循環に陥るケースが多く見られます。
たとえば、「確認したからこそ、問題を回避できた」という強い感覚を持っていて、「火の元を3回確認したから火事にならなかった」と考え、本来1回で十分な場面でも、複数回確認しないと安心できない状態になってしまいます。
しかしこの「安心のための確認」が日を追うごとにエスカレートすると、かえって確認せずにはいられないという不安のサイクルに巻き込まれ、確認行為そのものが、かえって不安を強化する原因になってしまいます。
「なぜ確認するのか」「なにを確認するのか」は人によって異なり、「確認強迫=鍵や火の元の確認」という単純な図式では収まりません。たとえば、洗浄強迫に含まれるケースとして、机の上にあるものを何度も確認して「自分に汚れがつかなかったかどうか」を気にする人もいます。また、自分の発言を繰り返し振り返って「変なことを言わなかったか」「誰かを傷つけていないか」と確認することもあります。
整理整頓型強迫
整理整頓型強迫は、物の配置や向きが自分の中の「こうあるべき」に合っていないと、不快感やイライラ、モヤモヤが生まれます。たとえば蛇口を強く閉めないと落ち着かずに何度も締め直してしまったり、家具や小物を左右対称に並べないと気になって仕方がなかったりします。
スマートフォンのアプリの並び順にもこだわり、少しでもズレがあると再配置する人もいます。
また、文章を読んでいる際に同じ行を何度も読み返してしまったり、自分で書いた文章を何度も消して書き直したりするなど、繰り返し行動が目立ちます。顔を洗う、歯を磨く、スイッチを押すといった日常の簡単な動作であっても、「なんか気持ち悪い」と感じて、やり直してしまいます。
このタイプの強迫症は、他のタイプと比べて「強迫行為をやり終えるとスッキリする」感覚が得られる傾向があります。
たとえば確認強迫の人は「火事が怖い」といった理由がありますが、整理整頓型強迫の人は、ただ単に「気持ち悪い」「こうでなければならない」といった感覚的な違和感があるだけで、明確な理由があって繰り返し行動を行っているわけではありません。
縁起強迫
縁起強迫とは、「これをやったら不吉」「これを避けないと悪いことが起きる」といった感覚に支配されるタイプの強迫症(強迫性障害)です。たとえば「4(死)」や「9(苦)」といった数字を不吉と捉え、それらを含む部屋番号や日付を避けたり、会話の中でも使わないようにしたりします。
ただし、他人が聞いても意味がわからないような「縁起」のルールも多く、自分だけに通用する“マイルール”に縛られている場合もあります。たとえば「部屋には右足から入る」「右手と左手で同じ回数だけ物に触れる」「特定のルートを通らないといけない」といった、非論理的だけれど本人にとっては強いこだわりを持つ行動パターンが見られます。
こうした行動は、周囲から見ると奇妙に思えるかもしれませんが、本人にとっては「それを守らないと不安」「守れば安心できる」といった感覚が非常に強く、やめたくてもやめられないのです。マイルールの数が増えるにつれて、日常生活に支障が出てしまい、「壊してはいけないルール」が増えていくこと自体が大きなストレスになります。
想像型強迫
想像型強迫とは、自分でも納得できないような考えが繰り返し頭に浮かび、それを何とか打ち消そうとすることで苦しむタイプの強迫症です。
たとえば、「自分が知らない間に誰かを傷つけてしまったのではないか」「無意識に万引きをしてしまったのではないか」「誰かに対して悪口を言ってしまったのではないか」といった思いが、理由もなく頭に浮かんできて、それが何度も繰り返されます。
また、「恋人のことを本当に好きなのか」「自分は親としてふさわしいのか」「本当は子どもを愛していないのでは」といった人間関係に関する疑念が浮かぶこともあります。
これらは実際に起きていないにもかかわらず、本人にとっては強い不安を引き起こします。目に見える行動としての強迫行為が少なく、頭の中だけで打ち消しや反芻(同じことを何度も考える)といった行動が繰り返されることが多いため、周囲からは気づかれにくい場合もあります。
想像型強迫は「確認のしようがない」ことが多く、心の中で延々と考え込んでしまう傾向があります。ときには、自分の行動や言動を頭の中で何度も思い
確認したくても確かめようがないため、「誰かに尋ねる」「ネットで調べる」といった代替行動が現れる場合もあります。
「私って普通だよね?」と他人に何度も聞いたり、犯罪のニュースを検索したりして、自分と比較して安心しようとするケースもあります。こうした行動をとることで一時的な安心感につながっても、根本的な不安は残り、繰り返し確認や打ち消し行動が続いてしまうことが少なくありません。
強迫症はどうして悪化するのか
強迫症が悪化していく背景には、多くの場合「ちょっとした気がかり」がきっかけです。たとえば、トイレのあとに「手はちゃんときれいかな」と感じてもう一度洗ったり、外出前に「ちゃんと鍵をかけたかな」と何度か確認したりする、誰にでも起こりうる行動から始まります。この段階では、「ちゃんと洗ったから大丈夫」「確認したから安心」と納得できています。
しかし、こうした行動を繰り返すうちに、確認や洗浄などの強迫行為をしないと落ち着かなくなる状態へと進んでいきます。たとえば、以前は「少し汚れているかも」程度に思っていた人が、「ものすごく汚染されているかもしれない」と考えるようになり、強い不快感や恐怖感にかられて、すぐにでも洗わなければ我慢できなくなるようになります。
さらに、恐怖を感じる対象に対してどんどん過敏になり、それまで気にならなかったような刺激にも過剰に反応するようになります。最初はトイレのあとだけだったのが、「外気に触れるだけで汚れるのでは」「人混みに入るだけで何かに感染するのでは」と考え、生活の範囲がどんどん狭くなってしまうこともあります。
加えて、強迫観念を「考えまい」と意識するほど、かえってその考えが頭に浮かびやすくなります。しかも、当初は安心のために行っていた強迫行為も、回数が増えるにつれて次第に苦痛になり、「できればやりたくないけど、やらないと不安」というジレンマに陥っていきます。その結果、「不安を感じる状況自体を避ける」という方向に行動が変わり、外出時にはトイレを使わない、他人との接触を避けるなど、自分なりの回避ルールが積み重なっていきます。
こうしたルールが日常生活をどんどん制限するようになり、最終的には学校や職場、家庭内でも影響が出るようになることも少なくありません。
強迫症の治療法
強迫症は自然に良くなることはあまり期待できませんが、きちんと治療すれば回復が見込める病気です。薬を飲んでよく寝て休むという、いわゆる「他の病気にも効きそうな休養法」だけでは十分ではなく、本人が自分の強迫的な思考や行動のパターンに気づき、それを少しずつ変えていくことが回復への鍵になります。
また、強迫症とうつ病は、それぞれ異なる病気ではありますが、強迫症は長期間にわたって苦しい状態が続くと、気分が沈みやすくなり、うつ病を併発することも少なくありません。そのため、できるだけ早めに治療を開始することが大切です。
薬物療法と行動療法が中心
強迫症の治療には、薬物療法と行動療法(ERP)が中心になります。
行動療法では、強迫観念に伴う不安に少しずつ慣れていき、不安に対して過剰に反応せずにすむ力を養います。薬物療法では、強迫観念や不安感を和らげる効果のある薬(主にSSRI)が用いられます。最近では、マインドフルネスも補助的に取り入れられることがあります。
行動療法では、あえて不安や不快感を引き起こす状況に身を置き、そこで普段している強迫行為を行わずに耐える練習を繰り返します。効果は高い一方で、「嫌なこと」に自ら向き合う必要があり、苦痛を伴うため途中で辛くなってしまう人もいます。
薬物療法は、不安や違和感に対する感受性を抑えることで、強迫観念にとらわれすぎず、「今、するべきこと」に集中しやすくなります。ただし、薬の服用を自己判断でやめると再発のリスクが高まるため注意が必要です。
薬物療法と行動療法を併用することで、治療に対する心理的な負担が軽減され、取り組みやすくなるとされています。医師と相談しながら、それぞれの治療法の仕組みや特性を理解することが大切です。
周囲の協力が不可欠
強迫症の治療には、本人の努力に加えて、まわりの人の理解と協力が欠かせません。ただ、善意からの行動がかえって症状を悪化させてしまうこともあります。たとえば、「本人が楽になるなら」と毎回確認に応じたり、「そのうち落ち着くだろう」と様子を見ていたりするだけでは、なかなか治療に結びつかないものです。
大切なのは、まず強迫症という病気についてまわりが正しく理解し、必要に応じて治療を勧めることです。本人が抱える不安に過剰に巻き込まれず、「そうなんだね」「ふーん、なるほどね」と、やや距離を保ちながら受け流す姿勢も有効な場合があります。本人が不安に向き合う練習をしているときには、過度な手助けを控えることが、治療の一環になることもあります。
家族や職場など身近な人たちの接し方が変わることで、本人の生活環境が少しずつ変化し、それが回復のきっかけになることもあります。治そうとする気持ちを否定せず、焦らせず、本人のタイミングで治療に向き合えるよう、寄り添いながら支えることが大切です。
ストレスチェックの活用
ストレスチェック制度とは、労働者の心身の負担を可視化し、ストレス状況を把握してメンタル不調を未然に防ぐ目的で導入されたものです。常時50人以上の事業所で義務化されていて、2024年10月の政府検討会報告により50人未満の全事業所にも義務が拡大される予定です。
ストレスチェックは、あくまで職場での心理的なストレス反応や環境要因を広く把握するためのツールであり、特定の精神疾患を診断するものではありませんから、強迫症の診断や判定にストレスチェックをそのまま活用することはできません。
しかし一方で、強迫症の方が自覚しづらいストレスや不安、疲労の蓄積などを客観的に見つめるきっかけにはなります。ストレスチェックを行い、ストレスの感じ方や生活の中での疲労感を可視化することで、強迫行為にエネルギーを取られていることに初めて気づくケースもあります。
ストレスチェックは、“気づき”の手段として活用することができ、自分の心の状態に目を向ける入口として活用できる可能性があるのです。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
強迫症は、不安や恐怖から繰り返し浮かんでくる考え(強迫観念)と、それを打ち消すために繰り返す行動(強迫行為)によって、日常生活に支障が出る病気です。本人の意に反して行動がやめられないことが多く、周囲の理解と支えも大切になります。
ストレスチェック制度は、本人では自覚しづらい疲れや不安のサインを見つける手がかりになるツールです。ストレスチェックを定期的に行い、結果をもとに面談やサポートの機会を設けることで、職場でも精神的な負担に早く気づき、必要な支援につなげやすくなります。
ストレスチェッカーは、官公庁や上場企業、大学、大規模病院など、さまざまな現場で使われている国内最大級のストレスチェックツールです。受検画面やメール文面のカスタマイズ、未受検者への自動リマインド、リアルタイムでの進捗確認、医師面接希望の収集など、実際の運用に合わせて柔軟に活用できます。
2025年5月からは、無料プランとWEB代行プランで「プレゼンティーイズム(体調や心理的な負担でパフォーマンスが落ちている状態)」の測定にも対応しました。自覚のない疲れや気力の低下を数値で把握できます。
導入を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
:参照記事
>パニック障害とは?症状や原因を精神科医が解説

