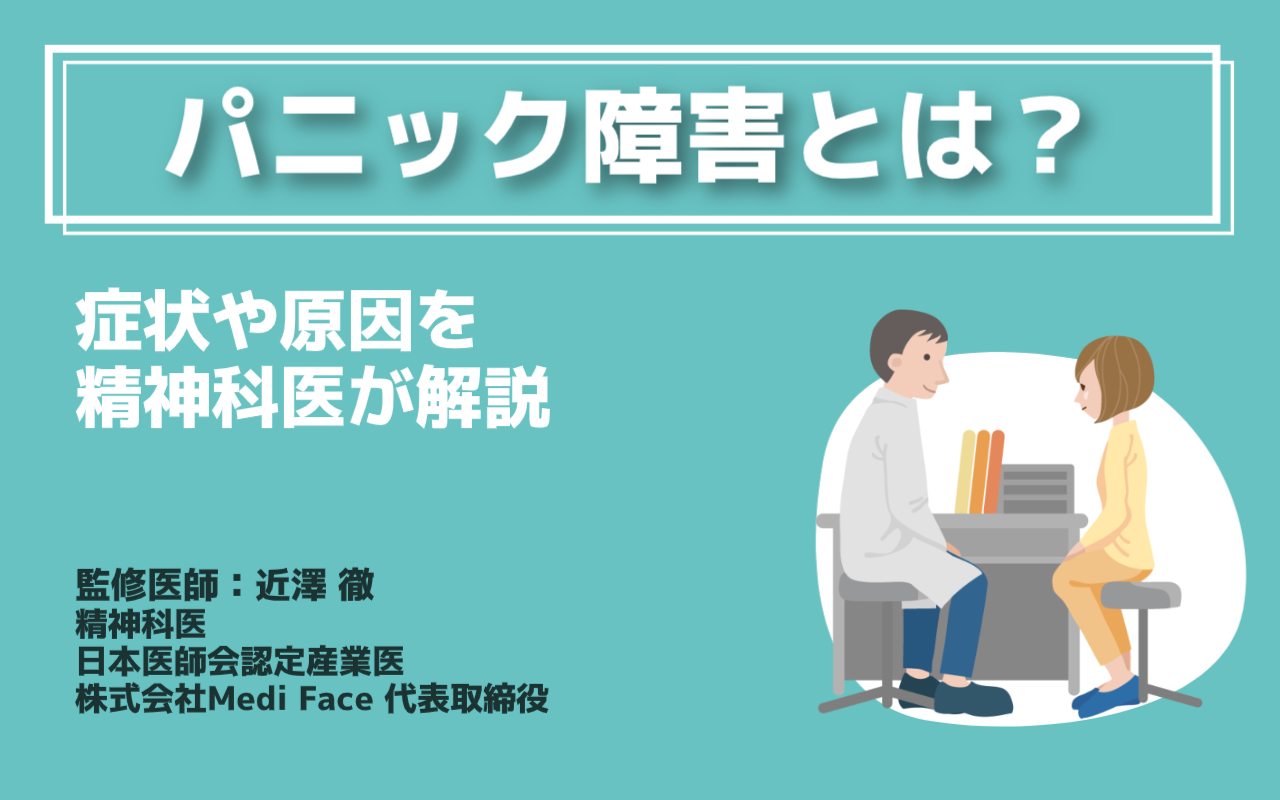
パニック症(パニック障害)は、理由もなく突然起こる強いパニック発作を何度も繰り返す病気です。
パニック症のある人が職場にいる場合、無理に励まさず、急な変化やプレッシャーを避ける配慮が大切です。職場全体に正しい理解を促し、無理のない業務配分と柔軟な働き方をサポートする姿勢が求められます。
(監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹)
目次
パニック症(パニック障害)とは
パニック症とは、パニック発作を繰り返す疾患です。
身体的な原因はないにもかかわらず、さまざまな不快な症状が突然生じます。
パニック症は、100人に1~3人程度にみられ、決してまれな病気ではありません。
10人に1人は一生のうちに一度はパニック発作を経験すると言われますが、発作を経験したすべての人がパニック症にあたるわけではありません。発作の頻度やきっかけ、不安の程度などを含めて総合的に判断されます。
パニック症の主な症状
パニック症は、動悸、息苦しさ、めまい、発汗、手足の震え、吐き気、腹痛、胸の圧迫感など、多様な症状が現れます。こうした発作は前触れもなく突発的に始まり、通常は数分から30分ほどでおさまるものの、その体験は非常に衝撃的で、「またあの発作が起きたらどうしよう」という強い不安を日常的に抱えるようになります。
多くの場合、複数の症状が一気に出現し、同じようなタイミングで徐々におさまっていきます。
どのような症状が現れやすいかは人それぞれで、たとえば「急に心臓がバクバクし始めて、このまま倒れるのでは」と感じる人もいれば、「原因が思い当たらないのに吐き気や腹痛に襲われた」と訴える人もいます。いずれも、本来ならば体の異常があって現れるような症状ですが、パニック症では身体検査をしても異常が見つかりません。そのため、本人にとっては非常に切実で深刻な問題であっても、周囲の理解を得にくいという難しさも伴います。
パニック症とパニックの違い
「パニック症」と「パニック」は、言葉が似ていても意味する内容はまったく異なります。日常会話でよく使われる「パニック」とは、予想外の出来事や緊急事態に直面し、冷静さを失って慌てたり混乱したりする状態を指します。「パニクる」といった表現があるように、原因がはっきりしていて、それに対する一時的な反応として起こるものです。
一方、「パニック症」の場合は、明確な理由もなく突然、激しい不安や身体症状が現れる「パニック発作」を繰り返す病気です。発作は静かな環境で安静にしているときや、夜中の就寝中に起こることもあり、周囲の状況や本人の意志とは無関係に生じます。
「パニック症」と聞いて、「冷静さを失いやすい人」「感情や行動のコントロールが難しい人」といったイメージを持たれることもありますが、こうした誤解は偏見につながりやすいため、正しく理解することが大切です。
パニック症と似た症状の病気
パニック発作の際に見られる、激しい動悸、息苦しさ、めまいといった症状は、身体的な病気でも現れることがあるため、単なる心因性のものと自己判断するのは危険です。突然強い症状に襲われたとき、それが身体の異常によるものか、パニック発作によるものかを症状だけで見分けるのは難しく、医療機関で適切な診断を受けることが重要です。
パニック症と似た症状を起こす身体疾患には以下のようなものがあります:
・鉄欠乏性貧血
酸素を運ぶ能力が低下することで、動悸や息切れを感じやすくなります。特に女性に多く見られます。
・甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)
新陳代謝を促す甲状腺ホルモンの働きが活発になりすぎて、疲れやすくなり、動悸、息切れ、発汗、体重減少が見られます。
・褐色細胞腫
副腎にできる腫瘍で、カテコールアミンというホルモンが過剰に出ることにより、動悸、発汗、立ちくらみなどの症状が現れやすくなります。
・心臓の病気(狭心症・不整脈・僧帽弁逸脱症など)
心拍のリズムの乱れや胸の痛みが起きることがあり、症状が一時的な場合でも検査が必要です。
・低血糖
血糖値が下がりすぎることで、動悸、脱力、ふるえ、ひどいときは意識障害が起こる可能性があります。
・更年期障害
特に女性に見られ、ホットフラッシュ(突然ののぼせ)、発汗、耳鳴り、不整脈などが発作的に出現します。
・てんかん(側頭葉てんかんなど)
自律神経症状として発汗、過呼吸、頻脈のほか、非現実感や意識が途切れたりすることがあります。
・メニエール病
耳の内耳に関係する疾患で、突然ぐるぐると回るような激しいめまいが生じ、これが数時間続く点がパニック発作とは異なります。
パニック症の治療法
パニック症は、単に休養を取っていれば自然と治るというものではありません。適切な治療を受けることが回復への第一歩です。
特に薬物療法はパニック症の治療において有効とされています。あわせて、生活リズムを整え、ストレスをためにくい日常を意識することや、不快な感覚や状況を受け流せるような思考の習慣を身につけていくことも重要です。
こうした治療とセルフケアを重ねることで、やがて薬に頼らずに生活できるようになり、発作のことを意識せずに日常を送れるようになれば、治癒といえる状態になります。実際、多くの方が完治し、問題なく社会生活を送っています。
ただし、治療にかかる期間には個人差があります。発作への恐怖の度合いや避ける行動の強さによって回復のスピードは異なり、短期間で落ち着く人もいれば、数か月以上かけてじっくり向き合う必要のある人もいます。
パニック症の職場における影響と周囲の理解
これまでご紹介したとおり、パニック症とは、突然理由もなく強い不安や身体的な症状(動悸、息苦しさ、めまい、吐き気など)に襲われる発作を繰り返す精神疾患で、発作そのものに加え、「また発作が起きるかもしれない」という予期不安を常に抱えて生活することになります。
体調が安定しているように見えても、内心では強い不安を感じながら業務にあたっていることも少なくありません。そのため、突然の体調不良で仕事を一時的に中断したり、業務の途中で早退したりするようなことが起こる可能性もあります。
こうした状況を本人だけの問題とせず、職場全体で理解と柔軟な対応が求められます。まず大切なのは、パニック症に対する正しい知識を持つことです。単に「精神的に弱い」「気の持ちよう」といった誤解を避け、医学的な疾患であるという前提で接することが信頼関係の第一歩となります。
業務上の配慮としては、業務内容や働く場所・時間に一定の柔軟性を持たせることが有効です。業務負荷の調整、リモートワークの導入、通勤時間の緩和など、個々の症状に応じた調整が望まれます。
一方で、本人が職場に対して自分の状態をどこまで共有するかはプライバシーにも関わる問題です。無理に打ち明けさせるのではなく、本人の意思を尊重しながらサポートの体制を整えていくことが大切です。
パニック症を持つ人でも、環境が整えば安定して働き続けることは十分可能です。職場における理解と適切な配慮が、本人の自信と安心感につながり、それが結果的に職場全体の生産性やチームワークを高めることにもなります。精神的な不調に対する偏見をなくし、安心して働ける環境づくりは、現代の職場に求められる重要な課題のひとつです。
パニック症とストレスチェック
ストレスチェックとは、仕事や人間関係による心理的負荷を数値化し、自分自身の状態を客観的に把握するツールです。
ストレスチェックは、パニック症の早期発見につながる可能性があります。高ストレスと判定された場合には、パニック症の初期症状であるパニック発作や、それにつながる心身の緊張や不安が背景にある可能性があります。その段階で気づきを得ることで、専門機関への相談や受診のきっかけとなり、早めの対処につながることが期待されます。
特に、発作の原因が特定できないと感じている人にとって、ストレスチェックによって心身の緊張に気づくことが、医療機関への受診や環境の見直しにつながるケースがあります。また、職場の管理者がチェック結果をもとに適切なサポートを検討するきっかけにもなります。自覚しにくいストレスを可視化し、早期にケアへつなげるための有効な手段です。
本質的な判断には使えない
ストレスチェックで測定される項目には、仕事の量や質、人間関係、職場環境といったストレスの原因に加えて、身体的な不調や心理的な反応といった自覚症状も含まれます。
ストレスチェック制度を活用することで、本人が気づかないうちにたまっているストレスの存在が可視化され、心身の状態に目を向けるきっかけになります。
ただし、ストレスチェックはあくまでも一次的な評価ツールであり、パニック症そのものを診断するものではありません。高ストレスと判定された場合には、産業医との面談を通じて状態を確認し、必要に応じて医療機関での診察を受けることが勧められています。職場での早期対応が、その後の予防や治療につながる可能性もあるため、気になるサインが見られた場合には、ためらわず相談することが大切です。
ストレスチェックの活用方法
パニック症を抱える本人にとっても、ストレスチェックは自身の状態を客観的に見つめ直すきっかけになります。また、職場側にとっては、従業員の精神的な負荷を軽減するための施策を検討する重要な材料となります。たとえば、過重労働の見直しや、業務の柔軟な分担、相談体制の整備など、環境面からの支援が可能になります。
パニック症に限らず、心の不調に気づいたら、早めに医療機関に相談し、適切なサポートを受けることが大切です。ストレスチェックはそのための第一歩となる存在です。
緊張や不安、対人関係のストレスが数値として表れることで、自分のコンディションに合った対処法を考えやすくなります。また、組織としても高ストレス者の傾向や職場環境の問題を早期に察知することで、適切な対応を取りやすくなります。さらに、ストレスチェックは面談のきっかけづくりにもなり、定期的なケアの体制をつくる一助になります。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
パニック症は、適切な治療を受けることで改善が期待できる疾患です。「症状の軽減」や「社会生活への支障がなくなるレベルまでの回復」は十分期待できますし、状況によっては、服薬なしで生活できる状態に回復する人もいます。
ストレスチェック制度は、心身の状態を客観的に把握し、早期にケアにつなげるための有効なツールです。本人が気づきにくい疲労や不調の兆しを見つける手助けにもなります。
ストレスチェック制度を活用することで、本人のストレス状態の早期把握が可能となり、精神的負荷の軽減に繋げられます。定期的なチェックと面談の機会を設けることで、異変に気づきやすくなり、必要な支援を早期に講じることができます。職場での支援体制とストレスチェックを組み合わせることで、本人の安心感が高まり、無理のない働き方の継続がしやすくなります。
ストレスチェッカーは、官公庁や上場企業、大学、大規模病院など、さまざまな現場で使われている国内最大級のストレスチェックツールです。受検画面やメール文面のカスタマイズ、未受検者への自動リマインド、リアルタイムでの進捗確認、医師面接希望の収集など、実際の運用に合わせて柔軟に活用できます。
2025年5月からは、無料プランとWEB代行プランで「プレゼンティーイズム(体調や心理的な負担でパフォーマンスが落ちている状態)」の測定にも対応しました。自覚のない疲れや気力の低下を数値で把握できます。
導入を検討されている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
:参照記事
>統合失調症の症状、治療法を精神科医が解説

