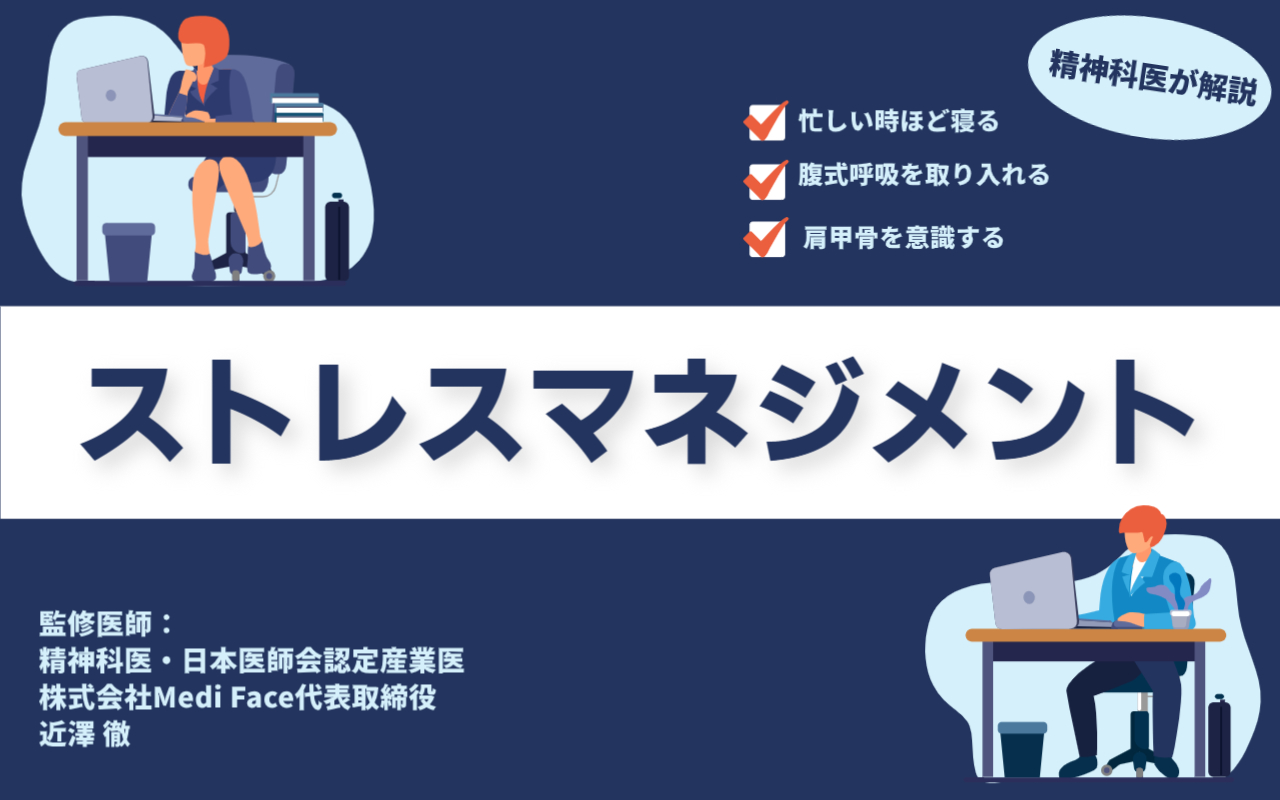
ストレスマネジメントとは、ストレスと上手に付き合うための工夫や方法です。深呼吸や軽い運動、十分な睡眠など、日常生活の中で心身を整えることが基本ですが、自分のストレスの原因を知り、その影響を理解することも大切です。
目次
ストレスマネジメントとは
ストレスマネジメントとは、日々の生活で避けられないストレスとうまく付き合っていくための方法です。ストレスは脳や自律神経、心身のバランスに影響を与えるため、それを悪化させないようにする工夫が求められます。
ストレスマネジメントでは、何が自分にとってストレスの原因なのかを正しく理解し、それに対して自分がどんな反応をしているのかを冷静に観察・分析することが大切です。感じ方や考え方のクセを知ることで、ストレスへの捉え方を少しずつ調整していくことができるようになります。リラクゼーション法、適度な運動、人とのつながりを大切にすることなど、日常に取り入れやすい方法も多くあります。自分に合ったやり方を見つけて、無理なく続けることが大切です。
(1)ストレスマネジメントの重要性
ストレスマネジメントは、心と体の健康を維持するうえで欠かせません。ストレスは誰にでも起こり得る自然な反応ですが、放っておくと不眠や食欲不振、イライラ、集中力の低下など日常生活に影響を及ぼします。さらに進行すると、うつ病や自律神経失調症といった心身の不調にもつながりかねません。
ストレスマネジメントを実践することで自分の状態に気づきやすくなり、心身の不調を予防する力がつきます。また、困難な状況でも冷静に対処しやすくなり、人間関係や仕事のパフォーマンスにもよい影響を与えます。
単にストレスをなくすことが目的ではなく、ストレスとうまく付き合いながら、自分のペースを保つことが大切です。
ストレスを感じること自体は悪いことではなく、それにどう対応するかが健康的な生活のカギを握ります。
(2)ストレスが職場に及ぼす影響
ストレスは、心身の健康だけでなく生産性にも大きな影響を与えます。
職場では、ストレスが原因で集中力の低下や判断ミス、体調不良による欠勤や離職などが起こりやすく、組織全体のパフォーマンスに悪影響を及ぼします。
企業においては、ストレスマネジメントの重要性を理解し、従業員が自分のストレスに気づき、適切に対処できるような環境づくりが求められます。定期的な研修の実施や、相談体制の整備、ストレスチェックの実施、柔軟な働き方の導入などを通じて、個人が無理をしすぎずに働ける職場づくりが不可欠です。ストレスとうまく付き合う力が、結果的に仕事の質やチームの信頼関係の向上にもつながります。企業がストレスマネジメントを積極的に広めることは、従業員の健康維持と組織の安定運営の両面で大きな意味を持ちます。
(3)ストレスマネジメントの職場への導入
ストレスマネジメントを導入するには、まず経営層がその重要性を理解し、組織全体として取り組む姿勢を明確にすることが出発点です。そのうえで、従業員のストレス状況を把握するためのアンケートやストレスチェックを実施し、現状を可視化します。
次に、社員向けにストレスの正しい知識や対処法を学ぶ研修やセミナーを開催し、自分のストレスに気づき、コントロールする力を養う機会を設けます。
さらに、相談窓口や産業医との連携体制を整えることで、メンタル不調の早期発見と対応を可能にします。職場環境の改善も重要で、長時間労働の見直しや、コミュニケーションの活性化、柔軟な勤務制度の導入など、働きやすさに配慮した制度設計も有効です。
導入後は効果の検証と継続的な改善を行い、単発で終わらせず、企業文化として根づかせていくことが長期的な成果につながります。
(4)Googleで取り入れているストレスマネジメント
Googleは、従業員のストレス軽減とメンタルヘルス向上のために、さまざまな取り組みを行っています。代表的なものとして、2007年に開発された「Search Inside Yourself(SIY)」プログラムがあります。これは、マインドフルネスと感情知能を組み合わせた研修で、集中力や共感力、ストレス耐性の向上を目的としています。
SIYはGoogle内での成功を受けて、現在では外部組織にも提供されています 。
また、Googleはテクノロジーを活用したストレス管理にも注力しています。FitbitやPixel Watch 2に搭載されたセンサーは、心拍数や皮膚電気活動を測定し、ストレスの兆候を検出します。ユーザーは通知を受け取り、ガイド付き呼吸法やマインドフルネスセッションを通じて、リアルタイムでストレスに対処できます 。
また、Googleはマネージャー向けのメンタルヘルス研修も実施しています。
管理職が部下のストレスサインを早期に察知し、適切なサポートを提供できるようになります。社内には「Blue Dot」などのピアサポートネットワークもあり、従業員同士が気軽に相談できる環境が整っています 。
(5)ストレスマネジメントとストレスチェック
ストレスマネジメントとストレスチェックは、どちらも心身の健康を守るうえで重要な役割を果たしますが、それぞれの目的と機能には違いがあります。
ストレスマネジメントは、ストレスとうまく付き合いながら日常生活や仕事の中で心と体を安定させるための方法や考え方を指し、日々のセルフケアや行動の積み重ねが基本となります。
一方、ストレスチェックは、自分の現在のストレス状態を客観的に把握するための手段であり、定期的に自身のストレスの傾向や変化に気づくきっかけを与えてくれます。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、従業員のメンタルヘルス対策としてストレスチェックの実施が義務化されています(今後、全事業場で義務化の予定)。
これは、仕事に関するストレス要因(仕事量、人間関係、役割の明確さなど)や、ストレスによる心身の反応(不安感、倦怠感、意欲の低下など)を測定することで、ストレスが高い状態にある人を早期に把握し、必要な対応につなげることを目的としています。
ストレスチェックの結果を活用することが、ストレスマネジメントの第一歩となります。ストレスチェックの結果から自分がどのような環境や場面でストレスを感じやすいかが見えてくると、それに対してどのように対処すればよいのか、自分に合った対処法を考える材料になります。たとえば、感情の切り替えが苦手な場合はマインドフルネスや呼吸法、過集中による疲労が多い場合は休憩の取り方や時間の使い方を見直すなど、ストレスマネジメントの方法を選ぶための判断材料として有効です。
また、企業側がストレスチェックをもとに職場環境の課題を把握し、働き方や人間関係の改善に取り組むこともできます。個人のストレス反応だけに着目するのではなく、組織全体で予防的なアプローチを取ることが、働く人の健康維持につながります。
つまり、ストレスチェックは「現状を知るためのツール」であり、ストレスマネジメントは「よりよく生きるための行動の積み重ね」です。この2つは単体では完結せず、連動してこそ本来の効果を発揮します。定期的なチェックを通じて自分の状態を知り、それに基づいたストレスマネジメントを実践することで、ストレスとうまく付き合いながら健やかに過ごすための基盤が整います。個人の健康だけでなく、職場や社会全体の健全な運営にもつながる、大切な取り組みです。
今すぐできる! 10個のストレスマネジメント
ストレスマネジメントを行うことで、心身の健康が保たれ、集中力や判断力が向上します。その結果、業務効率や生産性が高まり、ミスやトラブルの予防にもつながります。ストレスマネジメントha,
安定したパフォーマンスを維持するうえで欠かせない取り組みです。
(1)感情に合わせて音楽を活用する
気分が落ち込んだときやイライラするとき、音楽は手軽に心を整える手段になります。落ち着きたいときには静かなメロディー、気持ちを高めたいときにはリズムのある音楽など、そのときの感情に合った音楽を選ぶことで、自分の気分に働きかけることができます。音楽は脳や自律神経に直接影響を与えるため、無理に感情を押さえ込むよりも、自然な形でリラックスや気分転換を促してくれます。
自分なりのテーマソングを決めておくのも、おすすめです。冷静になりたい時は牧歌的な歌、ここぞという時には元気の出る歌を決めておいて、いざという時に口ずさめるようにしておくと、脳をコントロールするのに役立ちます。
(2)考え方に柔軟性を持たせる
「こうあるべき」「絶対にこうしないといけない」といった極端な思考は、ストレスを溜め込みやすくします。物事を少し違う角度から見てみたり、「まあ、そんなこともある」と受け流したりする柔軟な姿勢が、精神的な余裕につながります。
周りに理解しにくい言動をする人がいても、「あの人は変わっている、理解できない」で終わらせるのではなく、その背景を考えてみたり、自分の行動と比較したりすると、新しく見えてくるものがあるはずです。
自分も周囲にも完璧を目指さず、失敗や不調を認めることで心にゆとりが生まれ、自分にも周囲にも優しくなれます。
(3)睡眠は大切!忙しい時ほど寝よう
仕事や家事が立て込んでいると、つい睡眠時間を削ってしまいがちですが、睡眠は心身のリセットに不可欠です。
質の良い睡眠を十分とることは、脳のメンテナンスのために欠かせないものです。
また、自律神経は体内時計が深くかかわっていて、夜にしっかり睡眠をとることで自律神経の働きも整ってきます。寝不足は思考力や集中力を下げるだけでなく、感情のコントロール力も弱めてしまいます。忙しいときこそ意識的に早めに休むことで、翌日のパフォーマンスも上がり、ストレスにも強くなれます。短時間でも質の良い睡眠をとることが大切です。
なかには、不眠に悩む人もいると思いますが、そのような人は寝ようと焦らずにイメージトレーニングをするのもおすすめです。うとうとするだけでも効果はあるものだ、寝たい時に寝ればよいといった大らかに考えることも大切です。
(4)生活リズムを見直す
起きる時間、寝る時間、食事のタイミングなど、生活のリズムが乱れると、自律神経のバランスが崩れやすくなります。その結果、イライラしやすくなったり、集中力が落ちたり、胃腸の不調や睡眠の質の低下といった体のトラブルが出やすくなります。ストレスへの耐性も下がるため、普段なら気にならないようなことに強く反応してしまうこともあります。
だからこそ、まずは自分の生活パターンを振り返ってみることが大切です。たとえば、夜中までスマホを見て寝つきが悪くなっているなら、寝る1時間前にはスマホを手放して、ぬるめのお風呂にゆっくり入るなど、睡眠に向けた準備を意識してみるとよいでしょう。朝は、決まった時間に起きてカーテンを開けて朝日を浴びるだけでも、体内時計が整いやすくなります。
朝ごはんも重要なポイントです。忙しいとつい抜いてしまいがちですが、パンと果物だけでも口にすることで、体と脳に「1日が始まった」と伝えることができます。生活リズムを整えることは、難しいテクニックではなく、身近な習慣の積み重ねです。毎日を気持ちよく過ごす土台として、少しずつ整えていくことがストレス軽減にもつながります。
(5)腹式呼吸を意識する
身体を動かして自律神経を整える時の基本が、「腹式呼吸」です。ストレスがかかると呼吸が浅くなりがちですが、意識的に腹式呼吸を取り入れることで心拍数が落ち着き、自律神経が整いやすくなります。
通常、交感神経の働きが高まると呼吸は速く浅くなります。そして、副交感神経の働きが高まると、呼吸は深くゆっくりになります。
つまり、意識して呼吸を深くゆっくりすると、交感神経の働きが抑えられて副交感神経の働きが促されるようになるのです。
ストレスにさらされると人は交感神経の働きが強くなるため、副交感神経の働きを高めてバランスをとるために、腹式呼吸がおすすめなのです。
ちなみに、腹式呼吸はゆっくりとお腹を膨らませるように息を吸い、吐く時間を長めにするのがポイントです。短時間でも、1日数回深呼吸をするだけで、頭や体がすっきりし、気分の切り替えにもなります。
(6)運動や趣味を楽しむことの大切さ
軽い運動や趣味の時間は、ストレスを外に発散する大切な手段です。体を動かすと、ストレスを和らげるホルモンが分泌され、気分が自然と前向きになります。
とはいえ、あまりに運動や趣味を張り切ってしまうと、それはそれで逆効果になり心身のバランスを崩しやすくなります。
「楽しい」「快適」「面白い」と感じるとき、脳内ではドーパミンが多く分泌され、気分が自然と前向きになります。このドーパミン優位の状態は、ストレスに強い心をつくるうえでも重要です。だからこそ、何かを「やらなきゃ」ではなく、「やりたいからやる」という気持ちで取り組むことが大切です。たとえば、散歩が好きなら毎日15分歩くだけでもいいし、音楽や絵を描くのが好きなら、その時間を無理なく確保するのも立派なストレス対策です。周囲の人と笑い合う時間や、好きなカフェで過ごすひとときなど、自分が心地よいと感じられる時間を意識的に生活に取り入れることで、心の余裕が生まれます。こうした小さな「楽しい」の積み重ねが、ストレスマネジメントなのです。
(7)歩行や立ち姿勢を改善する
姿勢が悪いと呼吸が浅くなったり、筋肉がこわばったりして、知らないうちに体に負担がかかっています。
正しい立ち姿勢とは、下腹の丹田と呼ばれる場所に力を集中させて、顔や腕に余計な力を入れず、胸を張った美しい姿勢です。
猫背やうつむき加減で歩くと、胸が閉じて呼吸が浅くなり、自律神経が乱れやすくなり、ストレスへの耐性が落ちてしまいます。
逆に、背筋を伸ばして、視線をまっすぐ前に向けて歩くと、呼吸が深くなり、血流もよくなり、副交感神経を優位にし、リラックスしやすい状態をつくることができます。
また、歩くテンポや足の運び方も気分とリンクしています。リズムよく落ち着いたペースで歩くと、心も自然と落ち着いてきます。これは「行動が感情に影響を与える」という、心理学的な原則に基づいたものです。
日常の歩き方や立ち姿勢を意識するだけで、体のこわばりが緩み、気分も安定しやすくなります。肩の力を抜き、背筋を自然に伸ばすことで、呼吸が深くなり、ストレスの軽減にもつながります。
(8)肩ではなく肩甲骨を意識する
本来の腕の付け根は、肩ではなく肩甲骨の内側にあります。
腕の付け根を肩だと思ったまま無理に作業をすると、どうしても肩こりが起こりやすくなってしまいます。さらにデスクワークやスマホの使用が多いと、つい肩が前に入りやすくなり、肩まわりがガチガチにこります。肩甲骨を意識して動かすことで、血流が改善され、肩こりや首の疲れが和らぎます。簡単なストレッチや肩甲骨を回す体操を日常に取り入れると、体の緊張がほぐれ、気持ちにもゆとりが出てきます。
(9)怒りをコントロールする方法を見つける
イライラや怒りをためこんでしまうと、心だけでなく体にも大きな負担がかかります。血圧が上がったり、呼吸が浅くなったり、睡眠の質が落ちたりすることもあるため、感情を無理に抑え込むのではなく、「あ、今ちょっとイラついているな」と気づくことが何より大事です。たとえば、会議中に腹が立つ発言があったとき、その場で感情的に反応するのではなく、一度深呼吸してクールダウンするだけでも冷静さを保てます。また、モヤモヤを紙に書き出してみると、思考が整理されて感情が収まりやすくなります。感情は悪者ではなく、「今の自分の状態を知らせてくれるサイン」です。怒りを否定せず、うまく扱う方法をいくつか用意しておくと、ストレスの連鎖を断ち切ることができます。
(10)自分で自分を認めてあげる
たとえどんなに能力があっても、万人に受けることはまずありません。誰に認めてもらうのが一番大切なのかといえば、それは自分自身です。社会的に間違ったことをするのは論外ですが、自分をしっかりと認めて進めば、実力も向上しますし、次第に周囲も理解してくれるはずです。
自己肯定感を持って行動することも、重要なストレスマネジメントのひとつなのです。ストレスが強くなると、自分を責めたり否定したりしやすくなります。小さなことでも「できた」と感じたら、自分をねぎらう習慣を持つことが大切です。誰かに褒められなくても、自分自身で自分を認めることで、心に安定感が生まれます。無理に完璧を求めず、「これで十分」と思える感覚を大事にすることが、ストレスと付き合う力になります。
:参照記事
>ストレスからくる病の症状|社員の不調、どこで気づく?
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹
| 【監修医師】 精神科医・日本医師会認定産業医 株式会社Medi Face代表取締役 近澤 徹  オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。 |

