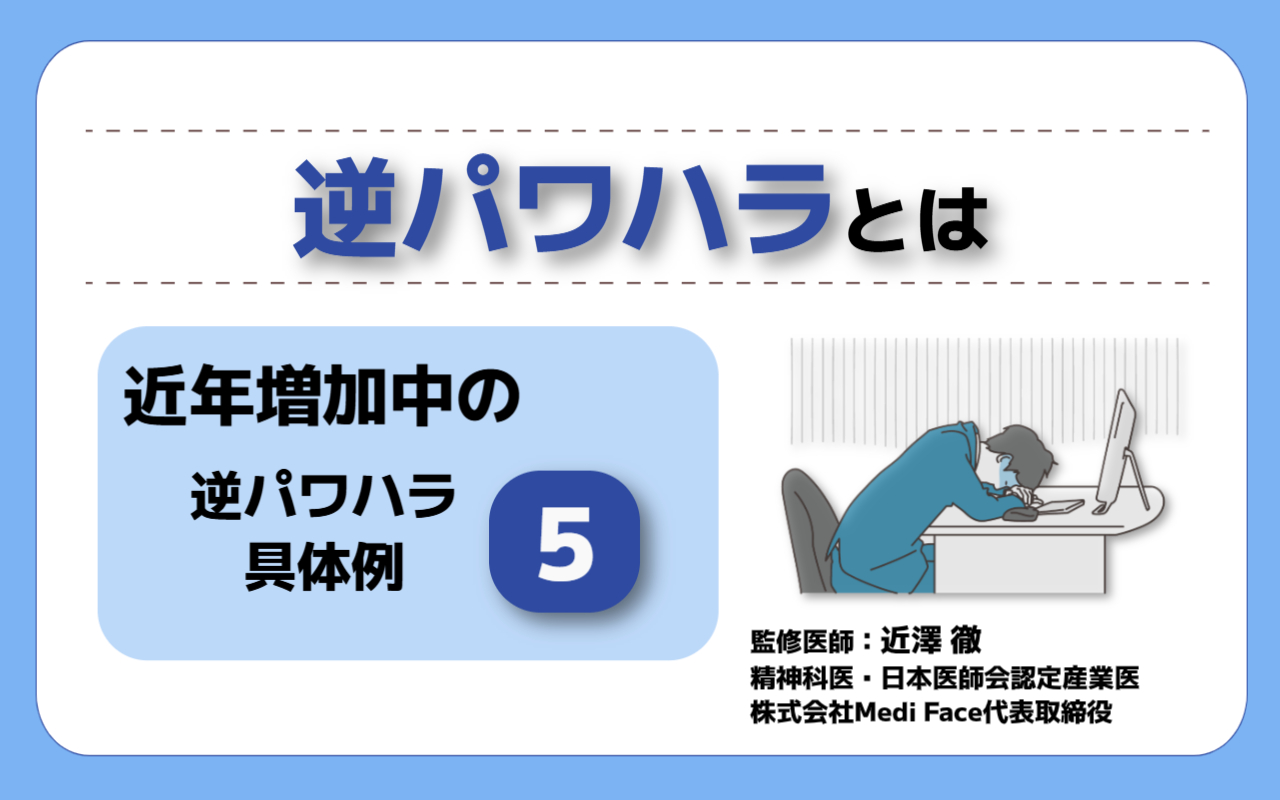
逆パワハラ(部下から上司へのハラスメント)は、管理職の精神的負担を増大させ、職場環境の悪化を招く要因になります。逆パワハラを防ぐためには、逆パワハラの事例と対処法を理解し、周知することが大切です。さらにストレスチェックを導入・活用することで、逆パワハラを未然に防ぎ、健全な職場環境を維持できます。
目次
逆パワハラの事例と対処法
近年、部下から上司へのハラスメント、いわゆる逆パワハラが増えていると言われています。上司が仕事上のミスを注意しただけなのに「パワハラだ」と騒がれたり、「あんな上司とはやっていけない、解雇してほしい」と要求されたりするケースが発生し、企業としても対応を迫られる場面が増えています。
こうした逆パワハラの問題は、上司と部下の関係性の変化や職場環境の影響を受けており、特にハラスメント対策が強化される中で、「指導」と「パワハラ」の線引きが難しくなっていることが背景にあります。上司が適切な指導を行っているにも関わらず、部下が不満を抱えて過剰に反発することで、上司の精神的な負担が増大し、職場の雰囲気が悪化するケースも少なくありません。
(1)労基署に行くと言われた
適切な指導を行ったつもりなのに、「それはパワハラです」と訴えられ、「弁護士に相談します」「労基署に行きます」と言われることがあります。なかには、何度も同じミスを繰り返している部下に注意をしただけで、「精神的に辛いのに追い打ちをかけられた」としてパワハラだと主張してくるケースもあるようです。
こうした場面で管理職が「弁護士や労基署に相談されたら会社に迷惑がかかる」と不安になるのは無理もありませんが、過剰に心配する必要はありません。労基署が関心を持つのは、労働基準法などの法令に違反している企業そのものであり、個々の従業員を問題視するわけではないからです。
また、仮に労基署に相談されたとしても、その場で何かが大きく動くことは少なく、多くの場合は「まずは弁護士に相談を」と案内されるにとどまります。そしてもし「慰謝料を払ってくれないなら訴える」などと金銭を求められた場合、それは脅しであり、内容によっては恐喝罪に該当する可能性もあります(刑法第249条)。
こうした問題が起きたときは、感情的にならず、部下の主張や背景をていねいに聞いたうえで、適切な対応を検討していくようにしましょう。
(2)上司の解雇を会社に求める
自分のほうが上司よりも優れていると思い込んでいて、指示に従わず、勝手な行動を取る部下がいます。ひどい場合には、「あの上司の下では働けません。異動させてください」「むしろ解雇してほしい」といった主張をしてくることもあります。
もちろん、「上司が気に入らない」「自分のほうが優秀だから指示に従いたくない」といった個人的な理由だけで、異動や解雇が認められることはありません。
こういったケースでは、まずは部下がなぜその上司と一緒に働けないと考えているのか、その背景や理由をしっかり確認することが大切です。
そのうえで、人事権はあくまで会社にあるものであり、たとえ本人や所属部署、あるいは組合などからの要望であっても、会社が一方的に受け入れるものではないという点を、丁寧に説明して理解を得るようにしましょう。
(3)ネットに悪意のある投稿をされた
「セクハラをしている」「不倫している」などの噂を、SNSなどを通じて広める行為は、たとえそれが事実であっても、パワハラにおける「精神的な攻撃」に該当します。こうした悪質な行動に及ぶ人には、自己肯定感の低さや承認欲求の強さが見られることが多く、プライドが高く指摘に逆上したり、病気を装って同情を引こうとしたり、虚言が多いなどの特徴もあると言われています。
もちろん、このような行為は断じて許されるものではありません。会社としては、まずは事実関係を確認し、必要であれば行為者に謝罪を求めたうえで、毅然とした対応を取ることが求められます。
また、個人に対する嫌がらせであっても、内容や影響によっては、会社全体の業務を妨害する行為とみなされ、威力業務妨害罪(刑法第234条)にあたる可能性もあることを、当事者だけでなく、社内全体にしっかり周知しておくことが大切です。
加えて、労働契約を結んで働く以上、従業員には「会社の信用を損なうような言動はしてはならない」という信用保持義務があることも、事前にしっかり伝えておくようにしましょう。
(4)妊娠をした部下に配置転換を打診したらマタハラと言われた
妊娠して、つわりがひどくなってきた女性社員に対し「これまで通りの勤務は体に負担が大きいだろう」と考え、定時に帰れる部署への異動を提案したところ、「それはマタハラ(マタニティハラスメント)です」と言われた、というケースがあります。
ただし、本人の体調や勤務状況を考慮したうえで、業務上必要な措置として異動の打診をすること自体は、マタハラには該当しないと労働省も明言しています。異動を「強制する」のでなく、「相談・打診」という形であれば問題ありません。
このような場面では、まず「体調を心配していること」「これからも職場の一員として期待していること」、そして「異動の打診はあくまで業務上の配慮であり、法律的にも認められた対応であること」をていねいに説明しましょう。そのうえで、本人の意向もしっかり聞きながら、無理のないかたちで配置転換の提案を進めていくことが大切です。
(5)指示に従わない
「嫌いだから」「この仕事はやりたくないから」といった理由で、指示に従わないというケースもあります。
しかし、意図的に業務の遂行を遅らせたり、上司から指示された仕事をしなかったりといった行為は、服務規律違反で雇用関係を解消されても仕方のない行為です。
労働者は、労働契約に基づく労務提供義務があり、会社は従業員に対して指揮監督・命令ができる業務命令権を有しています。
この労務提供を前提に、賃金を得ているにも関わらず労務の提供を怠るのであれば、戒告処分の対象となることを説明しましょう。
また、集団で示し合わせて指示に従わない行為は、パワハラの「人間関係からの切り離し」に該当しますので、その点も説明しましょう。
逆パワハラを回避する方法
逆パワハラを防ぐためには、ハラスメントの基準を明確にし、「適切な指導」と「パワハラ」との違いを社内で共通認識として持つことも大切です。管理職向けの研修を実施し、部下との適切な関わり方を学ぶ機会を設けることで、誤解を防ぐことができます。また、上司が部下の理不尽な要求に対処するための相談窓口を設置し、企業として一方的なクレームに対応できる体制を整えることも効果的です。
(1)逆パワハラの対処法を周知する
逆パワハラを未然に防ぐためには、まず管理職と一般社員の両方に「逆パワハラとは何か」「どのような行為が逆パワハラに該当するのか」を周知することが大切です。社内研修やハラスメント防止マニュアルを作成し、具体的な事例を交えながら指導とハラスメントの違いを説明すると、誤解を防ぐことができます。
また、管理職が部下と適切にコミュニケーションを取れるよう、1on1ミーティングの導入やフィードバックの仕方を学ぶ機会を設けるのも効果的です。逆パワハラは、上司と部下の信頼関係が希薄な場合に起こりやすいため、日常的に良好な関係を築けるような仕組みづくりが求められます。
企業としては、「適切な指導はパワハラではない」という意識を社内に浸透させることも大切です。
(2)適切な相談窓口を設置する
逆パワハラの問題を抱えた管理職が適切に相談できる窓口を設けることは、企業として欠かせない対策の一つです。多くの職場では、ハラスメントの相談窓口が設置されていますが、上司から部下へのパワハラを想定したものがほとんどです。そのため、管理職が部下からの理不尽な要求やハラスメントに悩んでいても、相談しづらい環境になっているケースが多く見られます。
逆パワハラに関する相談窓口を明確に設け、管理職が気軽に相談できる体制を整えることで、問題が深刻化する前に適切な対応が可能になります。また、相談窓口の存在を社内でしっかり周知し、管理職だけでなく一般社員にも「双方が適切に働ける環境づくりが重要である」ことを認識させることも大切です。社内だけでなく、外部の専門機関と連携した相談窓口を設置するのも効果的な方法の一つです。
(3)ストレスチェックを管理職にも徹底する
逆パワハラを防ぐためには、管理職のメンタルヘルスにも十分な配慮が必要です。そのため、ストレスチェックを全従業員だけでなく、管理職にも徹底して実施することが重要です。管理職は部下との関係で精神的な負担を抱えやすく、逆パワハラによるストレスが蓄積されることで、うつ病や適応障害などのメンタルヘルス不調に陥るリスクもあります。ストレスチェックの結果を分析し、高ストレスの管理職には医師との面談を推奨するなど、適切なサポートを提供することが求められます。また、組織全体のストレス状況を把握し、逆パワハラが発生しやすい職場環境を特定することで、根本的な対策を講じることも可能になります。ストレスチェックを活用し、管理職の心理的負担を軽減する仕組みを整えることが、職場の健全な労働環境の維持につながります。
まとめ
企業はハラスメントの基準を明確に定めたうえで、従業員への誤解やトラブルを未然に防ぐため、定期的に研修や周知活動を行うことが求められます。特に、上司と部下の間で認識のズレが生じやすいケースでは、管理職側が適切に対応できるよう、専門の相談窓口を設けておくことが効果的です。
さらに、管理職自身が部下からの理不尽な要求やクレームに疲弊しないよう、メンタルヘルスを守る仕組みやフォロー体制の整備も不可欠です。ストレスチェックの結果を活用し、早めに課題を把握し対応することで、大きな問題に発展する前に対処が可能になります。
企業全体として、風通しの良い職場づくりを進めるとともに、いわゆる「逆パワハラ」が発生しにくい環境を整えることが、これからの人材定着や組織の安定にとってますます重要になっていくものと思われます。
:参照記事
>パワハラの裁判例|パワハラ認定された例&されなかった例
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹
| 【監修医師】 精神科医・日本医師会認定産業医 株式会社Medi Face代表取締役 近澤 徹  オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。 |

