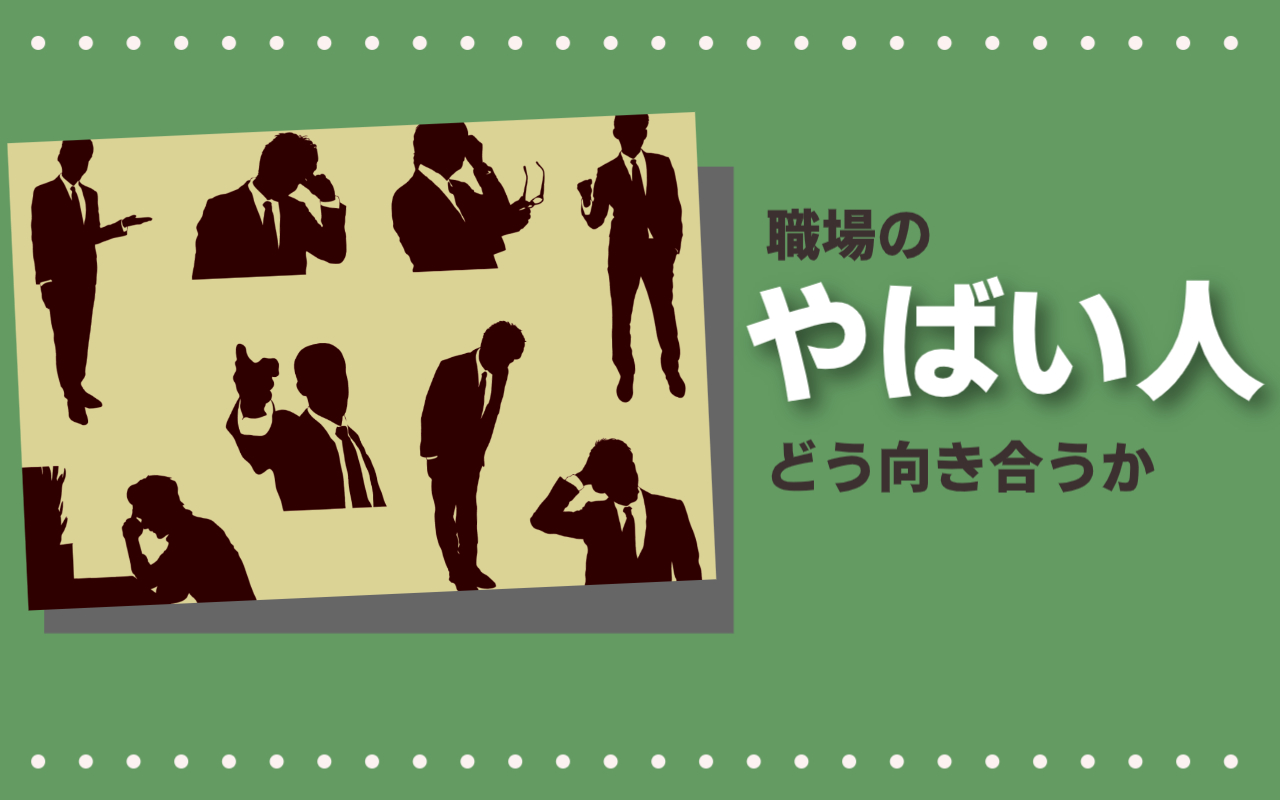
職場には、怒鳴る・威圧する・他人のせいにするなど、いわゆる“やばい人”と呼ばれるタイプの人が存在します。こうした人物が一人いるだけで、周囲のストレスは増大し、チームの雰囲気や生産性が大きく損なわれることがあり、放置できない深刻な課題です。
この記事では、職場の“やばい人”のタイプ別特徴と、企業・個人それぞれが取るべき具体的な対処法をご紹介します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
「職場のやばい人」とは
「職場のやばい人」とは、周囲との協調が難しく、職場全体の人間関係や業務に悪影響を与える行動を繰り返す人のことを指します。怒鳴る・威圧するといった攻撃的なタイプだけでなく、被害妄想が強く常に「自分ばかり責められている」と感じるタイプ、ミスを認めず他人に責任を押し付けるタイプ、感情の起伏が激しく周囲を振り回すタイプなども含まれます。こうした人の存在は、チームの士気低下やストレスの増加、離職の引き金にもなりかねません。
攻撃型(怒鳴る・八つ当たり)
攻撃型の“やばい人”は、職場で怒鳴る、威圧する、八つ当たりをするなど、感情をコントロールできずに他人にぶつけるタイプです。本人は「指導のつもり」「自分は正しい」と思っていることも多く、悪気がない場合もありますが、周囲にとっては強いストレス源になります。
たとえば、会議中に部下のミスを大声で叱責したり、業務の遅れを誰かに押し付けたりするような発言を繰り返します。その場は収まっても、職場全体の空気がピリピリし、コミュニケーションが萎縮することで業務効率も下がっていきます。
このタイプは「自分が認められていない」「思うようにコントロールできない」と感じていることが背景にあることが多く、単なる性格の問題として片付けるのは危険です。
被害妄想型(被害意識が強い)
被害妄想型の“やばい人”は、「自分ばかり責められている」「上司や同僚に嫌われている」といった強い被害意識を抱き、実際には存在しない攻撃を感じ取ってしまうタイプです。周囲の何気ない一言や行動を「自分への批判」と受け取り、過剰に反応してしまいます。
上司が別の部下に注意しているだけなのに「自分のことを遠回しに言っている」と感じたり、メールの返信が遅れただけで「無視された」と思い込んだりして、不信感を募らせるようなケースがあります。
このタイプは、被害意識が強いあまり、自己防衛的な発言や反発的な態度をとることが多く、チーム内の人間関係をぎくしゃくさせてしまいます。さらに、「自分は悪くない」「みんなが自分をいじめている」と思い込むことで孤立し、職場内でのトラブルに発展することも少なくありません。
無責任型(責任転嫁しがち)
無責任型の“やばい人”は、自分のミスを認めず、他人や環境のせいにして責任を回避するタイプです。トラブルが起きても「自分は聞いていなかった」「それは〇〇さんの指示だった」と言い訳を繰り返し、結果的に周囲にしわ寄せがいくケースが多く見られます。
たとえば、納期の遅延を指摘された際に「必要な資料をもらっていなかった」と他部署を責めたり、報告漏れを「忙しかったから」「誰も確認してくれなかった」と正当化したりするような言動が典型例です。
このタイプの厄介な点は、本人に「悪気がない」ことです。自分のミスを素直に受け止められないため、同じ問題を繰り返し、周囲の信頼を失っていきます。その結果、チーム内の連携が崩れ、他のメンバーのストレスが増す悪循環に陥ることもあります。
感情不安定型(気分が不安定)
感情不安定型の“やばい人”は、機嫌や態度の浮き沈みが激しく、日によって言動が大きく変わるタイプです。昨日は機嫌が良くても、今日は些細なことで怒り出したり、突然落ち込んだりと、周囲がその感情に振り回されやすいのが特徴です。
同じ業務報告でも「なんで今言うの?」と怒鳴ったかと思えば、翌日には笑顔で雑談する――そんな極端な態度の変化が見られます。
このタイプの人は、感情の起伏を自分でコントロールできず、ストレスや不安をそのまま外に出してしまう傾向があります。そのため、同僚や部下が過剰に気を使い、チーム全体の心理的安全性が失われてしまうことも少なくありません。特に管理職がこのタイプの場合、職場全体に緊張感が漂い、メンタル不調の温床となる危険があります。
虚言癖型(嘘が多い)
虚言癖型の“やばい人”は、日常的に事実と異なる発言をするタイプです。本人に悪意がない場合もありますが、周囲を混乱させ、信頼関係を崩す要因となります。「上司から直接任された」と言っていない指示をねつ造したり、「取引先がこう言っていた」と嘘の情報を流して場をコントロールしようとしたりするケースがあります。さらに、「自分がやっておきました」と成果を横取りするような行動も見られることがあります。
このタイプの特徴は、嘘を「自分をよく見せるため」または「その場を取り繕うため」に使っている点です。本人の中では一貫性がなく、指摘されても「そんなつもりじゃなかった」と言い逃れることも多いものです。しかし、周囲にとっては混乱や不信の原因となり、職場全体のコミュニケーションを損ねます。
二面型(媚び・裏表がある)
二面型の“やばい人”は、上司や立場の強い人には愛想よく接する一方で、部下や同僚には冷たく当たるなど、明らかに態度を使い分けるタイプです。
表向きは社交的で印象が良いため、外からは問題が見えにくいケースも多々あります。
たとえば、上司の前では「チームのために頑張ります」と笑顔で発言しながら、裏では「自分ばかり損している」と不満を漏らし、他人の陰口を広めて職場の人間関係を乱すケースがあります。
このタイプの厄介な点は、周囲の信頼を少しずつ蝕むことです。本人は「うまく立ち回っている」と思っていても、部下や同僚からすれば「信用できない」「腹の内が読めない」と感じ、チームの士気が低下します。場合によっては、グループ間の分断や情報共有の遅れを招き、業務効率にも悪影響を及ぼします。
完璧主義型(極端なマイクロマネジメント)
完璧主義型の“やばい人”は、細部にこだわりすぎて周囲を過剰に管理し、結果的に職場全体のストレスを高めてしまうタイプです。いわゆるマイクロマネジメント傾向が強く、部下の仕事に逐一口を出し、「報告は30分ごとに」「メール文面は自分の指示通りに」など、過度な確認を求めます。
また、部下が作成した資料を「フォントが違う」「語尾が気に入らない」と何度も修正させ、納期より“自分の理想”を優先するケースもあります。
このタイプの特徴は、完璧を追い求めるあまり、他人の裁量を認められないことです。本人としては「品質を保ちたい」「チームのため」という善意から行動していることも多いのですが、結果的に部下の自主性を奪い、職場の空気を重苦しくしてしまいます。部下は「何をしてもダメ出しされる」と感じ、自信を失い、離職やメンタル不調につながることもあります。
見栄っ張り型(キラキラ依存)
見栄っ張り型の“やばい人”は、常に「自分をよく見せたい」「優秀だと思われたい」という承認欲求が強く、実際の成果よりも“どう見えるか”を重視するタイプです。“キラキラしたい症候群”型とも呼ばれ、SNSでの自己演出や社内での過剰なアピールが目立つ傾向があります。
たとえば、社内ミーティングでは「自分がチームを引っ張った」と強調する一方で、裏では他人の成果をさりげなく横取りすることもあります。また、上司の前では完璧な報告をするものの、実務面ではミスを隠して放置しているケースも見られます。
このタイプの問題点は、チームの信頼関係を損なうだけでなく、周囲のモチベーション低下を招くことです。表面的な成功にばかり意識が向くため、ミスを共有できず、問題の早期発見が遅れることもあります。さらに、自分の評価を下げないために他者を悪く言う傾向があり、職場の人間関係に不和を生じさせることもあります。
「職場のやばい人」が職場に与える影響
「職場のやばい人」がいる環境では、チーム全体のストレス負荷が急激に高まります。怒鳴る、責任転嫁をする、感情をぶつけるといった言動は、周囲の集中力を奪い、業務効率や士気を大きく低下させます。結果として、離職率が上がり、残された従業員にも疲弊が広がる“負の連鎖”が起こります。さらに、職場のストレスが慢性化すると、二次的なメンタル不調が増え、ストレスチェックの集団分析でも全体スコアが悪化する傾向が見られます。
チームのストレス負荷増加
職場に「やばい人」がいると、チーム全体のストレス負荷が一気に高まります。
常に怒鳴ったり威圧的な態度を取ったりする上司がいる職場では、周囲が常に緊張状態に置かれ、「ミスをしたら怒られる」「発言したら否定される」と萎縮してしまいます。その結果、自由な意見交換ができなくなり、チームの生産性が低下します。
また、責任を他人に押し付けるタイプの同僚がいる場合も厄介です。自分のミスを隠すために他人を巻き込み、トラブルが起きても「自分は関係ない」と逃げるため、チーム全体の信頼関係が崩れます。ある企業では、こうした人物の存在が原因で「誰も本音を言わなくなった」「報告・連絡・相談が機能しなくなった」といった事態が発生しました。
さらに、感情の起伏が激しい人がいる職場では、「今日は機嫌が良いか」「地雷を踏まないように話そう」と、周囲が常に相手の顔色を伺うようになってしまいます。
業務効率・士気の低下
「職場のやばい人」が存在すると、業務効率と士気は目に見えて低下します。完璧主義で細部に過剰にこだわる上司がいる職場では、部下が自由に意見を出せず「ミスを恐れて動けない」という空気が生まれます。その結果、いわゆる「報連相」が滞り、意思決定のスピードが遅くなります。ある企業では、上司の一言に部下が何度も資料を修正するうち、重要なプレゼンの準備が間に合わず、取引先からの信頼を失ったという事例もあります。
また、感情の起伏が激しい人物がチームにいると、周囲は常に顔色をうかがうようになり、本来の業務に集中できません。こうしたストレス環境が続くと、心理的な疲労が蓄積し、社員のパフォーマンスが低下していきます。最終的には「この職場では頑張っても報われない」と感じる人が増え、モチベーションが下がり、離職の引き金にもなります。
離職率上昇
「職場のやばい人」が、離職率の上昇を招くケースは少なくありません。
感情の起伏が激しく、部下に当たり散らす上司がいる職場では、「自分が次の標的になるかもしれない」と恐れた従業員が次々に退職していく例があります。特に、叱責や否定の言葉が日常化している環境では、優秀な人ほど早く見切りをつけ、静かに去っていきます。
また、虚言癖のある同僚や責任転嫁を繰り返す人物がいる場合、トラブル処理の負担が周囲に集中します。努力しても評価されず、不公平感が募ることで「ここで働き続ける意味がない」と感じる従業員が増えていきます。ある企業では、一人の管理職のパワハラまがいの言動が原因で、1年で半数の従業員が離職し、採用コストや教育コストの増大という深刻な経営課題につながりました。
二次的なメンタル不調の連鎖
「職場のやばい人」がいると、本人だけでなく周囲のメンタルにも悪影響が及び、二次的なメンタル不調が連鎖的に発生します。たとえば、怒鳴ったり八つ当たりを繰り返したりする上司の下では、直接叱責されていない部下までもが常に緊張し、胃痛や不眠などの身体症状を訴えるようになります。いわゆる“職場の空気が重い”状態が続くと、チーム全体が慢性的なストレスにさらされ、次第に集中力や判断力が低下していきます。
また、虚言癖や責任転嫁を繰り返す同僚がいると、他の従業員がその尻拭いに追われることになります。「自分ばかりが負担を背負っている」「努力しても報われない」という感情が蓄積し、燃え尽き症候群や抑うつ状態に発展することも少なくありません。
実際ある企業では、特定の上司の不適切な言動が原因で複数人が休職し、その負担がさらに別の社員に波及する“負のスパイラル”が起きました。
ストレスチェックの集団分析でも、このような職場では「職場の人間関係」や「仕事のコントロール感」に関するスコアが低く出る傾向があります。個人の問題として放置せず、早期に組織的な介入を行うことで、連鎖的なメンタル不調を防ぐことが重要です。
ストレスチェック結果への影響
「職場のやばい人」がいると、ストレスチェックの結果にも明確な影響が現れます。たとえば、感情の起伏が激しく、周囲に怒鳴り散らす上司がいる職場では、「職場の人間関係」「上司の支援」「職場の一体感」といった項目のスコアが著しく低下します。ある企業では一人の管理職が部署全体に強圧的な態度を取っていた結果、部署単位のストレスチェック結果が全社平均を大きく下回り、複数の社員が高ストレス者として抽出されました。
また、責任転嫁や虚言を繰り返すタイプの同僚がいると、「自分ばかりが負担を背負っている」「努力が報われない」と感じる従業員が増え、「仕事のコントロール感」や「職場の公平感」に関するスコアも低下します。さらに、こうした職場では、従業員がストレスを抱えていても「どうせ改善されない」と諦めてしまい、相談や報告の件数が減少する傾向も見られます。
ストレスチェックは、職場の健康状態を客観的に可視化できるツールです。特定の部署やチームの結果が極端に悪化している場合、その背後に「やばい人」の存在や、職場風土の歪みが潜んでいる可能性があります。定期的な集団分析と、問題の早期発見・介入が、健全な職場づくりの第一歩となります。
「職場のやばい人」への対応策(企業)
“職場のやばい人”対応する際は、感情的に反応せず、事実に基づいて冷静に会話することが大切です。また、人事担当者は「本人の性格の問題」と片付けず、ストレスチェックなどを活用して職場全体の心理的負荷を把握することが有効です。本人には、感情を落ち着かせる時間を設ける、産業医との相談を促すなど、無理のないサポートを行うことが求められます。
記録・事実ベースの対応
「職場のやばい人」への対応で最も重要なのは、感情ではなく記録と事実に基づいた対応を行うことです。トラブルメーカーとされる人の多くは、感情的なやり取りや曖昧な指摘では改善しません。むしろ「自分は悪くない」「誤解されている」と被害者意識を強め、問題がこじれるケースもあります。
たとえば、ある企業では部下への暴言や叱責を繰り返す上司が問題となりました。上司本人は「指導の一環」と主張しましたが、日々の発言や行動を日報形式で記録し、第三者を交えたヒアリングを行ったところ、明確なパワーハラスメントに該当すると判断されました。このように、日時・内容・状況を具体的に記録することで、客観的な判断材料が得られます。
記録をとることは、企業としてのリスク回避にもつながります。万が一、本人や関係者から「不当な処分だ」「名誉を傷つけられた」と訴えられた際にも、事実ベースの記録が法的根拠として機能します。
人事部門は、感情的な訴えや噂話に流されず、エビデンスに基づく対応体制を整えることが大切です。
相談ルートの明確化
「職場のやばい人」への対応で見落とされがちなのが、相談ルートの明確化です。トラブルが発生しても、「どこに、どのように相談すればいいのか」を知らないまま我慢してしまうケースは少なくありません。特に、加害者が上司やリーダーの場合、直属の上司に相談できず問題が長期化する傾向があります。
ある企業では、パワハラ被害を受けた従業員が「誰に相談しても無駄だ」と諦めてしまい、結果的に退職に至りました。その後、会社が社内報やイントラネットを通じて、人事・産業医・外部相談窓口など複数の相談ルートを明示したところ、相談件数が増加し、早期対応が可能になった事例があります。
相談ルートを明確にする際は、「相談しても不利益を受けない」「内容は守秘義務で保護される」という安心感を従業員に伝えることが欠かせません。さらに、相談後の対応フローを社内で共有しておくことで、「どう処理されるのか」が可視化され、相談のハードルが下がります。
ストレスチェックの集団分析で人間関係のストレスが高い結果が出た場合にも、こうした相談体制の整備と周知が再発防止の鍵となります。
ストレスチェックの集団分析の活用
「職場のやばい人」への対応を企業として行う際に有効なのが、ストレスチェックの集団分析の活用です。個人のストレス反応だけを見るのではなく、部署ごとの傾向を分析することで、特定の人や職場構造に潜む問題を客観的に把握できます。
たとえば、ある企業では「上司との関係」に関するスコアが特定の部署だけ極端に低いことがわかりました。ヒアリングを行った結果、部署内に威圧的な言動を繰り返す管理職がいたことが判明。本人への指導と同時に、1on1ミーティングの導入や外部相談窓口の設置を行ったところ、半年後のストレスチェック結果では大幅な改善が見られました。
集団分析は、特定の社員を名指しで問題視するものではなく、職場全体の健康状態を「データ」で見える化する仕組みです。ストレスが高い要因が「人」なのか「業務負担」なのか、「人間関係の構造」なのかを分析することで、再発防止につながる改善策を立てることができます。
また、経営層にとっても、離職防止や生産性維持の観点から有効な指標となります。やばい人を「個人の問題」で終わらせず、ストレスチェックのデータを根拠に組織としての課題として捉えることが、健全な職場づくりへの第一歩です。
「職場のやばい人」への対応策(個人)
「職場のやばい人」と関わるとき、最も大切なのは自分のメンタルを守ることです。相手を変えようとせず、まずは距離を取り、必要以上に関わらない工夫をしましょう。感情的に反応すると、トラブルが長期化したり、こちらが悪者にされたりするリスクもあります。会話は「あなたが悪い」ではなく、「このような事実があり困っている」と冷静に伝えるのがポイントです。どうしても改善が見られない場合は、上司や人事、産業医など組織の支援制度を活用する勇気を持ちましょう。
距離をとる
「職場のやばい人」との関係で最も重要なのは、適切な距離をとることです。相手に深入りしすぎると、理不尽な言動に巻き込まれたり、感情的な反応を誘発されてしまったりすることがあります。特に、攻撃的・感情不安定・被害妄想型の人は、相手の反応に過敏に反応する傾向があり、距離が近いほどトラブルが増える傾向にあります。
なかには、常に機嫌が変わる上司に「どうしたら機嫌を取れるか」と気を遣い続けた結果、自分の仕事に集中できず心身をすり減らしてしまうケースもあります。このようなときは、必要最低限の業務連絡にとどめる、メールなど記録が残る方法でやり取りするなど、冷静に線を引くことが大切です。
ちなみに、「距離をとる=無視する」ではありません。相手の言動に過剰に反応せず、事実だけを淡々と伝える姿勢を保つことがポイントです。相手のペースに巻き込まれないためには、自分のストレス反応を客観的に把握し、体調変化や不眠などのサインを見逃さないようにすることも必要です。
どうしても関係が改善されない場合は、上司や人事に相談し、配置転換などを検討してもらうのも一つの手段です。無理をして関係を修復しようとせず、自分を守るために適切な距離をとる勇気を持つことが、長く働くための最善策です。
感情で反応しない
「職場のやばい人」に対して最も避けるべき対応の一つが、感情で反応してしまうことです。怒りや苛立ちで言い返したくなる気持ちは自然ですが、相手はその反応を“攻撃の燃料”として利用することがあります。感情的に対抗すると、さらに挑発が激しくなったり、「自分は悪くない」と被害者意識を強めたりするケースも少なくありません。
常に他人を批判する同僚に反論した結果、「あの人が攻撃してきた」と周囲に言いふらされ、かえって立場が悪くなるというケースがあります。このような人は、相手を巻き込んで感情的な混乱を生み出すことに長けているため、冷静さを失った瞬間に状況を悪化させてしまうのです。
効果的なのは、「感情」ではなく「事実」で応じることです。「あなたが悪い」と言うのではなく、「このような発言があり困っています」「業務に支障が出ている」と客観的に伝えるようにしましょう。また、会話の内容は記録を残しておくと、後々のトラブル防止にも役立ちます。
そして、どれほど理不尽でも、相手の土俵に上がらないことが大切です。深呼吸をして気持ちを整える、席を外す、信頼できる上司に相談するなど、感情のコントロール方法を身につけましょう。自分の冷静さを保つことこそ、最も効果的な防御であり、長期的にはメンタルの安定と職場での信頼維持につながります。
共感より「事実」で話す
「職場のやばい人」と関わるとき、共感よりも“事実”で話すことが非常に重要です。相手の気持ちを汲もうとして共感的に接すると、一見関係が良くなりそうに見えますが、実際には誤解を招き、トラブルを深めることがあります。特に被害妄想型や感情不安定型の人は、「自分を理解してくれた」と誤って解釈し、依存的になったり、逆に些細なすれ違いで攻撃的になったりするケースもあります。
ある事例では、「上司が自分を嫌っている」と訴える同僚に「そんなことないよ」と共感を示すと、「あなたもそう思っているんだ」とねじ曲げて受け取られ、余計に問題がこじれてしまいました。このような誤認を防ぐためにも、感情的な同調ではなく“事実に基づく対話”が大切です。
具体的には、「○○さんが注意していたのは、業務の手順についてですよ」といった形で、感情ではなく起こった出来事を整理して伝えます。曖昧な言葉を避け、証拠や記録を残すことも有効です。また、話の焦点を「誰が悪いか」ではなく、「どうすれば業務が改善できるか」に向けると、建設的な対話に変わります。
共感は人間関係を円滑にするために必要なスキルですが、相手が「やばい人」である場合には慎重さが必要です。事実ベースの冷静な対応こそが、誤解や感情的な衝突を防ぎ、自分の心を守る最も効果的な方法なのです。
自分のメンタルを守るが最優先
「職場のやばい人」と関わるときに最も大切なのは、相手を変えようとするよりも、自分のメンタルを守ることです。攻撃的な発言や理不尽な要求に日々さらされると、「自分が悪いのでは」と感じてしまったり、相手のペースに巻き込まれて心身をすり減らしてしまったりすることがあります。しかし、相手の性格や行動を根本から変えるのはほぼ不可能であり、無理に理解しようとするほどストレスが蓄積してしまいます。
たとえば、感情の起伏が激しい上司に「嫌われないように」と気を遣い続けた結果、胃痛や不眠といった身体の不調に悩まされるケースは少なくありません。このような状態を放置すると、メンタル不調や休職につながるリスクもあります。
繰り返しになりますが、まずは「自分を守る」ことを最優先にしましょう。相手の言動を真に受けず、「これは、この人の問題」と切り離して考えることがポイントです。ストレスを感じたときは、休息をとる、信頼できる同僚や上司に相談する、産業医やカウンセラーに話すなど、早めのケアが重要です。
また、ストレスチェックを活用して自分の心身の状態を客観的に把握することも効果的です。「無理をしない」「逃げることも選択肢」と考えることは、弱さではなく、自分の健康を守るための賢明な判断です。
支援制度を活用する勇気
「職場のやばい人」に悩まされているとき、我慢して一人で抱え込んでしまう人は少なくありません。「自分が弱い」「大げさにしたくない」と感じてしまうかもしれませんが、組織の支援制度を活用することは“逃げ”ではなく、自分を守るための適切な行動です。
企業には、産業医面談、EAP(従業員支援プログラム)、人事・総務への相談窓口、ハラスメント相談窓口など、メンタル不調や職場トラブルに対応するための仕組みが整えられていることが多くあります。これらは、問題を客観的に整理し、必要に応じて上司や関係部署を巻き込みながら、環境改善を図るための支援を受けることができる制度です。
たとえば、理不尽な叱責を繰り返す上司について人事部や産業医に相談したことで、面談を通じた配置転換や指導改善が行われ、職場の雰囲気が改善したという事例もあります。制度を使うこと自体が「会社に問題を知らせる第一歩」になるのです。
もし、「相談したら自分の評価が下がるのでは」と不安を感じている場合は、匿名での相談や、第三者機関を通じた相談サービスの利用も検討しましょう。大切なのは、自分のメンタルやキャリアを守る勇気を持つこと。制度を正しく使うことは、個人を守るだけでなく、組織全体の健全性を高める第一歩でもあります。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
「職場のやばい人」は、個人の問題に見えて、実は職場全体のストレスや生産性に影響を及ぼす深刻な要因です。攻撃的、被害妄想的、無責任、感情不安定など、そのタイプはさまざまですが、共通しているのは「周囲の心身を疲弊させる存在」であることです。対応の基本は、感情で反応せず、事実に基づいて冷静に対処すること。そして、必要に応じて相談窓口や産業医など、組織の支援制度を活用する勇気を持つことが大切です。ストレスチェックや集団分析を通じて、職場環境の改善に結びつけていくことが、組織全体の健全化にもつながります。
国内最大級「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、多様な組織で導入されてきた信頼と実績を持つストレスチェックツールツールです。
未受検者への自動リマインド機能やリアルタイムでの進捗確認、医師面接希望者の収集など、実務に即した管理機能を標準搭載。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能になり、欠勤や離職に至る前の段階で課題を早期に発見し、対策を講じることができます。導入や運用に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>ストレスチェックサービスおすすめ22選

