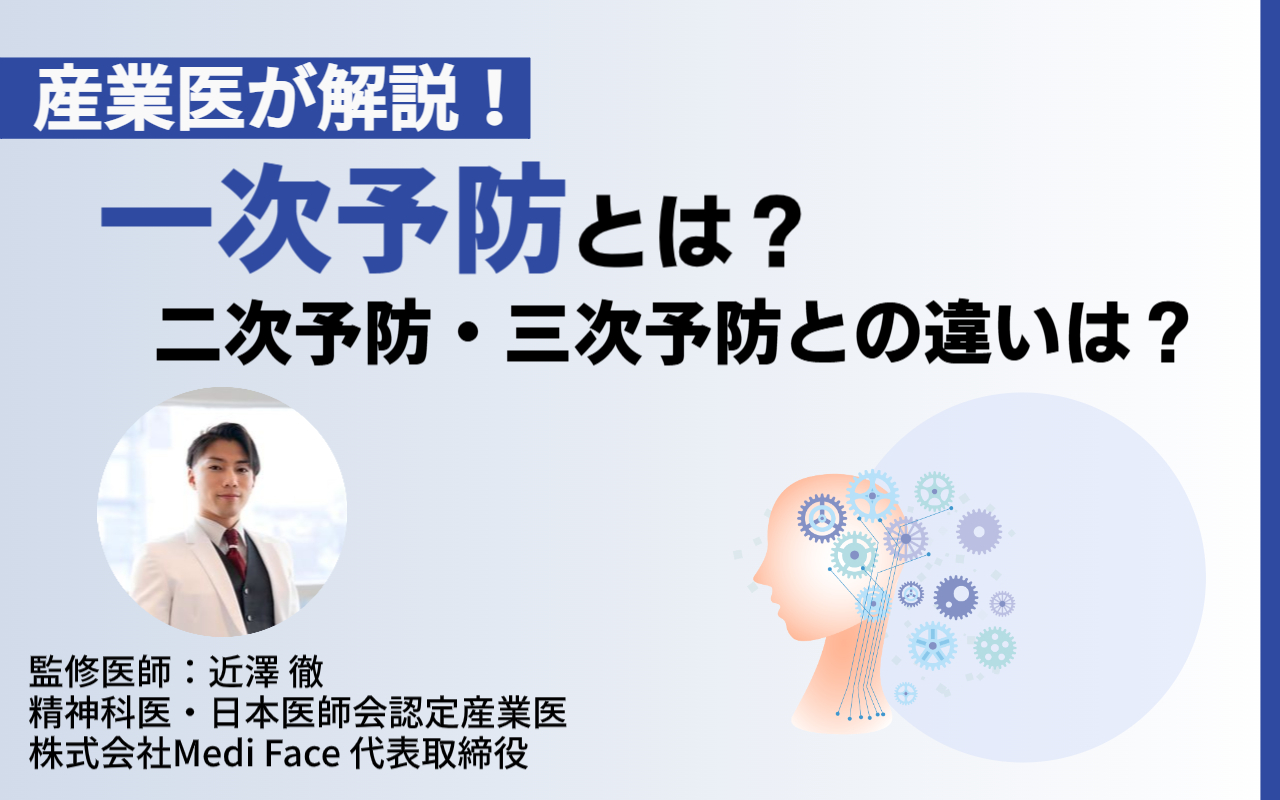
メンタルヘルス対策における一次予防とは、病気や健康障害を未然に防ぐための取り組みのことを指します。具体的には、職場の環境改善や教育研修、ストレスチェックなどを通じて、メンタルヘルス不調の発生自体を防ぐことを目的としています。
目次
一次予防とは
昨今は、雇用形態の多様化、人間関係の希薄化、職場のコミュニケーションの低下などが原因で仕事上のストレスが高まっています。
このようなストレスがあるにも関わらず、何の対策もとらずに働き続けていると、やがて心身の健康に影響を与え、うつ病などのメンタルヘルス不調となることがあります。
その結果、従業員が休職したり退職したりすれば、業務の遂行そのものに様々な支障をきたすことになります。
そこで事業場では、メンタルヘルス対策として、一次予防、二次予防、三次予防といった対策を講じる必要があります。
一次予防とは、メンタルヘルス不調を未然に防止するための組織としての施策で、ストレスチェックや教育研修、職場環境改善などが挙げられます。
また、二次予防、三次予防とは、相談対応や休職中のフォローなど、個別対応が主となります。
(1)ストレスチェック
ストレスチェック制度とは、2015年に50人以上の事業場で実施が義務づけられている制度です(なお、今後は50人未満の事業場においても義務化される可能性があります)。
ストレスチェック制度の主な目的は、働く人のストレスの状況を定期的に検査して、自身のストレスの状態を知り、自身でコントロールするセルフケアに活かすことです。
また、新たなメンタルヘルス不調者を出さないために、高ストレス者と判断された人に対しては、医師による面接指導を受けるよう勧奨します。
(2)職場環境の改善
職場環境の改善とは、職場環境そのものを見直し、職場にあるストレス要因を改善するというものです。
メンタルヘルス不調につながるストレス要因の代表例といえば、職場の人間関係と仕事の問題ですが、メンタルヘルス不調を訴える個人に対応しているだけでは、根本的な解決にはつながりません。
つまり、職場環境にストレス要因があるのであれば、組織としてその課題を取り上げて改善していく必要があるのです。
ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果から集団分析を行ってストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることができます。
(3)教育研修
教育研修も、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための重要な対策のひとつです。従業員がストレスの兆候や対処法を理解することで、早期のセルフケアや周囲への相談がしやすくなります。また、管理職がストレスの影響を知り、職場環境の改善や部下のメンタルヘルスに配慮できるようになることも大きな意義です。
教育研修を進めるうえでは、従業員向けにはストレスの仕組みやセルフケアの方法を学ぶ研修を実施し、ストレスへの気づきと対処力を高めます。管理職向けには、部下の変化に気づくポイントや相談対応の方法を学ぶ研修を行います。実践的なワークショップやケーススタディを取り入れ、職場で活かせる知識を提供することも効果的です。定期的な研修と継続的なサポートにより、健康的な職場環境を維持できます。
二次予防・三次予防とは
これまでご紹介してきたとおり、メンタルヘルス対策には、一次予防、二次予防、三次予防があります。
一次予防が主に組織対応であるのに対し、二次予防、三次予防は個別対応となります。
(1)二次予防
二次予防とは、上司や同僚の支援・気づき、相談対応などです。
職場では、上司や同僚がストレスのサインに気づき、適切な支援や相談対応を行うことが重要になります。
上司や同僚の支援・気づき
メンタルヘルス不調のサインとして、業務効率の低下、遅刻や欠勤の増加、表情の変化、対人関係の変化などが挙げられます。上司や同僚がこうした兆候にいち早く気づき、声をかけることが早期対応につながります。
相談対応
上司は、部下が安心して相談できる環境を整えることが大切です。傾聴の姿勢を持ち、決めつけずに話を聞き、必要に応じて産業医やカウンセラー、人事担当者と連携してサポートを行います。職場内での適切な対応により、メンタルヘルス不調が深刻化する前に対策ができるため、働きやすい環境づくりにもつながります。
(2)三次予防
三次予防も、二次予防と同様、個別対応が主となります。
メンタルヘルス不調による休職者に対するフォローや職場復帰支援などが挙げられます。
休職者へのフォロー
休職中には適度なタイミングで連絡を取り、無理のない範囲で状況を確認することが大切です。復帰に向けた不安を軽減するため、産業医やカウンセラーとの相談機会を設けることも有効です。
職場復帰支援
復職時には、段階的に業務を調整し、無理のないペースで仕事に戻れるよう支援します。上司や同僚は、本人の様子を見守りつつ、負担がかかりすぎないよう配慮し、定期的な面談を行いながらフォローを続けます。職場全体で理解とサポートを行うことで、再発を防ぎ長く働き続けられる環境を整えることが期待できます。
一次予防の重要性
一次予防は、メンタルヘルス対策においても非常に重要な役割を果たします。
メンタルヘルス不調は、発症してからの治療や回復に時間がかかることが多いため、そもそも不調を防ぐことが最も効果的な対策となります。従業員の心身の健康が保たれることで、生産性の向上や職場の活性化にもつながりますし、医療費や休職・離職に伴うコストを削減できるため、企業にとってもメリットは大きいです。
(1)メンタルヘルス不調の発症を防止できる
一次予防の最大の目的は、病気を未然に防ぐことです。ストレスチェックを通じて、職場や個人のストレス状況を把握し、過度なストレスがかかる前に対策を講じることで、メンタルヘルス不調(うつ病、適応障害など)の発症を防ぐことができます。
(2)健康維持と生活の質(QOL)の向上
病気になってから治療するよりも、予防するほうが身体的・精神的負担が少なく、健康な状態を長く維持できます。ストレスチェックを活用することで、職場環境の改善や適切な休養が促され、働く人の健康と生活の質(QOL)の向上につながります。
(3)医療費や社会的コストの削減
病気の予防ができれば、治療費や医療機関の負担を減らすことができます。特に、メンタルヘルスの不調による長期休職や離職は企業や社会にとって大きな損失となるため、ストレスチェックを活用して早めに対策を取ることは、経済的にも重要な役割を果たします。
ストレスチェックを通じて、早期の気づきと環境改善を行うことで、健康を守り、持続的な働き方を支えることができます。
まとめ
以上、メンタルヘルス不調を防止するための一次予防についてご紹介しました。
ストレスチェックは、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための一次予防として重要な役割を担います。従業員が自身のストレス状況を把握し、早い段階で対策を講じることで、うつ病や適応障害などの深刻なメンタルヘルス不調を防ぐことができます。
また、ストレスチェックの結果をもとに職場の環境を改善することで、働きやすい職場づくりにつながり、長期的な生産性の向上にも貢献します。特に、組織単位でストレス要因を分析し、業務負担の見直しや職場の人間関係の改善を行うことは、企業全体の健康経営にも直結します。
さらに、ストレスチェックを定期的に実施することで、従業員が自分のストレス状態に気づき、セルフケアの意識を高めることができます。結果的に、職場全体のメンタルヘルスを維持し、休職や離職のリスクを減らすことにもつながるため、積極的な活用が求められます。
:参照記事
>ストレスチェックの高ストレス者が中間管理職に多い職場とは
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹
| 【監修医師】 精神科医・日本医師会認定産業医 株式会社Medi Face代表取締役 近澤 徹  オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。 |

