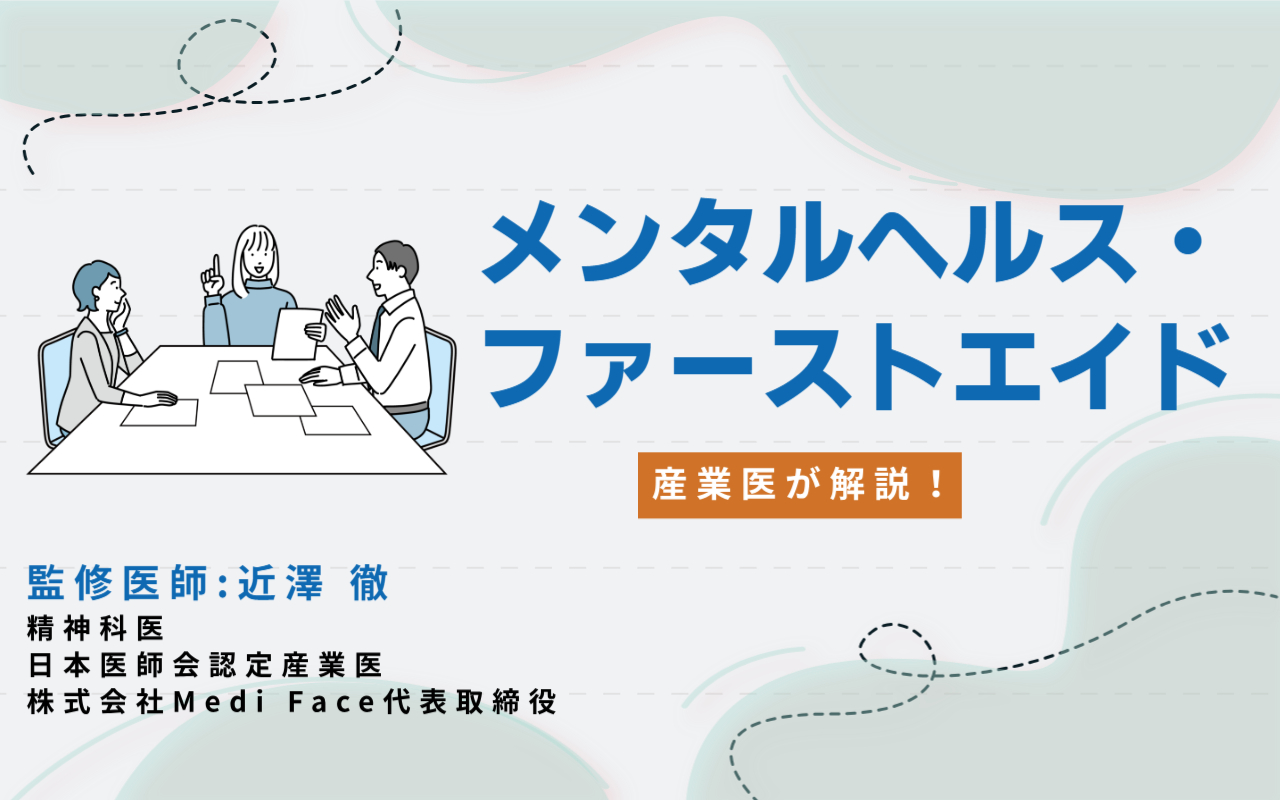
メンタルヘルス・ファーストエイド(MHFA)は、心に不調を感じている人が適切な支援につながるよう、周囲の人が初期対応を行うための知識とスキルです。
MHFAは上司や人事担当者だけでなく、同僚同士の支え合いにも効果を発揮します。ストレスチェックの結果や職場の取り組みなどでの気づきを一過性のものにせず、日々の職場内コミュニケーションに自然に組み込んでいくことで、より早い段階での対応や、安心して話せる環境づくりにつながっていきます。
目次
メンタルヘルス・ファーストエイドとは
メンタルヘルス・ファーストエイド(MHFA)とは、心の不調や精神的なトラブルを抱える人に対し、専門家ではない一般の人が初期対応として行う「心の応急手当」のことです。体のケガや病気に応急処置があるように、精神的な不調にも早期対応が重要です。大切なのは、問題に気づくこと、本人を責めずに話を聴くこと、そして必要に応じて専門機関につなぐことです。
評価と対応には、①気づく、②傾聴する、③支援を提案する、④必要に応じて専門家を紹介する、⑤周囲のサポートを整えるといった「ALGEEモデル」が使われます。また、自分自身の心の健康も忘れずにケアし、完璧を求めすぎず、あくまで「寄り添う姿勢」を大切にすることが基本です。偏見を持たず、安心して話せる環境を整えることが、心の回復を助ける第一歩となります。
(1)早期の気づきがカギ
心の不調は外から見えにくいため、表情・言動・生活リズムの変化など、些細なサインに気づくことが最初の一歩です。
メンタルヘルス・ファーストエイドでは、早い段階で心の不調に気づくことがとても重要です。精神的な問題は、身体の不調と違って目に見えにくいため、本人さえも気づいていないことがあります。だからこそ、身近な人のちょっとした変化に気づけるかどうかがカギになります。たとえば、表情が暗い、会話が減った、遅刻や欠勤が増えたなど、ささいな変化でも、いつもと違う様子を見逃さずに声をかけることが大切です。「なんとなく元気がないな」と思ったら、それが心のサインかもしれません。心の問題は、早く気づいて対応することで、回復までの道のりがぐっと短くなる可能性があります。
(2)評価と対応のステップを守る
メンタルヘルス・ファーストエイドでは「ALGEE」という5つのステップ(後述)を基盤に対応し、混乱を防ぎます。
メンタルヘルス・ファーストエイド(MHFA)では、「ALGEE」という5つのステップに沿って対応することが基本とされています。ALGEEは、①Approach(声をかける)②Listen(傾聴する)③Give support(サポートを伝える)④Encourage help(専門機関などへの相談を促す)⑤Encourage self-help(本人のセルフケアも後押しする)という流れで構成されています。ALGEEは、迷ったときに立ち戻れる基本の枠組みでもあり、安定した関わり方の助けになります(後述)。
(3)否定せず、話を聴く姿勢をもつ
批判や説教は避け、相手の気持ちを受け止める「傾聴」の姿勢が大切です。共感的に聴くことで信頼関係が築かれます。
メンタルヘルス・ファーストエイドにおいて大切なのは、相手の話を評価せず、しっかりと耳を傾ける「傾聴」の姿勢です。困っている人が最も求めているのは、「理解してもらえた」という安心感であり、正論やアドバイスではありません。つい励ましたくなったり、問題を解決しようと口をはさみたくなったりしますが、それよりもまずは相手の気持ちを受け止めることが第一です。
「つらかったね」「そう思うのは当然だよ」といった共感の言葉が、信頼関係を築く第一歩となります。批判や説教は避け、「話を聞いてくれてよかった」と思ってもらえる関わり方を心がけることが大切です。
(4)アドバイスより“寄り添い”を優先
すぐに答えを出そうとせず、「それは大変だったね」など相手の気持ちに寄り添うことが安心感につながります。
メンタルヘルス・ファーストエイドでは、答えを急いで出そうとするよりも、まずは相手の気持ちに寄り添う姿勢が大切です。話を聞いてすぐに「こうすればいい」とアドバイスをしたくなるかもしれませんが、当事者にとってはまだ気持ちの整理がついていないことも多く、助言がかえって負担になることもあります。大切なのは「それは大変だったね」「話してくれてありがとう」といった言葉で、相手の気持ちを認めることです。気持ちを受け止めてもらえると、相手は安心し、自分のペースで次に進む力を取り戻していけます。寄り添うとは、問題を一緒に抱えるのではなく、相手のそばにいる姿勢を持つこと。焦らずに、安心して話せる空気をつくることが何より大事です。
(5)専門機関へのつなぎを意識する
メンタルヘルス・ファーストエイドは“応急対応”であって、診断や治療を行うものではありません。必要に応じて、精神科医やカウンセラーなど専門家につなぐことが最終目標です。
メンタルヘルス・ファーストエイド(MHFA)は、あくまで一時的な支えを提供する“応急対応”です。ここで大切なのは、自分が専門家ではないことを理解し、無理に解決しようとせず、必要に応じて専門機関へつなぐという意識を持つことです。無理をせず、自分にできる範囲で関わりながら、専門的なサポートへとつなげることが、MHFAのゴールのひとつです。
(6)ALGEEモデルを活用する
メンタルヘルス・ファーストエイド(MHFA)では、対応の基本として「ALGEE(アルジー)」という5つのステップを活用します。
•A:Approach(近づく)
まず「A:Approach(近づく)」では、相手の状況を尊重しつつ、慎重に声をかけます。
•L:Listen(傾聴する)
次に「L:Listen(傾聴する)」では、否定や評価をせずにじっくり話を聴くことが大切です。
•G:Give support(サポートを提供)
「G:Give support(サポートを提供)」では、安心できる言葉や場を提供し、孤立感を和らげます。要な場合にスムーズに橋渡しを行います。
•E:Encourage help(専門家につなげる)
「E:Encourage help(専門家につなげる)」では、カウンセラーや医師など専門的な支援です。
•E:Encourage other supports(家族・友人などの支援をすすめる)
最後の「E:Encourage other supports(家族・友人などの支援をすすめる)」では、周囲の支えを活用するよう促します。
この5ステップに沿って行動することで、混乱せずに落ち着いた対応ができるようになります。
(7)心の応急手当は「安全な空間づくり」から
安心して話せる雰囲気や場所の提供が、相手の本音を引き出すきっかけになります。
メンタルヘルス・ファーストエイドでは、心の応急手当を行ううえで「安心して話せる空間づくり」がとても大切になります。相手が本音を話せるかどうかは、その場の雰囲気や関係性によって大きく左右されます。人目が気にならない静かな場所、落ち着いて座れるスペース、あるいはスマートフォンを置いてじっくり向き合う姿勢など、ちょっとした配慮が相手の心を開く助けになります。また、表情や声のトーン、身振り手振りも大切です。「あなたの話をしっかり聴くよ」という姿勢を示すことで、相手は「ここなら大丈夫」と感じ、本音に近い気持ちを話しやすくなります。話を引き出す前に、まずは相手が安心できる環境づくりが第一歩です。
(8)偏見やスティグマを持ち込まない
精神的な不調に対する先入観や誤解は禁物です。「怠けている」「甘えている」といった表現は避けましょう。
メンタルヘルス・ファーストエイドでは、偏見やスティグマを持ち込まないことが基本です。精神的な不調を抱える人に対して、「弱い人だ」「怠けている」「甘えている」といった先入観や決めつけは、大きな傷を与えることになりかねません。こうした誤解や偏見が、本人にとっては症状よりも深刻な負担になることもあります。不調を抱える人が安心して支援を受けられるようにするには、支える側の無意識の思い込みに気づくことも重要です。判断や評価はせず、相手の話に素直に耳を傾け、「こういう状況にあるんだな」と理解しようとする姿勢が求められます。偏見のない目線が信頼関係をつくり、必要なサポートにつなげる土台にもなります。まずは、自分の中にある思い込みを手放すことから始めましょう。
(9)自分自身のメンタルケアも大切
人のケアを行うには、自分の心の余裕も必要です。疲れすぎているときには、無理に関わらず、他の支援者につなげる判断も重要です。
メンタルヘルス・ファーストエイドを行ううえで忘れてはいけないのが、自分自身の心のケアです。相手を支えるには、まず自分にある程度の余裕が必要です。自分が疲れ切っていたり、感情的に不安定な状態だったりすると、冷静に相手と向き合うことが難しくなるだけでなく、かえって誤った対応をしてしまうこともあります。相手の話を受け止めることは、ときに想像以上のエネルギーを使います。そのため、「今の自分には難しい」と感じたときは、無理せず他の信頼できる人につなぐことも大切な選択です。支援者自身が心身ともに健康であることは、長くサポートを続けるための土台になります。時には休んだり、誰かに自分の話を聞いてもらったりしながら、自分を整えることも意識していきましょう。
(10)「完璧にやろう」と思わなくていい
メンタルヘルス・ファーストエイドは医療行為ではありません。うまく話せなくても、関心を示す姿勢そのものが支えになります。
メンタルヘルス・ファーストエイドは、医師のように診断や治療を行うものではありません。あくまで、心に不調を抱える人に「最初の手を差し伸べる」応急的な支援です。そのため、「完璧に対応しなければ」と思いすぎる必要はありません。うまく話せなくても、正しい言葉を見つけられなくても大丈夫です。大切なのは、目の前の人に関心を持ち、寄り添おうとする姿勢です。完璧なサポートを目指すよりも、自分なりに丁寧に接し、できる範囲で支えることを意識しましょう。ほんの一言や、静かにそばにいるだけでも、その存在が心の支えになることは少なくありません。
まとめ
必要なのは、特別なスキルよりも「関心」と「寄り添う姿勢」です。メンタルヘルス・ファーストエイドは、誰もが身につけておきたい“心の救急知識”といえるでしょう。
メンタルヘルス・ファーストエイド(MHFA)とストレスチェックは、職場や日常生活で心の不調に早く気づき、適切な対応をとるために有効なツールです。ストレスチェックは、従業員自身が自分のストレス状況を把握するきっかけになります。結果をもとに、必要であれば産業医やカウンセラーなどの専門家への相談につなげることができます。一方、MHFAは周囲の人が不調に気づいたとき、相手の話を丁寧に聴き、安心できる関係を築きながら、必要に応じて専門機関へ橋渡しするための考え方とスキルです。ストレスチェックで得られた気づきをMHFAの実践に活かすことで、心の不調を抱える人を孤立させず、早期にサポートする流れを作ることができます。どちらも一人ひとりのこころの健康を守るための重要な手段です。
:参照記事
>季節性うつ病とは|症状・対策・治療法
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹
| 【監修医師】 精神科医・日本医師会認定産業医 株式会社Medi Face代表取締役 近澤 徹  オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。 |

