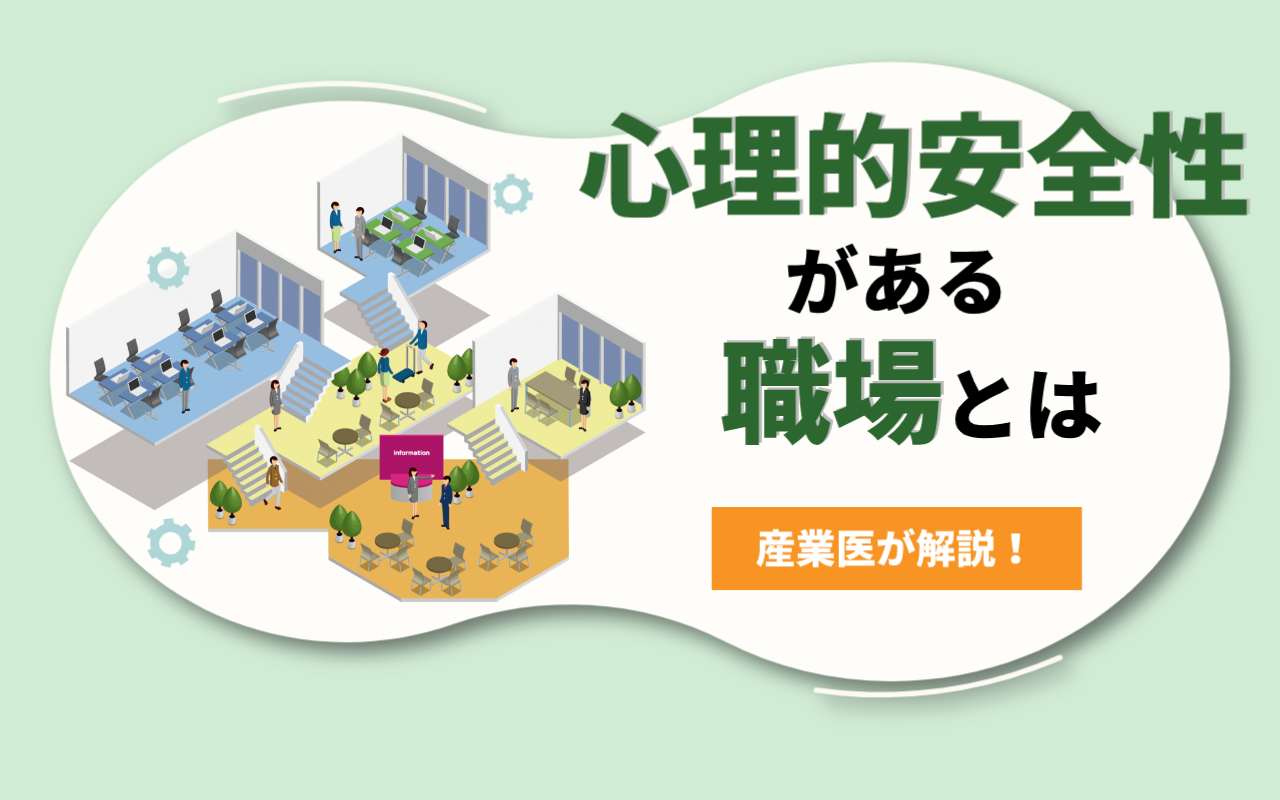
「心理的安全性」とは、職場で自分の意見や感情を安心して表現できる状態で、「心理的安全性のない職場」では、発言が減り、ミスや問題が報告されにくくなり、結果的にトラブルの隠蔽や離職につながる恐れもあります。
したがって、心理的安全性の低下にいち早く気づき、早めに対策を打つことが、組織の健全な成長につながります。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
心理的安全性とは? なぜ重要なのか
心理的安全性のある職場とは、職場で自分の意見や感情を安心して口にできる状態のことです。
たとえば、会議中に何か意見をした際に、笑われたり責められたりせず、むしろ「面白い意見だね」と受け止めてもらえる環境です。
これは単に人間関係が良いというだけでなく、上下関係や立場に関係なく自由に発言できる土台があるということです。
一方で、心理的安全性が欠けると、ミスの報告や相談がためらわれ、問題が表面化しにくくなります。結果として、業務の質が下がり、職場の空気が重くなり、離職にもつながるリスクも高まると言われています。
Googleのプロジェクト・アリストテレスで注目
心理的安全性は、Googleが実施した「プロジェクト・アリストテレス」によって注目されるようになりました。
Googleの「プロジェクト・アリストテレス」とは、効果的なチームの条件を探るために2012年にスタートした調査プロジェクトです。180以上のチームを対象に、構成や性格、働き方など多角的なデータを収集・分析したもので、最も生産性の高いチームに共通していたのは「心理的安全性」の高さでした。
つまり、メンバーが発言や失敗を恐れずに安心して行動できる空気が、成果に直結していたという結論です。
つまり、専門性やチーム構成よりも、自由に発言できる空気や信頼関係のある環境が、チームのパフォーマンスに大きく影響していたことが分かり、世界中の企業が注目するきっかけとなりました。
安心して話せる職場は生産性が高い
「心理的安全性」が高い職場では、メンバーが自分の考えや疑問を安心して発言できるため、結果として生産性が高くなる傾向があります。
失敗や課題を率直に共有でき、「次はどう改善する?」と建設的なやり取りが行われ、結果的に新しいアイデアや改善策が生まれやすくなります。
情報共有やチーム内の連携がスムーズになり、結果として仕事の効率や質が向上し、メンバーが余計なストレスや萎縮から解放されることで、目の前の仕事に集中できるようになり、一人ひとりのパフォーマンスが最大限に引き出されます。
さらに、メンバー同士の信頼関係が深まり、チーム全体としての一体感やモチベーションの向上にも好影響をもたらします。
Z世代は“空気感”に敏感:職場選びの新基準
Z世代は職場の“空気感”に非常に敏感で、上下関係の厳しさやルールの多さよりも、「ここで自分らしくいられるか」「失敗しても受け入れてもらえるか」といった心理的な安心感を重視する傾向があります。
そのため、管理体制や待遇だけでなく、職場の雰囲気や人間関係が「自分に合うかどうか」が、就職先や転職先を選ぶ際の新たな基準になっています。心理的安全性が高い職場は、若手が主体的に働きやすく、組織にとっても定着率の向上やチーム力の強化につながります。
「心理的安全性が低い職場」のリスク
心理的安全性が低い職場では、意見や疑問が表に出にくく、ミスやトラブルの報告もためらわれる傾向があります。その結果、小さな問題が放置されて深刻化したり、業務の非効率が続いたりするリスクが高まります。また、相談しづらい空気があると、ハラスメントや不満が見過ごされ、離職にもつながりかねません。
意見が出ない → ミス報告がされないリスク
「こんなこと言ってもいいのかな」「ミスしたら責められるかも」といった不安がある職場では、発言や行動が抑制されます。そして、このような沈黙の積み重ねが、重大なミスや信頼関係の崩壊につながるケースも少なくありません。上司に本音を言えない、同僚に助けを求められない、そんな空気のなかでは人材の定着も難しくなります。
逆に、心理的安全性のある職場環境では、メンバー同士が自然とフォローし合い、些細な問題にも素早く対応できるようになります。
つまり、心理的な安心感は、メンバーの主体性や協力意識を引き出す基盤であり、生産性の高い組織づくりには欠かせない要素と言えるのです。
「沈黙」は離職への第一歩
心理的安全性が低い職場では、「何も言わない」「言えない」状態が続きやすくなります。実は、この“沈黙”こそが、離職のサインとなることがあります。意見や悩みを伝えられない環境では、孤立感や不満が蓄積され、やがて「ここでは働き続けられない」という判断につながりやすくなります。
つまり、発言がないからといって問題がないわけではなく、声が出ない空気こそが、職場に潜む深刻なリスクなのです。
さらに、沈黙は周囲にも伝染し、組織全体の風通しを悪化させる可能性もあります。心理的安全性の確保は、個人だけでなくチーム全体の活力維持にも直結します。
相談できない空気はハラスメント温床?
心理的安全性が低い職場では、ハラスメントが起きていても声を上げづらく、問題が表に出ないまま放置される危険があります。
特に、加害者が上司や先輩といった立場の場合、相談すること自体に心理的なハードルが生まれます。この“相談できない空気”こそが、ハラスメントの温床になりやすく、被害の深刻化や長期化にもつながります。
また、周囲が見て見ぬふりをする構造も生まれやすく、被害者だけでなく組織全体の信頼感が損なわれていきます。
心理的安全性が確保されていれば、問題が小さいうちに声を上げやすくなり、早期発見や予防的な対応も可能です。管理職やリーダーが率先して耳を傾ける姿勢を見せることで、安心して相談できる職場づくりが進みます。
心理的安全性は“数値化”できる
心理的安全性は目に見えないものですが、ストレスチェックを活用することで“数値化”することが可能です。
たとえば、「上司や同僚からの支援」「働きやすさ」などの設問により、職場内の安心感や信頼関係の度合いを把握できます。また、部署ごとの集団分析を行えば、心理的安全性が低下している部署等を特定する手がかりにもなります。さらに、自由記述欄のコメントからは、職場の“空気感”や微妙な変化を言語化できる場合もあり、具体的な改善アクションにつなげやすくなります。
ストレスチェックで職場を可視化する
ストレスチェックとは、職場で働く人がどのような精神的ストレスを抱えているかを把握するための制度です。
Googleの「プロジェクト・アリストテレス」では、チームの成果に最も影響を与える要素として「心理的安全性」が重視されましたが、ストレスチェックも働きやすさや人間関係の安心感など、心理的安全性に関わる要素を数値化し、組織の状態を可視化することができます。
ストレスチェックは、働く人のストレス状況や職場環境に関する質問に答えることで、「上司や同僚からの支援の有無」「職場の一体感」「業務負荷の重さ」などを明らかにし、「安心して働ける環境が整っているか」「改善が必要なポイントはどこか」を可視化でき、心理的安全性の向上や離職防止にもつなげることができます。
集団分析で“空気の悪い”部署を発見
ストレスチェックの集団分析を活用すれば、心理的安全性が低下している部署やその傾向を早期に把握できます。
「上司や同僚の支援があるか」「自由に意見を言える雰囲気があるか」などの設問を通じ、働きやすさに関する職場の空気を数値化できます。たとえば、ある部署で「意見を言いにくい」と感じる人が多い場合、会議運営や上司の傾聴姿勢を見直す改善策などを、早期に講じることが可能になります。
自由記述欄が“空気の変化”になることも
ストレスチェックの自由記述欄には、単なる数値だけでは把握できない“職場の空気感”や心理的な不安、違和感が率直に書き込まれることがあります。
「最近、会議で発言しにくい雰囲気がある」「上司に相談したくても距離を感じる」といった声は、心理的安全性の低下や職場内のコミュニケーション不全を示す重要なサインです。
したがって、自由記述のコメントは、ひとつひとつに目を通し、改善のヒントとして活用する姿勢が大切です。心理的安全性を高めるには、定量的な分析に加え、こうした定性的な“生の声”をどう拾い上げ、対話につなげていけるかが鍵になります。
心理的安全性を高めるための実践アプローチ
心理的安全性を高めるには、上司と部下の1on1やフィードバックの場を日常的に設けることが効果的です。また、ストレスチェックの結果を活用した職場環境の改善、外部相談窓口の整備なども有効です。
1on1やフィードバックの場づくり
心理的安全性を高めるためには、日常的に安心して話せる場づくりが欠かせません。特に効果的なのが、上司と部下との定期的な1on1ミーティングや、チーム全体でのフィードバックの機会をつくることです。1on1では、業務の進捗だけでなく、仕事に対する不安やモヤモヤ、ちょっとした気づきなども共有できる環境を整えることが大切です。
「これを言っても大丈夫」と感じられる場があることで、メンバーの主体性が引き出され、チーム全体の関係性も深まります。また、フィードバックの時間には、ポジティブな言葉を中心に相手の行動を認めることで、安心して意見を出せる空気が育ちます。
「聴く力」研修で上司の関わり方を見直す
心理的安全性の高い職場づくりには、上司の「聴く力」が重要なカギとなります。
ここでいう「聴く力」は、ただ話を聞く(聞こえる)だけでなく、相手の気持ちや背景に寄り添いながら丁寧に耳を傾ける「傾聴」のことを指します。
上司が日頃から部下の話に真剣に耳を傾け、否定せずに受け止める姿勢を見せることで、「ここでなら安心して話せる」という空気が少しずつ育まれていきます。
そのため、管理職向けに「聴く力」を高める研修を実施し、無意識のうちに生まれる圧力や遮り、決めつけといった関わり方を見直す機会を設けることが効果的です。相手の言葉をそのまま受け止める、適度な相づちやうなずきで安心感を与えるといった基本動作を身につけることが、チーム全体の信頼関係の土台となり、心理的安全性の向上につながります。
外部相談窓口を整え“声が出せる”環境を作る
心理的安全性を高めるためには、職場内だけでなく、外部にも安心して相談できる窓口を設けることが有効です。社内では言いづらいことでも、外部の第三者になら話せるというケースは少なくありません。
特に、パワハラやセクハラ、職場の人間関係など、デリケートな問題ほど外部窓口の存在が心の支えになります。
相談内容が適切に扱われることを明示し、匿名でも対応可能な体制を整えることで、「何かあれば相談できる」という安心感が生まれ、日常の中でも声を出しやすい雰囲気が育ちます。
また、外部窓口の活用は、会社側にとっても職場の課題を早期に把握する手段となり、重大な問題の深刻化を防ぐ手立てになります。
ストレスチェックの結果を行動につなげる工夫
心理的安全性の高い職場をつくるためには、「働きやすさ」を可視化し、継続的に改善していくサイクルが重要です。空気感や人間関係といった抽象的な要素も、ストレスチェックの結果や集団分析、自由記述の声を通じて見える化できます。数値やコメントをもとに現状を把握し、そこから課題を洗い出して具体的な改善策につなげることが、職場の健全な成長を支えるポイントになります。
“働きやすさ”を可視化し、改善のサイクルへ
ストレスチェックの数値や1on1での結果を参考にしながら課題を明確にし、PDCAサイクルに沿って取り組みを進めていくことが大切です。
ストレスチェックの結果を部署ごとに集計・分析するだけでなく、性別・年代・雇用形態などで分けて集団分析を行うことで、より深い課題が浮かび上がってきます。たとえば、女性の方が男性よりもストレス要因の得点が高いという結果が出た場合、セクシャルハラスメントやジェンダーハラスメントといった問題が潜在的に存在している可能性があります。
こうした結果を受けて制度の見直しや環境整備を進めることが、心理的安全性の向上に直結します。
心理的安全性の向上はすぐに結果が出るものではありませんが、見える形にしながら改善を重ねていくことが、信頼と働きがいのある職場づくりの第一歩です。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
心理的安全性とは、職場で自分の意見や感情を安心して伝えられる状態を指し、信頼関係や協力を促して生産性向上につながります。ストレスチェックは職場の心理的安全性を可視化し、改善のきっかけづくりに活用できます。
日本最大級のストレスチェック制度「ストレスチェッカー」では、無料プランやWEB代行プランなど、さまざまなプランが用意されています。
2025年5月1日からは、「プレゼンティーイズム(体調や心理的負荷による生産性低下)」の測定が可能になり、本人が気付かない疲労やモチベーション低下も数値化でき、早期対応が可能になります。まずは体制づくりの第一歩として、ぜひご相談ください。
:参照記事
>心理的安全性とは?高める方法は?

