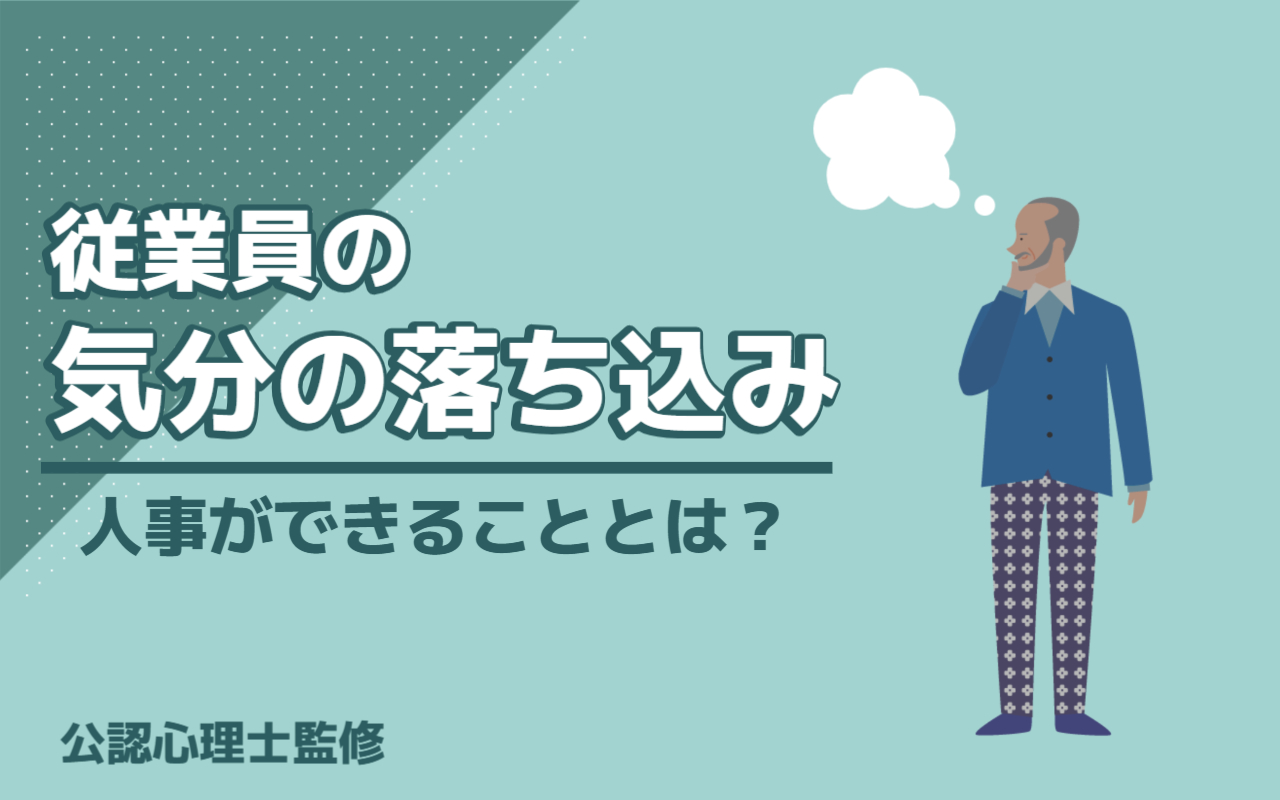
「気分の落ち込み」は誰にでも起こり得る心のサインです。
なんとなくやる気が出ない、集中できない、いつもより疲れやすい――こうした状態が続くと、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすこともあります。単なる一時的な不調なのか、それともストレスや環境による深刻な問題なのかを見極め、早めに対処することが大切です。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)
目次
気分の落ち込みの主な原因とは
気分の落ち込みに関する相談のなかで、最も多いのが人間関係のストレスです。家庭や職場、友人関係での摩擦や孤立感は、精神的な負担となり気分の落ち込みを招きます。
対人関係に限らず職場環境でのストレスも、気分の落ち込みを招きます。長時間労働や過度なプレッシャー、評価への不満などが積み重なると、心身に大きな影響を及ぼします。
また、女性の場合は月経周期や更年期、出産前後などでホルモンが大きく変動し、気分の変化につながることがあります。さらに、睡眠不足や栄養不足も大きな要因です。休養が足りなかったり食生活が偏ったりすると、脳の働きに影響し、意欲の低下や不安感を引き起こします。
原因は一つではなく複数が重なり合って現れることが多いため、自分の生活や環境を振り返り、改善できる部分を見つけることが重要です。
人間関係
家族、友人、職場など人と関わる場面は日常の大部分を占めており、その中で生じる摩擦や孤独感が心に大きな影響を与えます。
職場での上司や同僚との不和、家庭内での意見のすれ違い、友人関係での疎外感などは、強いストレスとなって気分の落ち込みを引き起こすきっかけになります。
また、SNSの普及により人間関係の範囲は広がりましたが、それがかえって比較や不安を生み、孤独感を強める要因となることも少なくありません。人間関係のストレスは目に見えにくいため、自分では気づかないうちに心の負担が積み重なっている場合もあります。
職場環境のストレス
仕事そのものや職場の仕組みが心に負担を与えるケースは少なくありません。長時間労働や慢性的な残業は、心身の疲労を蓄積させ、意欲の低下や気分の落ち込みにつながります。また、過度な業務量や短い納期に追われる環境では、プレッシャーが強くかかり、ストレスが慢性化しやすくなります。
評価制度やキャリアの見通しが不透明な場合も、不安感や無力感を抱きやすく、やがてメンタルに影響を及ぼします。
さらに、労働環境の物理的な要因が、気分の落ち込みにつながることもあります。
職場の騒音や照明、休憩が取りにくいレイアウトなどが積み重なり、気づかぬうちにストレスの原因となることがあります。こうした職場環境由来のストレスは、従業員個人の努力だけで解消できるものではなく、組織としての改善が求められます。
ホルモンバランスの乱れ
体内のホルモンは感情や自律神経の働きに大きく影響を与えます。
特に女性は、月経周期や妊娠、出産、更年期といったライフステージごとにホルモン分泌が大きく変化し、その影響で気分の落ち込みや不安、イライラを感じることがあります。
男性でも加齢や生活習慣の乱れによりテストステロンが減少すると、意欲の低下や気分の不調が生じることが知られています。
睡眠不足・栄養不足
十分な睡眠は心身の疲労を回復させ、脳の働きを整える役割を担っています。しかし、睡眠時間が短かったり眠りの質が悪かったりすると、感情のコントロールが難しくなり、イライラや不安感、気分の落ち込みが強まります。特に慢性的な睡眠不足は、自律神経やホルモンのバランスを乱し、うつ状態の引き金にもなります。
また、栄養不足も心の健康に大きな影響を及ぼします。ビタミンB群や鉄分、オメガ3脂肪酸など、脳の働きに不可欠な栄養素が不足すると、神経伝達物質の働きが低下し、やる気の低下や憂うつ感につながります。
気分の落ち込みは個人の問題だけではない
気分の落ち込みは個人の問題にとどまらず、組織全体に影響を及ぼします。
従業員が意欲を失えば生産性が下がり、業務効率の低下を招きます。さらに状態が悪化すると、休職や離職につながり、人材不足や採用・育成コストの増加といった経営リスクにも直結します。組織として気分の落ち込みを放置せず、予防や改善に取り組む姿勢が、健全な職場環境づくりと企業の持続的成長につながります。
生産性の低下のリスク
気分の落ち込みは、従業員一人ひとりの心の問題にとどまらず、組織全体のパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。気分が沈んだ状態が続くと集中力や判断力が低下し、作業効率が落ちるだけでなく、チーム全体の生産性が下がり、他のメンバーにも負担が波及する悪循環を生み出します。
個々の従業員の気分の落ち込みを軽視せず、生産性低下のリスクを予防する仕組みづくりは、健全な職場環境を維持し、企業の持続的な成長を支える重要な取り組みなのです。
休職のリスク
気分の落ち込みは、休職につながる大きなリスクをはらんでいます。気分の低下が長引くと集中力や意欲の低下、業務効率の悪化が見られ、やがて心身のバランスを崩し、医師の判断で休養を余儀なくされるケースも少なくありません。休職は従業員にとって生活やキャリアに大きな影響を与えるだけでなく、企業にとっても業務の停滞や人材不足、代替要員の確保・育成コスト増加といった経営的損失を伴います。特に中核人材が休職した場合、その影響は組織全体に及びます。
離職のリスク
気分の落ち込みが続くとモチベーションや集中力が失われ、職場への不満が強まり、「この環境では続けられない」という思いが離職という選択につながってしまうことがあります。特に、業務量の過多や評価制度への不満、十分なサポート体制が整っていない環境では、従業員は孤立感を深めやすく、転職や退職を決断せざるを得ない状況に陥ります。
離職は単に人材が減るだけでなく、採用や育成にかかるコストの増大、業務の停滞、社内の士気低下といった経営上の損失を招きます。
職場全体へ与える影響
従業員1人の不調が、組織全体のパフォーマンスを揺るがす可能性があります。
従業員が休職や離職をすると、周囲のメンバーに業務の負担が集中し、不公平感が広がることでチーム全体の士気が低下してしまいます。さらに、雰囲気が重くなることで職場全体の活気が失われ、モチベーションの連鎖的低下を引き起こすリスクもあります。その結果、業務効率の低下や離職の連鎖につながるなど、組織全体に大きな悪影響を及ぼしかねません。
従業員の気分の落ち込みのサイン
従業員の気分の落ち込みを早期に察知するためには、日常の小さな変化に目を向け、いつもと違うサインに気づくことが欠かせません。
気分の落ち込みのサインとしては、遅刻や欠勤の増加、業務パフォーマンスの低下、表情や発言の変化などが挙げられます。こうした兆候を見逃さず、さらに相談窓口の整備やストレスチェック制度を活用することで、休職や離職といった深刻な事態を未然に防ぐことができます。
遅刻・欠勤の増加
分かりやすいサインの一つが「遅刻や欠勤の増加」です。
これまで安定して出勤していた従業員が遅刻を繰り返すようになったり、突発的な欠勤が目立つようになったりした場合、単なる体調不良や一時的な事情ではなく、精神的な不調が背景にある可能性があります。
この段階で放置すれば、業務への影響が大きくなるだけでなく、本人がさらに追い込まれ、休職や離職につながるリスクも高まります。
企業としては、こうした変化を単なる勤怠問題として扱うのではなく、早めに声をかけて状況を確認し、相談窓口などへつなげる仕組みを整えることで、従業員の不調を軽減し、組織全体の健全な運営を守ることにつながります。
業務パフォーマンスの低下
これまで安定した成果を上げていた従業員がミスを繰り返すようになったり、納期の遅れや作業効率の低下が見られたりする場合、その背景には精神的な不調が隠れている可能性があります。
気分の落ち込みは集中力や判断力を弱め、業務への意欲も減退させるため、結果としてアウトプットの質やスピードに影響を及ぼします。
こうした変化を単なる能力不足や怠慢と決めつけてしまうと、本人の負担はさらに増し、最悪の場合、休職や離職につながる恐れがあります。
表情や発言の変化
普段は明るく会話をしていた人が、口数が減ったり笑顔が少なくなったりする場合、内面で大きな負担を抱えている可能性があります。また、発言のトーンが以前よりも否定的になったり、「疲れた」「もう無理だ」といった言葉が増えたりするのも注意すべき兆候です。
単なる気分の波として片付けてしまうのではなく、小さな変化に気づきやすい環境をつくり、必要に応じて面談や相談窓口への案内など早めのサポートにつなげることが重要です。
人事の「気づき」と本人の自覚が大切
従業員の気分の落ち込みを早期に察知し、適切に対応するためには、周囲の「気づき」だけでなく、本人が自分の変化に気づくことが欠かせません。自らの不調を早く自覚できれば、深刻化する前に相談や対応につなげることが可能となります。そのためには、ストレスチェックやセルフケア教育を通じて、従業員本人が自分の状態を客観的に把握できる仕組みを導入することが効果的です。
また、本人が気づきを得た際には、それを口にしやすい雰囲気づくりが不可欠です。「問題視」ではなく「サポート」という姿勢で接し、安心して声を上げられる環境を整えることが重要です。相談窓口や柔軟な勤務制度の整備は、本人が自覚した小さな変化を早期に共有するための大きな後押しとなります。
一方で、気分の落ち込みを本人が感じていたとしても、必ずしも自分から相談できるとは限りません。そのため周囲の観察や配慮も必要です。
勤怠データや評価結果に加え、上司や同僚からのフィードバックを活用し、周囲と本人の両方の気づきを生かして異変を早期に察知する仕組みを整えることが求められます。
ストレスチェックの活用
従業員の気分の落ち込みを軽減するためには、ストレスチェック制度や相談窓口の整備、柔軟な働き方の導入などを通じて従業員が早期にサポートを受けられる環境を整えることが重要です。休職を未然に防ぐ取り組みは従業員の健康維持と定着率の向上につながり、結果的に企業の安定した成長を支える大切な基盤となります。
ストレスチェックとは
従業員の心理的な負担の程度を把握するために有効な仕組みの一つが「ストレスチェック」です。
ストレスチェックとは、従業員に質問票を用いて心の健康状態を可視化する制度で、従業員の気分の落ち込みを「個人の問題」とせず、組織全体で予防・改善に取り組むために活用できる制度です。
現在は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、年1回以上の実施が義務付けられていますが、今後は、50人未満の事業場についても、義務化されることが決まっています。
ストレスチェックを導入するメリット
ストレスチェックの大きな目的は、メンタル不調の早期発見と職場環境の改善です。結果を個人にフィードバックすることで、従業員自身が自分の状態に気づき、必要に応じて産業医や専門機関への相談につなげることができます。
また、ストレスチェックの結果について集団分析を行えば、部署ごとのストレス要因を把握し、長時間労働や業務量の偏りなど、職場環境全体の課題を明らかにすることが可能です。
産業医や相談窓口の活用
従業員の気分の落ち込みを早期に発見し、深刻化を防ぐためには、産業医や相談窓口の活用が非常に重要です。従業員は気分の落ち込みを感じても、上司や同僚には言いにくく、抱え込んでしまうことが少なくありません。
産業医は医学的知見から従業員の健康状態を評価し、必要に応じて就業上の配慮や治療につなげることができます。
一方、社内外の相談窓口は、従業員が気軽に悩みを打ち明けられる場として機能し、早期対応につながります。
ストレスチェックの活用事例
ある製造業のA社ではストレスチェックを導入し、集団分析の結果を職場環境の改善に積極的に取り入れました。その結果、従来は把握しづらかった職場の課題が明確化されました。
たとえば、部署ごとのストレス傾向を分析したことで、特定の部署に長時間労働や業務の偏りが集中していることが明らかになり、業務配分や人員配置の見直しが行われました。また、従業員が自身のストレス状態を客観的に認識するきっかけとなり、メンタルヘルスの不調を未然に回避できたケースもありました。
こうした取り組みを積極的に行うことで、休職や離職の防止に成果を上げ、最終的には定着率や生産性の向上に寄与したと報告されています。
ストレスチェックは単なる法令遵守のための義務ではなく、従業員の気分の落ち込みを早期に察知し、組織全体の健康経営を推進するための実践的なツールであることが分かります。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。
まとめ
従業員の気分の落ち込みを放置すると、集中力やパフォーマンスの低下につながり、生産性が落ちるだけでなく、ストレスの蓄積や将来への不安から離職を引き起こす危険性も高まります。
こうした影響を可視化し、改善につなげる有効な手段がストレスチェック制度です。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁や上場企業、大学、大規模病院などで導入されており、未受検者への自動リマインドやリアルタイム進捗確認、医師面接希望の収集など、実務に寄り添った機能が特長です。
さらに2025年5月からは、無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担によるパフォーマンス低下)」の測定に対応し、欠勤には至らないものの生産性が下がっている従業員の状態も把握できるようになりました。ぜひ導入をご検討ください。
:参照記事
>上司ガチャとは?ストレスにどう気づく?

