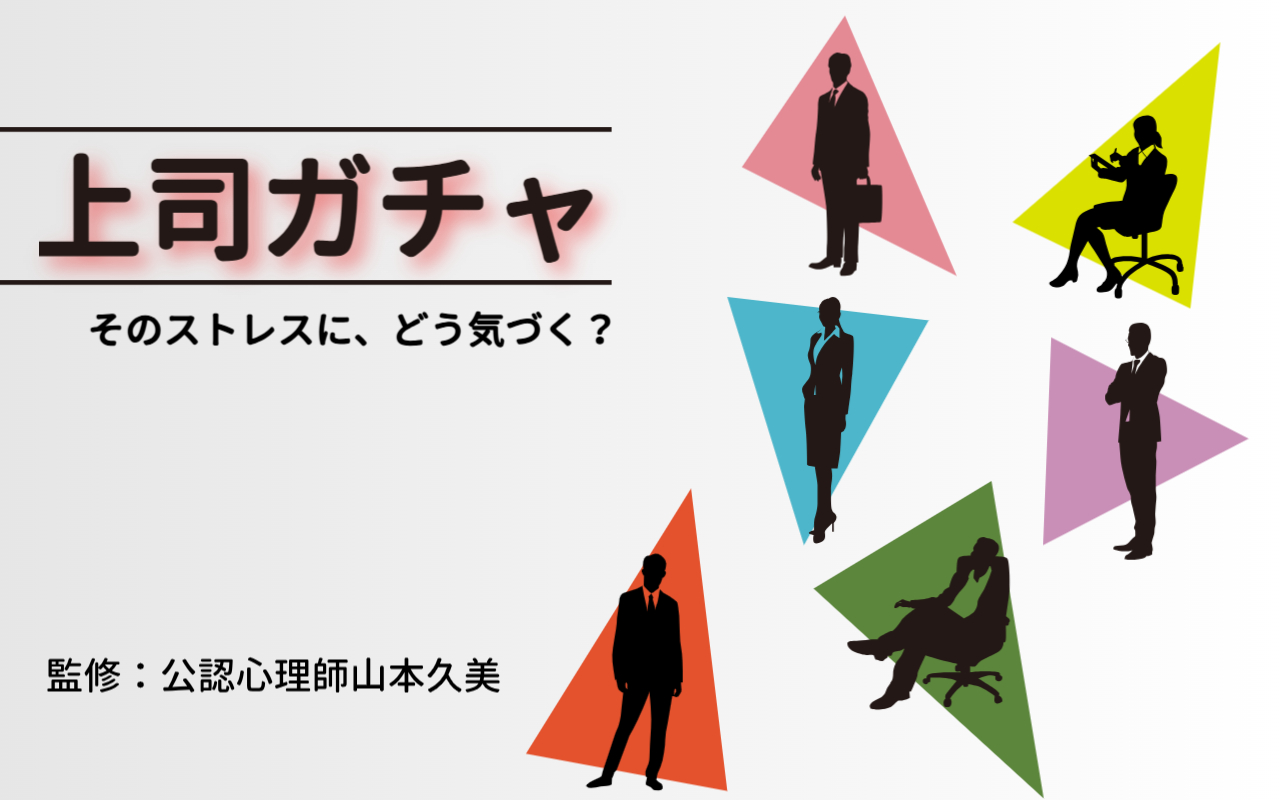
「上司ガチャ」とは、配属された上司との相性によって職場の満足度や働きやすさが左右される現象を指します。特に若手従業員やZ世代にとっては深刻なストレス要因となり、我慢が続けばメンタル不調や離職のリスクに直結します。上司との相性は“見えにくい職場リスク”で、単なる性格の不一致では片づけられません。人事労務担当者は、ストレスチェックや面談を通じて早期に兆候を把握し、必要に応じたサポートや配置転換などの対応を行う体制整備が求められます。
目次
「上司ガチャ」が職場ストレスの引き金に
「上司ガチャ」とは、配属された上司との相性によって仕事の満足度や職場環境が大きく左右される現象を指す言葉です。SNSを中心に広がった言葉で、若手従業員やZ世代を中心に共感を集めています。
相性の問題はハラスメントのように明文化しづらく、当人も「自分のわがままかもしれない」と我慢してしまいがちです。しかしそのまま放置すれば、メンタル不調や早期離職、生産性低下といった人事労務上のリスクに直結します。
「上司ガチャ」を他人事にせず、現代の職場環境に即した“見えにくいストレス要因”として、組織全体で向き合うことが求められています。
上司との相性は職場のリスク要因
「上司ガチャ」という言葉に象徴されるように、特に若手は、配属先の上司との関係性に強く影響を受ける傾向があります。指示が曖昧だったり、話しかけづらい雰囲気があったりすると、日々の小さなストレスが蓄積し、メンタル不調やエンゲージメントの低下、ひいては離職へとつながるケースもあります。
重要なのは、こうした相性の問題を「個人の資質」や「性格の不一致」で済ませず、組織的なリスクとして捉える視点です。
人事労務担当者は、定期面談やストレスチェックの結果を通じて、上司と部下の関係性に歪みがないかを見極め、必要に応じて配置転換やサポート体制の見直しを行うことが求められます。
「個人の問題」と放置するリスク
「上司と合わない」「指示がわかりにくい」「話しかけづらい」など、上司との関係に悩む従業員について、「本人の問題」「我慢すれば解決する」と放置してしまうことは、職場全体にとって大きなリスクとなります。
違和感やストレスが蓄積すれば、メンタル不調や早期離職につながる可能性があります。
人事労務担当者として重要なのは、こうした相性の問題やコミュニケーション不全を「性格の問題」「甘え」と片づけず、職場環境の課題として捉える視点です。表面的には問題が見えにくくても、定期面談やストレスチェックを通じて兆候を把握し、組織全体の信頼と活力の低下を招かないように早期の対応や配置見直しを行う体制づくりが求められます。
相談できない空気は職場の危機
「こんなことで相談していいのか」「言ったところで何も変わらない」と感じ、誰にも打ち明けられないまま我慢を重ねる従業員は少なくありません。こうした“相談できない空気”が職場に蔓延しているとしたら、それはすでに組織としての危機状態と言っても過言ではありません。従業員が声を上げづらい環境では、小さな違和感やストレスが放置され、やがてメンタル不調や突然の離職といった形で表面化するリスクが高まります。
人事労務担当者として重要なのは、「相談されないこと」自体が警告サインであるという認識です。
相談しやすい職場づくりは、単に個人を守るだけでなく、組織の持続的な健全性を守るためにも大切です。定期的な1on1やストレスチェックの活用に加え、上司を介さずに意見や不安を伝えられる仕組みを整えることが求められます。
上司ガチャに人事が気づくポイント
上司との相性が合わない「上司ガチャ」に悩む従業員は、必ずしも直接その不満を口にするとは限りません。むしろ「我慢すべき」「上司に逆らえない」と感じ、表面的には問題が見えにくいケースがほとんどです。だからこそ人事労務担当者には、間接的なサインから早期に気づく視点が求められます。
「遅刻や欠勤が増えた」「発言が減った」「「急に人との関わりを避けるようになった」などの変化は要注意です。また、ストレスチェックの結果から、組織別における「高ストレス判定が出た割合(高ストレス者率)」や「上司との関係」についての分析など、ていねいに確認することが重要です。
「上司ガチャ」の問題は、早期に気づいて対応すれば防げることも多く、組織の健全性を守るうえで欠かせない視点となります。
欠勤・遅刻は黄色信号
欠勤や遅刻といった勤怠の変化があれば、黄色信号です。
特に真面目で責任感の強い従業員ほど、不調を言葉にせず、無理を重ねた末に突発的な欠勤や遅刻というかたちで表れることがあります。こうした変化は、必ずしも怠慢ではなく、背景に「上司との相性」や「指示のストレス」が隠れていることもあるため、人事労務担当者は注意深く見守る必要があります。
勤怠管理は形式的なチェックにとどまらず、メンタルヘルス不調の予兆を把握するためにも重要です。「朝がつらい」「月曜になると体調が悪くなる」といった声があれば、ストレスによる不調を疑うべきです。欠勤・遅刻を単なる勤怠の乱れと捉えず、“黄色信号”として初期段階で気づき、面談やフォローにつなげることが、組織のリスク管理につながります。
行動の変化を見逃さない
関係性に悩む従業員ほど本音を口にできず、無理を重ねた結果、行動に変化があらわれることが多いものです。
「発言が減る」「表情が乏しくなる」「Slackやチャットの返信が極端に早くなる・遅くなる」「会議中に視線を合わせなくなる」「昼休みに一人で過ごすようになる」――こうした微細なサインは、メンタル不調につながる可能性があります。人事労務担当者は、「行動が変わった理由」に注目して、上司の指導スタイルが本人にとって過度な負荷になっていないか、指示の仕方が適切かなど、現場の状況を見直す視点が求められます。職場での“いつもと違う”は、放置すれば深刻なメンタル不調や離職リスクにつながります。
我慢している従業員ほど危ない
上司との関係に悩んでいる従業員の中には、不満や違和感を口に出せず、ひたすら我慢を続けてしまう人がいます。特に真面目で責任感の強いタイプほど、「自分が至らないだけ」「迷惑をかけたくない」と感じて声を上げず、限界まで無理をしてしまいがちです。
問題を表に出す従業員は対応しやすい一方で、何も言わない従業員の不調は気づかれにくく、突然の休職や退職という形で表面化することがあります。人事担当者は「何も言わない=問題がない」と受け取るのではなく、ストレスチェックや日常のちょっとした行動変化を通じて、見えないサインに敏感になる必要があります。沈黙は必ずしも順応ではなく、SOSである可能性があると認識することです。
ストレスチェックを“人事の気づき”に変える
ストレスチェックは、単なる年1回の義務的な検査ではなく、職場の人間関係や働き方に内在するリスクを可視化する「人事の気づきのツール」として活用することが重要です。
高ストレス判定だけでなく、部署や上司単位で傾向を分析すれば、「特定のチームに不調が集中している」「リーダー交代後に数値が悪化している」など、組織課題も発見できます。また、医師面談の案内や相談チャネルを整えることで、従業員が安心して声を上げやすい環境づくりにもつながります。ストレスチェックを“形式的なもの”に終わらせず、人事が職場の状態に気づくきっかけとして活用することが、職場改善のために重要です。
ストレスチェックは「従業員の声を拾う仕組み」
ストレスチェックは、メンタル不調者の洗い出しのためのツールではなく、「従業員の声を拾う仕組み」として活用します。
また、ストレスチェックには、自由記述欄を設けることは可能で、人事労務が“見えにくい職場の課題”を早期に察知するための有効な手段となります。
また、組織の傾向を分析することで、特定の部署や上司に関わるストレス傾向を把握し、組織改善の方向性を探ることも可能です。重要なのは、実施すること自体を目的にせず、その結果をどう活かすか。従業員の声に耳を傾ける姿勢を示し、必要に応じてフィードバックや職場環境の見直しにつなげることです。
高ストレス判定者への対応フロー
上司との関係が原因でストレスを抱えている場合、放置すればメンタル不調や退職リスクにつながる可能性が高まります。まずは、産業医面談を案内し、希望があれば速やかに実施する体制を整えておきます。
面談結果に基づいて、勤務時間の調整や配置転換など、必要な措置を講じる準備も必要です。また、該当者だけでなく、同様のストレス傾向が部署単位で広がっていないかを確認し、上司側への指導や組織改善につなげる視点も求められます。高ストレス判定は単なる個人の問題ではなく、職場全体の課題として捉え、具体的な対応フローと改善施策の両輪で支えることが重要です。
匿名で相談できるチャネルの整備
上司との関係に悩む従業員の中には、「直属の上司に言えない」「職場内で知られたくない」と感じ、問題を抱えたまま沈黙してしまうケースが少なくありません。そのため、従業員が匿名で安心して相談できるチャネルの整備も検討しましょう。たとえば、外部の相談窓口(EAP)を契約したり、上司を介さず人事や第三者機関に直接声が届く「声のポスト」を設置したりといった対策が効果的です。
重要なのは、“言いやすい空気”をつくるだけでなく、“言える仕組み”を実際に用意すること。相談先が分かりやすく明記されているか、匿名での投稿が本当に守られる設計になっているかなど、従業員の立場に立った設計が信頼感につながります。こうしたチャネルは、不満や不安が深刻化する前にキャッチする「予防」の役割も果たします。誰かが声を上げたとき、それを活かせる組織であることが、職場の健全性を支える鍵となります。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。
まとめ
従業員の“上司ガチャ”といった見えないストレスに早期に気づくには、ストレスチェックチェック後の分析と対応が鍵になります。ストレスチェッカーでは、2025年5月1日から、無料プランおよびWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調や心理的負荷による生産性の低下)」の測定が可能になります。
本人が自覚していない疲労ややる気の低下も数値として可視化でき、深刻化する前に対応するきっかけが得られます。
また、部署ごとのストレス傾向や、不調が出やすい要因を把握することも可能です。「上司との関係性」によるストレスなど、定性的に把握しづらいリスクに対しても、職場改善のヒントを得ることができます。ストレスチェックを“活かす”体制づくりの第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。
:参照記事
>職場における精神保健福祉/公認心理士監修

