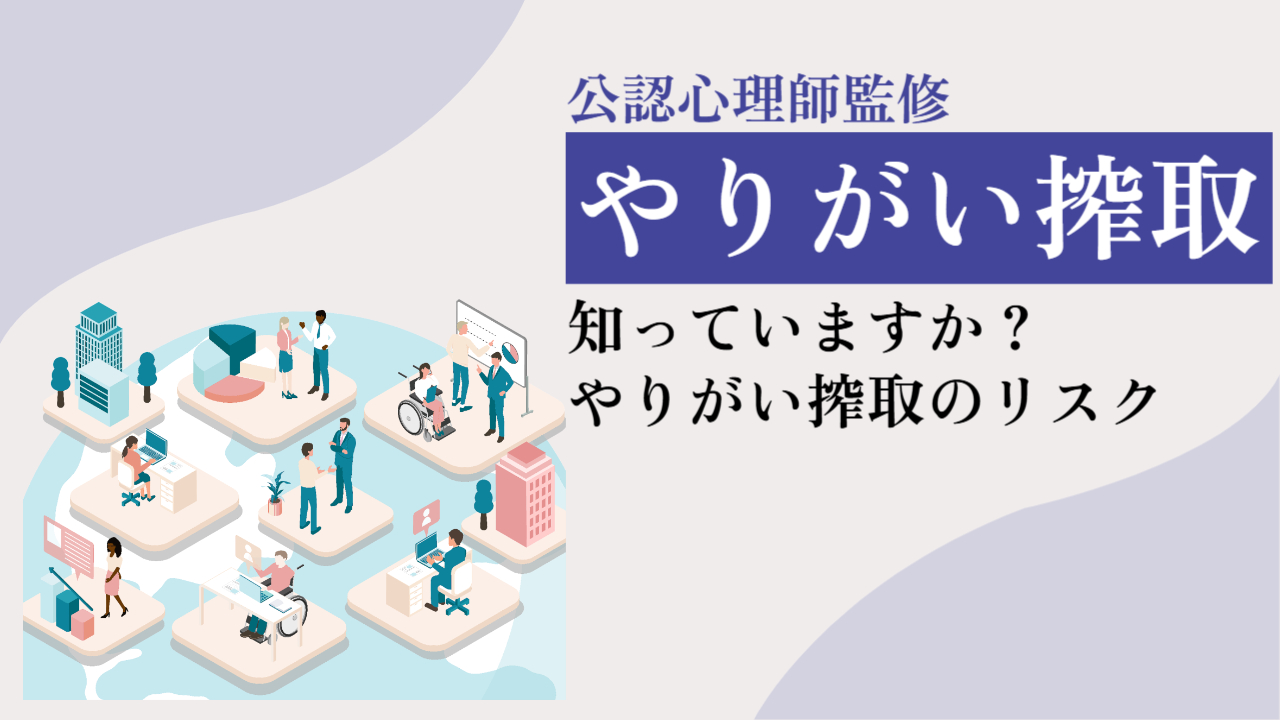
やりがい搾取とは、「成長できる」「やりがいがある」といった言葉で過重な業務やサービス残業を正当化し、労働環境の負担を軽視する状態を指します。一見前向きな職場に見えるため、本人も不調に気づきにくく、周囲も見落としがちです。
こうした環境では、ストレスチェックの数値が低く出ることもあるため、集団分析の傾向をていねいに読み解くことが重要です。発言量の偏りや、熱意に見える“焦り”が現れていないかなど、1つの分析項目(尺度)の数値に現れにくいサインを関連する複数の分析項目(尺度)から拾い、働き方のバランスを見直すきっかけに活用しましょう。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)
目次
「やりがい搾取」とは?
「やりがい搾取」とは、仕事に対する熱意や情熱を過剰に求め、正当な報酬や適切な労働環境を提供しないまま働かせる状態を指します。
企業が本来なら評価や待遇で応えるべき成果を、「やる気」や「やりがい」といった言葉で片づけて、自分たちに都合よく利用してしまうケースもあれば、反対に、働く側が「好きな仕事だから仕方ない」と、知らず知らずのうちに受け入れてしまっているケースもあります。
やりがい搾取のリスク
やりがい搾取のリスクは、離職やメンタル不調として突然表面化する点にあります。
働いている本人は「やりがいがあるから頑張れる」と自分を納得させながら、実際には過剰な業務負担や不十分な待遇を我慢し続けているため、蓄積された疲労や不満がある時点で限界に達し、突然の離職や深刻なメンタル不調という形で表面化します。
「新プロジェクトを任され評価されていた若手従業員が、引き継ぎもなく突然退職」「熱心に働いていた中堅従業員が、ある日を境に長期の休職に入る」といった事例は決して珍しくありません。
さらに、メンタル不調を抱えた従業員が労働基準監督署に相談・駆け込んだり、長時間労働やメンタル不調を理由とした損害賠償請求を行ったりするリスクもあります。
また、やりがい搾取が蔓延すると「頑張っているように見えないと評価されない」という無言の圧力が職場に広がり、チームの心理的安全性(安心して意見や相談ができる職場の状態)がじわじわと低下します。
現場で起きた「やりがい搾取」
事例1:保育現場でのやりがい搾取
保育現場では低賃金かつ長時間労働という過酷な環境が常態化しています。多くの保育士が「子どもたちとの日々が楽しいから」というやりがいを支えに働き続けていますが、そのやりがいが待遇改善を後回しにする口実となり、業務負担や疲労の蓄積を許容してしまう構造が問題視されています。やりがいを理由に耐え続けることが、離職や人材不足の悪循環を招くリスクが指摘されています。
参考:朝日新聞デジタル 公式サイト/「やりがい搾取」な保育現場 低い配置基準、手厚くするほど薄給に
事例2:医師の自己研鑽がやりがい搾取のリスク
医師の時間外労働を「自己研鑽」と位置づける慣習が、長時間労働を正当化する温床になっていると弁護士が警告しています。
診療後のカンファレンスや自主的な勉強会、研究活動などが勤務時間外とされる一方、実質的には業務の一部であり負担は大きいと指摘しており、十分な休息が取れず、心身の健康悪化やメンタル不調、離職リスクが高まる恐れがあることから、識者は、自己研鑽と業務の境界を曖昧にせず、適切に労働時間として管理・評価する必要性を強調しています。
参考:朝日新聞デジタル 公式サイト/医師の自己研鑽、経営側が利用すれば「やりがい搾取」に 識者が警告
また、別記事では、十分な収入やワークライフバランスを求め、医師が美容医療分野へ転職する動きが広がっており、地域医療や診療科の人手不足を加速させていると指摘されています。
参考:朝日新聞デジタル 公式サイト/美容医療に流れ込む若手医師、背景に保険診療の「やりがい搾取」も
やりがい搾取のサイン・兆候
従業員が「やりがい搾取されている」と感じている場合、その心境は態度や行動、言動に表れます。たとえば、会議や面談で発言が減り、意見を求められても消極的になる、必要最低限の業務しか行わなくなるといったパフォーマンス低下が見られます。
また、「どうせ評価されない」「自分ばかり負担が多い」など、不公平感をにじませる発言や皮肉が増えることもあります。
SNSや私的な場で会社や上司への不満を漏らす頻度が増えるのも一つのサインです。
さらに、有休取得の増加や遅刻・早退、体調不良の訴えが目立ち始めた場合は、メンタル面の疲弊が進んでいる可能性が高く、早期の対応が求められます。
やりがい搾取は、本人も気づきにくい
やりがい搾取の厄介な点は、当事者である本人がその状況に気づきにくいことです。「好きな仕事だから」「成長のチャンスだから」「みんな頑張っているから仕方ない」と、自らの疲労や不調を見過ごし、自己犠牲を正当化してしまいがちです。上司やチーム内に「これくらいやって当然」という空気があると、なおさら本人も断れず、無理を続けてしまいます。
周囲も「熱意がある」「期待に応えてくれている」と捉えてしまうため、負担が偏ったまま長時間放置されやすく、やがて突然の離職やメンタル不調といったかたちで表面化してしまうのです。
上司も「期待している」で済ませがち
上司が「期待している」「頼りにしている」といった言葉でモチベーションを高めようとする一方で、それが具体的な支援や業務調整を伴わない場合には、結果的に従業員へ過度な負担を押しつけている可能性があります。
特に優秀で責任感の強い人ほど、その言葉を重く受け止め、「期待に応えたい」「迷惑をかけたくない」と無理を重ね、不調を口にできず「何も言わずに辞める」ケースが多く見られます。
また、チーム全体に「これくらいやって当然」「文句を言わず頑張るのが美徳」といった“暗黙の圧力”が漂っていると、無理をしている人が声を上げづらい空気になります。
やりがい搾取は、会社側に問題ないことも
「やりがい搾取」は、必ずしも会社側に明確な問題がある場合だけで起きるとは限りません。
上司や同僚がきちんと評価しているつもりでも、その評価が本人に十分に伝わっていない場合や、本人が「成果はもっと認められるべきだ」と強く感じており、期待と現実の差が不満につながっている場合もあります。
また、SNSや転職サイトの声に影響を受けて、「自分も同じかも」と思い込んでしまうケースも見られます。
いずれにせよ、違和感を放置すると退職やメンタル不調などのリスクにつながるため、早めの対話や状況把握が必要です。
やりがい搾取を回避するための施策
やりがい搾取を防止するには、人事担当者が「やりがい」だけに依存したマネジメントから脱却し、制度と運用の両面から健全な働き方を支える必要があります。
まずは、待遇や業務量と熱意が見合っているかを定期的に見直す仕組みを設け、過度な期待や責任の偏りがないかチェックしましょう。1on1面談やストレスチェックの集団分析を活用することで、表に出にくい疲労感や心理的負担を早期に把握することが可能です。
また、管理職には「期待」や「感謝」だけで済ませず、成果や貢献を正当に評価し、業務分担やキャリア形成についての対話を重ねるよう促すことが大切です。
外部相談窓口の設置やアンケートの実施も有効で、本音が拾える環境づくりにつながります。
やりがい搾取を数値化するストレスチェック
ストレスチェックは、目に見えにくい職場の重圧や違和感を“数値”として可視化できる有効な手段です。
特に集団分析を活用することで、特定の部署やチームに疲労やストレスが集中しているかどうかを把握しやすくなります。
集団分析では、「仕事の量が多すぎる」「責任が重すぎる」「上司との関係に悩んでいる」「報酬への満足度が低い」といった項目に対する傾向が、グラフや数値で明確に示されます。数値が極端に高かったり低かったりする箇所があれば、そこには“頑張りすぎている”可能性や、プレッシャーが見過ごされている状態が潜んでいるかもしれません。
ストレスチェックは単なる義務ではなく、職場に埋もれた「見えないサイン」を掘り起こす重要なツールとして、ぜひ活用すべきです。
ストレスチェック結果を人事・管理職と共有する
やりがい搾取を防ぐためには、ストレスチェックの結果を単に数値として眺めて保管するだけでなく、人事や管理職としっかり共有し、職場での対話につなげていくことが重要です。個人のストレス度だけでなく、部門ごとの傾向や集団分析から見える兆しをていねいに読み解くことで、「表面化していない不満はないか」といった視点を持つことができます。
たとえば、特定の部署だけ上司との関係性のスコアが低い場合、そこには「やりがい」という言葉で正当化されてしまっている過重な期待や責任があるかもしれません。そうした傾向を管理職と一緒に確認し、実際にメンバーと面談を行うことで、現場の“リアルな声”に耳を傾けるきっかけになります。
「やりがい」と「待遇」「裁量」のバランスを見直す
やりがい搾取を防ぐためには、「やりがい」だけに依存した職場環境から脱却し、「待遇」や「裁量」とのバランスを見直すことが重要です。
成長できる環境であっても、給与や労働時間、仕事の自由度が伴っていないと、従業員は次第に疲弊してしまいます。
人事や管理職は、「やりがい」という言葉に過剰に頼るのではなく、制度や環境面での整備を通じて、働きがいを持続可能なものにしていく必要があります。目に見える待遇や実際の仕事の裁量を見直し、「頑張りすぎないこと」を組織全体の価値観として共有することが、やりがい搾取を防ぐ第一歩です。
1on1や定期面談で心理的安全性のチェック
1on1や定期面談は、表には出にくい不満や疲労感を拾い上げる貴重な機会です。
1on1や定期面談では、評価や指示ではなく“傾聴”を意識する姿勢が重要です。個々の感じているプレッシャーや不安に耳を傾ける場として1on1を機能させれば、知らず知らずのうちに陥っているやりがい搾取の兆候に早期に気づくことが可能になります。
また、日常的に上司や人事が「頑張っているね」「期待しているよ」と声をかけるだけでなく、「無理していないか」「やりすぎていないか」といった視点で尋ねることも大切です。
外部相談窓口の設置、アンケートの実施も有効
社内の人間関係や評価への影響を気にして声を上げづらい人にとって、外部の第三者による相談窓口は、心理的なハードルを下げる重要な役割を果たします。社内での発言は「告げ口」と受け取られる不安や、評価への悪影響を懸念してためらう人も少なくありませんが、外部窓口であれば、「自分の悩みが正当か」を客観的に確認できる機会となり、感情的な不満と事実の切り分けにも役立ちます。
また、アンケートをとるのも有効です。
「頑張りすぎていると感じることがあるか」「感謝や成果に見合う評価があるか」といった質問をすることで、組織の見えにくい負荷を可視化しやすくなります。人事担当者は、こうした仕組みの整備を通じて、従業員が安心して声を出せる土台をつくり、表面的には見えにくい「やりがい搾取」の芽を早期に摘み取ることが求められます。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。
まとめ
やりがい搾取という状態に早期に気づくには、ストレスチェック後のていねいな分析と対応が鍵になります。
ストレスチェッカーでは、2025年5月1日より、無料プランおよびWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調や心理的負荷による生産性の低下)」の測定が可能になり、本人がまだ自覚していない疲労感やモチベーションの低下といった変化も数値として可視化でき、問題が深刻化する前に対策を講じるきっかけが得られます。
また、部署ごとのストレス傾向や、不調が出やすい要因の把握も可能です。「上司との関係性」「業務負荷の偏り」「職場の一体感の欠如」など、定性的に把握しづらい要素も浮き彫りになり、職場改善に向けた具体的なヒントが得られます。ストレスチェックを“実施して終わり”にせず、実際に“活かす”体制をつくる第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。
:参照記事
>ゆるブラックとは?公認心理師 監修

