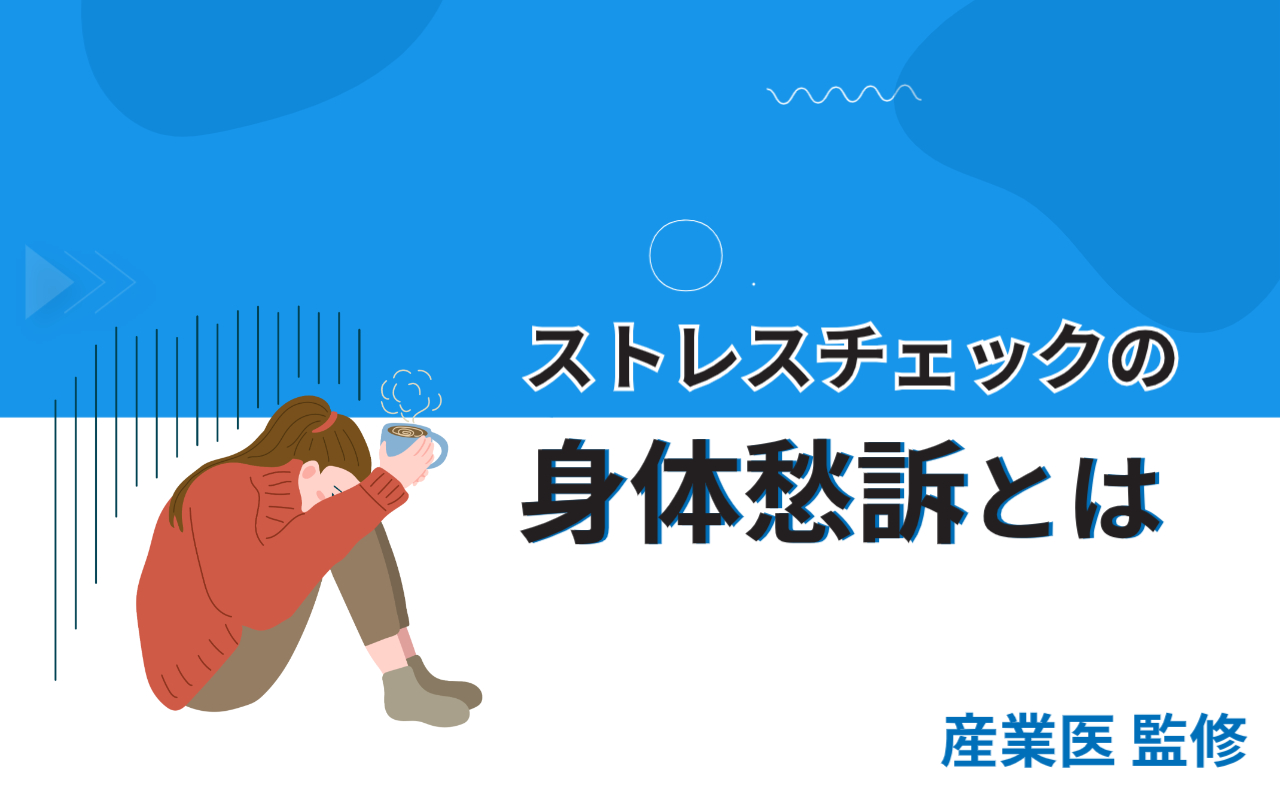
ストレスチェック制度は、従業員の心理的なストレス反応だけでなく、職場環境によるストレス要因や個人の特性(修飾要因)を多角的に把握できる制度です。
ストレスチェック制度では、ストレスなどの心理的反応だけでなく「身体愁訴(しんたいしゅうそ)」についても測定することができます。
身体愁訴とは、頭痛や倦怠感、めまいなど、検査で異常が見つからないにもかかわらず体の不調を感じる状態を指します。この記事では、身体愁訴の特徴と職場での対応について解説します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
身体愁訴(しんたいしゅうそ)とは
身体愁訴(しんたいしゅうそ)とは、頭痛やめまい、倦怠感などの身体的な不調を感じる状態を指します。症状が日によって変わったり、複数同時に現れたりすることもあります。身体愁訴は、過労やストレス、心理的な負担などが背景にあることが多く、心と体のバランスの乱れを示すサインとして現れることもあります。
参考:厚生労働省/職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル
身体愁訴の主な症状
「身体愁訴(しんたいしゅうそ)」とは、本人が自覚している体の不調全般を指す言葉です。頭痛、倦怠感、胃痛、めまいなどが代表的で、検査で原因が特定できるものから、医学的に異常が見つからないケースまで含まれます。職場では、ストレスや過労、人間関係など心理的要因が関係していることも多く、身体愁訴はメンタル面の不調を知らせるサインとなることがあります。
全身の不調:疲れやすい、体がだるい、気力が出ない
筋肉関節の不調:肩こり、首のこり、腰痛、手足のだるさ、関節の痛み
感覚器の不調:頭痛、めまい、目の疲れ、耳鳴り、音や光への過敏反応
消化器の不調:食欲不振、腹痛、便秘、下痢、吐き気
睡眠の乱れ:寝つきが悪い、眠りが浅い、朝早く目が覚める、夢が多い
その他:動悸、息切れ、喉の違和感、皮膚のかゆみ、生理不順など
ストレスチェックでは、質問票の中に「首筋や肩がこる」「腰が痛い」「目が疲れる」といった身体愁訴に関する項目が含まれています。これらの設問に対して、「ほとんどいつも」「たいてい」「ときどき」「ほとんどない」などの選択肢から回答する形式になっています。回答の中で「ほとんどいつも」や「しばしばある」といった頻度が高い場合、心身にかかるストレスが強く、身体的な負担が蓄積している可能性が高いと判断される可能性があります。
ストレスチェッカーとは
「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・医療機関などで利用されている国内最大級のストレスチェックツールです。
未受検者への自動リマインドや進捗確認、医師面接希望者の管理など、現場で必要な機能を標準搭載しているのはもちろん、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも、体調不良や心理的負担による生産性低下「プレゼンティーイズム」の測定が可能です。
ストレスチェックは、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務化されることとなりました。
導入や運用の相談は、ぜひお気軽にお問合せください。
「体調不良=心のサイン」である可能性
身体の不調が続く場合、単なる体の問題ではなく「心のサイン」である可能性もあります。強いストレスや過労、不安、緊張などが続くと、自律神経のバランスが崩れ、体調に影響を及ぼすことがあります。つまり、身体愁訴は“心身のSOS”として現れているケースも多いのです。
特に真面目で責任感の強い人ほど、自分の不調を我慢してしまい、気づかないうちに心身が限界を迎えることがあります。身体の症状だけを見て原因を探しても解決しにくい場合は、心の疲れにも目を向けることが大切です。自分の体調変化を「心からのメッセージ」として受け止め、無理をせず休息をとること、生活リズムを整えることが回復への第一歩になります。
パフォーマンス低下の原因になることも
仕事の繁忙期や人間関係のストレスなど、心理的・社会的要因が影響しやすく、環境の変化やプレッシャーによって症状が悪化することもあります。
また、身体愁訴は一時的に現れても、原因が特定できないまま放置されると慢性化しやすく、日常生活や仕事のパフォーマンス低下につながることがあります。集中力の欠如やモチベーションの低下、欠勤の増加といった形で職場にも影響を及ぼすことがあり、企業としても見過ごせない課題です。
職場で見られる身体愁訴のサイン
職場で見られる身体愁訴のサインには、「体調不良での早退が増えた」「医務室や保健室の利用が多い」「病院をいくつも受診しても原因が分からない」といった傾向があります。慢性的な疲労や不眠、集中力の低下が続く場合は、パフォーマンスにも影響します。ストレスチェック結果でも、身体愁訴のある人ほどストレス反応が高く出る傾向が見られます。
最近よく体調不良で早退している
職場で見られる身体愁訴のサインのひとつに、「最近よく体調不良で早退している」という行動があります。たとえば、頭痛やめまい、胃痛などの不調を訴えて早退するものの、医療機関での検査では異常が見つからないケースです。
ある企業では、年度末の繁忙期に早退が増えた従業員の業務内容を見直したところ、過重なタスクと上司との意思疎通不足が要因と判明しました。休養後の面談で業務量を調整し、チーム内でフォロー体制を整えたことで、再発が防がれたといいます。
身体の不調は、心のストレスが形を変えて現れる「心身のSOS」である場合も多く、単なる怠慢や体力不足と決めつけるのは危険です。早退の増加は、職場環境やメンタルの不調を示すサインとして捉え、本人との対話や職場全体のサポート体制見直しが求められます。
集中力の低下
「集中力の低下」は特に注意すべき兆候のひとつです。
ある従業員が長時間勤務とプレッシャーの中で作業効率が急激に落ち、同僚との会話も減っていったケースがありました。検査では異常が見つからなかったものの、実際は強いストレスと睡眠不足が原因でした。上司との面談で業務量を見直し、定期的な休息時間を確保したところ、集中力とパフォーマンスが回復しました。
身だしなみへの無関心
以前はきちんとしていた従業員が、ある時期から服装や髪型に気を使わなくなったり、清潔感を欠くようになったりする場合、それは単なる怠慢ではなく、心身の不調が背景にあることがあります。
たとえば、ある企業では、長期間続く慢性的な疲労を訴えていた従業員が、第に身だしなみに無頓着になり、表情も乏しくなっていったというケースがありました。医療機関での検査では異常が見つからなかったものの、実際には強いストレスと軽度のうつ状態が原因でした。業務の負担を軽減し、産業医との定期面談を取り入れた結果、少しずつ体調と意欲が回復していったといいます。
このように、身だしなみの変化は、心の疲弊やストレスによるエネルギー低下を示す重要なサインです。見た目の変化を「だらしない」と片づけるのではなく、背景にある心理的・身体的な負担に目を向け、声をかけることが早期対応の第一歩になります。
ストレスチェックの結果への影響
身体愁訴は、ストレスチェックの結果に明確に表れることがあります。ストレスチェックは本来、心理的なストレス反応を測定する仕組みですが、身体面の設問(例:「肩こりがひどい」「頭痛が続く」「疲れが取れにくい」など)にも注意が必要です。これらの回答が高い傾向にある場合、心身のバランスが崩れ始めているサインといえます。
ある企業では、職場全体のストレスチェック結果から「身体的疲労に関する項目」のスコアが突出して高く、調査の結果、慢性的な残業と人員不足が背景にあることが分かりました。その後、勤務時間の見直しと休暇取得促進を行ったところ、数か月後の再測定では身体愁訴の訴えが大幅に減少したといいます。
このように、身体愁訴は「個人の体調の問題」にとどまらず、職場環境や組織運営に潜むストレス構造を示す重要な指標でもあります。
ストレスチェックでの対応と活用
ストレスチェックは、身体愁訴に気づくきっかけとして大変有効です。肩こりや頭痛、倦怠感など、心身の負担が高い人は「高ストレス群」として抽出されやすく、本人が自覚しづらい不調の早期発見につながります。必要に応じて産業医面談やカウンセリングにつなげることで、症状の悪化を防ぐことができます。また、集団分析によって部署ごとの傾向を可視化し、長時間労働や職場環境の改善策を検討することも大切です。
本人の気づきを促すのに有効
頭痛や肩こり、倦怠感、胃の不快感などの症状は、検査で異常が見つからない場合でも、心身のストレスが原因であることが多くあります。しかし本人は「ただの疲れ」「加齢のせい」と考え、深刻に受け止めないことが少なくありません。
ストレスチェックでは、心理的ストレス反応に加え、身体的な不調に関する質問項目を含むことで、回答を通して自分の状態を客観的に振り返ることができます。自らの心身状態に気づくことは、病院受診や休養、または上司や産業医への相談につながる第一歩となります。
企業としても、ストレスチェックの結果を単なる義務ではなく“気づきの機会”として活用することが重要です。
高ストレス群として抽出されやすい
身体愁訴を抱える人は、自覚的な症状が少なくても、ストレスチェック結果では高ストレス群として検出されることがあります。
企業にとって重要なのは、この結果を単に“数値の高い人”として扱うのではなく、「心身のSOS」として受け止めることです。産業医や管理職が面談を通じて状況を把握し、業務量の見直しや職場環境の改善、早期の休養やカウンセリングにつなげることで、メンタルヘルス不調の予防にもつながります。身体愁訴は、ストレスの見えないサインを可視化する重要な指標といえるでしょう。
産業医面談やカウンセリングへつなげる
ストレスチェックの結果をもとに産業医面談やカウンセリングへつなげることは、企業にとって非常に重要な取り組みです。放置すれば、慢性化やうつ病などのメンタルヘルス不調に発展するリスクも高まります。
産業医面談では、医学的な視点から職場環境や働き方を見直し、業務軽減や勤務形態の調整など、具体的な改善策を検討できます。また、カウンセリングを通じて本人がストレス要因を整理し、セルフケアの方法を学ぶことも、再発防止に効果的です。
企業側にとっても、こうした対応は単なる「個人支援」にとどまりません。早期介入により、長期休職や離職を防ぎ、人材流出のリスクを軽減できます。さらに、従業員が安心して相談できる体制を整えることで、心理的安全性の高い職場づくりにもつながります。
集団分析と職場環境改善
ストレスチェックで得られるデータを集団分析に活かすことで、身体愁訴の傾向を職場単位で把握し、根本的な職場環境の改善につなげることができます。例えば、「肩こり」「倦怠感」「頭痛」などの訴えが特定の部署や業務に集中している場合、長時間労働や人員配置の偏り、コミュニケーション不足など、構造的な問題が潜んでいる可能性があります。こうしたデータを可視化することで、個人の不調を「個人の問題」として片づけるのではなく、組織全体の課題として捉えられる点が大きな利点です。
また、集団分析を定期的に行うことで、メンタルヘルス不調の早期発見にもつながります。従業員のストレス反応が高まる兆しを把握し、配置転換や業務改善などの対策を早めに講じることで、休職や離職を防ぐことができます。結果として、生産性の維持・向上につながり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。
さらに、従業員の健康を重視し、データに基づいて環境改善を行う姿勢は、社内外に対して「従業員を大切にする企業」というブランドイメージを高める効果もあります。身体愁訴への対応は、個人のケアにとどまらず、企業価値の向上そのものにつながる重要な経営課題といえます。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
身体愁訴(しんたいしゅうそ)は、体の不調として現れながら、その背景に心理的ストレスが隠れていることが多いサインです。ストレスチェックは、こうした「心身のSOS」を早期に可視化する有効なツールです。個人の気づきを促すだけでなく、集団分析を通じて職場全体の負担傾向や業務構造の問題を把握し、環境改善へつなげることができます。また、産業医面談やカウンセリングによる早期介入は、休職や離職の防止、生産性の維持に寄与します。身体愁訴への理解と対策は、従業員の健康を守り、組織力を高める第一歩です。
国内最大級「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、多様な組織で導入されてきた信頼と実績を持つストレスチェックツールツールです。
未受検者への自動リマインド機能やリアルタイムでの進捗確認、医師面接希望者の収集など、実務に即した管理機能を標準搭載。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能になり、欠勤や離職に至る前の段階で課題を早期に発見し、対策を講じることができます。導入や運用に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>ストレスチェックサービスおすすめ22選

