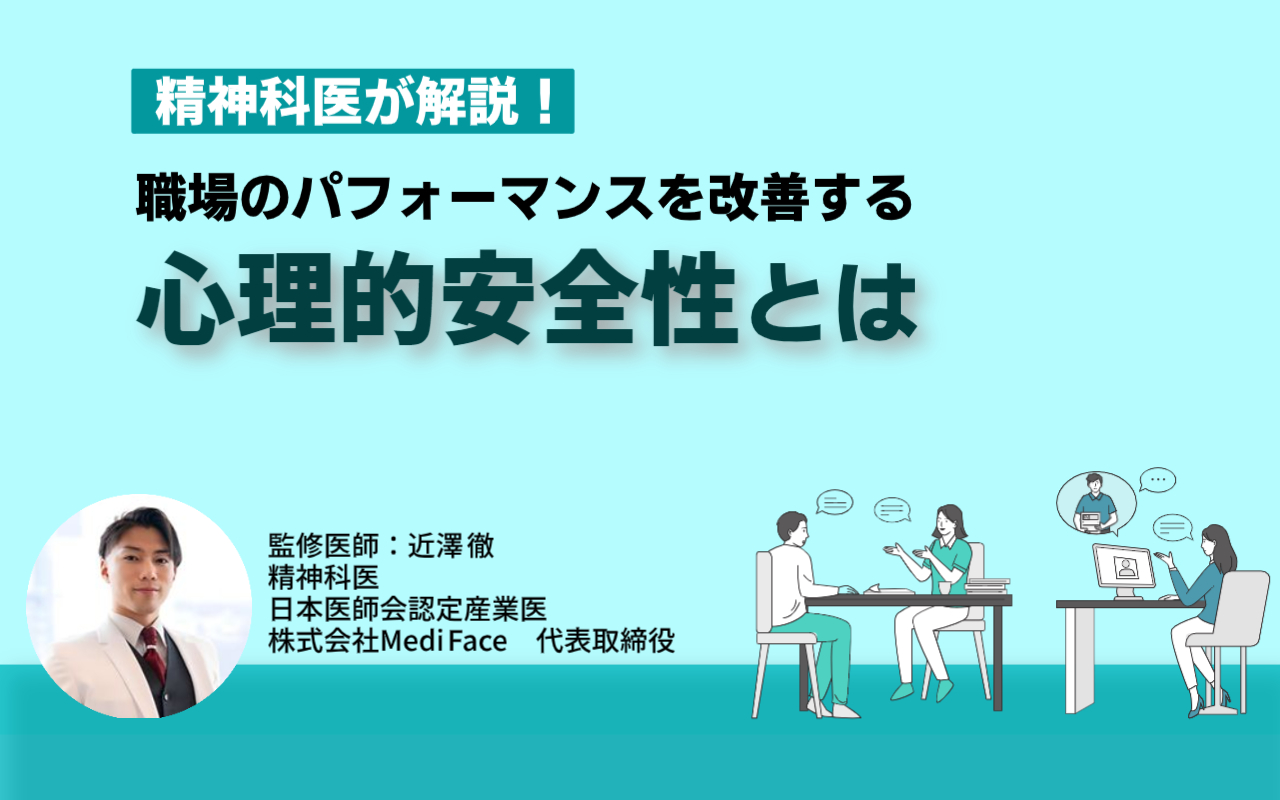
チームが優れたパフォーマンスを発揮するために、近年注目されているのが「心理的安全性」という概念です。心理的安全性とは、ハーバード大学のエイミー・C・エドモンドソン氏が提唱したもので、「チームのメンバーが対人リスクを取ることに対して安心感を持ち、率直に意見を述べることが許される状態」と定義されています。もう少し分かりやすくいうと「助けを求めたりミスを認めたりしても、誰も罰せられないことが保証されている感覚」ということになります。
最近は、離職率の高さが問題視されていますが、この心理的安全性を高めることで、離職率の低減やメンタル不調者の減少、パフォーマンスの向上などさまざまなメリットが期待できます。この記事では、職場の心理的安全性を高める具体的な方法も紹介します。
目次
心理的安全性とは
心理的安全性とは、どのような言動・行動をとろうとも、組織に拒絶されない状態のことを指します。ビジネスシーンにおいて言えば、「上司や同僚に意見をしても拒絶されない関係が構築されていれば、心理的安全性が保たれている」と考えることができます。
この概念が注目されたきっかけの一つは、Googleが行った「プロジェクト・アリストテレス」の結果です。Googleの研究によれば、優れたチームには共通して心理的安全性が高いという特徴があったというものです。
心理的安全性のある職場では、次のようなメリットが見込めます。
|
・パフォーマンスの向上 ・活発な意見交換 ・メンタル不調者の減少 |
心理的安全性のある職場はパフォーマンスが向上する
心理的安全性に関する研究では、心理的安全性が情報共有、仕事の成果、従業員の満足度に密接に関連していることが示されています。心理的安全性が確保された職場では、従業員が自由に意見を述べたり、新しいアイデアを提案したりすることができるため、会社のために積極的に働こうというモチベーションが向上し、パフォーマンスの向上が期待できます。
また、心理的安全性が高い環境では、同僚間の信頼と協力が深まり、情報共有が円滑に行われるため、チーム全体の生産性も向上します。さらに、健全な競争意識が芽生え、相乗効果を生む可能性もあります。
心理的安全性のある職場は活発な意見交換が実現する
心理的安全性の高い職場では、メンバーが意見を拒絶される心配がないため、活発な意見交換が期待できます。誰もが安心して自分の意見やアイデアを共有できるため、クリエイティブな発想や建設的な議論が自然と生まれます。結果として、問題解決が迅速に行われるだけでなく、新たなアイデアや革新的な取り組みも促進されます。
特に成長途中の会社では、様々な意見やアイデアが必要不可欠です。企業が次のステージに進むためには、多様な視点からのフィードバックや新しいアプローチが求められます。そのため、心理的安全性を高めて社員一人ひとりが自信を持って意見を述べられる環境を整えることで、企業全体の成長を加速させることができます。
心理的安全性のある職場はメンタル不調者が減少する
心理的安全性のある職場では、従業員一人ひとりが尊重され、マネージャーとの関係性も良好であるため、メンタルヘルス不調者の減少が期待できます。社員が安心して悩みや困難を打ち明けられるため、問題が深刻化する前に対処することができる確率が高まります。結果として、メンタルヘルス不調者が減少し、離職率の低減効果も期待できるでしょう。
メンタルヘルス不調者が減少すれば、社員のモチベーションや仕事のパフォーマンスが向上し、職場全体の雰囲気も良くなります。離職率が低い職場は、社員の定着率が高まり、新入社員に対する教育コストの削減にもつながります。長く働き続ける社員が多ければ、組織全体の経験値やノウハウが蓄積され、業務の効率化や質の向上にも寄与します。
心理的安全性を高めるには
職場の心理的安全性を高めるには、以下のポイントが重要です。
|
・質問・相談しやすい環境作り ・価値観の共有 ・評価制度の導入 ・ストレスチェックの活用 |
質問・相談しやすい環境作りを行う
質問や相談をした際に、それを一蹴されるような職場では、心理的安全性があるとは言えません。質問や相談に対して親身に寄り添う環境を作ることで、心理的安全性の向上が見込めます。特に、新しいアイデアや意見が生まれやすい環境を作るためには、どんな意見でも真摯に受け止める姿勢が重要です。
ただし、なかには相談や質問を年の離れた上司にするのは気が引けるケースも考えられます。そこで、年の近い社員をメンターとして教育を担当させるのも一つの手です。メンター制度を導入することで、新入社員や若手社員が気軽に質問や相談をできる環境が整い、心理的安全性が高まります。メンター自身も成長の機会を得ることができ、組織全体のスキルアップにもつながります。
価値観をチーム内で共有する
価値観があまりにもかけ離れている職場だと、自分の意見は拒絶されていると感じてしまうリスクがあります。そのため、職場で価値観を共有することも、心理的安全性を高める上で重要です。共通の価値観やビジョンを持つことで、チーム全体が一体感を持ち、協力して目標達成に向かうことができます。価値観の共有は、組織文化の基盤となり、社員同士の信頼関係を強化する助けとなります。
適切な評価制度を導入する
心理的安全性を向上させるためには、社員を適正に評価する制度を導入することも大切です。制度が整備されれば、社員は積極的に意見を投げかけるようになるでしょう。重要なのは、その意見を拒絶せずに受け入れる体制を整えることです。その意見をマイナスに評価してしまうと、心理的安全性は一気に下がってしまいます。評価をする際には、決してネガティブな印象を与えないように注意しましょう。意見がたとえ不採用になったとしても、そのプロセスを丁寧に説明し、意見を出したこと自体を評価する姿勢が求められます。
意見や提案に対しては単に否定するのではなく、どうすれば改善できるか、どのような点が評価されるのかを明確に伝えることで、社員は安心して次の提案に挑戦できます。
さらには、意見や提案が実際に採用され、成功した事例を共有する方法もおすすめです。他の社員が積極的に意見を出す動機付けとなりますし、成功事例は、心理的安全性が高い職場の象徴となり、組織全体の信頼感を醸成することにつながります。
ストレスチェックを活用して早期に問題を把握する
職場でストレスチェックを行うことで、社員が何に対して不満を抱いているのかを把握できます。
ストレスチェックの項目には、「職場の方針に自分の意見が反映されている」という項目も含まれており、これは、心理的安全性の定義と同じような要素を持っています。この評価項目が低ければ、職場の風通しが悪く、心理的安全性が保たれていないことを示唆しています。
具体的には、定期的にストレスチェックを行い、「職場の方針に自分の意見が反映されている」という項目の評価が低い場合、その原因を探ります。そして原因を把握した後で、改善策を立案します。例えば、意見が反映されていないと感じている社員が多い場合には、意見を積極的に取り入れる仕組みを導入することが考えられます。実施した改善策の効果については定期的に評価し、必要に応じて調整を行います。社員からのフィードバックを積極的に取り入れ、さらなる改善を目指します。
まとめ
心理的安全性のある職場では、それぞれの従業員が尊重され、マネージャーとの関係性も良く、メンタルヘルス不調者も減少し、離職率の低減が期待できます。
心理的安全性が確保された職場では、従業員が互いに尊重され、マネージャーとの関係性も良好になります。その結果、メンタルヘルスの不調を抱える従業員の減少も期待されます。このように、心理的安全性は、チームのパフォーマンス向上と従業員のウェルビーイングを促進するために重要な要素となっています。
価値観を共有し、意見の評価制度を導入し、さらにストレスチェックを活用して職場への不満を早い段階で認識することで心理的安全性を高めることは、チームが高いパフォーマンスを発揮するために非常に重要な要素といえるのです。
一方で、心理的安全性が保たれすぎていれば、「ぬるま湯」になるリスクも存在します。職場の雰囲気が緩くなりすぎないよう、上司が上手くマネジメントすることも重要です。
| 【監修医師】 精神科医・日本医師会認定産業医 株式会社Medi Face代表取締役 近澤 徹 
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。 |

