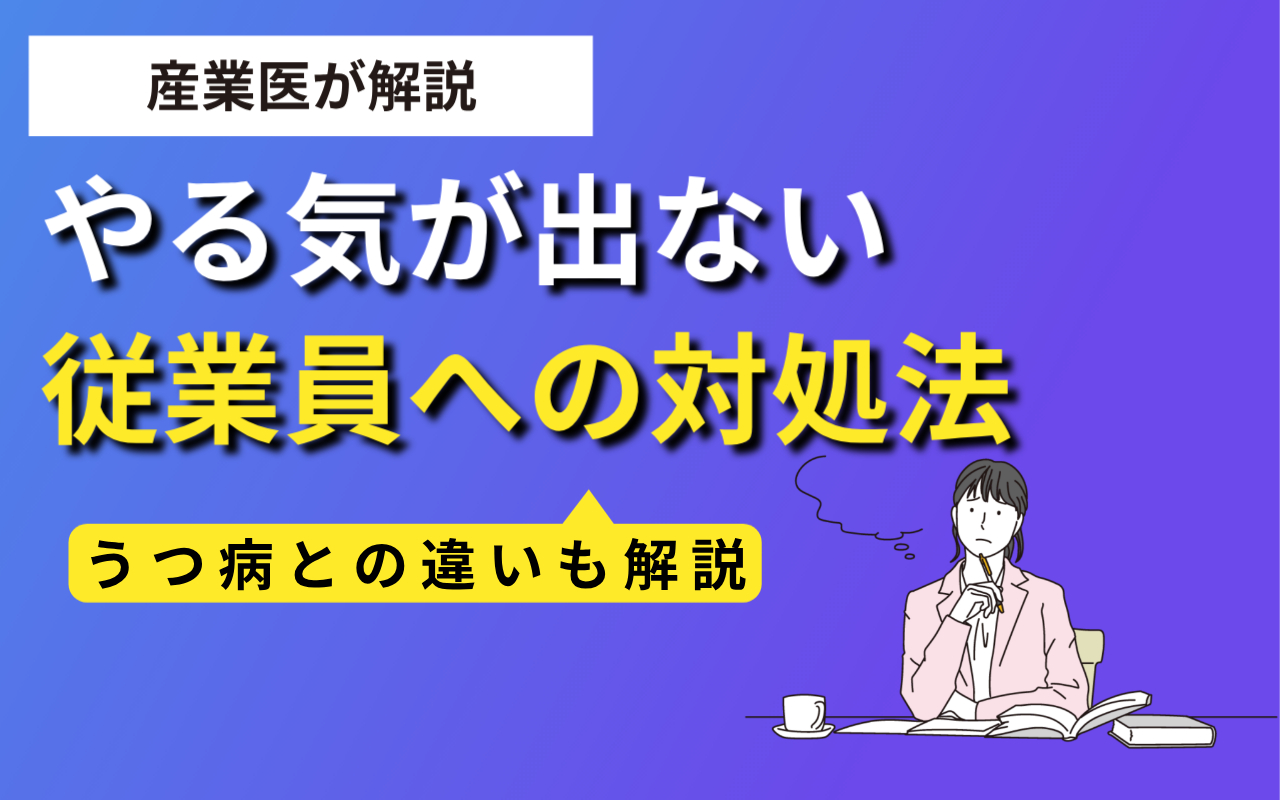
従業員の「やる気が出ない」状態は、企業にとって非常に悩ましい問題です。
従業員が慢性的にやる気を失っている場合、その背景には単なる疲労や一時的なストレスではなく、うつ症状が潜んでいる可能性があります。
放置すると休職や離職につながり、組織全体の環境や生産性に深刻な影響を与えることもあります。
こうしたリスクを未然に防ぐには、ストレスチェック制度を有効に活用し、従業員の小さな変化を早期に把握することが重要です。また、相談窓口の整備や柔軟な働き方の導入といったサポート体制など、従業員が安心して支援を受けられる環境も求められます。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
やる気が出ない=うつ?
「やる気が出ない」状態は、単なる疲労や一時的な気分の落ち込みではなく、メンタルヘルス不調の可能性も考えられます。メンタルヘルス不調は、業務への集中力低下や欠勤・休職など、企業全体のパフォーマンスにも影響を及ぼす深刻な問題です。企業としては、従業員の小さなサインを見逃さないことが重要です。
やる気が出ない従業員が増えている背景
近年、「やる気が出ない」と訴える従業員が増えています。
長時間労働や人手不足による業務過多、評価制度の不透明さやキャリアの見通しの不安定さは、従業員の心理的負担を増大させます。さらに、テレワークやハイブリッド勤務の普及によって働き方の柔軟性は高まった一方で、同僚や上司との関係が希薄化し、孤独感や不安を強める要因にもなっています。
加えて、物価上昇や将来への経済的不安も重なり、従業員の心身のストレスは一層強まっています。
職場でよく見られるサイン
職場で「やる気が出ない」と訴える従業員には、メンタルヘルス不調のサインが隠れている可能性があります。
以前は積極的に取り組んでいた仕事に対して急に関心や意欲を示さなくなる、集中力や判断力が低下しミスが増える、遅刻や欠勤が多くなる、会議や雑談など同僚との関わりを避けるといった行動が見られます。
些細なことで落ち込む、怒りっぽくなる、自己否定的な発言が増えるなども代表的な兆候です。また、頭痛や腹痛、慢性的な疲労感、不眠や過眠といった身体症状として現れることも少なくありません。
やる気が出ない原因と「うつ」
「やる気が出ない」という状態が数週間以上続き、仕事への意欲低下や集中力の欠如、自己否定的な発言が目立つ場合は、単なる一過性の疲労ではなく「うつ」の兆候であると考えられます。人事担当者は「やる気が出ない うつ」の可能性を正しく理解し、ストレスチェックや定期的な面談を通じて従業員の変化に気づく仕組みを整えることが重要です。
一時的なストレスと、うつ病の違い
「やる気が出ない」という状態を見極める上で重要なのが、一時的なストレスによる落ち込みと、うつ病との違いです。
人は誰しも仕事の繁忙期や人間関係のトラブルなどで一時的に気分が沈むことがあります。この場合は、十分な休養や環境の改善で比較的短期間に回復することが多く、根本的な生活機能に大きな影響を及ぼさないのが特徴です。
一方で、うつ病は脳内の神経伝達の働きに変化が生じることにより、長期間にわたって「やる気が出ない」「興味を持てない」といった症状が続きます。さらに、睡眠障害や食欲不振、体のだるさなど心身両面に影響を及ぼすため、通常の休養だけでは改善が難しくなります。
併発しやすい症状(集中力低下など)
うつ病は、抑うつ気分だけでなくさまざまな併発症状が見られることが多く、職場でのパフォーマンス低下につながります。
代表的なのは集中力や判断力の低下で、ミスが増えたり、業務処理のスピードが落ちたりといった影響が出ます。
また、物事への興味や喜びを感じにくくなる「興味喪失」や、慢性的な疲労感、睡眠障害、食欲不振などの身体的な症状も伴います。
こうした症状が複合的に現れることで、「やる気が出ない うつ」は一時的なストレス反応との区別が難しくなる場合があります。
DSM-5にみるうつ病の診断基準
DSM-5によるうつ病の診断基準は、企業の人事担当者が従業員の不調を理解するうえで重要な指標となります。うつ病は「抑うつ障害群」に分類され、「大うつ病性障害」とも呼ばれています。診断の目安は、抑うつ気分や興味・喜びの喪失といった中核症状を含む9つの症状のうち、少なくとも5つ以上が2週間以上続く場合とされています。
主な症状には、気分の落ち込み、意欲の低下、食欲や体重の変化、不眠や過眠、極端な疲労感、集中力の低下、自己評価の低下、さらには死にたい気持ちまでが含まれます。
人事が取るべき具体的な対応
「やる気が出ない」という状態を抱える従業員に対して、人事担当者が適切に対応することは、早期の回復や離職防止に直結します。
まず大切なのは、無理に励ましたり叱責したりしないことです。「頑張れ」「気合が足りない」といった言葉は、また、企業が導入しているストレスチェック制度を積極的に活用し、職場全体のメンタルヘルス状況を把握することも有効です。必要に応じて産業医や外部の相談窓口へつなげ、専門的なサポートを受けられるよう橋渡しを行うことが重要です。
無理に励まさない・叱責しない
「やる気が出ない」の状態にある従業員に対して、人事担当者がまず意識すべきことは、無理に励ましたり叱責したりしないことです。
職場では「もっと頑張って」「気持ちの問題だ」といった言葉をかけがちですが、これは本人に「理解されない」という孤独感や「自分はダメだ」という自己否定感を強め、症状を悪化させる要因となりかねません。
パフォーマンス低下を責めるのではなく、「体調を第一に考えてほしい」「必要なサポートがあれば相談してほしい」といった安心感を与えるメッセージを伝えることが大切です。
プライバシーに配慮した声掛け
メンタルヘルスに関する話題は、本人にとって非常にデリケートな領域であり、他の同僚の前で問いかけたり、業務の場で突然切り出したりすることは避けるべきです。声をかける際は、静かな環境や個室などで「最近少し疲れているように見えるけれど、体調は大丈夫ですか?」といった配慮ある言葉を用い、本人が安心して話せる雰囲気を作ることが重要です。また、状況を聞き出すことを目的とするのではなく、「必要なサポートがあればいつでも相談してほしい」という姿勢を示すことが大切です。従業員が自ら話す準備ができるまで待ち、決して無理に聞き出さないことが信頼関係の維持につながります。
ストレスチェック制度の活用
「やる気が出ない」という状態に早期に気づくためには、ストレスチェック制度の活用が非常に有効です。
ストレスチェックは、従業員が日常的に感じている心理的負担や疲労感を数値化し、客観的に把握できるツールで、従業員自身が自分の状態に気づくきっかけになると同時に、人事や管理職が組織全体のストレス傾向を把握することも可能となります。
「やる気が出ない」といった漠然とした訴えは、本人も原因を明確にできない場合が多く、ストレスチェックを通じたデータの裏付けが状況把握に役立ちます。
産業医や外部相談窓口につなぐ
「やる気が出ない」といった状態が疑われる従業員を適切にサポートするためには、企業の人事担当者が産業医や外部相談窓口につなぐ役割を果たすことが重要です。
うつ病の可能性がある従業員は、自ら相談に行くことが難しい場合が多く、孤立を深めてしまうことがあります。そこで、人事担当者がプライバシーに配慮しながら声をかけ、必要に応じて産業医の面談につなぐことで、早期に専門的な支援を受けられる体制を整えることができます。産業医は医学的な観点から職場環境の調整や就業配慮を提案できるため、従業員本人だけでなく職場全体にとっても有益です。また、産業医だけでなく外部の相談窓口やカウンセリングサービスを紹介することも有効です。公的なメンタルヘルス相談窓口やEAP(従業員支援プログラム)を利用することで、安心して専門家の意見を得られる環境を提供できます。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
「やる気が出ない うつ」という状態は、単なる一時的な疲れやストレスではなく、うつ病のサインである可能性があります。
このサインを早期に見極め、適切に対応することです。職場でのパフォーマンス低下や欠勤の増加だけでなく、従業員の健康悪化や離職リスクにも直結するため、組織全体にとって看過できない問題です。無理に励ましたり叱責するのではなく、プライバシーに配慮した声かけを行い、必要に応じて産業医や外部相談窓口へつなげることが求められます。また、ストレスチェック制度を積極的に活用し、集団分析によって職場全体の課題を把握することも効果的です。こうした取り組みを組織的に進めることで、従業員が「やる気が出ない うつ」のサインを抱え込まずに相談できる環境を整えられます。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁や上場企業、大学、大規模病院など多様な現場で導入実績があり、未受検者への自動リマインド、リアルタイムの進捗確認、医師面接希望の収集など実務に即した機能を備えています。さらに2025年5月からは、無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能となり、欠勤に至らない段階での課題も把握できます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>ストレスチェックサービス徹底比較22選

