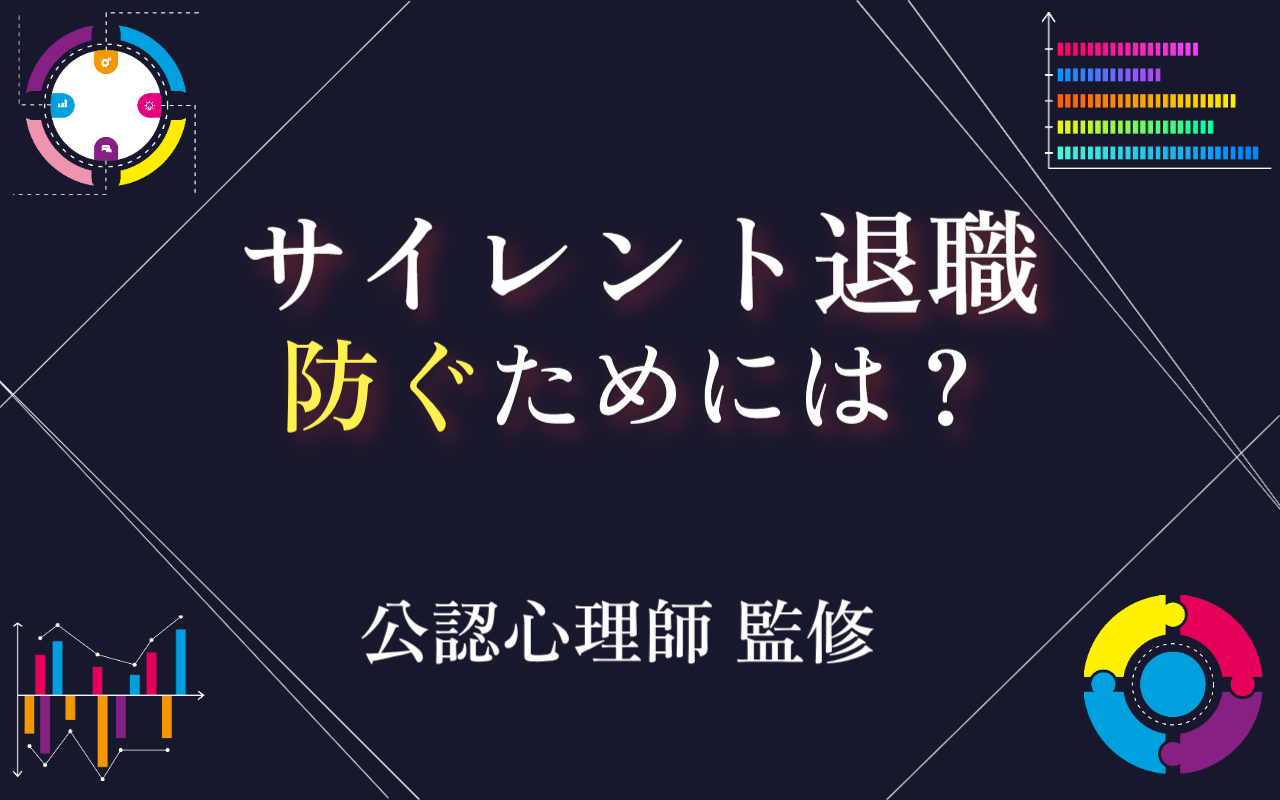
近年、ある日突然退職してしまう「サイレント退職」が増えています。
「サイレント退職」が増えてくると、生産性や職場の士気が下がり、優秀な人材の流出や企業文化の悪化、さらには競争力の低下にもつながります。
この記事では、サイレント退職の兆候を早期に察知するためのポイントや、サイレント退職を防ぐためのストレスチェックの活用方法をご紹介します。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)
目次
サイレント退職とは何か
サイレント退職とは、近年若い世代を中心にSNSなどで話題になっている言葉です。
メンタル不調を抱えながらも周囲に気づかれないよう明るく振る舞い、ある日突然退職してしまうことから、「サイレント退職」と呼ばれています。
一見元気そうに見えるため、同僚や上司が心配して声をかけても「大丈夫です」と笑顔で答え、明確なSOSを出さないため、企業側も事前に兆候を察知して対応するのが難しいという特徴があります。
サイレント退職と従来の退職との違い
サイレント退職と従来の退職との大きな違いは、その過程と表れ方にあります。従来の退職は、上司や人事との面談や意思表示を経て、最終的に組織を離れるという明確なプロセスがあります。
一方、サイレント退職は、本人がはっきりと退職意志を示さないまま、徐々に挑戦的な業務や責任ある役割を避け、組織との心理的距離を広げていくという特徴があります。
このため、外からは「普通に勤務している」ように見える場合も多く、上司や同僚が気づきにくい傾向があります。
なぜサイレント退職は起きるのか
サイレント退職の背景には、「やりがいや達成感の喪失」があると言われています。
以前は新しいプロジェクトや顧客対応にやりがいを感じていた社員が、成果を出しても反応が薄い、感謝の言葉や評価がほとんどない状況が続くと、仕事への意欲が次第に低下します。
さらに、努力や成果が正当に評価されないことへの不満も大きな要因とされます。成果が評価制度に反映されず、上司からのフィードバックも形だけとなれば、「何をしても変わらない」という諦めの気持ちが生まれます。
昇給や昇進といった待遇面での停滞感も深刻です。長年勤めても給与が上がらない、昇進の機会が不透明で公平感がない場合、将来のキャリアビジョンを描けなくなり、モチベーションはさらに下がります。
これらに加え、過度な業務負担や長時間労働、職場内の人間関係の摩擦、意思疎通不足といったストレス要因が重なることで、従業員は表面的には業務をこなしながらも内心では離職の準備を進めることになります。
サイレント退職が企業に与えるリスク
サイレント退職が企業に与える影響は、非常に深刻です。
プロジェクトの中核を担っていた社員が事前の引き継ぎもなく退職すると、納期遅延や品質低下が発生し、顧客からの信頼を失う可能性があります。
また、残された社員に業務負担が集中し、新たな離職やモチベーション低下を招く悪循環に陥ることもあります。
また、サイレント退職が繰り返されれば、企業文化が「どうせ辞める人が多い職場」という負の印象を持たれてしまい、優秀な人材の採用力も低下していきます。
サイレント退職のサインを見抜くポイント
サイレント退職のサインを見抜くには、日常の小さな変化を見逃さないことが重要です。
たとえば、以前は会議で意見を述べていた従業員が、突然「特にありません」と答えるようになるのは要注意です。
また、業務の幅や質の変化にも注意が必要です。
担当外の仕事や新しいプロジェクトへの参加を避け、「自分の範囲だけ」をこなすようになった場合、積極性の低下が疑われます。
さらに、いわゆる「報連相(報告・連絡・相談)」が減り、メールやチャットの返信が遅くなる、必要最低限の連絡しかしなくなったといった行動もサイレント退職のサインです。
サイレント退職の予兆は、勤務態度にも現れます。残業や休日出勤を極端に避ける、昼休憩を長く取る、在宅勤務中のオンライン会議でカメラを常にオフにするなど、関与度の低さが見えるケースもあります。
人間関係では、同僚との雑談や社内イベントへの参加が減り、周囲とのつながりが薄くなることがあります。
サイレント退職とストレスチェックの活用
ストレスチェック制度とは、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、職場環境の改善につなげることを目的とした制度です。
従業員のモチベーション低下やストレスの兆しを数値や傾向で把握でき、部署単位で集団分析なども可能なことから、サイレント退職の予防に活用できます。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、職場環境の改善につなげることを目的とした制度です。現在は、50人以上の事業場に対して年1回の実施が義務化されていますが、今後は全事業場が対象となる予定です。
心理的負担の程度や職場の課題を測定し、本人へのフィードバックや必要に応じた医師面接につなげます。集団分析を行なうことで、部署ごとのストレス傾向や課題を可視化できます。
集団分析で見える部署ごとのリスク
ストレスチェック制度の集団分析では、部署単位で集計することで、特定の部署に長時間労働や人間関係のストレスなど偏ったリスクが集中していないかを可視化できます。
サイレント退職は「個人の問題」と見られがちですが、実際には職場環境の影響が大きく、部署単位で似た傾向が出やすいものです。
サイレント退職の兆候について集団分析を行うと、たとえば以下のような兆候が見えてきます。
・特定の部署だけストレススコアが高く、同時に「仕事の裁量がない」「上司との信頼関係が低い」といった項目が他部署と比べて悪化している。
・離職率や異動希望率が高い部署で、ストレス要因として「職場の一体感が低い」「評価が不公平」といった分析結果がみられる。
・「仕事のやりがい」「成長実感」に関する回答が、他部署より極端に低い。
こうした状態を放置すると、従業員は目立った不満を表に出さないまま、徐々に業務への関与を減らし、最終的にサイレント退職へ移行するリスクが高まります。
つまり、集団分析は「サイレント退職の温床」を早期に見つける有効な手段になります。
サイレント退職=高ストレス者ではない
サイレント退職した従業員は、必ずしも「高ストレス者」として判定された従業員とは限りません。むしろ精神的負担は低くても、仕事へのやる気や関与度が下がっているケースが多く見られます。
そのためストレスチェックでサイレント退職予備軍を抱える部署を見抜くには、高ストレス者率の把握だけでなく、回答傾向や集団分析の結果に注目することが重要です。
「仕事の意義を感じない」「成長できていない」と答える割合が高い場合や、「同僚や上司との一体感が低い」項目で低評価が目立つ場合、さらに「職場改善の意見がない/出さない」という消極的姿勢が強い場合は要注意です。
これらは精神的な不調というより、職場へのエンゲージメント低下を示すサインです。
加えて、離職率や異動希望数、有給消化率の低さといった人事データを組み合わせて分析すれば、表面上は問題なく働いているように見えても、実際には静かに職場から心が離れていっている従業員層を把握しやすくなります。
プレゼンティーイズムの測定
プレゼンティーイズム(Presenteeism)とは、体調不良やメンタル不調により十分なパフォーマンスを発揮できないまま勤務を続けている状態を指します。
プレゼンティーイズムの測定は、サイレント退職の予防に有効です。
従業員が不満や不調を口にしなくても、集中力の欠如や作業効率の低下といった兆候を数値で捉えられるため、表面化しにくい関与度低下を早期に察知できるからです。
ストレスチェッカーでは2025年5月1日からプレゼンティーイズムの測定ができるようになっていて、本人が自覚していない疲労感やモチベーション低下も数値化できます。
>プレゼンティーイズムとは
ストレスチェックと併用すべき取り組み
サイレント退職の予防のためには、ストレスチェックだけでなく、パルスサーベイや匿名アンケートで従業員の本音を把握することが重要です。さらに、メンタルヘルス研修で意識を高め、リモートや時短、フレックスなど柔軟な働き方を取り入れることで負担を軽減します。あわせて、表彰や評価制度を見直し、貢献が適切に認められる環境を整えることも大切です。
パルスサーベイの活用
パルスサーベイとは、従業員に対して数問程度の短いアンケートを週1回や月1回など高い頻度で実施し、その時々のモチベーションやストレス状態をリアルタイムで把握するためのツールです。
たとえば、「今週の仕事のやりがいはどうですか」「上司とのコミュニケーションは円滑ですか」といった質問を定期的に行うことで、業務負担や人間関係の悪化、エンゲージメント低下といったサイレント退職の予兆を早期に察知できます。この結果をストレスチェックと組み合わせることで、長期的なメンタル不調に陥るリスクと短期的な変化を両方把握でき、タイムリーかつ的確な改善策の立案が可能となります。
匿名アンケートで本音を引き出す
サイレント退職の予備軍は、表立って不満を言わず、匿名性の高い場でしか本音を語らない場合があるので、匿名アンケートも有効です。
「この職場を友人に勧めたいと思うか」「明日から別の部署に異動できるとしたら希望するか」「上司からのサポートは十分か」「今の職場で長く働きたいと思うか」などの質問に対し、低評価や否定的な意見が目立つ部署は、早期にフォローや改善策を講じる必要があります。
自由記述欄を設ければ、数字だけでは見えない具体的な悩みや要望も拾える可能性があります。ストレスチェックと併用すれば、数値的分析と生の声の両面から状況を把握でき、より効果的な対策が可能になります。
メンタルヘルス研修の実施
サイレント退職予備軍は、表面的には業務をこなしながらも、心身の疲弊や職場への関与度低下が進んでいる状態であり、放置すると生産性やチームワークの低下につながります。
サイレント退職予防のためのラインケア研修では、上司や管理職が部下のモチベーション低下や関与度の薄れを早期に察知し、適切に対応できるスキルを養うことを目的とします。
発言や態度の変化、業務への主体性低下などの兆候を具体的に見極める観察スキル、責めずに本音を引き出す声かけや傾聴の技術、そして業務調整や相談窓口へのスムーズなつなぎ方を学びます。早期対応により、静かに仕事への意欲を失う状態を防ぎ、職場全体の活力維持と離職防止につなげます。
働き方の柔軟化(リモート、時短、フレックス)
サイレント退職予備軍は、長時間労働や通勤負担、家庭との両立の難しさなどを背景にモチベーションを失うケースが多く見られます。
そのため、リモートワークや時短勤務、フレックスタイム制度などの柔軟な働き方は、こうした予備軍を防ぐ有効な手段となる可能性があります。
週2日の在宅勤務を導入した企業では、通勤時間の削減により従業員の睡眠時間や自己学習時間が増え、生産性が向上した事例があります。
また、フレックス制度を活用して混雑時間を避けて通勤できるようにした結果、ストレス関連の欠勤が減った例もあります。
子育てや介護との両立をサポートする時短勤務は、特に女性従業員の離職防止に効果的です。
表彰や評価制度の見直し
サイレント退職予備軍は、成果や努力が正当に評価されていないと感じることでモチベーションを失い、関与度が低下します。そのため、人事評価だけでなく、日常業務での小さな成果や貢献もタイムリーに認める仕組みが有効です。
たとえば、プロジェクト成功時に全員の努力を称える「チームアワード」や、顧客からの好意的なフィードバックを受けた従業員を即座に称賛する「スポット表彰」、評価基準を業務量や成果だけでなく、チームワークや創意工夫などを評価する「多面的評価」などは、従業員が「見てもらえている」「認められている」という実感を持ちやすくなり、仕事への関与度向上につながります。
透明性の高い評価プロセスを導入すれば、不公平感を減らし、組織全体の士気を高める効果も期待できます。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。
まとめ
ストレスチェックは、サイレント退職の予兆を見抜くための有効なツールとして活用することできます。特に警戒すべきは、日頃は前向きに働き評価も高い社員が、突然辞意を示すケースです。
ストレスチェックでは、業務量や責任の重さ、上司との関係性、仕事への達成感といった複数の指標から、こうした“静かなSOS”を浮かび上がらせることができます。さらに集団分析を活用すれば、特定部署の傾向や、特定職層での疲弊など、組織構造に潜む課題も明らかになります。
大切なのは、数値に表れるわずかな変化を見逃さず、早期に対話や環境改善を行うことです。ストレスチェックは、サイレント退職予備軍を守るだけでなく、組織全体の安定性と持続的な成長力を高めることが可能にするツールと言えるのです。
:参照記事
>やりがい搾取とは?公認心理師が解説

