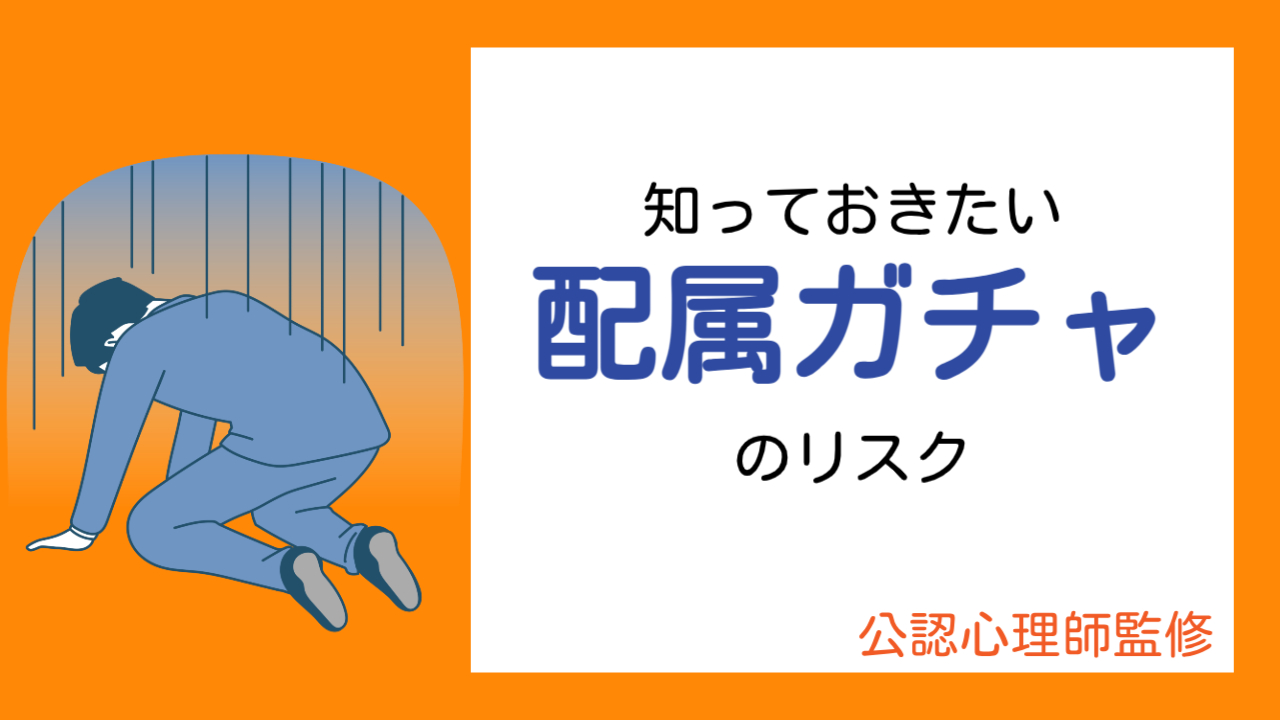
配属ガチャとは、入社後の配属先が本人の希望や適性とは関係なく決まってしまう状況を指します。企業側の人員配置の都合によって起こる場合が多いとされることから、キャリア形成上の不安要因になりやすいと指摘されており、近年注目を集めています。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)
目次
配属ガチャとは
「配属ガチャ」とは、新卒社員が入社後にどの部署や勤務地に配属されるのかが、自分の希望や適性ではなく、企業側の事情や運によって左右されるように感じられる状況を指す言葉です。カプセルトイの“ガチャ”になぞらえ、「結果が開けてみるまで分からない」という意味で使われています。
SNSや転職サイトで話題
「配属ガチャ」は、SNSや転職サイトなどで広く使われています。配属後に「希望部署に行けた=当たり」「まったく興味のない部署に配属された=ハズレ」といった表現が見られ、X(旧Twitter)やTikTokでは「研究職希望だったのに、工場勤務になった」「営業は向いていないのに、ノルマの厳しい部門へ回された」など、戸惑いや不満をつづった体験談が頻繁に投稿されています。
新卒配属や異動の不透明さが原因?
配属ガチャが広まった背景には、企業側の配属プロセスが不透明である点が指摘されています。新卒一括採用やジョブローテーションを前提とした人事制度では、配属は各部署の人員計画や経営判断に基づいて決められることが多く、学生や従業員は入社・異動前に自身の配属先を知ることができません。
さらに「なぜその部署に配属されたのか」という理由について会社側から十分な説明がなされないケースも多く、不信感を招きやすい状況になっています。
配属ガチャのリスク(従業員側)
配属ガチャによって希望外の部署に配属されると、日々の業務に興味を持てずやりがいを感じにくくなることから、仕事へのモチベーションが下がってしまうケースが少なくありません。
また、「なぜこの部署なのか」という理由づけが企業側から十分に説明されない場合、自分のキャリアビジョンとの間にギャップが生じ、「このまま働き続けて良いのだろうか」と悩むケースも多く、結果として早期離職の一因となることも指摘されています。
意外な部署で自分の新たな適性を発見できたという好転例もありますが、企業側が十分な説明やサポートを行わずに配属を進める場合には、従業員は不信感を抱きやすく、働き続ける意欲の低下につながるリスクがあります。
配属ガチャのリスク(企業側)
従業員が希望しない部署で働くことにより、仕事への意欲やモチベーションが低下しがちで、結果として業務効率や生産性が落ちるリスクがあります。
また、適性に合わない業務や人間関係の中で過ごすことはストレス要因となりやすく、メンタルヘルス不調につながる可能性もあるため、企業側は休職や労務対応などに時間とコストを割く必要が生じます。
さらに、配属への不満や将来への不安から早期離職につながるケースも多く、人材育成にかけた採用・研修コストが回収できなくなる点も大きな損失です。特に優秀な人材ほど、機会損失を避けるために他社へ流出する傾向があります。
ストレスチェックで配属ガチャを可視化
ストレスチェック制度を活用すれば、配属ガチャによる影響を客観的に可視化できます。
「上司のサポート」「業務量」「人間関係」などの尺度別にストレス度を分析することで、高ストレス部署や高ストレス職種を特定しやすくなります。そして、ストレスの高い配属先や職務に偏りがないかを把握し、企業側は配属の見直しやサポート体制の強化など、データに基づいた配属改善に取り組むことが可能になります。
「上司のサポート」「業務量」など尺度別分析
ストレスチェック制度は、従業員の心身状態を把握するだけでなく、配属ガチャによる影響を可視化する手段としても非常に有効です。
「仕事の負担(業務量)」「上司の支援」「職場の人間関係」などの尺度別に分析を行うことで、部署ごと・職種ごとのストレス傾向を詳細に把握することができます。
希望に合わない部署に配属された従業員は、仕事に興味が持てないことから、生産性の低下やモチベーション喪失、さらにはメンタル不調や離職につながる恐れがあります。そこで、配属ガチャを“可視化”すれば、人材配置の適正化と組織力向上を実現するための大きな手がかりとなります。
高ストレス部署や高ストレス職種の特定
希望外の部署に配属されると、業務内容や人間関係への興味を持てず、仕事への意欲やモチベーションが低下しやすくなるため、結果的に高ストレス状態に陥ることがあります。特に「業務量が多い」「上司からのサポートが少ない」「裁量がなく自由度が低い」などの環境要因が重なると、メンタル面での負担が大きくなり、生産性の低下や早期離職につながるリスクも高まります。
一方、ストレスチェックを活用し、部署ごとにストレス要因を可視化することで、配属ガチャによる影響を早期に察知することができるようになります。高ストレス部署を特定し、業務内容やマネジメントの見直しを行うとともに従業員自身も自らのストレス要因を把握できるため、セルフケアや相談行動につなげやすくなります。
集団分析を活かした配属改善のアプローチ
配属ガチャによるミスマッチを解消する手段として、ストレスチェックの集団分析を活用することもできます。
ストレスチェックは、本来は従業員の心身の健康状態を把握しメンタル不調を未然に防ぐための制度ですが、部署ごとの結果を集団分析すれば、人員配置や配属に伴うストレスの違いを「見える化」するツールとしても活用できます。
ある企業では、集団分析をもとに新人配属が特定の部署に集中していた偏りを是正し、業務量の再配分と管理職向けのマネジメント研修を実施。結果としてストレス指数が改善し離職率も抑制されました。
このようにストレスチェックを配属評価・改善サイクルに組み込むことで、感覚や運任せの「配属ガチャ」から、データに基づく戦略的人員配置へと進化させることが可能になります。
ピープルアナリティクスによる配属最適化の最前線
ピープルアナリティクスとは、人材に関するさまざまなデータを分析し、組織運営や人事施策に活用する手法のことであり、近年は配属や異動の最適化にも導入が進んでいます。
従来の配属は「上司の勘」や「現場の都合」に依存しがちだったため、いわゆる“配属ガチャ”“異動ガチャ”と言われるミスマッチが起こる要因となっていました。ピープルアナリティクスでは、ストレスチェック、適性検査、業績評価、エンゲージメントサーベイなどのデータを組み合わせ、どの部署でどのような人材が成果を上げやすいのか、離職を防ぎやすいのか、といった傾向を客観的に導き出すことができます。
HRテックで変わる“運任せでない配属”とは
HRテックとは、人材(Human Resources)とテクノロジーを組み合わせたソリューション全般を指し、適性検査、AIマッチング、人事データ分析、クラウド人事システムなどが代表例です。これらのツールを用いれば、従業員一人ひとりの性格や特性、ストレス傾向、過去の評価、スキル、キャリア志向などを精緻に可視化でき、部署が求める人物像との適合度から「誰をどこに配属すべきか」を導き出すことが可能になります。
また、配属後もストレスチェックなどを継続的にモニタリングすることで、ミスマッチが起こった部署を早期に察知し、再配置やフォローにつなげられます。
ストレスチェック×業績データによる成功事例
あるメーカーでは、この結果を基に高ストレス部署に新人を集中して配属していた状況を是正し、業務量の平準化とマネジメント研修を実施。半年後には部門別ストレス指数が改善し、離職率も低下しました。
さらに、ストレスチェックを経年で分析することで、異動後のストレス増減も追跡でき、「営業部門から企画部門に異動した社員のストレスが下がる傾向にある」といった傾向を把握することもできました。
近年は、このような蓄積データを元に、希望と適性を踏まえた配属判断、異動希望制度の改善、配属後のフォロー設計など、データに基づいた配属改善アプローチを実践する企業が増えています。
監修:山本 久美(株式会社HRデータラボ 公認心理師)

大手技術者派遣グループの人事部門でマネジメントに携わる中、社内のメンタルヘルス体制の構築をはじめ復職支援やセクハラ相談窓口としての実務を永年経験。
現在は公認心理師として、ストレスチェックのコンサルタントを中心に、働く人を対象とした対面・Webやメールなどによるカウンセリングを行っている。産業保健領域が専門。
まとめ
「配属ガチャ」のようなミスマッチが発生すると、従業員は業務や職場環境に関心ややりがいを持ちにくくなり、モチベーションやエンゲージメントが低下しがちになります。結果的に集中力やパフォーマンスが落ち、生産性の低下につながるほか、ストレスの蓄積や将来への不安が早期離職を引き起こす危険性も高まります。
こうした配属による影響を可視化し、改善につなげる手段として有効なのがストレスチェック制度です。ストレスチェックは個人の精神的負担を数値化すると同時に、集団分析を通じて部署間でのストレスの偏りを明確にすることができます。
ストレスチェックは配属ガチャがもたらす生産性低下や離職率上昇といったリスクを未然に防ぎ、組織全体の働きやすさとエンゲージメント向上に貢献する貴重なデータ源となります。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁、上場企業、大学、大規模病院などさまざまな現場で利用されており、受検画面や案内メールの文面カスタマイズ、未受検者への自動リマインド、リアルタイム進捗確認、医師面接希望の収集など、現場の業務に寄り添った柔軟な機能が特長です。2025年5月からは、無料プランとWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担によるパフォーマンス低下)」の測定に対応し、欠勤には至らないものの、生産性が下がっている従業員の状態も可視化できるようになりました
。配属ガチャや異動ガチャに伴うストレスを早期に発見し適切なフォローを行うためにも、ぜひ導入をご検討ください。
:参照記事
>上司ガチャとは?ストレスにどう気づく?

