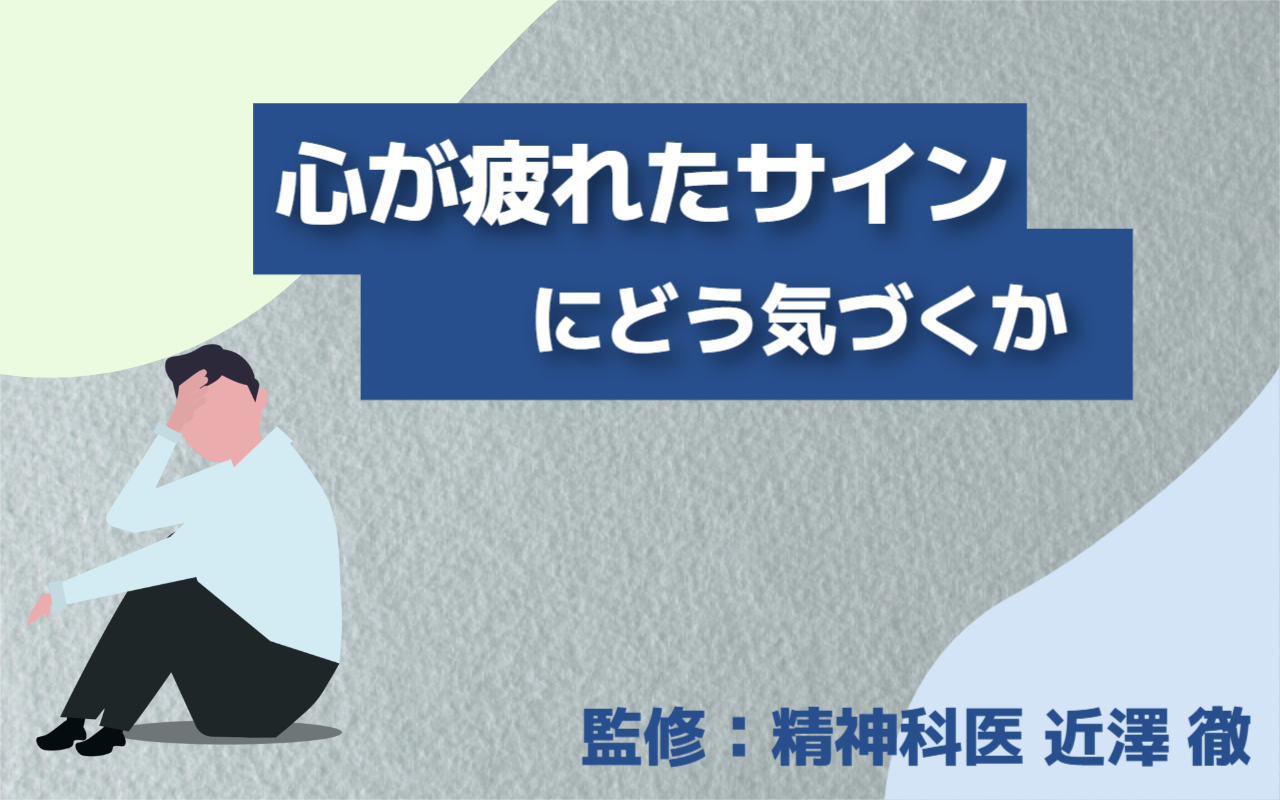
日々の業務や人間関係の中で、従業員が「心が疲れたサイン」の兆候を察知できるかどうかは、企業にとって大きな課題です。
気づかないまま放置してしまえば、生産性の低下や欠勤・休職、さらには離職につながり、組織全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
近年は「健康経営」が注目される中で、従業員一人ひとりの心のコンディションをていねいに把握する仕組みが求められています。
この記事では、「心が疲れたサイン」の具体例と、人事部が取るべき初期対応、そしてストレスチェック制度の活用方法について解説します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
「心が疲れたサイン」の具体例
「心が疲れたサイン」として代表的なのが、勤怠の乱れです。遅刻や欠勤が増える背景には、心身の不調が潜んでいる場合があります。
また、業務パフォーマンスの低下も重要なサインで、集中力や判断力の低下、ミスの増加などに表れます。その他にも、表情が乏しくなった、言動が消極的になったなどの変化があらわれることもあります。
これらの兆候を早期に把握し、相談しやすい環境を整えることが、従業員の健康と職場全体の安定につながります。
勤怠の乱れ
「心が疲れたサイン」として最も分かりやすいのが、勤怠の乱れです。
これまで安定して勤務していた従業員が、遅刻や早退、欠勤を繰り返すようになる場合、心身の不調が背景にある可能性があります。もちろん、一時的な体調不良や家庭の事情によるケースもありますが、特に明確な理由が見当たらない場合は「心が疲れている」サインとして見逃すべきではありません。
さらに、勤怠の乱れが長期化すると、周囲の従業員に負担が集中し、職場全体の士気低下を招く恐れがあります。
業務パフォーマンスの低下
これまで安定して成果を上げていた従業員が、急に仕事のスピードが落ちたり、ミスや確認漏れが目立つようになったりした場合、単なるスキル不足ではなく心の不調が関係している可能性があります。
集中力や判断力の低下は、本人の努力だけでは改善できないケースが多く、また、本人が自覚していない場合も多いので、特に注意が必要です。
業務パフォーマンスの低下は、個人の問題にとどまらず、チーム全体の効率や成果にも直結します。負担の偏りや不公平感が広がると、周囲のモチベーション低下や職場の雰囲気の悪化を招きかねません。
表情や言動の変化
普段は明るく積極的だった従業員が急に口数が減ったり、笑顔が見られなくなったり、逆に、些細なことで苛立ちを見せたり、攻撃的な言動が増えたりするケースがあります。
表情や言動の変化についても本人が自覚しにくいことが多く、気づかないままストレスを蓄積させてしまう危険性があるため、こうした変化を「問題」として追及するのではなく、「サポートが必要なシグナル」と捉える姿勢が大切です。
職場での行動の変化
以前は積極的に会議や雑談に参加していた従業員が突然発言を控えるようになったり、必要以上に孤立して一人で過ごす時間が増えたりすることがあります。また、協調性が低下し、些細なことで同僚と衝突する、指示を受けても反応が鈍くなるといった行動も心の不調の兆しと考えられます。
性格の変化や一時的な気分の問題に見えるかもしれませんが、放置すると不調が進行し、業務への支障や人間関係の悪化につながる恐れがあります。
なぜ「心が疲れたサイン」に気づくことが重要か
「心が疲れたサイン」に気づくことは、従業員個人の健康を守るだけでなく、組織全体の健全な運営を維持するためにも極めて重要です。従業員が心の疲れを抱えたまま働き続けると、集中力や判断力が低下し、業務の効率が落ちることで生産性全体に悪影響を及ぼします。
さらに、不調が進行すれば休職や離職につながるリスクが高まり、その結果、業務の負担が周囲に偏り、不公平感やチームの士気低下を招きかねません。こうした状況が連鎖すると、職場全体の雰囲気が重くなり、活気やモチベーションの低下といった二次的な影響も広がります。
休職や離職のリスクを防ぐ
従業員が心の疲れを抱えたまま放置されると、不調が深刻化し、長期の休職や退職に至るケースが少なくありません。
適切なケアが行われず、優秀な人材が数か月にわたって休職し、その後退職した事例も少なくありません。
これは本人のキャリアに大きな影響を及ぼすだけでなく、組織にとっても人材の損失や採用・育成コストの増加、さらには職場全体の士気低下といった大きなダメージにつながります。
職場全体の雰囲気や生産性に影響
心の疲れを抱えた従業員は集中力や判断力が低下し、業務効率が落ちるだけでなく、コミュニケーションの質も下がりがちです。その結果、チーム内に不協和音が生まれ、協力体制が弱まることがあります。さらに、周囲のメンバーが業務をカバーする状況が続けば、不公平感や不満が広がり、士気の低下や離職意向の高まりにつながる可能性もあります。
また、欠員を補うために周囲の従業員へ過剰な負担がかかり、結果的にチーム全体のモチベーションが低下する悪循環を招きかねません。
人事が取るべき初期対応
「心が疲れたサイン」に気づいた際には、まずは勤怠や言動の変化を踏まえ、メンタル不調の可能性を冷静に確認します。その際、いきなり問題視するのではなく、雑談ベースで自然に話を聞き、本人が話しやすい雰囲気をつくることが有効です。必要に応じて相談窓口や産業医につなぎ、専門的な支援を受けられるようにすることも重要です。また、個人の不調はチーム全体に影響するため、職場環境の調整や業務負担の見直しも同時に検討し、組織全体で支える姿勢が求められます。
メンタル不調の可能性を確認
「心が疲れたサイン」が見えた時の初期対応は、従業員がメンタル不調を抱えていないかを冷静に確認することです。大切なのは、いきなり指摘や叱責をするのではなく、本人の立場に寄り添いながら状況を把握する姿勢です。
ある職場では普段より遅刻が増えた社員に対し、上司が感情的に叱った結果、かえって不安や孤立感を深め、最終的に休職につながった事例があります。
一方で、別の企業では、上司が「最近疲れていない?」と声をかけ、昼休みに一緒に話を聞く時間を設けたことで、本人が抱えていた業務の負担や家庭の事情が明らかになり、早めに業務調整や産業医への相談につなげることができました。このように、初期対応次第で従業員の回復や組織への定着率は大きく変わります。
雑談ベースのアプローチ
「心が疲れたサイン」を見つけたとき、雑談ベースで自然にアプローチすることも効果的です。従業員が抱えるメンタルの不調は、必ずしも表立って語られるわけではなく、勤怠の乱れや業務パフォーマンスの低下、表情や言動の変化といった小さな兆候から見えてくることが多くあります。しかし、いきなり指摘をすると本人に負担や防衛反応を与え、状況を悪化させかねません。そのため、日常の会話の中で「最近どう?」といった気軽な声かけを行い、安心して話せる雰囲気をつくることが重要です。
相談窓口や産業医の活用
従業員が心身の不調を抱えていても、直接上司や人事に打ち明けることには抵抗を感じるケースが少なくありません。そのため、従業員が一人で抱え込まず早期にサポートへつながるため社内に安心して相談できる窓口を設けることが重要です。
また、従業員本人がストレスチェックの結果や自身の状態を踏まえて面談を希望した場合、産業医が客観的な立場からアドバイスを行い、必要に応じて勤務調整や治療との両立支援を提案します。
「心が疲れたサイン」を見逃さず、適切な窓口や専門家へ導くことは、従業員の健康保持と組織全体の安定につながりますし、安心して働ける職場風土が醸成され、結果的に生産性や定着率の向上にも結びつきます。
職場への影響も考慮
従業員一人の不調は個人の問題にとどまらず、周囲の業務負担の増加や不公平感を生み、チーム全体の士気低下につながることがあります。特に休職や離職に発展した場合、他のメンバーが業務をカバーするケースが多く、集中力や生産性の低下、さらには新たな不調者の発生という悪循環を招くリスクも高まります。
また、気づかないまま放置されれば、職場の雰囲気が重くなり、モチベーションの低下や離職率の上昇といった組織的なダメージにつながりかねませんから、職場全体への波及効果を見据えた対応が不可欠です。
具体的には、業務分担の見直しや柔軟な勤務制度の導入、コミュニケーション機会の増加などを通じて、チームの負担感を軽減し、全体のバランスを保つことが大切です。さらに、ストレスチェックの集団分析を活用し、部署ごとのストレス傾向を把握して改善に取り組むことも効果的です。
ストレスチェックの活用
「心が疲れたサイン」に早期に対応するためには、本人の気づきを促す仕組みと、職場全体の課題を明らかにするためのアプローチが欠かせません。
そこで活用したいのが、ストレスチェック制度です。
ストレスチェックとは、従業員が自身の心理的ストレス状態を把握できる制度で、常時50人以上の事業場に義務づけられており、今後は全事業所が対象となります。
ストレスチェックの個人結果は本人のみに通知され、人事は匿名の集団分析を用いて部署の傾向を把握し、業務量や働き方、コミュニケーション環境の改善に活かします。
さらに、ストレスチェックの集団分析を活用し、部署ごとの傾向や職場環境の課題を把握して改善につなげることが求められます。
ストレスチェックは義務
ストレスチェックは、これまで常時50人以上の労働者がいる事業場に義務付けられてきました。しかし、2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が正式に成立し、この制度は段階的に対象が拡大され、2028年までにはすべての事業場での実施が必須となる見込みです。
つまり、企業規模に関係なく従業員一人ひとりが自分の心の状態に気づき、必要な支援につながれる体制を整えることが求められているということです。
ただ、企業としては義務として対応するだけでなく、この制度を活用して職場環境改善や予防的ケアに積極的に取り組むことが重要です。
組織全体のストレス傾向も把握できる
ストレスチェックの集団分析は、職場全体の状況を客観的に把握するための有効なツールです。部署ごとのストレス傾向を明らかにすることで、長時間労働や業務負担の偏り、コミュニケーション不足といった課題を見つけ出し、組織的な改善策につなげることが可能です。こうした分析を活かして業務環境の調整を行えば、個人の不調を防ぐだけでなく、チーム全体の士気や生産性の向上にも寄与します。
さらに、集団分析の結果からは長時間労働や業務の偏りといった職場環境の課題が浮き彫りになる場合があります。これを基に業務改善や配置の見直しを行えば、個人の不調を防ぐだけでなく、組織全体の生産性や定着率の向上にもつながります。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
心が疲れたサインを見過ごしてしまうと、集中力の低下やパフォーマンスの悪化につながり、生産性が落ちるだけでなく、ストレスの蓄積や将来への不安から早期離職を招くリスクも高まります。こうした影響を把握し、改善につなげる有効な仕組みがストレスチェック制度です。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁や上場企業、大学、大規模病院など幅広い現場で導入されており、未受検者への自動リマインドやリアルタイムの進捗確認、医師面接希望の収集など、現場の実務に対応した機能を備えています。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担によるパフォーマンス低下)」の測定に対応し、欠勤に至らない段階でも生産性が下がっている従業員の状態を可視化できるようになりました。まずは、お気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>メンタルブレイクのリスクを産業医が解説

