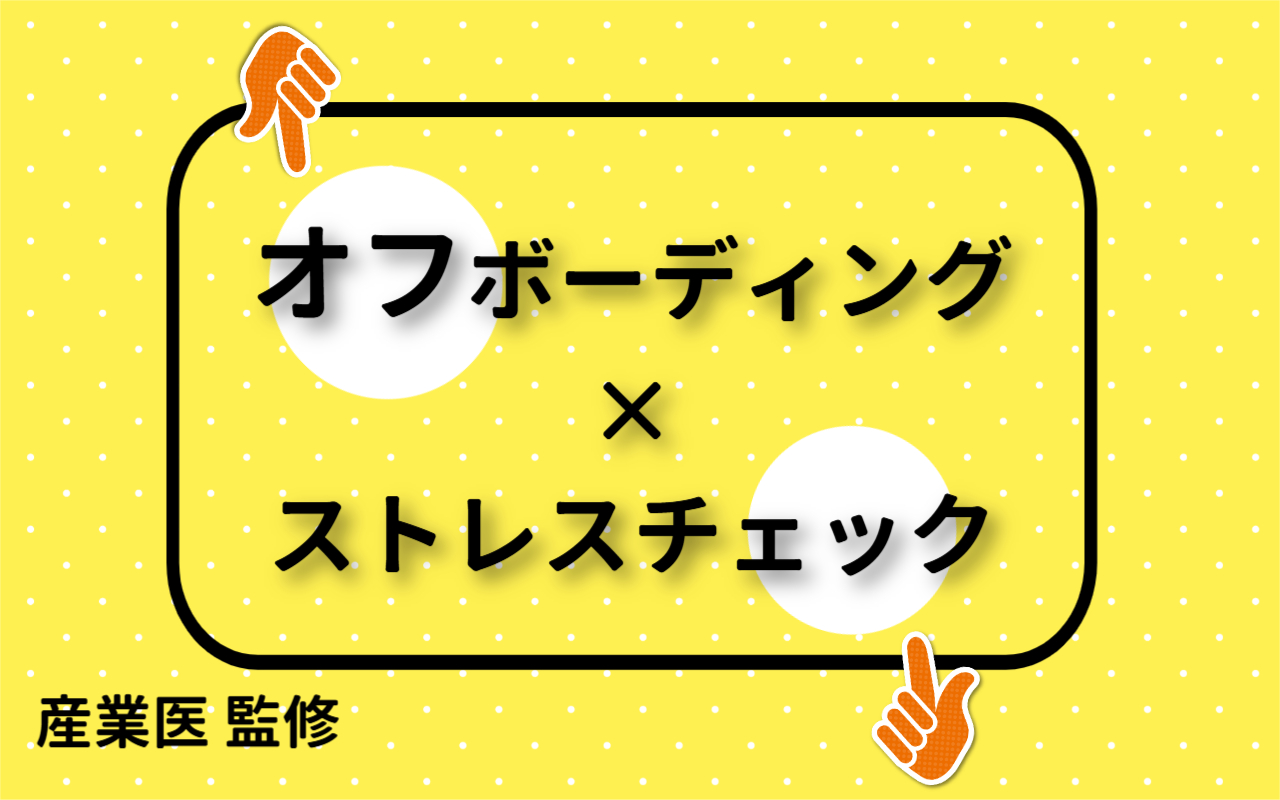
企業における「オフボーディング(退職手続き)」は、単なる事務的な対応ではなく、職場環境や従業員のメンタルヘルスを見直す重要な機会です。退職時は、在職中に蓄積されたストレスが表面化しやすいケースもあり、残る従業員にも心理的影響が及ぶことがあります。
本記事では、オフボーディングとストレスチェックを組み合わせた効果的な活用法を解説します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
オフボーディングとは
オフボーディングとは、従業員が退職する際に行う一連の対応やプロセスのことを指します。具体的には、業務の引き継ぎ、社内機器の返却、退職面談、最終的な給与処理などの実務だけでなく、円滑なコミュニケーションを通じて退職者と良好な関係を保つための取り組みも含まれます。
オフボーディングの重要性
ていねいなオフボーディングを実施することで、組織の信頼性を高め、退職後も企業に対して良い印象を持ってもらうことができます。これはいわゆる「アルムナイ(出戻り)採用」や、口コミ・SNSなどを通じた企業イメージにも好影響を与えます。逆に、対応が不十分だと不満が残り、ネガティブな発信やトラブルにつながるリスクもあります。
さらに、退職は職場の課題を見直す重要なタイミングでもあります。離職理由や業務改善のヒントを把握することで、人材定着率の向上や職場環境の改善につなげることができます。つまり、オフボーディングは単なる終わりの手続きではなく、「次の成長への始まり」として捉えるべきプロセスなのです。
円満な退職の実現
退職の場面は、組織に対する印象を大きく左右する最後の接点でもあり、この対応次第で、退職者が企業に抱く印象が大きく変わります。
たとえば、感謝の気持ちを伝える面談や、スムーズな引き継ぎ支援、退職理由をていねいにヒアリングする仕組みを整えることで、退職者が「この会社で働けてよかった」と感じやすくなります。
その結果、離職後も企業のファンとなり、周囲に好意的な影響を与える可能性が高まります。
また、円満退職は社内の雰囲気にも良い影響を与えます。退職に不満や対立が残ると、在職者の不安や不信感が広がり、生産性の低下につながることもあります。逆に、穏やかな退職プロセスが定着している職場では、従業員同士の信頼関係が保たれ、安心して働ける環境が生まれます。
組織の混乱防止
退職が発生すると、業務の引き継ぎ不足や情報共有の遅れ、担当者不在による業務停滞など、さまざまなリスクが生じます。こうした混乱を防ぐためには、退職の意思が示された段階から計画的に対応を進めることが不可欠です。
具体的には、業務内容や取引先情報の可視化、マニュアル整備、引き継ぎスケジュールの明確化などを通じて、退職後も業務がスムーズに継続できる体制を整えることが求められます。
また、退職がチーム全体の士気や人間関係に影響を与えることも少なくありませんから、上司や人事担当者が適切に情報を共有し、チーム全体が前向きに受け止められるようサポートすることが大切です。
良好な関係性の維持
オフボーディングにおける「良好な関係性の維持」は、企業の信頼性やブランド価値を高める上で欠かせない視点です。退職はネガティブな出来事と捉えられがちですが、対応の仕方次第で「円満な別れ」として次につなげることができます。
たとえば、感謝の言葉を伝える面談や、退職後のアルムナイ(OB・OG)ネットワークの構築などを通じて、退職者とのつながりを保つことが可能です。こうした姿勢は「またこの会社と関わりたい」という前向きな印象を生み、将来的な再雇用(リターン採用)や業務提携にも発展する可能性があります。
一方で、関係性を軽視した対応は、退職者の不満やネガティブな発信につながり、採用活動や企業イメージに悪影響を及ぼすリスクがあります。
オフボーディングのプロセス
オフボーディングのプロセスは、退職者と企業の双方が円滑に次のステップへ進むための大切な流れです。
一般的には、①退職の申し出・確認、②業務の引き継ぎ計画、③退職面談、④最終出勤・手続き、⑤退職後のフォローアップという5つの段階に分けられます。まず退職意思が示された段階で、人事や上司が誠実に対応し、退職理由や背景を把握することが重要です。次に、引き継ぎ内容やスケジュールを明確にし、チーム内での業務停滞を防ぎます。退職面談では、在職中の経験や改善点などをていねいに聞き取ることで、組織課題の発見につなげられます。最終出勤日には感謝を伝える場を設けるなど、前向きな雰囲気で送り出すことが理想です。さらに、退職後も必要に応じて連絡を取り合うことで、良好な関係を維持できます。
退職の申し出・確認
オフボーディングの最初のステップである「退職の申し出・確認」は、今後の対応を左右する重要な段階です。従業員から退職の意思が伝えられた際は、感情的な反応を避け、まずは冷静に話を聞くことが大切です。
退職理由や背景をていねいにヒアリングすることで、職場環境やマネジメント上の課題を把握する手がかりにもなります。また、退職日や引き継ぎスケジュールを明確にし、社内調整をスムーズに進めることが求められます。
業務の引き継ぎ計画
「業務の引き継ぎ計画」は、退職後も業務を円滑に継続させるための最も重要なプロセスの一つです。退職が決まった段階で、担当業務の範囲や進行中の案件、取引先情報などを整理し、引き継ぎの優先順位を明確にすることが大切です。
また、誰にどの業務をどのタイミングで引き継ぐかを可視化し、スケジュールとして共有することで、チーム全体の混乱を防げます。マニュアルや共有ドキュメントを整備しておくことで、退職後の問い合わせ対応もスムーズになります。
退職面談
オフボーディングにおける「退職面談」は、退職者の声を直接聞き取り、組織の課題や改善点を明確にする重要な機会です。
形式的な面談ではなく、退職理由や在職中の不安・不満、良かった点などを率直に話してもらうことで、職場環境の実態を把握できます。
面談担当者は、傾聴の姿勢を保ち、退職者が安心して意見を伝えられる雰囲気づくりを心がけることが大切です。また、面談内容は人事や管理職と共有し、今後の離職防止策や職場改善に活かすことで、オフボーディングを企業成長につなげることができます。
最終出勤・手続き
「最終出勤・手続き」は、退職者を円滑かつ気持ちよく送り出すための重要な段階です。
最終出勤日には、貸与物の返却や各種書類の受け渡しなどの事務手続きに加え、これまでの貢献に感謝を伝える機会を設けることが望まれます。退職がネガティブな印象で終わらないよう、上司や同僚からのメッセージや送別の場を用意することで、退職者の満足度を高め、良好な関係を維持できます。また、社会保険や最終給与などの事務処理も迅速かつ正確に行うことで、信頼感のある企業対応を示すことができます。
退職後のフォローアップ
「退職後のフォローアップ」は、退職者との良好な関係を維持し、企業の信頼性を高めるための重要なステップです。
退職後も一定期間をおいて、アンケートやメールなどで近況を伺うことで、離職理由の再確認や今後の改善点を把握できます。
また、アルムナイ制度(OB・OGネットワーク)を活用し、情報共有や再雇用の機会を設けることで、退職者が企業のファンとして関係を続けやすくなります。誠実なフォローアップは、採用ブランディングにも寄与し、企業文化の成熟や人材循環の促進にもつながります。
ストレスチェックの活用
ストレスチェックを活用することで、従業員の退職リスクを早期に把握し、組織の課題を可視化できます。まず、定期的なストレスチェックを実施することで、メンタル不調や離職につながるサインを早期発見でき、予防的なフォローが可能になります。
さらに、ストレス傾向を分析すれば、表面的な退職理由だけでなく、職場環境や人間関係などの根本的要因を見極めることができます。こうした分析をオフボーディングと組み合わせることで、離職防止と職場改善の両立が実現します。
退職のサインを早期発見できる
ストレスチェックの活用によって、従業員のストレス状態を定期的に可視化することで、メンタル不調や業務への不満、人間関係のストレスなど、退職につながる前兆を把握できます。
特に、ストレス度の高い従業員が特定の部署や上司に偏っている場合は、職場環境やマネジメント体制に課題がある可能性が高く、早期の対策が求められます。
また、定期的なデータ分析を行えば、繁忙期や人事異動後など特定の時期にストレスが高まる傾向も把握でき、ピンポイントでのフォローが可能です。
こうした予兆の段階で産業医や管理職が介入し、面談や環境調整を行うことで、退職を防止し、従業員の定着率向上につなげることができます。つまり、ストレスチェックは単なる義務ではなく、離職予防のための「早期警告システム」として活用できるのです。
ストレス傾向から退職理由を見極める
ストレスチェックを活用することで、従業員のストレス傾向から退職の背景や理由をより正確に見極めることができます。
退職理由として多く挙げられる「人間関係の不満」「業務負荷の偏り」「評価やキャリアへの不安」などは、面談だけでは表面化しにくいケースもあります。
しかし、ストレスチェックの結果を分析すれば、どの部署でどのようなストレスが強く出ているか、個人ではなく組織単位での課題を把握することが可能です。たとえば、仕事の量やコントロール感に関する項目で高いストレスが出ていれば、業務量や役割分担の不均衡が潜在的な退職要因となっている可能性があります。
さらに、複数回の実施データを比較することで、どのようなストレス傾向が見られていたかを分析でき、将来的な離職防止に活かせます。集団分析することで、従業員のプライバシーを守りながら、組織の課題を客観的に把握できるのも利点です。ストレス傾向を的確に読み取り、職場改善に結びつけることが、健全なオフボーディングと離職防止の両立につながります。
80問版のストレスチェック
80問版のストレスチェックは、人的資本経営の実践だけでなく、オフボーディングにも効果的に活用できるツールです。従来の57問版よりも詳細な設問構成により、部署ごとのストレス要因をより正確に特定でき、退職につながる潜在的な課題を明らかにします。
たとえば、上司のリーダーシップや公正な態度、職場での承認(ほめてもらえる環境)、失敗に対する寛容さ、個人の尊重、公正な人事評価、多様な人材への対応、キャリア形成、ワーク・セルフ・バランス、ハラスメントの有無などを多面的に測定することで、どの要素が退職リスクを高めているかを把握できます。
さらに、この結果を活かしてPDCAサイクルを回せば、離職防止だけでなく、退職者が生まれた後の職場改善にもつなげられます。
たとえば、オフボーディング面談で得た情報とストレスチェック結果を照らし合わせることで、組織全体の課題を定量・定性の両面から分析可能です。80問版ストレスチェックは、まさに「在職から退職まで」を支える戦略的な人材マネジメントツールです。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
オフボーディングは、退職を単なる手続きではなく、組織改善と信頼構築の機会として活用できる重要なプロセスです。
ストレスチェックを組み合わせることで、退職のサインを早期に発見し、離職の背景にあるストレス要因を可視化できます。退職前後の心理状態をデータで捉え、PDCAをまわすことで、定着率向上と健全な職場づくりを実現します。オフボーディングとストレスチェックの併用は、人的資本経営の観点からも有効な戦略です。
国内最大級「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、多様な組織で導入されてきた信頼と実績を持つストレスチェックツールツールです。
未受検者への自動リマインド機能やリアルタイムでの進捗確認、医師面接希望者の収集など、実務に即した管理機能を標準搭載。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能になり、欠勤や離職に至る前の段階で課題を早期に発見し、対策を講じることができます。導入や運用に関するご相談もお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>ストレスチェックサービスおすすめ22選

