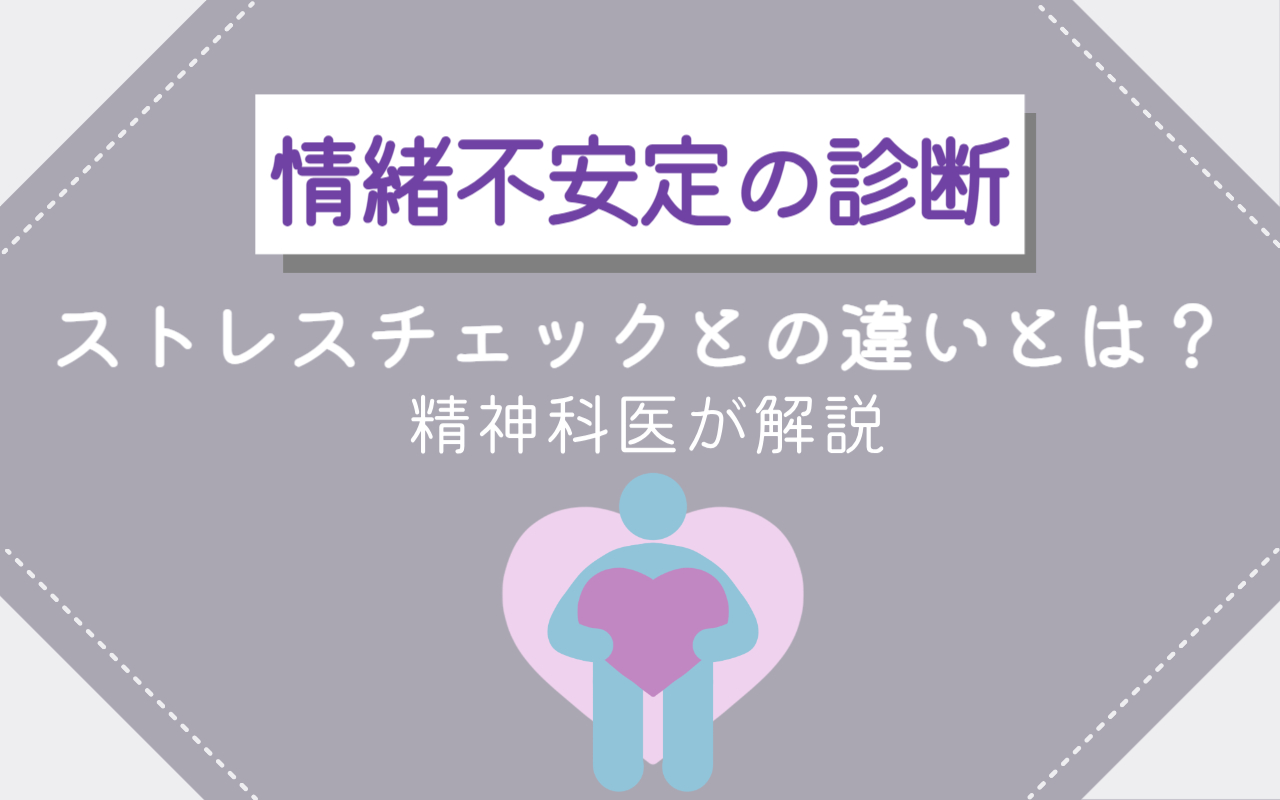
「情緒不安定」と聞くと、感情の起伏が激しい、些細なことで落ち込む、イライラしやすい――そんな状態を思い浮かべる方も多いでしょう。職場でも、部下や同僚の態度が急に変わる、仕事の集中が続かないといった様子から「大丈夫かな」と感じることがあります。
しかし、こうした状態が一時的なストレス反応なのか、それとも医療的なサポートが必要な「情緒不安定」なのかを見極めるのは簡単ではありません。
この記事では、情緒不安定のサインや診断の基準、ストレスチェックとの違いを整理し、適切に対応するためのポイントを分かりやすく解説します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
情緒不安定とは
「情緒不安定」とは、感情の浮き沈みが大きく、気分の切り替えが難しい状態を指します。イライラしやすい、突然落ち込む、涙もろくなるなどのサインが見られ、本人も「自分でコントロールできない」と感じやすくなります。
誰にでも一時的な気分の波はあるものですし、また、うつ病や適応障害といったメンタル不調とも似ている場合もありますが、診断の有無や原因の深さが異なり、見極めには専門的な判断が必要です。
情緒不安定のサイン
情緒不安定のサインとしてまず挙げられるのは、感情の波が大きくなることです。普段なら気にならないようなことで落ち込んだり、イライラしたりと気分の浮き沈みが激しくなります。些細な出来事にも過敏に反応し、感情のコントロールが難しくなることもあります。また、集中力や判断力が低下し、ネガティブな思考が頭から離れなくなるといったケースも見られます。こうした状態が続くと、仕事のパフォーマンスや人間関係にも影響を及ぼすため、早めの気づきと対応が大切です。
一時的な気分の波との違い
情緒不安定と一時的な気分の波は、似ているようでその「期間」「強度」「日常生活への影響」に明確な違いがあります。
情緒不安定は、数週間から数か月、あるいはそれ以上にわたって気分の浮き沈みが続きやすく、自分でも感情をコントロールできないと感じることが多いのが特徴です。怒りや不安、悲しみといった感情が極端に出やすく、周囲との人間関係や仕事のパフォーマンスにも支障をきたすことがあります。原因もストレスや環境要因だけでなく、過去のトラウマや心の傷など、より深い心理的背景が関係していることもあります。
一方、一時的な気分の波は数時間から数日と短期間でおさまるケースがほとんどです。ストレスや睡眠不足、ホルモンバランスの変化など、明確な原因があることが多く、時間の経過や休養によって自然に回復します。
メンタル不調との違い
「情緒不安定」と「メンタル不調」は似た印象を持たれがちですが、実は指す範囲に違いがあります。
情緒不安定とは、イライラしやすい、涙もろくなる、不安や落ち込みが続くなど、感情の起伏が激しい状態をいいます。ストレスや過労、睡眠不足、ホルモンバランスの乱れ、人間関係の悩み、過去のトラウマなどが原因になることが多いです。
一方でメンタル不調は、心の健康が全体的に損なわれている広い状態を指します。情緒不安定もその一部の症状として現れることがありますが、思考力や集中力の低下、判断力の鈍り、意欲の減退、無気力感など、感情面以外にもさまざまな変化を伴います。さらに、頭痛やめまい、倦怠感、不眠など身体的な症状を伴うケースも少なくありません。
情緒不安定で診察すべきケース
情緒不安定と思われる場合でも念のため診断すべき状態とは、気分の浮き沈みが激しく、感情のコントロールが難しい状態が続き、仕事や日常生活に支障をきたしている場合です。
特に、イライラや落ち込み、不安などが2週間以上続くと注意が必要です。こうした状態は、うつ病や双極性障害、適応障害、パーソナリティ障害などの一症状として現れることがあるからです。
どのような状態が「診察の対象」となるか
情緒不安定で診察すべきケースとは、感情の起伏が激しく、自分ではコントロールできない状態が続き、仕事や生活に支障が出ている場合です。たとえば、業務に集中できない、家事や学業が手につかないなど、日常の活動に影響が出ているケースが該当します。些細なことでイライラしたり、急に涙が出たり、楽しい気分が一転して落ち込むなど、感情の波が大きいのも特徴です。さらに、頭痛や不眠、倦怠感、動悸、食欲不振など、原因のはっきりしない身体的な不調が続く場合も、早めに診察をすべきです。
情緒不安定から予想される主な疾患名
情緒不安定な状態の背景には、さまざまな精神疾患が隠れていることがあります。代表的なものとしては、うつ病、双極性障害、適応障害、パーソナリティ障害などが挙げられます。
うつ病は、気分の落ち込みや無気力、集中力の低下、不眠、食欲不振などが特徴で、長期間にわたり意欲が出ない状態が続きます。
双極性障害では、気分が異常に高揚して活発になる「躁状態」と、落ち込みが強くなる「うつ状態」を周期的に繰り返すのが特徴です。
適応障害は、職場の人間関係や環境の変化など、特定のストレスが原因で情緒が乱れ、涙もろさや不安、無気力などの症状が現れます。
パーソナリティ障害では、対人関係のトラブルが多く、感情の起伏が激しい傾向がみられます。
これらの症状は一見似ているようで、原因や治療法は異なります。
情緒不安定の診察のプロセス
情緒不安定が続く場合、まず大切なのは「自分の状態に気づくこと」です。気分の落ち込みやイライラが2週間以上続く、感情の起伏が激しく仕事や人間関係に支障をきたしている、セルフケアをしても改善しないといった場合には、早めに精神科や心療内科を受診することが望まれます。診断のプロセスでは、医師が問診を通じて生活状況やストレス要因、感情の変化の経過をていねいに確認します。必要に応じて心理検査や血液検査を行い、うつ病や双極性障害、適応障害などの可能性を総合的に判断します。
診断結果に応じて、薬物療法やカウンセリング、環境調整など、本人の状態に合わせたサポートが行われます。自己判断で「まだ大丈夫」と放置してしまうと、状態が悪化し、職場復帰や人間関係の再構築に時間がかかることもあります。
ストレスチェック=診断ではない
ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスを守るために行う“セルフチェック”の制度であり、医学的な診断とは異なります。質問票を通じて、仕事の負担や人間関係などによるストレスの程度を把握することを目的としており、「情緒不安定かどうか」を診断するものではありません。ストレスチェックの結果で「高ストレス」と判定されたとしても、それは一時的なストレス反応である可能性もあります。
しかし、感情の起伏や不安定さが長期に続き、生活や仕事に支障をきたす場合は、医師による専門的な評価が必要です。
企業としては、ストレスチェックの結果を「診断」と混同せず、従業員の変化に気づく“きっかけ”として活用することが大切です。高ストレス者や不調を訴える社員がいた場合は、早期に産業医やメンタルヘルス専門機関への相談につなげましょう。ストレスチェックは、従業員が自分の状態に気づき、必要に応じて専門家の支援を受けるための第一歩となる制度です。
職場で見られる情緒不安定の事例
職場で情緒不安定のサインが見られる場合、まず気づくのは感情の起伏です。些細なことでイライラしたり、突然落ち込んだりと感情の波が激しくなります。次に、集中力の低下やミスの増加など、業務パフォーマンスの変化が現れます。欠勤や遅刻が増えるのも、心身の不調のサインかもしれません。また、これまで円滑だったコミュニケーションが減ったり、言葉遣いや態度が変わったりすることもあります。
感情の起伏が激しい
職場で「感情の起伏が激しい」状態とは、たとえば、会議中に些細な意見の違いで強く反発する、突然涙ぐんでしまう、注意を受けた後に極端に落ち込んでしまうなど、感情の振れ幅が大きいケースです。本人に悪気があるわけではなく、ストレスや心身の疲労によって感情のコントロールが難しくなっている可能性があります。また、通常であれば冷静に対応できる業務上のトラブルでも、感情的に反応してしまう傾向が見られることも。こうした状態が続くと、チーム内の雰囲気や業務遂行にも影響を及ぼします。
人事担当者としては、すぐに注意や指導をするのではなく、まず「最近疲れていませんか?」などの声かけで様子をうかがうことが大切です。
集中力の低下
職場で見られる情緒不安定のサインの一つが、「集中力の低下」です。以前はミスが少なかった従業員に、資料の誤字脱字や報告漏れが増える、指示を一度で理解できなくなるといった変化が見られることがあります。たとえば、会議で話を聞いても内容を覚えていない、作業に取りかかっても途中で手が止まるなど、思考がまとまりにくい状態が続くケースです。
これは、ストレスや不安、睡眠不足などが原因で脳のエネルギーが低下し、集中力を維持できなくなっている可能性があります。
また、集中力の低下は本人だけでなく、周囲にも影響します。作業の遅れがチーム全体の業務に波及し、本人も「迷惑をかけている」と自責の念を抱くことで、さらに情緒が不安定になる悪循環に陥ることもあります。人事担当者や上司は、単なる「やる気の問題」と捉えず、背景に心の不調が隠れている可能性を意識することが大切です。
欠勤・遅刻の増加
これまで遅刻や休みがほとんどなかった従業員が、朝起きられずに遅刻を繰り返したり、体調不良を理由に休みが増えたりといった変化が見られます。
なかには、「寝つけない」「朝がつらい」「会社に行こうとすると不安になる」といった状態が続き、結果として出勤が難しくなるケースも少なくありません。本人も「休みたくない」と感じていることが多く、罪悪感や焦りがさらにストレスを強めることもあります。
このような状況は、うつ病や適応障害などのメンタル不調の初期サインであることも多く、放置すると長期休職につながる恐れがあります。人事担当者や上司は、勤務状況の変化を単なる「怠け」や「モチベーションの低下」と誤解せず、背景に心の不調が潜んでいないかを意識することが重要です。まずは責めるのではなく、「体調はどう?」と穏やかに声をかけ、必要に応じて産業医や専門機関への相談を促すことが望まれます。ストレスチェックの結果で高ストレスが示された場合も、こうした変化を見逃さず早めにフォローすることが大切です。
コミュニケーションの変化
職場で情緒不安定のサインとして現れやすいのが「コミュニケーションの変化」です。たとえば、以前は同僚とよく雑談していた人が急に口数が減る、会議中に意見を言わなくなる、反対に些細なことで強い口調になるなど、言動のトーンが極端に変わることがあります。
また、メールの返信が遅くなる、表情がこわばる、必要最低限の会話しかしなくなるといった変化もサインのひとつです。背景には、ストレスや疲労による心の余裕のなさ、不安感の高まりなどが関係していることが多く、本人も「人と関わるのがしんどい」と感じている場合があります。
一方で、これまで消極的だった人が急に攻撃的になったり、感情的な発言が増えたりするケースもあります。こうした変化を放置すると、チーム内の人間関係が悪化し、職場全体の雰囲気にも影響を及ぼす可能性があります。小さな違和感でも早期に気づき、声をかけ、産業医や専門機関への相談につなげることが、従業員のメンタル不調の予防と職場環境の安定につながります。
ストレスチェックと情緒不安定の関係
ストレスチェックは、従業員のストレス状態を把握し、早期に不調の兆しに気づくための制度です。したがって、情緒不安定そのものを診断するものではありませんが、結果から心の不調を見つける“きっかけ”になることがあります。高ストレスと判定された人には、産業医や専門家による面談を実施するなど、フォローアップが重要です。ストレスチェックの目的は、社員個人を評価することではなく、職場全体のストレス要因を明らかにし、環境改善につなげることです。適切に活用すれば、情緒不安定の早期発見と再発防止にも役立ちます。
ストレスチェックは医療的な診断ではない
ストレスチェックは、従業員が抱えるストレスの程度を把握し、職場のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための仕組みです。しかし、これは医師による診断とは異なり、「情緒不安定かどうか」を判断するものではありません。ストレスチェックの目的は、従業員が自分の心の状態に気づき、必要に応じて早めにケアや相談につなげることにあります。
たとえば、ストレスチェックの結果で「高ストレス」と判定されても、それだけで情緒不安定や精神疾患と診断されるわけではありません。あくまで“気づき”のきっかけであり、その後の産業医面談や医療機関の受診によって、専門的な評価やサポートが行われます。
情緒不安定を早期に発見するきっかけになる
ストレスチェックは医師の診断や精神疾患の確定を目的とした“診断ツール”ではありません。しかし、労働者自身が今どれだけストレスを抱えているのかを客観的に振り返る重要な機会となり、情緒不安定の兆しを早期に見つけるきっかけとして非常に有効です。特に、日々の業務で忙しいと、自分の心の変化に気づきにくくなりがちですが、ストレスチェックによって負荷の大きさやストレス反応の強さが数値として示されることで、普段見落としがちなサインに気づけるようになります。
「高ストレス者のフォローアップ」
ストレスチェックは、「高ストレス者のフォローアップ」につなげるための大切な仕組みです。ストレスチェックの結果で「高ストレス」と判定された場合には、本人が希望すれば産業医面談を受けることができ、必要に応じて医療機関への受診や職場環境の調整につなげられます。
企業としても、ストレスチェックを単なる年次業務で終わらせず、結果を基に職場全体のストレス要因を分析し、業務量の見直しや上司との関係改善など環境面のケアを行うことが求められます。ストレスチェックは、従業員の「診断」ではなく、心の不調を見逃さず支援につなげるための“入り口”として活用することが大切です。
ストレスチェック結果を職場改善に活かす
ストレスチェックは、情緒不安定を含むメンタルヘルス不調の早期発見や職場改善につなげる重要な制度です。個人のストレス状態を把握するだけでなく、組織全体の傾向を分析することで、業務量の偏りや人間関係、職場環境などの課題を見つけ出すことができます。こうしたデータを活用し、職場内コミュニケーションの改善、業務負担の見直し、働きやすい環境づくりを進めることで、従業員の生産性向上にもつながります。
また、ストレスチェックを継続的に活用することで、メンタルヘルス不調を未然に防ぎ、休職や離職のリスクを減らす効果も期待できます。情緒不安定な状態を放置すると、本人だけでなくチーム全体のパフォーマンスにも影響しますが、早期に気づき、職場全体で支援できる体制が整えば、安心して働ける環境が生まれます。人事担当者にとって、ストレスチェックは「義務的な制度」ではなく、従業員の健康と組織の安定を両立させるための大切なマネジメントツールといえるでしょう。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
ストレスチェックは医療的な診断を行うためのツールではありませんが、情緒不安定の兆しを早期に発見するきっかけとして非常に有効です。数値化された結果によって、自分の心の状態を客観的に振り返ることができ、普段気づきにくいストレス反応や心の負担に気づく手助けとなります。また、職場全体の傾向を把握することで、環境改善や業務調整につなげることも可能です。高ストレスと判定された場合は、医師の面接指導につながる機会もあり、メンタル不調の悪化を防ぐための早期サポートが受けられます。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、幅広い組織で導入されてきた信頼と実績を持つサービスです。未受検者への自動リマインド機能やリアルタイム進捗確認、医師面接希望者の管理など、実務に即した機能を標準搭載しています。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能に。欠勤や離職といった深刻な事態に至る前に課題を早期発見し、対策を講じることができます。導入や運用に関するご相談も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>ストレスチェックサービスおすすめ22選

