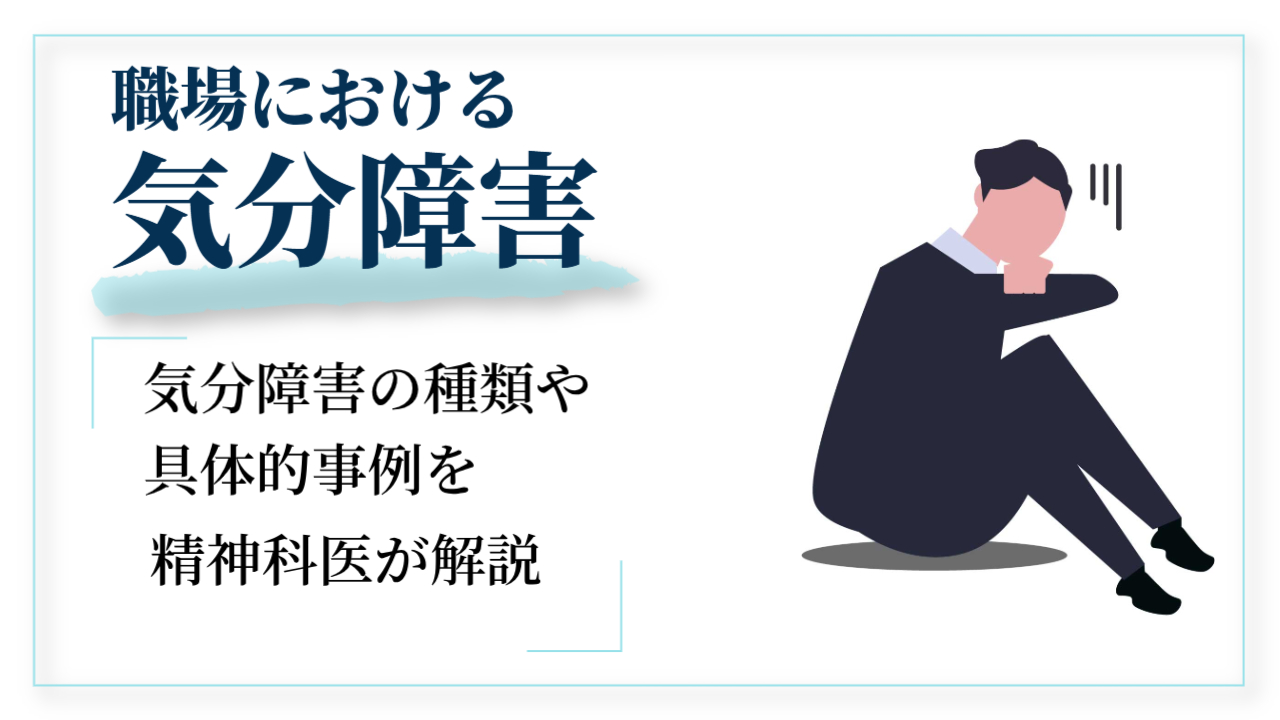
気分障害とは、日常生活や仕事に支障をきたす精神疾患の総称で、代表的なものにうつ病や双極性障害があります。単なる気分の落ち込みや一時的な不調と異なり、長期にわたり気分の低下や高揚が続くことで、集中力の低下や業務効率の悪化、対人関係の不和などを引き起こす可能性があります。
職場においては、従業員の生産性や離職リスクに直結するため、正しい理解と早期対応が求められています。
本記事では、気分障害の基本知識から職場で役立つ最新の対応方法までを解説します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
気分障害とは?
気分障害とは、気分の著しい変動が長期間続き、日常生活や社会生活に支障をきたす精神疾患の総称です。代表的なものにうつ病と双極性障害があります。国際的な診断基準であるICD-11では、「気分障害(Mood disorders)」は「気分症群」として分類され、うつ病性障害と双極性障害に大きく分けられています。ICD-10で用いられていた「気分[感情]障害」という呼称から整理され、診断基準も見直されました。
うつ病
うつ病は気分障害の代表的な疾患で、持続的な気分の落ち込みや興味・喜びの喪失が中心症状として現れます。単なる一時的な落ち込みとは異なり、2週間以上にわたって抑うつ気分が続き、仕事や日常生活に支障をきたすことが特徴です。主な症状には、集中力の低下、強い疲労感、睡眠障害(不眠や過眠)、食欲の変化、自己評価の低下、罪悪感や無価値感の増大などが含まれます。重症化すると、自殺念慮に至ることもあるため、早期発見と適切な支援が重要です。発症の背景には、過度のストレスや環境要因、性格的傾向に加え、脳内神経伝達物質の不均衡など生物学的要因も関与すると考えられています。
治療は抗うつ薬を中心とした薬物療法と、認知行動療法などの心理療法が併用されることが多く、休養や生活習慣の改善も欠かせません。
双極性障害
双極性障害は、気分障害の一種で、うつ状態と躁状態を繰り返す精神疾患です。うつ病と異なり、気分が落ち込む時期だけでなく、気分が高揚し活動的になる躁の時期があるのが大きな違いです。
躁状態では、睡眠が少なくても疲れを感じず、考えが次々と浮かび多弁になり、衝動的な行動や浪費、対人関係のトラブルを招くこともあります。
一方、うつ状態では強い無気力感や自己否定感に苦しみ、仕事や生活に大きな支障をきたします。症状は個人差が大きく、軽度で社会生活を維持できる場合もあれば、入院治療を要するほど重度に至るケースもあります。原因は脳の神経伝達物質の異常や遺伝的要因、強いストレスなど複数の要因が関与すると考えられています。治療には気分安定薬や抗精神病薬を中心とした薬物療法が行われ、再発予防のため長期的な服薬が必要となることが多いです。加えて、心理教育や生活リズムの安定も重要で、患者本人が症状の兆候を理解し、早期に対応できるよう支援することが求められます。
ICD-11 における気分障害の扱い
ICD-11における気分障害の分類は、従来よりも整理され、臨床や職場での対応に役立つ形へと進化しています。
大きく「抑うつ症群」と「双極症または関連症群」に分かれ、抑うつ症群には単一エピソードや反復性うつ病、気分変調症、混合抑うつ不安症が含まれます。一方、双極症群には双極性障害I型・II型や気分循環症が位置づけられ、抑うつと躁/軽躁が交互あるいは混在する病態が明確に整理されました。
特にICD-11では、躁状態と抑うつ状態が同時に現れる「混合エピソード」を正式に診断対象として扱う点が注目されます。これによって、従来あいまいだった症例も早期に把握し、適切な支援につなげやすくなりました。
さらに、抑うつエピソードの診断基準は「感情」「認知・行動」「身体的自律神経症状」の3つのクラスターで明確に示され、症状の数や期間(例:2週間以上)が具体的に要件化されています。DSM-5との整合性も高められているため、診断のばらつきが減少し、現場での実用性が向上しました。
職場における気分障害の兆候
職場における気分障害の兆候としては、以前より集中力が低下し業務効率が落ちる、遅刻や欠勤が増える、同僚とのコミュニケーションを避けるといった行動の変化が見られます。また、表情が乏しくなったり、疲れを口にする回数が増えたり、ちょっとしたことに過敏に反応するなど、感情面の不安定さもサインとなります。こうした兆候は単なる一時的な疲労と区別が難しい場合がありますが、長期的に続く場合は気分障害の可能性があるため、早めの声かけやサポートが重要です。
職場における「うつ病」の事例
ある30代の社員は、数か月前から業務に対する意欲が低下し、これまで問題なくこなしていた仕事に集中できなくなりました。
小さなミスが増え、報告やコミュニケーションも消極的になり、周囲から「元気がない」「以前と違う」と心配されるようになりました。本人も「疲れが取れない」「朝起きられない」といった身体的な不調を訴え、次第に遅刻や欠勤が増えていきました。当初は一時的な疲労やモチベーション低下と見られていましたが、医療機関を受診した結果、うつ病と診断されました。
うつ病は決して意志の弱さや怠慢ではなく、脳や神経の働きに関わるれっきとした疾患です。この事例のように、早期に気づき適切に対応することで、休養や治療を経て回復する可能性は十分にあります。
職場においては、業務量の調整や休職制度の活用、産業医や専門機関との連携が重要です。また、上司や同僚が「怠けている」と決めつけず、理解と支援の姿勢を持つことが、本人の安心感や回復につながります。
職場における「双極性障害」の事例
ある40代の社員は業務に大きな波を見せていました。
躁状態の時期には、短期間で大量の業務をこなし、新しい企画を次々と提案し、エネルギッシュに行動しました。しかし同時に、衝動的な判断や過剰な残業が増え、周囲を困惑させる場面も見られました。
その後、抑うつ状態に入ると一転して意欲を失い、出勤もままならなくなりました。
こうした気分の変動は本人だけでなくチーム全体に影響を及ぼします。重要なのは、病気を「性格の問題」と誤解せず、適切な治療や働き方の調整によって安定した就労のための取り組みが重要です。
職場における「気分変調症」の事例
職場における気分障害の中でも、気分変調症は見過ごされやすい疾患です。
気分変調症は「軽いうつ状態」が2年以上持続する慢性的な病気で、うつ病のような強い症状は現れにくいため、周囲から「少し元気がない人」「性格的に暗い人」と誤解されることが少なくありません。
ある社員は日常業務はこなせるものの、いつも疲れた様子で新しい取り組みに積極的に関わることができず、会議でも発言が少なくなっていました。成果物は一定の水準を保つ一方で、モチベーションの低さからチーム全体の雰囲気にも影響が及んでいました。また、慢性的な気分の落ち込みは自己評価の低下を招き、「どうせ自分にはできない」という思考の癖につながり、キャリアの停滞や早期離職リスクに直結することもあります。気分変調症は「軽いから大丈夫」ではなく、長期的に続くことこそ問題であり、職場では小さなサインを見逃さずに支援につなげることが重要です。
人事がすべき気分障害への対応
人事が職場における気分障害へ対応する際には、早期発見と適切なサポート体制の構築が重要です。
まず基本となるのはストレスチェック制度の活用です。
年に一度の実施を義務付けられているストレスチェックは、従業員自身の気づきを促すだけでなく、部署単位の傾向を可視化し、組織改善につなげる有効な手段となります。
また、高ストレス者が判定された場合には、放置せずに産業医面談につなぎ、必要に応じて外部の相談窓口や専門機関の利用を促すことが求められます。
さらに、就業規則に基づいた休職・復職制度を適切に運用し、安心して治療や療養に専念できる環境を整えることが大切です。復職の際には、段階的な就労や職場環境の調整など、柔軟な対応を行うことで再発を防ぎ、長期的な就業継続を支援できます。
ストレスチェック制度の活用
人事が気分障害への対応で最初に取り組むべきことのひとつが、ストレスチェック制度の積極的な活用です。
ストレスチェックは2015年から従業員50人以上の事業場で年1回の実施が義務付けられている制度ですが、今後は全事業場が対象となります。
目的は大きく三つあり、①従業員自身がストレス状態を自覚しセルフケアにつなげること、②高ストレス者を早期に把握して産業医面接など適切な支援につなげること、③集団分析によって職場環境を改善することです。
人事部門にとって特に重要なのは、集団分析を通じて部署ごとの特徴を可視化し、気分障害のリスクが高い部署を早期に把握できる点です。たとえば、同じ業務を行っている部門でも上司のサポートやコミュニケーションの有無によってストレス度合いが大きく異なることが明らかになります。
このようなデータを基に組織改善へと結びつけることで、従業員の心身の健康保持や離職防止にもつながります。ストレスチェックを「法律上の義務」で終わらせず、気分障害を未然に防ぐための有効なツールとして積極的に活用する姿勢が求められています。
産業医や外部相談窓口につなぐ
気分障害への対応において、人事が果たすべき大切な役割のひとつが、産業医や外部相談窓口につなぐことです。
気分障害は、うつ病や双極性障害など多様な症状を含み、職場でのパフォーマンス低下や欠勤・離職につながる恐れがあります。そのため、人事が単独で判断・対応しようとするのは限界がありますから、専門的な知見を持つ産業医やカウンセラーの介入が不可欠です。
産業医は、従業員の健康状態を医学的な観点から評価し、必要に応じて就業上の配慮や休職、復職の判断を行います。さらに、外部のメンタルヘルス相談窓口やEAP(従業員支援プログラム)を活用すれば、従業員は匿名で相談でき、職場では話しにくい悩みを安心して打ち明けられる場が確保されます。
就業規則に基づいた休職・復職制度の活用
気分障害は、症状が進むと長期的な療養を必要とするケースがあります。
まず休職制度を活用することで、従業員は安心して治療に専念でき、職場も無理な就労による悪化を防ぐことができます。休職期間中は、産業医や主治医の診断を踏まえ、人事が従業員と適度に連絡を取り、孤立感を和らげる配慮も欠かせません。
復職に際しては、医師の診断書をもとに段階的に就業を再開する「リハビリ出勤」など柔軟な仕組みを導入することで、再発を防ぎスムーズな職場復帰が可能になります。
また、復職後も人事が上司や同僚と連携し、業務量や勤務時間の調整を行うことが大切です。就業規則に基づいた休職・復職制度を整え、実際に活用できるように運用することは、従業員の安心感につながり、組織全体の信頼性や働きやすさを高める基盤となります。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
気分障害は、うつ病や双極性障害、気分変調症などを含む心の不調の総称であり、ICD-11 では抑うつ症群と双極症群に整理され、診断基準がより明確になりました。これにより、職場でも「見逃し」を防ぎ、早期対応が可能になります。従業員の変化は行動や表情に現れやすく、気分障害の兆候をいち早く察知することが重要です。そのためには、ストレスチェック制度を有効に活用し、必要に応じて産業医や外部相談窓口へつなぐ仕組みが欠かせません。また、就業規則に基づいた休職・復職制度を適切に運用することで、従業員が安心して療養し、再び職場で力を発揮できる環境を整えることができます。気分障害を理解し、データと制度を活用して組織改善につなげることが、人事に求められる実践的な対応といえるでしょう。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁や上場企業、大学、大規模病院など多様な現場で導入実績があり、未受検者への自動リマインド、リアルタイムの進捗確認、医師面接希望の収集など実務に即した機能を備えています。さらに2025年5月からは、無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能となり、欠勤に至らない段階での課題も把握できます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>メンタルブレイクのリスクを産業医が解説

