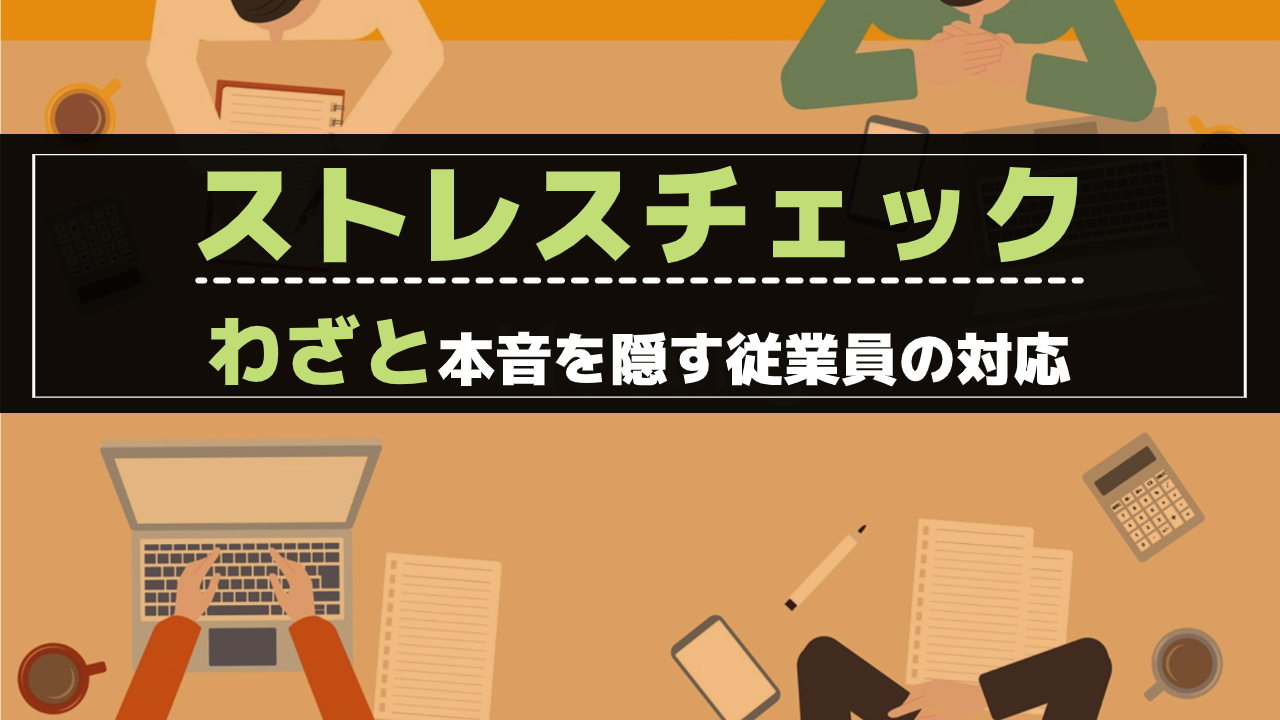
ストレスチェックを実施しても、「わざと、ストレスを感じていないように回答している」「わざと、高ストレス者になるように回答している」というケースが見られることがあります。
従業員本人が「本音を隠す」理由には、評価や人事への影響を恐れる気持ち、産業医面談への抵抗感、匿名性への不信感など、さまざまな心理が関係していると見られますが、その結果、本来もっとも支援や対策を講じるべき人のストレス状況を正しく把握できないという問題が生じます。
この記事では、「ストレスチェックをわざと隠す」従業員の心理と企業が取るべき対応策について解説します。
監修医師:近澤 徹
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役
目次
ストレスチェックで従業員が「わざと隠す」理由
従業員が、ストレスチェックで本来の心身状態について「わざと隠す」ような回答をする背景には、いくつかの心理的な要因があります。
まず多いのは、「ストレスが高い」と回答すると評価や人事に悪影響があるのではと不安に感じるケースです。また、産業医面談に呼ばれることへの抵抗感や、「どうせ匿名じゃないのでは」という不信感から、本音を避けてしまうこともあります。さらに、そもそもストレスチェックの目的が「個人を評価するものではなく、職場環境の改善を目的とした制度」であることを理解していない場合も多く、制度の趣旨が正しく伝わっていないことが原因となるケースも見られます。
評価や人事への影響を恐れている
ストレスチェックで「わざと本音を隠す」従業員のなかには、評価や人事への影響を恐れているケースがあります。
たとえば、ある企業では、管理職が「ストレスが高い従業員については、配置転換を検討する」と発言したことで、従業員が本音を答えにくくなったケースがありました。
本来、ストレスチェックは個人を評価するものではなく、職場全体の環境改善を目的としています。しかし、従業員が「回答内容が人事評価に使われるかもしれない」と感じてしまうと、形だけの実施にとどまり、もっともケアが必要な人の状況を把握できなくなってしまいます。
産業医面談への抵抗感
ストレスチェックで「わざとストレスを感じていないように回答する」従業員の中には、産業医面談への抵抗感を抱いているケースが少なくありません。
たとえば、ある企業では実際に「面談に呼ばれたくないから、ストレスがないと答える」というケースがありました。本人としては、「自分の弱さを見せたくない」「上司や人事に知られたら不利益になるのでは」といった不安が背景にあったものと見られます。
匿名性への不信感
ストレスチェックで「わざとストレスを隠す」従業員の中には、匿名性に不信感を抱いている人が少なくありません。
たとえば、ある企業では「回答内容から個人が特定されそう」「名前を書かなくても結局バレるのでは」という声が上がり、回答を控えめにしたり、全く受検しない社員が増えてしまいました。
ストレスチェックは本来、個人を評価するものではなく、職場全体の環境改善を目的としていますが、従業員が「どうせ結果が人事に伝わる」と思ってしまえば、正直な回答は期待できません。企業が本当にストレスの実態を把握したいなら、まずは「個人が特定されない制度であること」を明確に説明し、回答データの扱い方や保存方法を透明化することが欠かせません。
そもそもストレスチェックの目的を理解していない
そもそもストレスチェックの目的を正しく理解していない人も、多く見受けられます。
たとえば、ある企業では「ストレスチェックは会社が従業員を管理するためのもの」「成績評価の一環ではないか」と誤解する声があがり、本音を隠したり、形式的に回答したりするケースが見られました。こうした誤解は、実施時に目的や意義の説明が不足していることが主な原因です。
本来、ストレスチェックは「従業員一人ひとりが自分のストレス状態を把握し、職場全体で改善につなげる」ことを目的とした制度です。しかし、従業員が「自分のための制度」だと理解できていなければ、真剣に取り組む意識は生まれません。企業としては、制度の背景や活用方法を説明する機会を設け、「評価ではなくサポートのために行うもの」であると明確に伝えることが重要です。
「わざと隠す」ことが企業にもたらすリスク
従業員がストレスチェックで「わざと隠す」回答をすると、企業にとっても深刻なリスクが生じます。
まず、メンタル不調の早期発見が遅れ、サポートが必要な従業員を見逃すリスクがあります。また、集団分析の精度が下がり、職場の本当の課題を把握できなくなります。さらに、「どうせ形だけ」と従業員に思われると、制度自体への信頼が失われ、結果的に離職率の上昇や生産性の低下にもつながりかねません。
メンタル不調の早期発見が遅れる
ストレスチェックで従業員が「わざとストレスを感じていないように回答する」と、メンタル不調の早期発見が遅れてしまいます。
たとえば、ある企業では「本音を言うと面談に呼ばれるのが嫌で」と従業員が軽い不眠や頭痛を隠した結果、数か月後にうつ症状が悪化し、長期休職に至りました。本来であれば、ストレスチェックで高ストレス者として把握され、早期に産業医面談や勤務調整などの対策を取れたはずのケースです。
このように、「わざと隠す」回答があると、最もケアが必要な従業員のSOSを見逃してしまう危険があります。また、個人の不調が職場の人間関係やチーム全体のパフォーマンス低下につながることも少なくありません。
集団分析の精度が下がる
ストレスチェックで従業員が「わざとストレスを感じていないように回答する」と、集団分析の精度が大きく下がるという問題が起こります。
集団分析は、部署ごとのストレス傾向を数値化し、職場環境の改善につなげるための重要なデータです。しかし、実際には「本音を書くと人事に知られるかも」「面談に呼ばれるのが嫌だ」といった理由で、従業員がストレスを隠すケースが少なくありません。
たとえば、ある企業では職場の雰囲気が悪化していたにもかかわらず、ストレスチェックの集団分析では「問題なし」と出ていました。後に実際の退職者アンケートから、上司のパワハラや長時間労働が原因だったことが判明し、ようやく改善に動き出したという事例もあります。このように、信頼性の低いデータでは、企業が職場の課題を見誤り、対応が後手に回ってしまうのです。
正確な集団分析を行うためには、従業員が安心して本音を回答できる環境づくりが欠かせません。
「形骸化している」と見られ、従業員の信頼を失う
ストレスチェックで従業員が「わざとストレスを感じていないように回答する」背景には、企業側への不信感があることも少なくありません。実施しても何も変わらない、形だけの取り組みだと感じさせてしまうと、従業員のモチベーションや信頼を失う原因になります。
たとえば、ある企業では毎年ストレスチェックを実施していたものの、集団分析の結果を活用せず、フォローアップも行われませんでした。その結果、「やっても意味がない」「結局自己責任で終わる」といった声が上がり、受検率が大幅に低下しました。
ストレスチェックを形骸化させると、従業員は本音を隠すようになり、企業は本当の職場課題を把握できなくなります。さらに、従業員が会社に対して心理的な距離を感じるようになってしまえば、エンゲージメントや定着率の低下、生産性の損失へとつながります。企業が信頼を取り戻すには、ストレスチェックを「形式的な調査」ではなく、「従業員の声を活かす仕組み」として運用することが大切です。実際に環境改善や制度見直しにつなげることで、従業員は「会社が本気で自分たちの健康を考えている」と感じ、信頼関係を深めることができます。
離職率や生産性に悪影響
ストレスチェックで従業員が「わざとストレスを感じていないように回答する」と、離職率の上昇と生産性の低下に直面することもあり得ます。
実際、ある製造業の企業では、職場の人間関係に悩む社員が本音を隠して「問題なし」と回答していました。その後、上司とのトラブルが悪化し、本人が突然退職。チーム全体の士気も下がり、生産効率が一時的に20%近く落ち込む結果となりました。
このように、ストレスの実態を正確に把握できないまま放置すると、メンタル不調者の休職や離職が連鎖的に発生し、結果として企業のパフォーマンスに深刻な影響を及ぼします。また、従業員のストレス耐性だけに頼った組織運営は、長期的に見て優秀な人材ほど離れていく傾向にあります。
企業が取るべき5つの対応策
従業員がストレスを「わざと隠す」背景には、企業への不信感や仕組みへの理解不足があります。これを防ぐためには、まずストレスチェックの目的を正しく伝えることが重要です。さらに、匿名性やデータ管理の信頼性を確保し、安心して回答できる環境を整えましょう。また、管理職や上司へのメンタルヘルス教育を強化し、日常的に部下の変化に気づける体制を築くことも欠かせません。加えて、集団分析の結果を基に具体的な改善行動へとつなげ、「形だけではない」姿勢を示すことが信頼回復の鍵です。
ストレスチェックの目的を正しく伝える
従業員の中には、「結果が人事評価に影響するのでは」「産業医面談に呼ばれるのが嫌だ」といった誤解を抱き、正直に答えることを避けてしまう人もいます。
しかし、ストレスチェックは労働者を評価するためのものではなく、メンタルヘルス不調の予防や職場環境の改善を目的としています。しかし、その目的を企業が十分に周知していなければ、制度そのものが不信感を招き、せっかくの仕組みが形骸化してしまいます。
たとえばある企業では、導入時に「人事には個人の結果が伝わらない」「目的は、メンタルヘルス不調への早期の気づきや、集団分析を活用した職場改善である」と繰り返し説明したことで、受検率が前年比で20%向上しました。
企業がやるべきは「受けさせること」ではなく、「安心して本音を伝えてもらうこと」。そのためには、ストレスチェックの位置づけを明確にし、制度への信頼を築くことが欠かせません。結果として、従業員が率直に回答できる環境が整い、職場改善の精度が向上することが期待できます。
匿名性とデータ管理の信頼性を担保
従業員が安心して本音を答えられない環境では、いくら制度を整えても正確な結果は得られません。実際に、ある企業では「上司に結果を見られるのでは」と不安を感じた従業員が、全員ほぼ同じような低ストレス回答をしたため、集団分析の結果が形骸化してしまいました。
ストレスチェックの信頼性を高めるためには、まず「結果は個人が特定されない形で集計され、人事評価には一切使用されない」という点を明確に伝えることです。さらに、結果通知や面談希望の手続きも、プライバシーを保った仕組みで行うことが望ましいでしょう。従業員が「本当に守られている」と実感できる透明な運用こそが、信頼関係の基盤となり、ストレスチェックの精度向上と組織全体のメンタルヘルス向上につながります。
管理職・上司へのメンタルヘルス教育を強化
多くの従業員は、上司の態度や理解不足を理由に本音を出しづらくなります。
たとえばある企業では、管理職が「強い気持ちで乗り越えよう」と声をかけ続けた結果、部下が不調を訴えられず、最終的に長期休職につながった事例もあります。
管理職がメンタルヘルスの基礎知識を学び、ストレスのサインを早期に察知できるようになることで、職場全体の安心感が高まります。さらに、面談や日常の声かけで「話しても大丈夫」と感じられる風土が形成されれば、従業員はストレスチェックにも正直に回答しやすくなります。
企業としては、単なる研修の実施にとどまらず、ケーススタディやロールプレイを通じて“傾聴力”や“共感的対応”を育てることが効果的です。上司の理解が深まれば、ストレスチェックの精度も上がり、組織としての予防力が強化されます。
結果を「行動」に変える姿勢
ストレスチェックを実施しても、結果を職場の改善につなげられなければ、従業員は「どうせ形だけでしょ」と感じ、次第に本音で回答しなくなります。つまり、企業が「結果をどう活かすか」を見せる姿勢こそ、従業員の信頼を得る最大のポイントです。
ある企業では、ストレスチェック後の集団分析で「業務量の偏り」が課題として浮かび上がりました。そこで管理職会議で改善策を検討し、繁忙部署への応援体制を整備したところ、翌年の高ストレス者の割合が20%減少しました。このように、データを現場改善のきっかけとして活用することで、従業員は「会社が本気で環境を良くしようとしている」と実感できます。
また、改善内容や進捗を社内に公表することも大切です。「結果を踏まえ、○○の取り組みを始めました」といった情報発信を続けることで、ストレスチェックの意義が共有され、協力的な姿勢が育まれます。
本音を引き出すストレスチェック運用
多くの企業で問題となるのは、従業員が「どうせ結果を見ても何も変わらない」「回答内容で評価が下がるかも」と感じ、本音を隠して回答してしまうこと。これでは、本来もっとも支援が必要な人の状況を把握できず、早期対応の機会を逃してしまいます。
本音を引き出すためには、まず「ストレスチェックは評価のためではなく、職場環境を改善するためのもの」という目的を徹底的に繰り返し周知することが重要です。さらに、実施後のフィードバックを丁寧に行い、「結果を受けて職場でこう変わった」という改善の実績を積み重ねることで、信頼が生まれます。
また、従業員が気軽に意見を伝えられる匿名アンケートや面談の仕組みを導入することも有効です。形式的な実施ではなく、従業員が「正直に答えても大丈夫」と思える安心感をつくることが、本音を引き出す運用の第一歩。信頼関係の構築こそが、真に意味のあるストレスチェックにつながるのです。
監修:精神科医・日本医師会認定産業医/近澤 徹

【監修医師】
精神科医・日本医師会認定産業医
株式会社Medi Face代表取締役・近澤 徹
オンライン診療システム「Mente Clinic」を自社で開発し、うつ病・メンタル不調の回復に貢献。法人向けのサービスでは産業医として健康経営に携わる。医師・経営者として、主に「Z世代」のメンタルケア・人的資本セミナーや企業講演の依頼も多数実施。
まとめ
従業員がストレスを「わざと隠す」背景には、評価への不安や匿名性への不信感、そして「どうせ変わらない」という諦めがあります。しかし、その結果、企業は最もストレスを抱える従業員の実態を把握できず、早期対応の機会を失ってしまいます。正しい対策として、企業はまずストレスチェックの目的を明確に伝え、データの管理体制を強化することが大切です。また、管理職へのメンタルヘルス教育や結果を行動に移す姿勢、本音を引き出す運用を徹底することで、従業員の信頼が高まり、ストレスチェックが「形だけ」で終わらない職場づくりにつながります。
国内最大級のストレスチェックツール「ストレスチェッカー」は、官公庁・上場企業・大学・大規模医療機関など、幅広い組織で導入されてきた信頼と実績を持つサービスです。未受検者への自動リマインド機能やリアルタイム進捗確認、医師面接希望者の管理など、実務に即した機能を標準搭載しています。さらに、2025年5月からは無料プランやWEB代行プランでも「プレゼンティーイズム(体調不良や心理的負担による生産性低下)」の測定が可能に。欠勤や離職といった深刻な事態に至る前に課題を早期発見し、対策を講じることができます。導入や運用に関するご相談も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
:参照記事
>ストレスチェックサービスおすすめ22選

